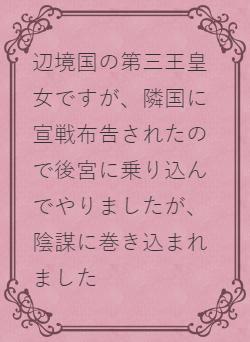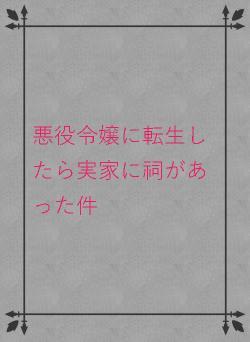空は青く、風はどこまでも澄んでいた。
境内に咲く花々が、陽光を浴びて揺れている。
夏花の神事に相応しい日だ。
清められた神楽殿、その中央に柚羽は立っていた。
絹の舞衣が風に揺れ、髪は項で一つに結ばれている。
その姿には迷いもなく、神前に仕える「花の巫女」としての威厳と美しさがあった。
神楽殿を囲むように座る人々が息を呑み、神職や来賓たちが静かに見守る。
その全ての視線が、柚羽ひとりに注がれていた。
(香は、もう遙真さんが消してくれた。だから大丈夫)
柚羽は目を閉じたまま、心の中でつぶやいた。
(紫乃が隠していた香も、記録も、すべて証拠として確保されている)
ゆっくりと息を吸い、笛の合図を皮切りに扇を開いた。
(私は舞う。ただ祈るために)
祈りの舞が、始まる。
手にした神楽鈴を鳴らすと、大太鼓と小太鼓が続く。
ひと振りの扇に花の香が乗り、柚羽は風と一体となる。足運びは静かに、けれど大地に力強く根を張っていた。
そこへ、朱塗りの柱の陰から一人の影が現れた。
光に目を細め、ゆらりと姿を現したのは紫乃だ。
彼女の髪は乱れ、表情は笑っているのにどこか焦点が合っていない。
(……来た)
柚羽は舞を止めなかった。
目を逸らせばすべてが崩れる。だから、ただ舞い続けた。
紫乃の視線が壇上へと向き、そして動きが止まる。
神楽殿の中心に、清らかに立つ柚羽の姿を見た瞬間だった。
「……あれは、私の場所よ! 退きなさい!」
そう叫んだ次の瞬間、紫乃が駆け出した。
鬼気迫る紫乃を前に、止める者はいない。誰もがその行動に息を呑んだままだった。
壇上に駆け上がり、柚羽の扇を奪い取る。
「私が――私こそが、正当な巫女よ!」
高らかに叫び、そのまま舞を始めた。
けれど、その所作は荒く、緩慢で、動きに流れがなかった。
何よりも神楽の場にあるはずの清涼な気配が、紫乃の周囲には感じられない。
静まる観客の空気に、紫乃は違和感を覚える。
向けられる視線の冷たさに紫乃はふと首を傾げた。
「……どうして? どうして、誰も……」
(私に見惚れないの?)
その瞬間、紫乃の周囲にふわりと漂う甘い香り。自らが用意し、使い続けてきた毒香の残り香だった。
排除されたと思っていた香は、紫乃自身の衣に染み込んでいた。
舞うほどに熱で香が揮発し、神前の空気を乱していく。
境内に咲く花々が、陽光を浴びて揺れている。
夏花の神事に相応しい日だ。
清められた神楽殿、その中央に柚羽は立っていた。
絹の舞衣が風に揺れ、髪は項で一つに結ばれている。
その姿には迷いもなく、神前に仕える「花の巫女」としての威厳と美しさがあった。
神楽殿を囲むように座る人々が息を呑み、神職や来賓たちが静かに見守る。
その全ての視線が、柚羽ひとりに注がれていた。
(香は、もう遙真さんが消してくれた。だから大丈夫)
柚羽は目を閉じたまま、心の中でつぶやいた。
(紫乃が隠していた香も、記録も、すべて証拠として確保されている)
ゆっくりと息を吸い、笛の合図を皮切りに扇を開いた。
(私は舞う。ただ祈るために)
祈りの舞が、始まる。
手にした神楽鈴を鳴らすと、大太鼓と小太鼓が続く。
ひと振りの扇に花の香が乗り、柚羽は風と一体となる。足運びは静かに、けれど大地に力強く根を張っていた。
そこへ、朱塗りの柱の陰から一人の影が現れた。
光に目を細め、ゆらりと姿を現したのは紫乃だ。
彼女の髪は乱れ、表情は笑っているのにどこか焦点が合っていない。
(……来た)
柚羽は舞を止めなかった。
目を逸らせばすべてが崩れる。だから、ただ舞い続けた。
紫乃の視線が壇上へと向き、そして動きが止まる。
神楽殿の中心に、清らかに立つ柚羽の姿を見た瞬間だった。
「……あれは、私の場所よ! 退きなさい!」
そう叫んだ次の瞬間、紫乃が駆け出した。
鬼気迫る紫乃を前に、止める者はいない。誰もがその行動に息を呑んだままだった。
壇上に駆け上がり、柚羽の扇を奪い取る。
「私が――私こそが、正当な巫女よ!」
高らかに叫び、そのまま舞を始めた。
けれど、その所作は荒く、緩慢で、動きに流れがなかった。
何よりも神楽の場にあるはずの清涼な気配が、紫乃の周囲には感じられない。
静まる観客の空気に、紫乃は違和感を覚える。
向けられる視線の冷たさに紫乃はふと首を傾げた。
「……どうして? どうして、誰も……」
(私に見惚れないの?)
その瞬間、紫乃の周囲にふわりと漂う甘い香り。自らが用意し、使い続けてきた毒香の残り香だった。
排除されたと思っていた香は、紫乃自身の衣に染み込んでいた。
舞うほどに熱で香が揮発し、神前の空気を乱していく。