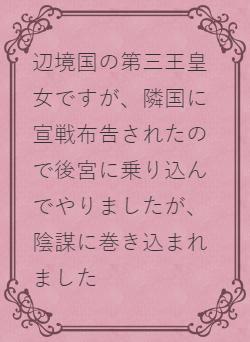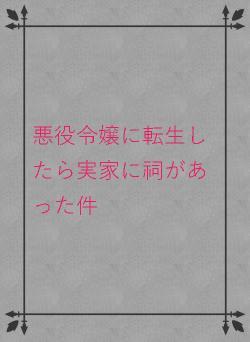幼い頃から、紫乃は人の顔色を読むのが得意だった。
けれど、それは人に合わせるためではなかった。
「どこをどうすれれば、相手が壊れるか」を測るための観察だった。
自分より弱い巫女見習いを泣かせては、何もなかったように頭を撫でる。
神職の見習いが粗相をすれば、それを誰より先に気づいて重罪だと話しを膨らませ両親に吹き込む。
けれど紫乃は一度も疑われなかった。
なぜなら、彼女は「選ばれた巫女」だったから。
ある日紫乃は、書庫で一冊の古い巻物を見つけた。
厳重に封がされていたそれは、「香による戦の記録」と題された禁書だった。
花の巫女を巡る家同士の争いの時代――
そこでは、敵家の巫女を病に伏せさせるために「毒香」が使われていたと記されていた。
今はもう使われない、記録にしか残らないその知識。
けれど紫乃は、胸の奥がぞくりとするほど、それに惹かれた。
(これ、面白そう)
密かに香を調合し、最初は小動物を相手に試した。
うまくいった。
次に、言うことを聞かない側仕えに使った。
香を嗅がせると正気を失い、最終的に塔から身を投げた。
(思ったより、簡単)
恐怖も、罪悪感もなかった。
むしろ、自分だけが知っている秘密の力に優越感を覚えていた。
その頃から、柚羽が神楽を舞う回数が増えていった。
母は言った。
「紫乃は身体が弱いから、無理をさせたくないの」
けれど紫乃には、それが遠回しな自分への失望に聞こえた。
舞うたびに柚羽は周囲の称賛を集め、逆に紫乃は添え物のような扱いになる。
姉が褒められるたびに、紫乃の中にある感情がが冷たく沈んでいった。
(私のために控えてくれていたはずの姉が、私を踏み台にして輝いている)
やがて、母の視線が変化する。どこか不安げに、紫乃を見つめるようになった。
そしてある日、母は決定的な言葉を紫乃に告げた。
「紫乃……あなたには、御神楽を継がせるわけにはいかない」
それは、紫乃にとって「死」に値する言葉だった。
母の部屋に飾る花に、香を忍ばせた。
程なく母は苦しんで死んだ。
医師は心臓の病と言ったが、紫乃は知っている。
(間違ったお母様は、消える運命だったのよ)
自分の母を殺した。そんな罪悪感は、今もかけらすら感じていない。
「私こそが、御神楽家を継ぐ巫女。私を否定するものは、みんな間違ってるのよ」
紫乃は、そう信じて疑わなかった。
けれど、それは人に合わせるためではなかった。
「どこをどうすれれば、相手が壊れるか」を測るための観察だった。
自分より弱い巫女見習いを泣かせては、何もなかったように頭を撫でる。
神職の見習いが粗相をすれば、それを誰より先に気づいて重罪だと話しを膨らませ両親に吹き込む。
けれど紫乃は一度も疑われなかった。
なぜなら、彼女は「選ばれた巫女」だったから。
ある日紫乃は、書庫で一冊の古い巻物を見つけた。
厳重に封がされていたそれは、「香による戦の記録」と題された禁書だった。
花の巫女を巡る家同士の争いの時代――
そこでは、敵家の巫女を病に伏せさせるために「毒香」が使われていたと記されていた。
今はもう使われない、記録にしか残らないその知識。
けれど紫乃は、胸の奥がぞくりとするほど、それに惹かれた。
(これ、面白そう)
密かに香を調合し、最初は小動物を相手に試した。
うまくいった。
次に、言うことを聞かない側仕えに使った。
香を嗅がせると正気を失い、最終的に塔から身を投げた。
(思ったより、簡単)
恐怖も、罪悪感もなかった。
むしろ、自分だけが知っている秘密の力に優越感を覚えていた。
その頃から、柚羽が神楽を舞う回数が増えていった。
母は言った。
「紫乃は身体が弱いから、無理をさせたくないの」
けれど紫乃には、それが遠回しな自分への失望に聞こえた。
舞うたびに柚羽は周囲の称賛を集め、逆に紫乃は添え物のような扱いになる。
姉が褒められるたびに、紫乃の中にある感情がが冷たく沈んでいった。
(私のために控えてくれていたはずの姉が、私を踏み台にして輝いている)
やがて、母の視線が変化する。どこか不安げに、紫乃を見つめるようになった。
そしてある日、母は決定的な言葉を紫乃に告げた。
「紫乃……あなたには、御神楽を継がせるわけにはいかない」
それは、紫乃にとって「死」に値する言葉だった。
母の部屋に飾る花に、香を忍ばせた。
程なく母は苦しんで死んだ。
医師は心臓の病と言ったが、紫乃は知っている。
(間違ったお母様は、消える運命だったのよ)
自分の母を殺した。そんな罪悪感は、今もかけらすら感じていない。
「私こそが、御神楽家を継ぐ巫女。私を否定するものは、みんな間違ってるのよ」
紫乃は、そう信じて疑わなかった。