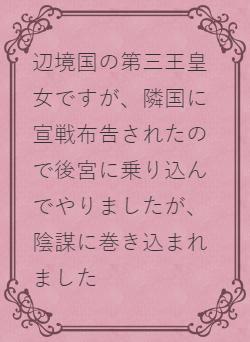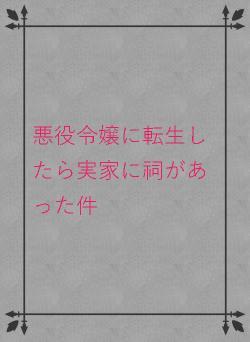神楽の準備が進む神楽殿に、鈍く湿った風が流れていた。
慌ただしく準備をする神職達を、紫乃は自室の窓辺に座り眺めている。
けれど、その瞳はどこか焦点が合っていなかった。
香に当てられ、心と身体の連携が取れなくなっていることにも、まだ誰も気づいていない。
唇の端に浮かべた微笑はひどく楽しげで、恐ろしいほど無邪気だった。
「……面白い神楽が始まるわ」
誰に向けるでもない囁きが、甘い香に混じって消えていく。
神楽殿の裏手、目に触れぬ場所には紫乃が密かに用意させた香炉が置かれていた。
焚かれているのは、淡く甘い香。
けれどその正体は精神を鈍らせ、理性をゆっくり削る毒香。
「ゆっくり広がって……気づいた時には、もう動けないのよ」
招待した客人たちは皆、席に座っていた。
誰もが笑みを浮かべ、式の始まりを静かに待っている。
けれど、紫乃には見えていた――その身体の動きが、僅かずつ鈍っていく様子が。
昨夜、雅弥にはたっぷりと香を吸わせてあった。
笑いながら酒臭い息で寄りかかってくる彼に、紫乃は耳元で囁いた。
「舞が始まったらね、お兄様の奥様を……神楽の席で殺してしまって。私の夫になるなら、そのくらいできるでしょう?」
香のせいで目が虚ろなまま、雅弥は何度も頷いていた。
その顔を見て、紫乃は喉の奥で笑った。
(これで、終わる。全部壊れるわ)
紫乃は、神楽殿を見上げた。
まもなく神事が始まる。
数時間後この場が修羅となり、血と絶叫が流れるのだと思うと、身体が小さく震えるほど愉快だった。
「神様は、私にだけ微笑んでくださるのよ。お姉様に見せてあげられないのが残念だわ」
ただ、壊して、奪って、笑いたい。それだけの純粋な狂気が、そこに燃えていた。
香の煙に包まれながら、紫乃は目を閉じる。
意識の底に、あの遠い日々がゆっくりと浮かび上がってくる。
「紫乃は特別よ。お前は花の巫女として才がある」
父も、母も、そう言って紫乃を育てた。
いずれは御神楽家を継ぐのは、柚羽ではなく紫乃。
その言葉は、紫乃にとって生きる意味に等しいものだった。
慌ただしく準備をする神職達を、紫乃は自室の窓辺に座り眺めている。
けれど、その瞳はどこか焦点が合っていなかった。
香に当てられ、心と身体の連携が取れなくなっていることにも、まだ誰も気づいていない。
唇の端に浮かべた微笑はひどく楽しげで、恐ろしいほど無邪気だった。
「……面白い神楽が始まるわ」
誰に向けるでもない囁きが、甘い香に混じって消えていく。
神楽殿の裏手、目に触れぬ場所には紫乃が密かに用意させた香炉が置かれていた。
焚かれているのは、淡く甘い香。
けれどその正体は精神を鈍らせ、理性をゆっくり削る毒香。
「ゆっくり広がって……気づいた時には、もう動けないのよ」
招待した客人たちは皆、席に座っていた。
誰もが笑みを浮かべ、式の始まりを静かに待っている。
けれど、紫乃には見えていた――その身体の動きが、僅かずつ鈍っていく様子が。
昨夜、雅弥にはたっぷりと香を吸わせてあった。
笑いながら酒臭い息で寄りかかってくる彼に、紫乃は耳元で囁いた。
「舞が始まったらね、お兄様の奥様を……神楽の席で殺してしまって。私の夫になるなら、そのくらいできるでしょう?」
香のせいで目が虚ろなまま、雅弥は何度も頷いていた。
その顔を見て、紫乃は喉の奥で笑った。
(これで、終わる。全部壊れるわ)
紫乃は、神楽殿を見上げた。
まもなく神事が始まる。
数時間後この場が修羅となり、血と絶叫が流れるのだと思うと、身体が小さく震えるほど愉快だった。
「神様は、私にだけ微笑んでくださるのよ。お姉様に見せてあげられないのが残念だわ」
ただ、壊して、奪って、笑いたい。それだけの純粋な狂気が、そこに燃えていた。
香の煙に包まれながら、紫乃は目を閉じる。
意識の底に、あの遠い日々がゆっくりと浮かび上がってくる。
「紫乃は特別よ。お前は花の巫女として才がある」
父も、母も、そう言って紫乃を育てた。
いずれは御神楽家を継ぐのは、柚羽ではなく紫乃。
その言葉は、紫乃にとって生きる意味に等しいものだった。