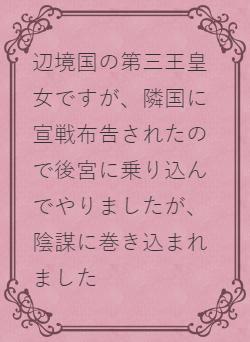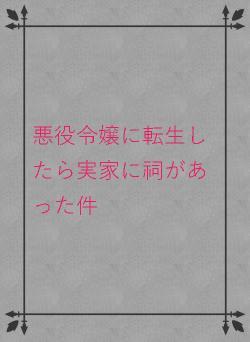しばしの静寂のあと、柚羽は小さく息をついた。
遙真は優しく手を握ってくれている。
それだけで、心がすこし強くなれた気がした。
けれど――
「……でも、やるべき事はあります」
柚羽はゆっくりと言葉を継いだ。
「御神楽家で次の催事……夏花の神楽があるんです。もしそれを放棄したら、秋の豊穣の約束は果たされません。神事は土地神との契約の意味もあります……失われれば、困るのは生活する人々です」
遙真の表情がわずかに曇る。
たしかにそれは、神事を司る者として無視はできない。
「代理の巫女を立てるにしても、もう時間がありません。今から舞を覚えて、正式な儀式を執り行える者はいないはずです」
「紫乃さんにはもう資格がない。あれだけの穢れにまみれた者に、神事の舞いは務まらない。どうすれば」
遙真の声に、わずかに怒気がにじむ。
「だから、私が舞います」
その言葉に、遙真が目を見開いた。
「柚羽さん、それは――」
「分かっています。私が舞えば、紫乃怒るでしょう。でも、それでもやるべきことなんです」
柚羽は、まっすぐに遙真を見つめた。
目の奥に宿るのは、恐れでも諦めでもなく、静かな覚悟だった。
「私が御神楽家に戻れば、きっと何か仕掛けてくるでしょう。けれど私は、逃げません。私が舞う必要があるんです」
遙真の喉が動いた。
言いたいことは山ほどあった。止めたい気持ちも、守りたい気持ちも。
だが、彼女の中にある決意の炎を、言葉で覆すことはできなかった。
「……分かりました。柚羽さんがその道を選ぶなら、私はすべてを尽くして、あなたを守ります」
「ありがとう、遙真さん。……本当は少し紫乃が恐い…でも、絶対に負けません。私は舞いであの家に最後に正しさを取り戻したい。それが私の、御神楽での役目です」
その言葉に、遙真は深く頭を下げた。
「あなたに、恥じぬように。私も、その意思に報います」
初夏の日差しが、二人を包み込んでいた。