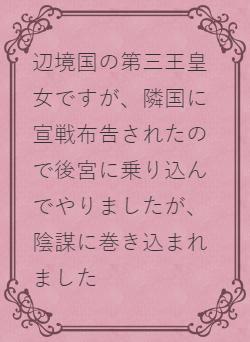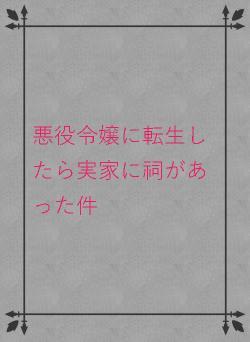継杜家の本殿奥、会議の間に家の重鎮たちが集っていた。
遙真はその中央で背筋を伸ばして報告を終えた。
「……以上が、御神楽家において確認された霊的乱れの記録です。星見の報告と合わせ、明確に穢れの徴候が出ていると判断いたしました」
彼が差し出したのは、霊的異常を記録した書類と、祭具に付着した香の痕跡を示す証拠だった。
星見が観測した神星の欠け。祭具の器から検出された「記憶を濁す香」などの毒香。
祝詞の場で起きた不審死、神職たちの急な辞職。
すべてが一つの家の中で、短期間に重なっていること。
重鎮たちは息を呑み、誰も異議を唱えなかった。
年長の祭主が、静かに言葉を落とす。
「まさか直系の紫乃が、殺人に手を染めるとはな」
「……もはや、御神楽家は社としての資格を失ったと考えるべきでしょう。神が離れておられる」
その言葉は、誰よりも遙真自身の胸を締めつけた。
自分がこの判断を下す日が来るとは。だが、今はもう躊躇ってはいけない。
「では継杜としての決議をここに。御神楽家の神事を全て停止し、今後の対応は遙真に一任する」
その一言が星見から告げられた瞬間、室内の空気が変わった。
形式こそ簡易だが、これは「御神楽家の当主」としての正式な任命と同義となる。
遙真は深く頭を下げた。
*
会議を終えて、遙真は庭の東屋で柚羽と向き合っていた。
「御神楽家が花の巫女としての資格を失ったというのは、本当ですか?」
「はい」
「でも……私は、御神楽家を……あの家を、なんとかしたい。紫乃のことも、まだ止められると思うんです」
そう訴えかける柚羽の声を、遙真はそっと遮った。
「すでに、御神楽家は穢れています。もう手の施しようがありません」
ざあっと強い風が吹き、竹の葉を揺らす。
遙真が、ゆっくりと口を開く。
「御神楽家を清める方法はありません。一度御神楽の名を消し、新たな血筋から花の巫女に相応しい方を迎える必要があります」
「名を消す……」
柚羽が言葉を繰り返した。
その意味が胸の奥に落ちるまで、ほんの数秒の沈黙があった。
――つまり、それは取り潰し。
「そんな……でも、私は――」
声が震えそうになるのを必死で抑えながら、柚羽は言った。
「私は……御神楽家を守りたいんです。母がいて、沙耶がいて、私が生まれ育った場所を……簡単に無くしたくない」
訴える言葉に自然と熱がこもる。
「私がこの命に替えても、汚れを祓います」
遙真は一瞬黙り込んだが首を横に振る。
「柚羽さん。あなたは自覚がないだけで、とても強い力を持つ巫女なんだ。御神楽家に留めておく事は、許されない」
その言葉に、柚羽は息を詰めた。
「継杜家の星見たちは、あなたを日本国を守る巫女の頂点に推挙しました」
「……そんな……」
「その役目に立てるのは、あなたしかいない」
柚羽は、膝の上で指を握りしめた。
御神楽家という「家」を守ることと、国を護る「花の巫女」としての使命。
ふたつはもう、両立しないのだと悟った。
遙真はその中央で背筋を伸ばして報告を終えた。
「……以上が、御神楽家において確認された霊的乱れの記録です。星見の報告と合わせ、明確に穢れの徴候が出ていると判断いたしました」
彼が差し出したのは、霊的異常を記録した書類と、祭具に付着した香の痕跡を示す証拠だった。
星見が観測した神星の欠け。祭具の器から検出された「記憶を濁す香」などの毒香。
祝詞の場で起きた不審死、神職たちの急な辞職。
すべてが一つの家の中で、短期間に重なっていること。
重鎮たちは息を呑み、誰も異議を唱えなかった。
年長の祭主が、静かに言葉を落とす。
「まさか直系の紫乃が、殺人に手を染めるとはな」
「……もはや、御神楽家は社としての資格を失ったと考えるべきでしょう。神が離れておられる」
その言葉は、誰よりも遙真自身の胸を締めつけた。
自分がこの判断を下す日が来るとは。だが、今はもう躊躇ってはいけない。
「では継杜としての決議をここに。御神楽家の神事を全て停止し、今後の対応は遙真に一任する」
その一言が星見から告げられた瞬間、室内の空気が変わった。
形式こそ簡易だが、これは「御神楽家の当主」としての正式な任命と同義となる。
遙真は深く頭を下げた。
*
会議を終えて、遙真は庭の東屋で柚羽と向き合っていた。
「御神楽家が花の巫女としての資格を失ったというのは、本当ですか?」
「はい」
「でも……私は、御神楽家を……あの家を、なんとかしたい。紫乃のことも、まだ止められると思うんです」
そう訴えかける柚羽の声を、遙真はそっと遮った。
「すでに、御神楽家は穢れています。もう手の施しようがありません」
ざあっと強い風が吹き、竹の葉を揺らす。
遙真が、ゆっくりと口を開く。
「御神楽家を清める方法はありません。一度御神楽の名を消し、新たな血筋から花の巫女に相応しい方を迎える必要があります」
「名を消す……」
柚羽が言葉を繰り返した。
その意味が胸の奥に落ちるまで、ほんの数秒の沈黙があった。
――つまり、それは取り潰し。
「そんな……でも、私は――」
声が震えそうになるのを必死で抑えながら、柚羽は言った。
「私は……御神楽家を守りたいんです。母がいて、沙耶がいて、私が生まれ育った場所を……簡単に無くしたくない」
訴える言葉に自然と熱がこもる。
「私がこの命に替えても、汚れを祓います」
遙真は一瞬黙り込んだが首を横に振る。
「柚羽さん。あなたは自覚がないだけで、とても強い力を持つ巫女なんだ。御神楽家に留めておく事は、許されない」
その言葉に、柚羽は息を詰めた。
「継杜家の星見たちは、あなたを日本国を守る巫女の頂点に推挙しました」
「……そんな……」
「その役目に立てるのは、あなたしかいない」
柚羽は、膝の上で指を握りしめた。
御神楽家という「家」を守ることと、国を護る「花の巫女」としての使命。
ふたつはもう、両立しないのだと悟った。