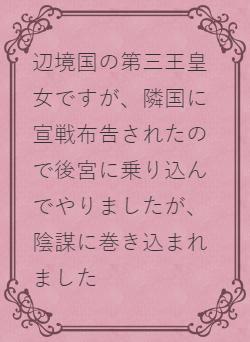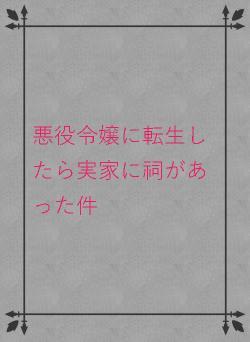日本国には古くから、あらゆる自然に神が宿ると信じられ、各地にその神を祀る社が存在する。
神社ごとに異なる役目が定められており、中でも御神楽家は「花の巫女」として季節の巡りを正しく祈願する役割を代々受け継いできた。
その務めは年に数度、神前で神楽を舞い神へお礼を伝えること。
神事としての舞は、決して見世物ではない。神と人を結ぶ交信の儀であり、巫女の舞いが正しく行われないと、季節が乱れるとされていた。
先代の巫女であった柚羽と紫乃の母も、その務めを果たしていたが、数年前に病で亡くなっている。以降、巫女の正当な跡取りが定まらぬまま、柚羽を筆頭に紫乃を含む数人の見習い巫女たちが交代で舞を奉じてきた。
そんな中、今年――柚羽が十八の歳を迎えた初夏。
全国の社を統括する継杜家より、柚羽が正式に「花の巫女」の跡取りとして任命されることが通達された。
神座の館にて、神職や関係者が見守る中で行われた任命の儀。柚羽は、その場で初めて正式な装束に身を包み、神前に立ち一人で神楽を舞った。
だが、その神事の最中に事件は起こった。
塔の上階から身を投げたのは、巫女見習いの中でも年長で、柚羽が最も信頼を寄せていた沙耶だった。
近頃は体調を崩して務めを外れることも多かったが、今日ばかりは支度を手伝うのだと早朝から張り切っていたのだ。
なのに彼女は、柚羽の舞いが終わる寸前。身投げした。
投身による即死。
当然儀式は中断し、柚羽への「花の巫女」正式任命は保留となった。
***
神楽の儀が中断され、沙耶の遺体が運び出されたあと、屋敷の空気が重く沈んでいた。
「また、あのときと同じじゃないか」
小さな声がどこからともなく聞こえる。
数年前の年納めの舞いの翌朝、若い巫女見習いが首をつって亡くなっていた。あの年納めの舞いの中心にいたのは柚羽だった。
悩みを抱えていたと誰かが言っていたが未だに原因は分かっていない。
「柚羽様が舞うと、死人が出る。……不吉だよ」
亡くなった紗那の魂を慰める儀式が執り行われた日、誰かがぽつりと呟く。
「死を呼ぶ巫女……」
「ここ数年、柚羽様の側仕えになった巫女ばかり辞めていくじゃないか」
「まさか、奥様の病も……?」
そんな囁きが、どこからともなく聞こえてきた。
じわじわと不安が人々の中に広がっていく。
(私のせいじゃない……だけど――)
柚羽は、強く手を握りしめた。
自分を責めるべきではないと分かっていても、胸の奥にざらつく影が消えなかった。
嫌な空気に、巫女や禰宜たちが顔を見合わせ始める。
不安が口々に漏れそうになったそのとき――
「静かにしなさい。憶測でものを言うものではないわ」
紫乃だった。人々の視線が一斉に彼女に向く。
「お姉様のせいじゃない。沙耶は体調が悪くて体の疲れがなかなか取れず……いっそ死んでしまおうか、なんて、そんなことまで言っていたわ。静養するよう勧めたけれど、あの人は頑なにお姉様の側を離れようとしなかった」
落ち着いた口調だったが、その言葉には揺るぎがなかった。
「悲しい結果になってしまったけれど、お姉様にはなんの責任もない。皆さん、どうかお姉様を責めないで……」
最初は毅然としていてた紫乃だが、次第に声を詰まらせる。
紫乃が前に出てきたことで、場の空気は落ち着きを取り戻した。
柚羽を糾弾する声は収まったが、次第に「花の巫女は紫乃様のほうが……」という声が口の端に浮かび始める。
その日を境に柚羽と紫乃の立場は、静かに入れ替わっていった。
神社ごとに異なる役目が定められており、中でも御神楽家は「花の巫女」として季節の巡りを正しく祈願する役割を代々受け継いできた。
その務めは年に数度、神前で神楽を舞い神へお礼を伝えること。
神事としての舞は、決して見世物ではない。神と人を結ぶ交信の儀であり、巫女の舞いが正しく行われないと、季節が乱れるとされていた。
先代の巫女であった柚羽と紫乃の母も、その務めを果たしていたが、数年前に病で亡くなっている。以降、巫女の正当な跡取りが定まらぬまま、柚羽を筆頭に紫乃を含む数人の見習い巫女たちが交代で舞を奉じてきた。
そんな中、今年――柚羽が十八の歳を迎えた初夏。
全国の社を統括する継杜家より、柚羽が正式に「花の巫女」の跡取りとして任命されることが通達された。
神座の館にて、神職や関係者が見守る中で行われた任命の儀。柚羽は、その場で初めて正式な装束に身を包み、神前に立ち一人で神楽を舞った。
だが、その神事の最中に事件は起こった。
塔の上階から身を投げたのは、巫女見習いの中でも年長で、柚羽が最も信頼を寄せていた沙耶だった。
近頃は体調を崩して務めを外れることも多かったが、今日ばかりは支度を手伝うのだと早朝から張り切っていたのだ。
なのに彼女は、柚羽の舞いが終わる寸前。身投げした。
投身による即死。
当然儀式は中断し、柚羽への「花の巫女」正式任命は保留となった。
***
神楽の儀が中断され、沙耶の遺体が運び出されたあと、屋敷の空気が重く沈んでいた。
「また、あのときと同じじゃないか」
小さな声がどこからともなく聞こえる。
数年前の年納めの舞いの翌朝、若い巫女見習いが首をつって亡くなっていた。あの年納めの舞いの中心にいたのは柚羽だった。
悩みを抱えていたと誰かが言っていたが未だに原因は分かっていない。
「柚羽様が舞うと、死人が出る。……不吉だよ」
亡くなった紗那の魂を慰める儀式が執り行われた日、誰かがぽつりと呟く。
「死を呼ぶ巫女……」
「ここ数年、柚羽様の側仕えになった巫女ばかり辞めていくじゃないか」
「まさか、奥様の病も……?」
そんな囁きが、どこからともなく聞こえてきた。
じわじわと不安が人々の中に広がっていく。
(私のせいじゃない……だけど――)
柚羽は、強く手を握りしめた。
自分を責めるべきではないと分かっていても、胸の奥にざらつく影が消えなかった。
嫌な空気に、巫女や禰宜たちが顔を見合わせ始める。
不安が口々に漏れそうになったそのとき――
「静かにしなさい。憶測でものを言うものではないわ」
紫乃だった。人々の視線が一斉に彼女に向く。
「お姉様のせいじゃない。沙耶は体調が悪くて体の疲れがなかなか取れず……いっそ死んでしまおうか、なんて、そんなことまで言っていたわ。静養するよう勧めたけれど、あの人は頑なにお姉様の側を離れようとしなかった」
落ち着いた口調だったが、その言葉には揺るぎがなかった。
「悲しい結果になってしまったけれど、お姉様にはなんの責任もない。皆さん、どうかお姉様を責めないで……」
最初は毅然としていてた紫乃だが、次第に声を詰まらせる。
紫乃が前に出てきたことで、場の空気は落ち着きを取り戻した。
柚羽を糾弾する声は収まったが、次第に「花の巫女は紫乃様のほうが……」という声が口の端に浮かび始める。
その日を境に柚羽と紫乃の立場は、静かに入れ替わっていった。