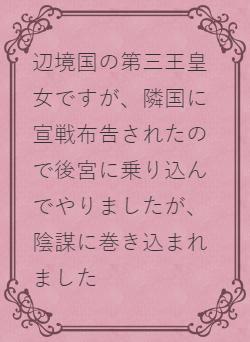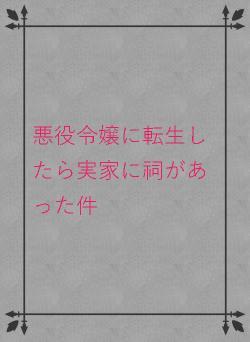花の巫女として認められるその時が、数日後に迫っていた。
神前の舞台で、紫乃はひとり舞う。「花の神楽」最後の確認だ。
扇をひと振りするたびに、袖がやわらかく風を含む。
手足が羽のように軽く、空気の抵抗すら感じない。
(……ああ、やっぱり。私こそが花の巫女なのだわ)
心の奥で、紫乃は静かに笑った。
全国の社を統括する継杜家に認められてしまえば、御神楽家で紫乃に逆らえる者はいなくなる。
(香を使って黙らせるのも、面倒なのよね)
巫女には様々な責務がある。季節ごとに細々とした催事や祈りの修業。しかし紫乃はそれらを滑稽なものだとずっと思っていた。
厳しい修行を積み、やっと得た紙と通じる力。それを全て人々のために使う。
(なんで私が、この力を平民ごときに与えなくてはいけないの?)
紫乃は祭事の細かな準備や日々の祈りなど、心底どうでもよかった。
雑事は使い捨ての巫女見習いや、下働きの神職にやらせるべきだ。
自分は年に数度、大きな催事のときだけ表に出て優雅に舞いさえすればいい。
その美しさと名だけで人々はひれ伏す。
どんなに綺麗ごとを並べたところで、力を持つ者が優位に立つのが世の理。
「花の巫女」に付随する加護なのだから、巫女自身が自分のために使って何が悪い。
紫乃は気づいていた。
花の巫女としての力は、誰と繋がるかによっても行き先を変えることができる。
だったら多くの有力者と関係を持ち、豊穣の恩を売ればいい。
楽をして生きるのに、これ以上に手頃な方法はない。
高遠家も紫乃からすれば、ただの「踏み台」にすぎなかった。
姉の婚約者だった高遠雅弥は、顔が整っているだけの馬鹿な男だ。褒めればすぐ気をよくし、媚びをみせれば簡単に言うことを聞いた。
扱いやすい、けれどそれだけ。
本当に狙っていたのは高遠家の長男。彼は既に高遠家を継いでおり、政治にも口を出せる立場にある。
彼と繋がれば、御神楽家の名も「形式上」だけ維持しながら、自分はより大きな権力と財を手に入れられる。
問題は長男が既婚者であること。
次の催事には、「花の巫女の正当な継承式」という理由を伝え、長男一家を招くことに成功した。
あとは自然な流れで長男と二人きりになれる時間を作るだけ。
体を重ねてしまえば、こちらのものだ。
だがそれだけでは足りない。確実に紫乃を必要とするよう仕向けなくてはと紫乃は計画を練った。
その際、邪魔になるのは、雅弥と長男の妻である。
だから雅弥には暗示と錯乱の香を使う。それを吸わせ、宴の場で長男の妻を暴行させる計画だ。強力な香だが、どうせ雅弥は使い捨ての道具にすぎない。
それに派手に暴れてくれた方が、紫乃にとって都合がいい。
暴力沙汰になれば、高遠家は雅弥を病人として扱い、座敷牢に閉じ込めるに違いない。妻の方は、高貴な血筋の箱入り娘だと聞いている。衆目の場で襲われれば、ショックで精神に異常を来すだろう。
そうなれば、長男は紫乃の恩恵を必要とする立場になる。
「花の巫女の加護で心の禍を祓える」――そう言えば、彼はきっと縋ってくるだろう。妻には適当な時期を見て香を使えばいい。
余計な雅弥は暗い座敷で寂しく人生を終える。
あれだけ擦り寄ってきた男が、醜態をさらして消えていく様を想像すると、紫乃の口元がゆっくりと綻んだ。
(……久しぶりに舞ったせいかしら? 手首が重いわ)
舞は紫乃の身体に染みついていた。母の舞いを一度見ただけで覚えてしまう紫乃は、天才だともてはやされ努力した記憶はない。
一方、柚羽の舞いは美しかったがどこか必死すぎた。
(お姉様ってば、こんな簡単な舞なのに。全然覚えられないんですもの)
紫乃の舞いは違う。軽やかで、空気と一体になれる。母も昔はよく褒めてくれた。
何も言わなくなったのは、いつの頃からだったか。
(私……何を考えて……?)
頭を振って余計な思考を振り払う。
紫乃は扇をたたみ静かに一礼すると、誰もいない神前でひとつ呼吸をついた。
来たる催事は、紫乃にとって新たな出発点になる。
そして、すべてを思い通りにする始まりになるはずだ。
神前の舞台で、紫乃はひとり舞う。「花の神楽」最後の確認だ。
扇をひと振りするたびに、袖がやわらかく風を含む。
手足が羽のように軽く、空気の抵抗すら感じない。
(……ああ、やっぱり。私こそが花の巫女なのだわ)
心の奥で、紫乃は静かに笑った。
全国の社を統括する継杜家に認められてしまえば、御神楽家で紫乃に逆らえる者はいなくなる。
(香を使って黙らせるのも、面倒なのよね)
巫女には様々な責務がある。季節ごとに細々とした催事や祈りの修業。しかし紫乃はそれらを滑稽なものだとずっと思っていた。
厳しい修行を積み、やっと得た紙と通じる力。それを全て人々のために使う。
(なんで私が、この力を平民ごときに与えなくてはいけないの?)
紫乃は祭事の細かな準備や日々の祈りなど、心底どうでもよかった。
雑事は使い捨ての巫女見習いや、下働きの神職にやらせるべきだ。
自分は年に数度、大きな催事のときだけ表に出て優雅に舞いさえすればいい。
その美しさと名だけで人々はひれ伏す。
どんなに綺麗ごとを並べたところで、力を持つ者が優位に立つのが世の理。
「花の巫女」に付随する加護なのだから、巫女自身が自分のために使って何が悪い。
紫乃は気づいていた。
花の巫女としての力は、誰と繋がるかによっても行き先を変えることができる。
だったら多くの有力者と関係を持ち、豊穣の恩を売ればいい。
楽をして生きるのに、これ以上に手頃な方法はない。
高遠家も紫乃からすれば、ただの「踏み台」にすぎなかった。
姉の婚約者だった高遠雅弥は、顔が整っているだけの馬鹿な男だ。褒めればすぐ気をよくし、媚びをみせれば簡単に言うことを聞いた。
扱いやすい、けれどそれだけ。
本当に狙っていたのは高遠家の長男。彼は既に高遠家を継いでおり、政治にも口を出せる立場にある。
彼と繋がれば、御神楽家の名も「形式上」だけ維持しながら、自分はより大きな権力と財を手に入れられる。
問題は長男が既婚者であること。
次の催事には、「花の巫女の正当な継承式」という理由を伝え、長男一家を招くことに成功した。
あとは自然な流れで長男と二人きりになれる時間を作るだけ。
体を重ねてしまえば、こちらのものだ。
だがそれだけでは足りない。確実に紫乃を必要とするよう仕向けなくてはと紫乃は計画を練った。
その際、邪魔になるのは、雅弥と長男の妻である。
だから雅弥には暗示と錯乱の香を使う。それを吸わせ、宴の場で長男の妻を暴行させる計画だ。強力な香だが、どうせ雅弥は使い捨ての道具にすぎない。
それに派手に暴れてくれた方が、紫乃にとって都合がいい。
暴力沙汰になれば、高遠家は雅弥を病人として扱い、座敷牢に閉じ込めるに違いない。妻の方は、高貴な血筋の箱入り娘だと聞いている。衆目の場で襲われれば、ショックで精神に異常を来すだろう。
そうなれば、長男は紫乃の恩恵を必要とする立場になる。
「花の巫女の加護で心の禍を祓える」――そう言えば、彼はきっと縋ってくるだろう。妻には適当な時期を見て香を使えばいい。
余計な雅弥は暗い座敷で寂しく人生を終える。
あれだけ擦り寄ってきた男が、醜態をさらして消えていく様を想像すると、紫乃の口元がゆっくりと綻んだ。
(……久しぶりに舞ったせいかしら? 手首が重いわ)
舞は紫乃の身体に染みついていた。母の舞いを一度見ただけで覚えてしまう紫乃は、天才だともてはやされ努力した記憶はない。
一方、柚羽の舞いは美しかったがどこか必死すぎた。
(お姉様ってば、こんな簡単な舞なのに。全然覚えられないんですもの)
紫乃の舞いは違う。軽やかで、空気と一体になれる。母も昔はよく褒めてくれた。
何も言わなくなったのは、いつの頃からだったか。
(私……何を考えて……?)
頭を振って余計な思考を振り払う。
紫乃は扇をたたみ静かに一礼すると、誰もいない神前でひとつ呼吸をついた。
来たる催事は、紫乃にとって新たな出発点になる。
そして、すべてを思い通りにする始まりになるはずだ。