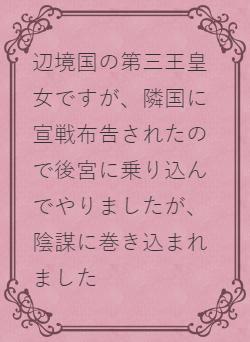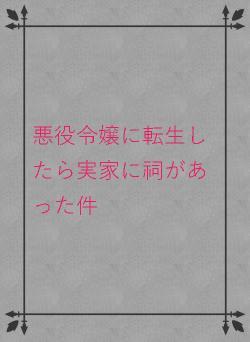御神楽家の奥座敷に、重々しい空気が漂っていた。
室内の温度は、どこまでも重く冷たい。
親族の年長者や神職の重鎮らが一列に座し、彼らを見渡せる一段上の上座に紫乃がいる。
「――柚羽様が現在、継杜家にいるというのは、どういうことか。お聞かせ願えますか」
問うたのは、親族の筆頭、七十を越えた長老格の男だった。
口調こそ穏やかだったが、そこには明らかな不審がにじんでいた。
紫乃は静かに頭を下げた。
「お尋ねいただき、ありがとうございます。柚羽姉様の件につきましては、先日、正式に「死の巫女」であると神託があったので、隔離措置を取った次第です」
表情は動かず、声にも一切の揺らぎはなかった。
淡々と、まるで事務処理を読み上げるかのように彼女は偽りの言葉を続けた。
「継杜家の判断で表沙汰にはなっておりません。しかし万が一の影響を考慮し、当家としても連携を取っております」
その場には一瞬、沈黙が走った。
年長者たちが顔を見合わせる中、一人の神職がそっと眉をひそめる。
「……神託とは?」
稀に神託を受ける巫女はいたが、神の声を聞けるのは正式に継いだ者だけだ。
だが紫乃は臆せず堂々と答える。
「神前にて舞った祝詞の直後、数年前の出来事も含め二人の巫女が亡くなりました。先日はご存じの通り父も…その上、姉は霊力を失ったまま。つまり姉は「神に穢れを与える体質になってしまった」のだと……。私は確かに、そう神託を聞いたのです」
「本来、清めの力を持つ巫女が穢れたと?」
「そうです」
と、紫乃ははっきり肯定する。
「これ以上、柚羽姉様の名前を巫女の名簿に置いておくことは、当家にとって不名誉です。除籍の手続きを、正式に進めたいと考えております」
そこまで告げたとき、座の空気が一層冷たくなる。
一部の親族の目が、明らかに違和感を覚えている色を帯びた。
「では紫乃様。……除籍後の行き先は、どうなるのか」
重鎮の一人が問いかける。
紫乃は、待っていましたと言わんばかりに微笑んだ。
「高遠家のご親戚より、良縁のお話をいただいております。由緒ある家柄の方で財もあり、誠に信頼のおけるお方です。姉とは多少、年齢は離れておりますが問題ではございません」
「その噂は耳にしておりましたよ。ですが相手のお歳は三十以上違うのでは流石に……」
控えめに声を上げたのは、母方の親族にあたる中年の女性だった。
紫乃はその方へ微笑みを向け冷ややかな声で告げた。
「姉様は「穢れ」を背負った身です。後添いでも望んで頂けたのは奇跡のようなもの。そのような物言いは、高遠家に失礼ではありませんか」
女性は一瞬目を見開いたが、すぐに俯く。
もう誰も、紫乃に反論する者はいなかった。
室内の温度は、どこまでも重く冷たい。
親族の年長者や神職の重鎮らが一列に座し、彼らを見渡せる一段上の上座に紫乃がいる。
「――柚羽様が現在、継杜家にいるというのは、どういうことか。お聞かせ願えますか」
問うたのは、親族の筆頭、七十を越えた長老格の男だった。
口調こそ穏やかだったが、そこには明らかな不審がにじんでいた。
紫乃は静かに頭を下げた。
「お尋ねいただき、ありがとうございます。柚羽姉様の件につきましては、先日、正式に「死の巫女」であると神託があったので、隔離措置を取った次第です」
表情は動かず、声にも一切の揺らぎはなかった。
淡々と、まるで事務処理を読み上げるかのように彼女は偽りの言葉を続けた。
「継杜家の判断で表沙汰にはなっておりません。しかし万が一の影響を考慮し、当家としても連携を取っております」
その場には一瞬、沈黙が走った。
年長者たちが顔を見合わせる中、一人の神職がそっと眉をひそめる。
「……神託とは?」
稀に神託を受ける巫女はいたが、神の声を聞けるのは正式に継いだ者だけだ。
だが紫乃は臆せず堂々と答える。
「神前にて舞った祝詞の直後、数年前の出来事も含め二人の巫女が亡くなりました。先日はご存じの通り父も…その上、姉は霊力を失ったまま。つまり姉は「神に穢れを与える体質になってしまった」のだと……。私は確かに、そう神託を聞いたのです」
「本来、清めの力を持つ巫女が穢れたと?」
「そうです」
と、紫乃ははっきり肯定する。
「これ以上、柚羽姉様の名前を巫女の名簿に置いておくことは、当家にとって不名誉です。除籍の手続きを、正式に進めたいと考えております」
そこまで告げたとき、座の空気が一層冷たくなる。
一部の親族の目が、明らかに違和感を覚えている色を帯びた。
「では紫乃様。……除籍後の行き先は、どうなるのか」
重鎮の一人が問いかける。
紫乃は、待っていましたと言わんばかりに微笑んだ。
「高遠家のご親戚より、良縁のお話をいただいております。由緒ある家柄の方で財もあり、誠に信頼のおけるお方です。姉とは多少、年齢は離れておりますが問題ではございません」
「その噂は耳にしておりましたよ。ですが相手のお歳は三十以上違うのでは流石に……」
控えめに声を上げたのは、母方の親族にあたる中年の女性だった。
紫乃はその方へ微笑みを向け冷ややかな声で告げた。
「姉様は「穢れ」を背負った身です。後添いでも望んで頂けたのは奇跡のようなもの。そのような物言いは、高遠家に失礼ではありませんか」
女性は一瞬目を見開いたが、すぐに俯く。
もう誰も、紫乃に反論する者はいなかった。