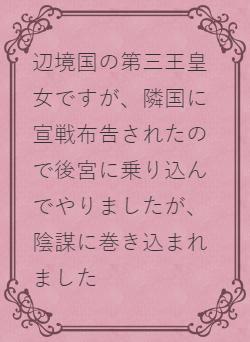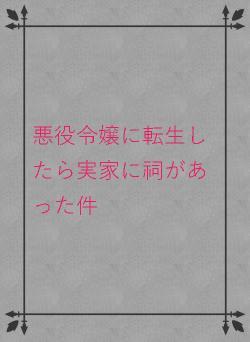「……お願いです。遙真さん、何が起こっているのか教えてください」
朝食を終えた後。
「散歩に」と誘われて出た庭先で、柚羽は遙真を見上げて問う。
遙真はわずかに口を開きかけて、すぐに閉じた。
「私は、知りたいんです。私のことも母のことも、沙耶のことも……何があったのか。……もう、目を背けたくありません」
静かな声だったが、震えを帯びていた。自分の祈りが神に届かず死を招いたのなら、責任を負わねばならない。
しばらくの沈黙のあと、遙真はゆっくりと頷いた。
「……では、お伝えします。ただし、少しきつい内容になるかもしれません」
「構いません」
柚羽は背筋を伸ばし、しっかりと遙真の目を見つめた。
*
最初に語られたのは、身に覚えのない香の痕跡についてだった。
母が亡くなる数日前、部屋に飾られていた花や香に混じって、極めて微量の鎮静作用と幻覚作用を持つ成分が検出されたという。
「当時の証拠は乏しいですが、今も同じ香が、ごくわずかに保存された器の中に残っていました。継杜家と通じている下男が証拠を保管しています」
遙真は、そう前置きしてから続けた。
「沙耶さんがっていた香壺の底にも、同じ成分が残っていました。そして……亡くなった日の朝、紫乃さんが彼女の部屋に入っていったという証言もあります」
柚羽は言葉を失う。
何かが胸の奥に沈んでいく感覚。ひとつずつ、疑問の答え合わせがされていく。
「……母が……。沙耶まで……」
「もうひとつ」
遙真の声が少しだけ硬くなった。
「あなたの身の回りを手伝っていた巫女見習いたち――彼女たちがあなたの元を離れた理由は、「死の巫女が怖かった」からではありません」
「……え?」
「紫乃さんから、圧力があったそうです。「お姉様に近づかないで」と。……それを、昨日ようやく証言してくれた者がいました」
「紫乃が……どうして?」
「あくまで予想でしかありませんが、紫乃さんは「花の巫女」に強い執着を持っているようです」
巫女になれば、神前で舞うことは許される。しかし「花の巫女」は一つの社に一人だけという決まりだ。
「でも、それだけで――紫乃が、沙耶さんや母まで……?」
全てを言葉にすることはできなかった。けれど遙真は、現実を口にする。
「ご両親があなたの霊力に頼りきりだったのは事実です。そして霊力が尽きた頃合いで、紫乃さんを花の巫女として立てるつもりでいた。しかし、誤算があったんです」
「誤算?」
「紫乃さんは巫女として為すべき修業を放棄していました。神事にも参加しなかったのは、先日お伝えしたとおりです。つまり、巫女になれる資格がない。…花の巫女だったお母様は、それに気づいたのでしょう」
いくら溺愛する娘でも、霊力がなければ花の巫女として認められない。
「諦めるようにと、諭したのだと思います。そして紫乃さんは、殺人という強硬手段に出た」
「……紗那は……」
「彼女は紫乃さんから、あなたを見張るよう命じられていたそうです。しかし紫乃さんに巫女としての資格がないと気づいてしまった」
だから香で錯乱させ、自殺に見せかけて殺したのだろうと遙真は淡々と告げる。紗那の前に自殺した巫女も、おそらく同じような理由で殺された。
柚羽は、静かに目蓋を閉じる。
心に浮かぶのは、にっこりと笑う無邪気な妹の姿。
『私ね、巫女になったら、お姉ちゃんみたいに綺麗に舞いたいの』
(あの笑顔が嘘だったの?)
「……信じられません……でも……でも、本当に……」
「紫乃さんの部屋に、使用されたとおぼしき毒香があるのは確認済みです」
柚羽は涙を堪えきれなくなった。ぽろぽろと静か涙をこぼす柚羽の肩に、遙真の手がそっと触れる。
「柚羽さん。……あなたのせいではありません。それだけは覚えていてください」
遙真の言葉に答えることができず、柚羽は両手で顔を覆った。