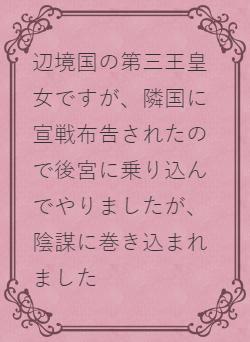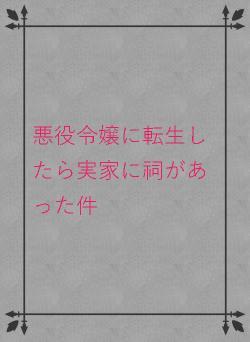柚羽が神坐の離れから姿を消して、三日が過ぎた。
紫乃は部屋の障子を開け放ち、庭に目を向けた。
風は弱く、梔子の枝には、もうほとんど花が残っていない。
その香りが好きだった。濃く甘くて、咲いているだけで空気が満たされるような気がした。
いつもの紫乃なら、美しいと思えたはず。けれど今日は、ただ苛立ちしか湧いてこない。
(どうやって逃げたのよ……)
怒りで喉の奥が焼けるように熱くなる。
「紫乃」
ふらりと入ってきたのは、雅弥だった。
髪は乱れ、その手には半分ほどに減ったワインボトルが握られている。彼は紫乃との婚約が決まった翌日から、御神楽の屋敷に居着いた。そして好き勝手に振る舞い、こうして昼間から酒を飲んでいる。
「まだ怒ってるのか? 別にいいじゃないか。金も持ってないんだし、そのうち帰ってくるさ」
脳天気な言葉に苛立つが、紫乃は感情を殺して微笑む。
「怒ってなんかいませんよ」
仮面を貼り直すように、ゆっくりと口角を上げる。
「むしろ、良かったと思ってるわ。お姉様は自ら巫女としてのお役目から逃げたのだもの」
「お前もだいぶ変わったな。前は何かと柚羽を持ち上げてたじゃないか」
「あら、私は今でもお姉様が好きよ」
うふふと笑う紫乃は、愛らしい。しかしその口から零れるのは冷徹な言葉だ。
「例の件はどうなったの? お姉様が一番「役に立つ」大切なお仕事。しっかりとお約束させたの?」
高遠家の縁者には、何人も資産家がいる。その中でも遠縁の老人は、本家をも凌ぐ資産を有すると噂されていた。
紫乃は、柚羽をその老人に嫁がせるつもりでいる。もちろん、ただ嫁がせるだけではない。
薬で大人しくさせて従わせ、資産を奪い取った後は、二人まとめて「処理」するつもりだ。
その計画を雅弥も知っている。むしろ先んじて動いたのは彼の方だ。
「若い後添いを用意するって持ちかけたら、あっさり遺言状を書き換えたよ。「俺達夫婦に、全財産を譲る」ってな。色ぼけジジイは扱いやすい」
得意げに笑いながら、雅弥は手にしたワインボトルから直接酒をあおる。その口元には、いやらしい色が混じっていた。
「柚羽が戻り次第、ジジイの所へ連れて行く算段は付けてある。お前の得意な「香」で、大人しくさせといてくれよ」
その言葉に、紫乃は何も言わず微笑むだけに留めた。
紫乃は部屋の障子を開け放ち、庭に目を向けた。
風は弱く、梔子の枝には、もうほとんど花が残っていない。
その香りが好きだった。濃く甘くて、咲いているだけで空気が満たされるような気がした。
いつもの紫乃なら、美しいと思えたはず。けれど今日は、ただ苛立ちしか湧いてこない。
(どうやって逃げたのよ……)
怒りで喉の奥が焼けるように熱くなる。
「紫乃」
ふらりと入ってきたのは、雅弥だった。
髪は乱れ、その手には半分ほどに減ったワインボトルが握られている。彼は紫乃との婚約が決まった翌日から、御神楽の屋敷に居着いた。そして好き勝手に振る舞い、こうして昼間から酒を飲んでいる。
「まだ怒ってるのか? 別にいいじゃないか。金も持ってないんだし、そのうち帰ってくるさ」
脳天気な言葉に苛立つが、紫乃は感情を殺して微笑む。
「怒ってなんかいませんよ」
仮面を貼り直すように、ゆっくりと口角を上げる。
「むしろ、良かったと思ってるわ。お姉様は自ら巫女としてのお役目から逃げたのだもの」
「お前もだいぶ変わったな。前は何かと柚羽を持ち上げてたじゃないか」
「あら、私は今でもお姉様が好きよ」
うふふと笑う紫乃は、愛らしい。しかしその口から零れるのは冷徹な言葉だ。
「例の件はどうなったの? お姉様が一番「役に立つ」大切なお仕事。しっかりとお約束させたの?」
高遠家の縁者には、何人も資産家がいる。その中でも遠縁の老人は、本家をも凌ぐ資産を有すると噂されていた。
紫乃は、柚羽をその老人に嫁がせるつもりでいる。もちろん、ただ嫁がせるだけではない。
薬で大人しくさせて従わせ、資産を奪い取った後は、二人まとめて「処理」するつもりだ。
その計画を雅弥も知っている。むしろ先んじて動いたのは彼の方だ。
「若い後添いを用意するって持ちかけたら、あっさり遺言状を書き換えたよ。「俺達夫婦に、全財産を譲る」ってな。色ぼけジジイは扱いやすい」
得意げに笑いながら、雅弥は手にしたワインボトルから直接酒をあおる。その口元には、いやらしい色が混じっていた。
「柚羽が戻り次第、ジジイの所へ連れて行く算段は付けてある。お前の得意な「香」で、大人しくさせといてくれよ」
その言葉に、紫乃は何も言わず微笑むだけに留めた。