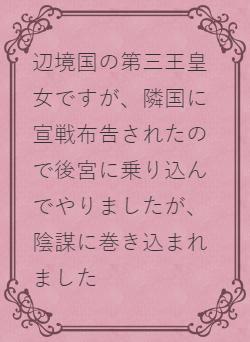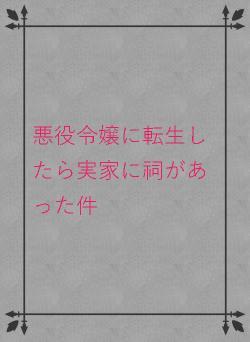真実を知った翌日、柚羽は床に伏せた。
熱が出たわけではない。ただ、身体が動かなくなったのだ。
心が先に疲れ果ててしまったのだと、後になって分かった。
目を覚ますと、窓からやわらかな朝の光が差し込んでいた。
そばには誰かが座っていて、その人影は布を水桶に浸しているところだった。
「……遙真さん……?」
声をかけると、遙真は少し驚いたように顔を上げた。
「起こしてしまいましたか。すみません、冷やしていたのがぬるくなってしまって」
「いいえ……」
枕元の温もりと気配に、柚羽はなんとなく安堵した。
そのまま短い沈黙が流れたあと、遙真は少し眉を下げる。
「……昨日は、疲れているあなたに、ひどい話を聞かせてしまった。父に叱られました。「気遣いが足りない」と」
柚羽はゆっくり首を横に振った。
「そんなことありません。ありがとうございます。……本当のことを、教えてくださって」
言葉を絞るようにしてそう返したとき、自分の中に少しずつ見えない力が戻ってくるのを感じた。
何も知らされずに壊れていくより、苦しくても「真実に触れている」ほうがずっと楽だった。
遙真は、その言葉を遮ることなく聞いてくれた。
柚羽は、彼の顔をしばらく見つめていた。
どこかで見たような、けれど知らないはずの穏やかさ。
ほんの少し、目をそらすのが惜しくなるような、静かなまなざしだった。
***
継杜家での暮らしは、穏やかに過ぎていく。
神事もない、祝詞を捧げる必要もない日々。
することといえば三度の食事と散歩だけ――しかし、かえって落ち着かない。
せめて庭の手入れの手伝いをしたいと遙真に頼み、ようやく許してもらった。
「朝は小鳥の声がよく聞こえるんです」
「実を付ける木が植えてありますから、それを目当てで来るのでしょう」
柚羽は遙真と並んで座り、他愛ない会話を交わす。そんな時間が自然と増えていった。
「柚羽さんが元気になってよかった」
「はい。たぶん……ちゃんと食べて、寝たからです」
「それも大切です。巫女であっても、人であることに変わりはありませんから」
気取ったところのない自然な口調だった。
柚羽の霊力は、まだ戻らない。それでも遙真は、修行を再開しろなどと急かすことはなかった。ただ側にいて、寄り添ってくれる。
家族以外の男性と二人きりで話すなんて、柚羽にとっては初めてだ。なのに遙真とは、穏やかな気持ちで話ができる。
遙真が「柚羽さん」と呼ぶと胸の奥がふわりと温かくなる。自分の胸に芽生えたこの気持ちが何かは、まだ分からない。けれど、嫌ではないと思えた。
***
数日が過ぎた頃のこと。柚羽が庭木の手入れを終え離れの廊下を通りかかったとき、書院から低い声が漏れているのが聞こえた。
「――御神楽家の内情については、星見の報告と一致しています。すでに兆候は出ていたと」
「禰宜の一部は、神楽の手順すら把握していないようだ。巫女の実働記録と照らし合わせると、やはり偏りが大きい」
話していたのは遙真ではなかったが、その声に彼の名が出た。
「遙真様には、引き続き調査をお任せします」
――様。
柚羽は、その呼び名に立ち止まった。
彼がこの家で何らかの立場を持っていることを、柚羽は理解する。
(私、遙真さんのこと何も知らない)
助けてもらい、こうして継杜家で正当な客人並みの歓待を受けている。「花の巫女」は地域社会にとっては特別な存在だが、全ての社を統括する継杜家からすれば特別扱いする相手ではない。
こうして柚羽が休養していられるのは、遙真が何かしら家人に指示をしているからだろう。
扉の奥ではまだ話し声が続いていたが、柚羽はそれ以上聞こうとはしなかった。
足音を立てないように、庭へと向かう。
(遙真さんに……聞いてもいいのかな)
けれど、問いかけた瞬間に何かが壊れてしまいそうな気がして。
その日は、何も言えなかった。
熱が出たわけではない。ただ、身体が動かなくなったのだ。
心が先に疲れ果ててしまったのだと、後になって分かった。
目を覚ますと、窓からやわらかな朝の光が差し込んでいた。
そばには誰かが座っていて、その人影は布を水桶に浸しているところだった。
「……遙真さん……?」
声をかけると、遙真は少し驚いたように顔を上げた。
「起こしてしまいましたか。すみません、冷やしていたのがぬるくなってしまって」
「いいえ……」
枕元の温もりと気配に、柚羽はなんとなく安堵した。
そのまま短い沈黙が流れたあと、遙真は少し眉を下げる。
「……昨日は、疲れているあなたに、ひどい話を聞かせてしまった。父に叱られました。「気遣いが足りない」と」
柚羽はゆっくり首を横に振った。
「そんなことありません。ありがとうございます。……本当のことを、教えてくださって」
言葉を絞るようにしてそう返したとき、自分の中に少しずつ見えない力が戻ってくるのを感じた。
何も知らされずに壊れていくより、苦しくても「真実に触れている」ほうがずっと楽だった。
遙真は、その言葉を遮ることなく聞いてくれた。
柚羽は、彼の顔をしばらく見つめていた。
どこかで見たような、けれど知らないはずの穏やかさ。
ほんの少し、目をそらすのが惜しくなるような、静かなまなざしだった。
***
継杜家での暮らしは、穏やかに過ぎていく。
神事もない、祝詞を捧げる必要もない日々。
することといえば三度の食事と散歩だけ――しかし、かえって落ち着かない。
せめて庭の手入れの手伝いをしたいと遙真に頼み、ようやく許してもらった。
「朝は小鳥の声がよく聞こえるんです」
「実を付ける木が植えてありますから、それを目当てで来るのでしょう」
柚羽は遙真と並んで座り、他愛ない会話を交わす。そんな時間が自然と増えていった。
「柚羽さんが元気になってよかった」
「はい。たぶん……ちゃんと食べて、寝たからです」
「それも大切です。巫女であっても、人であることに変わりはありませんから」
気取ったところのない自然な口調だった。
柚羽の霊力は、まだ戻らない。それでも遙真は、修行を再開しろなどと急かすことはなかった。ただ側にいて、寄り添ってくれる。
家族以外の男性と二人きりで話すなんて、柚羽にとっては初めてだ。なのに遙真とは、穏やかな気持ちで話ができる。
遙真が「柚羽さん」と呼ぶと胸の奥がふわりと温かくなる。自分の胸に芽生えたこの気持ちが何かは、まだ分からない。けれど、嫌ではないと思えた。
***
数日が過ぎた頃のこと。柚羽が庭木の手入れを終え離れの廊下を通りかかったとき、書院から低い声が漏れているのが聞こえた。
「――御神楽家の内情については、星見の報告と一致しています。すでに兆候は出ていたと」
「禰宜の一部は、神楽の手順すら把握していないようだ。巫女の実働記録と照らし合わせると、やはり偏りが大きい」
話していたのは遙真ではなかったが、その声に彼の名が出た。
「遙真様には、引き続き調査をお任せします」
――様。
柚羽は、その呼び名に立ち止まった。
彼がこの家で何らかの立場を持っていることを、柚羽は理解する。
(私、遙真さんのこと何も知らない)
助けてもらい、こうして継杜家で正当な客人並みの歓待を受けている。「花の巫女」は地域社会にとっては特別な存在だが、全ての社を統括する継杜家からすれば特別扱いする相手ではない。
こうして柚羽が休養していられるのは、遙真が何かしら家人に指示をしているからだろう。
扉の奥ではまだ話し声が続いていたが、柚羽はそれ以上聞こうとはしなかった。
足音を立てないように、庭へと向かう。
(遙真さんに……聞いてもいいのかな)
けれど、問いかけた瞬間に何かが壊れてしまいそうな気がして。
その日は、何も言えなかった。