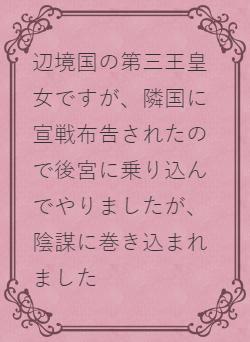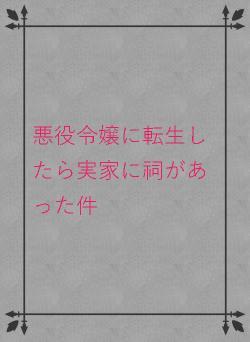翌朝、遙真が現れたのは朝餉を終えた頃だった。
「昨夜は、よく眠れましたか」
「はい…」
それが嘘ではないことに、自分でも驚いた。
「少し話をしましょう」
遙真に促され、柚羽は彼の執務室らしい部屋に案内される。彼はソファに座るよう柚羽を促し、自らもテーブルを挟んで座ると静かに話を始めた。
「御神楽家にいた頃、神事の記録をご覧になりましたか?」
「記録、ですか?」
「ええ。あなたがどの神楽を、どの月に舞ったか。誰が補佐に入ったか。そういった記録です」
柚羽は首を横に振った。
「記録は父が管理してて。私が見ることはありませんでした」
「やはり」
遙真の顔に、わずかに影が差した。
「柚羽様。あなたはこれまで、「花の巫女候補」として毎月三〜五回、神楽を舞ってこられたそうですね」
「でもそれは皆も――紫乃も、他の巫女たちも交代でした」
「いえ。紫乃様を含む他の巫女見習いは、ほとんど神前に立っていません。補佐に入った記録すら極めて少ない」
柚羽は言葉を失った。
「確認できただけでも、あなたが単独で神楽を舞った回数は、この五年間で三十二回。補佐もおらず、体調不良の際も休まずに舞われていたと」
「…でもそれは……巫女として、当然の……」
「当然ではありません」
遙真の声は、はっきりとしていた。
「御神楽家では、あなたの霊力を「尽きるまで使う」という方針だったようです。……霊力が弱まったのではなく、「使いすぎていた」。私はそう考えています」
ずっと見ない振りをしていた気がする。遙真の指摘に、胸の奥がつきりと痛んだ。
「…わたし…は……」
これまでずっと信じていた「当たり前」が、根元から崩れていく感覚に、体の奥が冷えるようだった。
「普通だと思っていました。皆、同じくらい働いているって。そう、思ってたんです」
否定も肯定もせず遙真は黙って聞いている。それが不思議と、柚羽には嬉しく感じられた。
「昨夜は、よく眠れましたか」
「はい…」
それが嘘ではないことに、自分でも驚いた。
「少し話をしましょう」
遙真に促され、柚羽は彼の執務室らしい部屋に案内される。彼はソファに座るよう柚羽を促し、自らもテーブルを挟んで座ると静かに話を始めた。
「御神楽家にいた頃、神事の記録をご覧になりましたか?」
「記録、ですか?」
「ええ。あなたがどの神楽を、どの月に舞ったか。誰が補佐に入ったか。そういった記録です」
柚羽は首を横に振った。
「記録は父が管理してて。私が見ることはありませんでした」
「やはり」
遙真の顔に、わずかに影が差した。
「柚羽様。あなたはこれまで、「花の巫女候補」として毎月三〜五回、神楽を舞ってこられたそうですね」
「でもそれは皆も――紫乃も、他の巫女たちも交代でした」
「いえ。紫乃様を含む他の巫女見習いは、ほとんど神前に立っていません。補佐に入った記録すら極めて少ない」
柚羽は言葉を失った。
「確認できただけでも、あなたが単独で神楽を舞った回数は、この五年間で三十二回。補佐もおらず、体調不良の際も休まずに舞われていたと」
「…でもそれは……巫女として、当然の……」
「当然ではありません」
遙真の声は、はっきりとしていた。
「御神楽家では、あなたの霊力を「尽きるまで使う」という方針だったようです。……霊力が弱まったのではなく、「使いすぎていた」。私はそう考えています」
ずっと見ない振りをしていた気がする。遙真の指摘に、胸の奥がつきりと痛んだ。
「…わたし…は……」
これまでずっと信じていた「当たり前」が、根元から崩れていく感覚に、体の奥が冷えるようだった。
「普通だと思っていました。皆、同じくらい働いているって。そう、思ってたんです」
否定も肯定もせず遙真は黙って聞いている。それが不思議と、柚羽には嬉しく感じられた。