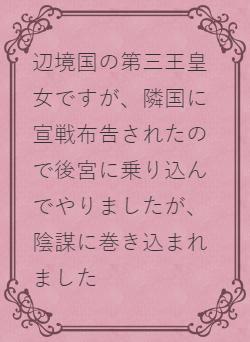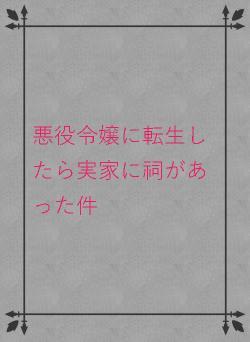初夏の朝、まだ露を含む風が静かに吹くなか――御神楽柚羽は神前に立ち、花の神楽を舞った。
白と淡紅を幾重にも重ねた巫女装束が、そよぐ風を受けて柔らかく揺れる。
背中の中程で束ねられた黒髪は、陽の光を受けて美しく煌めく。
細やかな動きひとつにも意味があり、祝詞の一音が神に届くよう祈る。
緊張を抱きながら、柚羽は一心に舞った。
そして、それは唐突に終わる。
ドスン、と高いところから何かを投げ落としたような音と、それに続くのは甲高い悲鳴。
拍手の音も、太鼓も、祈りの声も消え、嫌な沈黙が場を満たす。
まず動いたのは、外周で見守っていた禰宜の男衆だ。彼らは音のした拝殿の外へと駆けていく。
「……人が!」
「飛び降りだ……っ!」
誰かが叫ぶ声と、更なる悲鳴が重なった。
その声に柚羽ははっとして我に返り、周囲の目もお構いなしに神楽殿から降りて禰宜達のいる方に向かう。
神座の塔の下に、血の花が咲いていた。
人々が駆け寄り、ざわめきが広がる。
見下ろすように高くそびえる塔の上階は、巫女とその補佐の者しか入れない。
落ちたのは、柚羽の側仕え沙耶だった。
柚羽はその場に立ち尽くしていた。
寒さに震えるわけでも、恐怖で足がすくんだわけでもない。
ただ舞の余韻と、沙耶の血が撒き散らされた石畳の現実が、どうしても結びつかなかった。
(どうして?……今朝、この装束を整えてくれた時には、普通だったのに)
声も出せずその場に座り込んだ柚羽が沙耶の遺体に触れようとしたその時、透き通るような声が割って入る。
「いけませんお姉様。穢れが……!」
妹の紫乃だった。
声を聞いた禰宜達が弾かれたように動き、柚羽を遺体から引き離す。
巫女として、死の穢れは避けなければならない。
「親しくしていた紗那がこんなことになって、悲しむおお気持ちは分かります。ですがお役目を忘れないでください」
目に涙を浮かべながら諭す紫乃に柚羽も我に返った。
「……そう、ね」
頷くと紫乃が労るように柚羽の手を握る。
柚羽と同じ御神楽家の巫女としての血を引き、けれど誰よりも人々に慕われる妹。
亜麻色の髪に大きな瞳。凜として可愛げがないなんて陰口を叩かれる自分とは違う愛らしい容姿を持つ紫乃。
巫女としての素質は、たしかにある。
舞の所作も祝詞の声も、美しく整っていた。
けれど、柚羽は知っていた。紫乃は、あの過酷な修行に耐えられるような気質ではない。
それを続けさせれば、きっと壊れてしまう。
だからこそ、自分が前に立つしかないのだと。
しかし周囲の考えは違うらしい。取り乱した自分に向けられるのは、呆れたような視線ばかりだった。
「紫乃様は落ちついていらっしゃる」
「やっぱり、花の巫女には紫乃様のほうが――」
「柚羽様は、やはり「死の巫女」だったのでは……」
ひそひそと交わされる声が、ざわめきとなって広がっていく。
冷たい言葉が、柚羽の背に突き刺さるようだった。
白と淡紅を幾重にも重ねた巫女装束が、そよぐ風を受けて柔らかく揺れる。
背中の中程で束ねられた黒髪は、陽の光を受けて美しく煌めく。
細やかな動きひとつにも意味があり、祝詞の一音が神に届くよう祈る。
緊張を抱きながら、柚羽は一心に舞った。
そして、それは唐突に終わる。
ドスン、と高いところから何かを投げ落としたような音と、それに続くのは甲高い悲鳴。
拍手の音も、太鼓も、祈りの声も消え、嫌な沈黙が場を満たす。
まず動いたのは、外周で見守っていた禰宜の男衆だ。彼らは音のした拝殿の外へと駆けていく。
「……人が!」
「飛び降りだ……っ!」
誰かが叫ぶ声と、更なる悲鳴が重なった。
その声に柚羽ははっとして我に返り、周囲の目もお構いなしに神楽殿から降りて禰宜達のいる方に向かう。
神座の塔の下に、血の花が咲いていた。
人々が駆け寄り、ざわめきが広がる。
見下ろすように高くそびえる塔の上階は、巫女とその補佐の者しか入れない。
落ちたのは、柚羽の側仕え沙耶だった。
柚羽はその場に立ち尽くしていた。
寒さに震えるわけでも、恐怖で足がすくんだわけでもない。
ただ舞の余韻と、沙耶の血が撒き散らされた石畳の現実が、どうしても結びつかなかった。
(どうして?……今朝、この装束を整えてくれた時には、普通だったのに)
声も出せずその場に座り込んだ柚羽が沙耶の遺体に触れようとしたその時、透き通るような声が割って入る。
「いけませんお姉様。穢れが……!」
妹の紫乃だった。
声を聞いた禰宜達が弾かれたように動き、柚羽を遺体から引き離す。
巫女として、死の穢れは避けなければならない。
「親しくしていた紗那がこんなことになって、悲しむおお気持ちは分かります。ですがお役目を忘れないでください」
目に涙を浮かべながら諭す紫乃に柚羽も我に返った。
「……そう、ね」
頷くと紫乃が労るように柚羽の手を握る。
柚羽と同じ御神楽家の巫女としての血を引き、けれど誰よりも人々に慕われる妹。
亜麻色の髪に大きな瞳。凜として可愛げがないなんて陰口を叩かれる自分とは違う愛らしい容姿を持つ紫乃。
巫女としての素質は、たしかにある。
舞の所作も祝詞の声も、美しく整っていた。
けれど、柚羽は知っていた。紫乃は、あの過酷な修行に耐えられるような気質ではない。
それを続けさせれば、きっと壊れてしまう。
だからこそ、自分が前に立つしかないのだと。
しかし周囲の考えは違うらしい。取り乱した自分に向けられるのは、呆れたような視線ばかりだった。
「紫乃様は落ちついていらっしゃる」
「やっぱり、花の巫女には紫乃様のほうが――」
「柚羽様は、やはり「死の巫女」だったのでは……」
ひそひそと交わされる声が、ざわめきとなって広がっていく。
冷たい言葉が、柚羽の背に突き刺さるようだった。