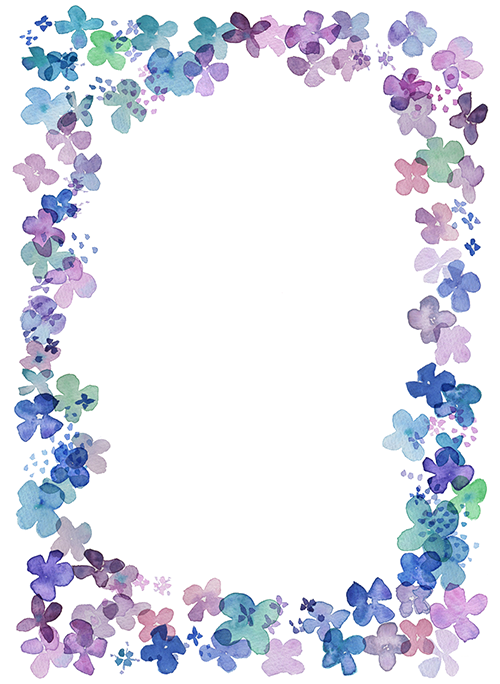6月の第一日曜日。テストの足音が近づいて来たその日、俺達は「芸術文化祭」の会場にいた。部活の一環で、芸術文化祭の作品を見るために。日曜日を潰して出かける、というのはちょっと気が乗らない。けれども先輩がいるから。芸術文化祭は学校の最寄り駅から3駅ほど離れたホールで行われる。展覧会の会場になったり、合唱コンクールが催されたり、兄貴の成人式もそこでやるくらいの大きめのホール。先輩の作品は優秀作品として、展示されていた。
「それじゃあ今日はお疲れ様でした。気を付けて帰ってくださいね」
本田先生の言葉と共に、解散する。スマートフォンの電源を入れて時間を確認する。14時半。このまま帰ってもいいけれど、少し時間がある。せっかく少し遠くの場所まで来たし……。
先輩はこれからどうするんだろう。俺が先輩に声をかけようとした時だった。
「星原くん」
「は、はいっ!?」
声をかけようとしたと同時に先輩に声をかけられたから、すっとんきょうな声になってしまう。
「この後、もし良かったら一緒に買い物でもいかない?」
「えっと、それっ、て、」
「星原くんが行きたいところがあれば、一緒に行きたいな、と思ってて。そして、もしよかったらその後、一緒にお茶でもしたいと思っていたんだ」
「ぜ、ぜ、是非、お願いしたいです」
「そっかそっか。行きたい場所、ある?」
「と、特には、ないので先輩にお任せします!」
「分かった。それじゃあちょっと文房具を解体から文房具屋さんに行く形でもいい?」
「は、はい!」
14時半。まだ、太陽が空高く登っている。夏の足音が近づく空気を味わいながら、俺達は歩いていた。この時間だから結構人通りが多い。俺は、少し心臓を高鳴らせながら、歩いていた。そして俺達は会館から歩いて少しの大きいデパートへと向かった。存在は知っていたけれども、ここに来るのは初めて。中に入る。なんとなくレトロな雰囲気のあるデパートだった。先輩と俺は3階の文具売り場へと向かった。
先輩は文具売り場でまるで鑑定士のように文具を眺めている。なんだか鑑定士、みたいに見ている。じっと、何かを品定めするように。けれどもその中に、どこか子どもがおもちゃを見るような視線が見える。先輩、文房具、好きなんだなって思った。
「ありがとう。日曜日なのに付き合ってもらって」
「その、こうして、先輩と一緒にお出かけしたかったので、嬉しいです」
「それは嬉しいよ。ここがこのあたりで一番好きな文房具屋なんだ」
「先輩、文房具お好きなんですか?」
「うん。好きだよ。特に筆記具が好きなんだ。万年筆とか。星原くんは文房具にこだわり、はある?」
「俺ですか? 特にこだわりはないですね」
文房具に関しては、書ければいい、という感じだった。夏休みの宿題の粗品で貰った安いプラスチックのシャープペンを使っていたりしている。
「じゃあ、書き心地、みたいなのはあまりこだわりがない感じかな」
「そうですね」
「ボディの色とかに好みは?」
「やっぱりあまりこだわりはないですね。でも、どこかの文房具屋で見た銀色の重たいシャーペンはなんとなくかっこいいな、と思っていましたね」
「それってもしかしてエンゼルのメタルシャーペン?」
先輩はスマートフォンを開いて俺にそれを見せてくれた。記憶の中のシャーペンがそのまま出てくる。
「そうです、それです! すごいですね!」
ぱっと言い当てられるなんて思わなくてびっくりしてしまった。びっくりが残ったまま俺は口にする。
「僕も使ってるんだ。これ。重たい、って有名なんだ」
「そうなんですね!」
「もしよかったら、これ、お揃いにしない?」
「お、お揃いですか!?」
「うん。もし嫌ではなかったら一緒に同じものを持ちたいな、と思っていたんだ。こんな熱心な後輩が入ってくれて、嬉しかったから。それに、部活が一緒だからね、お揃いにしたい、って思ってね」
「……! あ、ありがとうございます……! だ、大事にしますね……!」
俺は戸惑いながらもそう返事をする。そして先輩はうなずくと、シャープペンを購入した。
――
店から出た俺達。先輩といたからあっという間に感じたけれど、結構長居していたみたいで、もうすでに夕陽が沈みかけていた。
「お疲れ様。今日は付き合ってくれてありがとう」
「は、はい。その、こちらこそ、ありがとうございます」
俺は先輩の顔と、文具店のロゴが入った紙袋を交互に眺めてしまう。先輩とお揃い。確か、小澤がしていた。バド部全員でお守りを持つみたいに。まさか、そんなことが出来るとは思わなかった。部活のみんなでお守りを持つ、というよりも、これは、お揃い……、みたいな感じで余計に意識してしまった。
「星原くん」
先輩が俺のことを柔らかく呼んだ。
「な、なんでしょうか?」
「たくさんの作品の中で、僕は、星原くんの作品が、一番好きだった」
「え、えっと、あの、あ、ありがとうございます」
俺が一番好き、じゃなくて、星原くんの作品が一番好き。でも、嬉しい。心臓が跳ねる。先輩は俺が答えると、
「そして、作品だけじゃなくて、書いている星原くんの姿は、素敵だよ」
そう言われて、俺の心臓が跳ねた。今までにないような乱れ方で、ばくばくと、激しく心臓が跳ねる。
「そ、それは、一体……!」
「文章を書いている君の姿はイキイキしていて、眺めていてとても楽しんだ」
「そ、そう、ですか……? 無表情、じゃないですか?」
「そんなことないよ。一生懸命悩んでいたり、楽しみながら書いてくれるのがしっかり分かるよ。星原くんの姿は、とても魅力的だと思っている」
「み、魅力的……」
「うん」
「それにね、星原くんと一緒にいるの、すごく楽しいよ」
「っ……!」
先輩が、俺の方を見ている。夕日に照らされる、先輩の瞳。綺麗だ。誰かにこんな風に、言われたのは始めてだった。俺の心臓が、どくどくと音を立てている。先輩に初めて会った時よりもずっと激しい心臓の音が。今まで抱いていた俺の気持ちに、はっきりと、輪郭がついた気がした。
「また明日、星原くんと会えるのを楽しみにしているよ」
「は、はい……!」
学校の最寄り駅、先輩に手を振る。その間もずっと心臓がばくばくと激しく鼓動して、止まらない。俺の気持ちが、分かったような気がした。読ませてもらった先輩の作品の作品――恋愛小説の登場人物の気持ちと重なった。
俺の先輩に対する気持ちは「好き」なんだ。
――
その日の夜、家に帰って、夜になってからも、ずっと落ち着かなかった。
――たくさんの作品の中で、僕は、星原くんの作品が、一番好きだった
――文章を書いている星原くんの姿はイキイキしていて、眺めていてとても楽しんだ
――そんなことないよ。一生懸命悩んでいたり、楽しみながら書いてくれるのがしっかり分かるよ。星原くんの姿は、とても魅力的だと思っている
――それにね、星原くんと一緒にいるの、すごく楽しいよ
先輩の言葉と、先輩の姿を頭の中で何度も繰り返して、その度にふわふわとした心地になる。 先輩のやっぱり、先輩のことが好きだ……。自分の気持ちがはっきり分かった瞬間だった。
“先輩のことが、好き”
文章作成ソフトの上、そんな文字を、書いて、すぐに消した。恥ずかしくなって。
流石に明日も授業があるから早く寝よう。
ベッドの中に潜りこむ。俺のそばには銀色のシャーペン。先輩に買ってもらった、エンゼルのメタルシャーペン。ひんやりとした感触のボディ。きらきらと鈍く光っているそれは、 なんだか宝石みたいに見えてしまった。
そのまま、目を閉じる。
先輩のことがすき。
綺麗な顔。俺の事を気遣ってくれるところ。優しいところ。俺の作品を好き、って言ってくれるところ……
「俺、先輩のこと、好きなんだなあ……」
口にする。いつも抑揚の薄い声ではあるけれど、なんだか、その声ははっきりと、先輩に対する想いがこもっているような気がした。
「それじゃあ今日はお疲れ様でした。気を付けて帰ってくださいね」
本田先生の言葉と共に、解散する。スマートフォンの電源を入れて時間を確認する。14時半。このまま帰ってもいいけれど、少し時間がある。せっかく少し遠くの場所まで来たし……。
先輩はこれからどうするんだろう。俺が先輩に声をかけようとした時だった。
「星原くん」
「は、はいっ!?」
声をかけようとしたと同時に先輩に声をかけられたから、すっとんきょうな声になってしまう。
「この後、もし良かったら一緒に買い物でもいかない?」
「えっと、それっ、て、」
「星原くんが行きたいところがあれば、一緒に行きたいな、と思ってて。そして、もしよかったらその後、一緒にお茶でもしたいと思っていたんだ」
「ぜ、ぜ、是非、お願いしたいです」
「そっかそっか。行きたい場所、ある?」
「と、特には、ないので先輩にお任せします!」
「分かった。それじゃあちょっと文房具を解体から文房具屋さんに行く形でもいい?」
「は、はい!」
14時半。まだ、太陽が空高く登っている。夏の足音が近づく空気を味わいながら、俺達は歩いていた。この時間だから結構人通りが多い。俺は、少し心臓を高鳴らせながら、歩いていた。そして俺達は会館から歩いて少しの大きいデパートへと向かった。存在は知っていたけれども、ここに来るのは初めて。中に入る。なんとなくレトロな雰囲気のあるデパートだった。先輩と俺は3階の文具売り場へと向かった。
先輩は文具売り場でまるで鑑定士のように文具を眺めている。なんだか鑑定士、みたいに見ている。じっと、何かを品定めするように。けれどもその中に、どこか子どもがおもちゃを見るような視線が見える。先輩、文房具、好きなんだなって思った。
「ありがとう。日曜日なのに付き合ってもらって」
「その、こうして、先輩と一緒にお出かけしたかったので、嬉しいです」
「それは嬉しいよ。ここがこのあたりで一番好きな文房具屋なんだ」
「先輩、文房具お好きなんですか?」
「うん。好きだよ。特に筆記具が好きなんだ。万年筆とか。星原くんは文房具にこだわり、はある?」
「俺ですか? 特にこだわりはないですね」
文房具に関しては、書ければいい、という感じだった。夏休みの宿題の粗品で貰った安いプラスチックのシャープペンを使っていたりしている。
「じゃあ、書き心地、みたいなのはあまりこだわりがない感じかな」
「そうですね」
「ボディの色とかに好みは?」
「やっぱりあまりこだわりはないですね。でも、どこかの文房具屋で見た銀色の重たいシャーペンはなんとなくかっこいいな、と思っていましたね」
「それってもしかしてエンゼルのメタルシャーペン?」
先輩はスマートフォンを開いて俺にそれを見せてくれた。記憶の中のシャーペンがそのまま出てくる。
「そうです、それです! すごいですね!」
ぱっと言い当てられるなんて思わなくてびっくりしてしまった。びっくりが残ったまま俺は口にする。
「僕も使ってるんだ。これ。重たい、って有名なんだ」
「そうなんですね!」
「もしよかったら、これ、お揃いにしない?」
「お、お揃いですか!?」
「うん。もし嫌ではなかったら一緒に同じものを持ちたいな、と思っていたんだ。こんな熱心な後輩が入ってくれて、嬉しかったから。それに、部活が一緒だからね、お揃いにしたい、って思ってね」
「……! あ、ありがとうございます……! だ、大事にしますね……!」
俺は戸惑いながらもそう返事をする。そして先輩はうなずくと、シャープペンを購入した。
――
店から出た俺達。先輩といたからあっという間に感じたけれど、結構長居していたみたいで、もうすでに夕陽が沈みかけていた。
「お疲れ様。今日は付き合ってくれてありがとう」
「は、はい。その、こちらこそ、ありがとうございます」
俺は先輩の顔と、文具店のロゴが入った紙袋を交互に眺めてしまう。先輩とお揃い。確か、小澤がしていた。バド部全員でお守りを持つみたいに。まさか、そんなことが出来るとは思わなかった。部活のみんなでお守りを持つ、というよりも、これは、お揃い……、みたいな感じで余計に意識してしまった。
「星原くん」
先輩が俺のことを柔らかく呼んだ。
「な、なんでしょうか?」
「たくさんの作品の中で、僕は、星原くんの作品が、一番好きだった」
「え、えっと、あの、あ、ありがとうございます」
俺が一番好き、じゃなくて、星原くんの作品が一番好き。でも、嬉しい。心臓が跳ねる。先輩は俺が答えると、
「そして、作品だけじゃなくて、書いている星原くんの姿は、素敵だよ」
そう言われて、俺の心臓が跳ねた。今までにないような乱れ方で、ばくばくと、激しく心臓が跳ねる。
「そ、それは、一体……!」
「文章を書いている君の姿はイキイキしていて、眺めていてとても楽しんだ」
「そ、そう、ですか……? 無表情、じゃないですか?」
「そんなことないよ。一生懸命悩んでいたり、楽しみながら書いてくれるのがしっかり分かるよ。星原くんの姿は、とても魅力的だと思っている」
「み、魅力的……」
「うん」
「それにね、星原くんと一緒にいるの、すごく楽しいよ」
「っ……!」
先輩が、俺の方を見ている。夕日に照らされる、先輩の瞳。綺麗だ。誰かにこんな風に、言われたのは始めてだった。俺の心臓が、どくどくと音を立てている。先輩に初めて会った時よりもずっと激しい心臓の音が。今まで抱いていた俺の気持ちに、はっきりと、輪郭がついた気がした。
「また明日、星原くんと会えるのを楽しみにしているよ」
「は、はい……!」
学校の最寄り駅、先輩に手を振る。その間もずっと心臓がばくばくと激しく鼓動して、止まらない。俺の気持ちが、分かったような気がした。読ませてもらった先輩の作品の作品――恋愛小説の登場人物の気持ちと重なった。
俺の先輩に対する気持ちは「好き」なんだ。
――
その日の夜、家に帰って、夜になってからも、ずっと落ち着かなかった。
――たくさんの作品の中で、僕は、星原くんの作品が、一番好きだった
――文章を書いている星原くんの姿はイキイキしていて、眺めていてとても楽しんだ
――そんなことないよ。一生懸命悩んでいたり、楽しみながら書いてくれるのがしっかり分かるよ。星原くんの姿は、とても魅力的だと思っている
――それにね、星原くんと一緒にいるの、すごく楽しいよ
先輩の言葉と、先輩の姿を頭の中で何度も繰り返して、その度にふわふわとした心地になる。 先輩のやっぱり、先輩のことが好きだ……。自分の気持ちがはっきり分かった瞬間だった。
“先輩のことが、好き”
文章作成ソフトの上、そんな文字を、書いて、すぐに消した。恥ずかしくなって。
流石に明日も授業があるから早く寝よう。
ベッドの中に潜りこむ。俺のそばには銀色のシャーペン。先輩に買ってもらった、エンゼルのメタルシャーペン。ひんやりとした感触のボディ。きらきらと鈍く光っているそれは、 なんだか宝石みたいに見えてしまった。
そのまま、目を閉じる。
先輩のことがすき。
綺麗な顔。俺の事を気遣ってくれるところ。優しいところ。俺の作品を好き、って言ってくれるところ……
「俺、先輩のこと、好きなんだなあ……」
口にする。いつも抑揚の薄い声ではあるけれど、なんだか、その声ははっきりと、先輩に対する想いがこもっているような気がした。