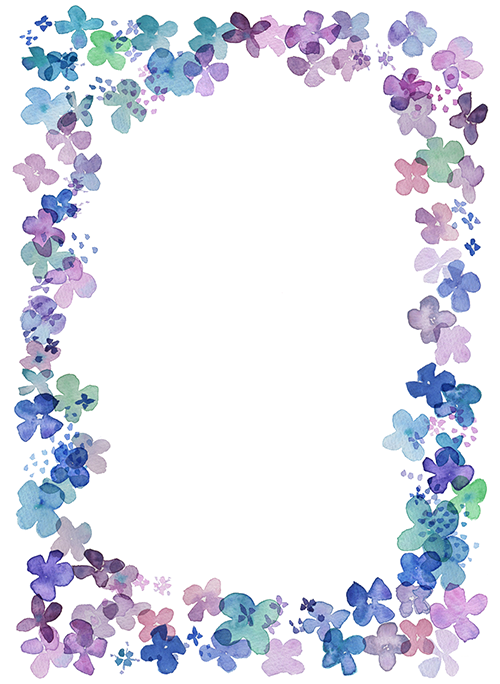歓迎会の次の日、月曜日の部活動。昨日書いた殴り書きのようなメモを印刷したものと照らし合わせて記入していく。あんなに書けなかったプロット表が嘘みたいにするすると埋められていく。
「いい案が思いついたみたいだね」
「は、はい……! 先輩のおかげです。ありがとうございます」
「僕のおかげじゃないよ。星原くんが頑張ったからだよ」
仮のタイトルは直球に「高校生二人がお花見に行く話」にした。プロット表の締め切りは二週間後。と聞くと長いかもしれないけれど、ゴールデンウィークも挟むからあまり時間はない。プロットは顧問の本田先生に見せることになっていた。
作業を初めて5分ほど経った頃だった。先輩に「星原くん」と名前を呼ばれる。
「な、なんでしょうか」
「もしかして手書きよりもパソコンで打つ方が楽かな?」
印刷したプロットを書き写した俺を見た先輩が言う。
「そうですね。この、プロットの前のメモみたいなのはパソコンで作りました」
高校入学以前にも、兄貴のお下がりのパソコンを使わせてもらっていた。もちろん文章を打つというよりは、ネットサーフィンの用途だけれど。あまりがっつり文章を打つ、という経験がなかったからあまり分からなかったけど、文章を打つのはパソコンの方が楽かもしれない。
「それならこっち来てパソコン使う?」
先輩は先輩の隣の席をぽんぽん、と軽く叩く。つまり、これは、俺が先輩の隣に来る、ということ? 俺の身体に緊張が走る。
「え、いいんですか?」
「うん。最新鋭、ではないけれど、文字を打つのには支障がないし、もしよかったらパソコン使って。プロットのテンプレートもあるし、それコピーして入力したらいいと思う」
少し答えはかみ合っていない。俺は先輩の隣に来てもいいんですか、と言う意味でいいんですか、と言ったけれども、先輩は「パソコンを使っていいんですか?」という意味にとったみたいだ。
先輩はニコニコしている、まるで歓迎するように。
「そ、それじゃあ、失礼します」
「はい。いらっしゃい」
そして俺は先輩の隣に座る。ふわっと柔らかいシトラスの匂いがする。多分、制汗剤。俺の体温が上がったのが分かった。それこそ、隣に超有名芸能人が座ってる、みたいな感覚が俺の身体に走っている。俺、この状況で執筆できるかな。心臓の跳ねる鼓動を、静まれ、と頭の中で念じながら、俺は、パソコンの電源を付けて、文字を打ち始めた。少し起動が遅かったけれども、打つことには全く支障がなかった。
「キーボード打つの、早いんだね」
「そ、そうでしょうか……」
高校入学の前は、兄貴のパソコンを使っていたから、打つのは速いほうなのかもしれない。けれどもドキドキに引きずられているのか、いつもよりも打つスピードは遅い。その間に、先輩は、さらさらとペンを動かしている。先輩のペンはなんかすごく高そうな万年筆だった。俺はつい、ペンの方に視線を向けてしまう。
「わ……」
紙のプロット表の上に文字が浮かびあがる。まるで魔法のよう。この様子をSNSのショート動画とかに投稿したら絶対にバズるだろうな、というくらいなめらかで美しい。つい視線を向けてしまう。プロット表を書いている、という動きなのに。この間まで向かい側にいたけれども自分の方のプロットが手一杯で気づかなかった。隣にいるから今、はっきりその綺麗さが分かった。
「どうしたの?」
「せ、先輩、文字、すごく綺麗ですね」
「そうかな? ありがとう」
それこそ文豪の博物館に置いていてもおかしくないくらいの綺麗な文字。つい、じっと眺めていたくなる。けれども、俺もちゃんとやらないといけない。俺もプロット表に向き合って書く作業をする。平常心、と頭の中で唱えて、俺はぱちぱちとキーボードを打ち込んでいく。
『高校生二人がお花見に行く話』の内容は主人公、月山(つきやま)と神山(かみやま)が同じクラスになったことをきっかけに、一緒にお花見に行く話。月山はちょっと俺に似せたところはある。月山はクラスでも目立たない男。神山は超優等生でモテモテのイケメン。
月山がある日神山の落とし物を拾ったことがきっかけで仲良くなる。そして、二人でお花見に行くことになる。そして紆余曲折ありながらも楽しく過ごす、という話だ。
「ふふ」
その時、先輩が微かな笑い声を漏らした。俺は思わず顔を先輩の方に向けてしまう。
「え、えっと。俺、なんか変なこと書いてました?」
「ううん、星原くんの笑顔が素敵だなって思って」
「え、笑顔、ですか……?」
俺は顔をぺたぺたと触る。笑顔になっている自覚が全くなかったからびっくりした。それこそ、「アンドロイドの星原」と言われているのに。
「楽しそうに書いていて、いいね」
「は、はい……」
無表情、とは言われたことがあるけれど、笑顔、になっているとは思っていなかった。
その言葉通り、先輩と二人、楽しくプロットを作っていた。
――
そして4月末。プロットの締め切り日。俺と先輩は職員室の本田先生の元にいた。本田先生にプロットを見てもらうために。文芸部ではプロットを書き終わった段階、そして大まかに書いた段階で一度顧問の本田先生に見てもらう必要がある。
「それじゃあ、まず、成神くんから見せてもらうね。成神くんに対してちょっと話したいことがあるから、一度外に出てもらってもいいかな。終わったらまた呼びに来るから」
「わかりました」
そして俺は一度職員室から出た。その間に俺は本田先生に渡すプロットを何度か眺める。とりあえずこれからどうなるかは分からないけれど形になった、という感じだ。
俺が職員室から出て、10分くらい経った頃に成神先輩が職員室の外に出た俺のことを呼びに来てくれた。
「先輩、お疲れ様です。何のお話をされてたんですか?」
「……えっと、僕のプロットと、そして今後の予定に関しての話、かな」
「そうなんですね、えっと差し支えなければ……」
先輩が言い淀むようにして言ったから、俺は、少し気になって、訊ねようとした。
「ごめんね! 星原くん! もうすぐ緊急の会議が入っちゃいそうで……。ちょっと急いでもらってもいいかな……!」
「あ、す、すみません……!」
けれども、本田先生が少し慌てた様子で俺を呼びに来たから、俺は急いで職員室の中へと入った。
「ごめんね、今から読むからね」
「お、お願いします……!」
先生は眼鏡のツルを持って眼鏡を動かしながら俺のプロット表の文字を眺めている。老眼みたいで、少し見えにくそうだった。
一体どんな評価になるんだろう。書き直し、とかになったりするのかな……。俺は眼鏡を動かしている先生を緊張しながら眺めていた。そして、先生の手が止まり、先生は眼鏡をかけ直す。
「素敵な話だね。それじゃあこれで進めてもらってもいいかな」
「は、はい」
にこりと笑いながら先生は俺にプロット表を返してくれた。だめだ、って突き返されなくて俺は安心する。先生はにこにこしていた。
「ところで、この神山って子、とても魅力的でいいね」
「そ、そうでしょうか」
「うん、すごく生き生き書けてるよ」
「あ、ありがとうございます」
神山は先輩をモデルにしたキャラクター。だから、なんだか褒められるのは、嬉しいような、俺の先輩への想いが出されてなんだか恥ずかしいような、そんな感覚が走った。
その感覚のまま、俺は職員室の外に出る。先輩が待っていてくれた。俺は先輩の元に向かう。
「待っていただいてありがとうございます」
「ううん、大丈夫。プロット、どうだった?」
「はい、OKでした!」
「僕もだよ。それじゃあ、これから部室で書き始めようか」
「わかりました……!」
そして、俺達は本文を書く作業へと移ることになった。先輩の隣、俺は文章をぱちぱちと打ち込んだ。けれども、俺ばかりパソコンを使っていていいのだろうか。
「先輩、あの、パソ……」
俺がそれを訊ねようとした時、先輩は隣にはいなくて、立ち上がっていた。そして、何かを持って席に戻って来る。その何か、を置いた時にどん、と音がした。
「こ、これは……?」
先輩の目の前にあったのは原稿用紙とざら紙だった。それこそ、週刊漫画くらいの熱さがある。
「下書き用のざら紙と原稿用紙だよ。僕はいつもこれに書いて、完成稿を入力しているんだ」
「げ、原稿用紙に……!? 時間かかんないんですか?」
「まあ、時間はかかるけれど、紙に書くのが好きだからね。
そして、先輩は原稿用紙に手描きで原稿を書き始めた。さっきプロット表に書いていたように、原稿用紙の上に隣にいるから余計にそれが見えてしまう。
心地のいい音が部屋の中に響いている。ちら、と先輩の方に視線を向ける。先輩の口角が上がったり、下がったり。なんだか眺めているのが楽しい。感情移入しているのかな。どんな話を書いているのかな。あんまりガン見すると迷惑だろうから、ちらちらと眺めてしまっている。先輩の表情が変わるのを眺めてしまっている。
「ん、星原くん、どうしたの? 何か言いたいことがあったりする?」
「い、いえ、なんでもないです。すみません」
俺は何事もなかったかのようにパソコンの画面に視線を向ける。先輩に気づかれてしまった。ちょっと恥ずかしさ、みたいな感情が出てくる。
「もし何か言いたいことがあったら、作業中でもいつでも話しかけていいからね。おしゃべりを長い時間するのはよくないけど、もし、息抜きとかしたくなったらいつでも言って」
「わかりました。ありがとうございます」
先輩、やっぱり優しいな。美形で優しい。モテるのも分かる気がする。そんな先輩とこうして二人きりでいられるの、やっぱり贅沢だな。と思った。
カリカリとした音。カタカタとしたパソコンのキーボードの音が交わっている。落ち着いた空気が流れている。こうして、先輩と二人で過ごす時間が、楽しかった。
――
締め切りまで残りはあと2週間ほど。部活の中の限られた時間で制作をしているから、先輩とおしゃべりをしている暇はない。先輩がペンを走らせる音と、俺のキーボードの音が響き続けている。
「……」
「……」
けれども、俺のキーボードの音がだんだんと遅くなって、そして、ついには、止まってしまった。
「うーん……」
途中まではすらすら書けていたのに、止まってしまった。展開も、これからどうする、は決まっているのに、何も書けなくなってしまった。プロットはしっかり書いたはずなのに、なんだかしっくり来ない気がして。うまく書けなくなってしまった。
「どうしたの、大丈夫?」
先輩が俺のことを心配してくれた。
「多分、大丈夫です」
きっとこれは一過性のものだと思って、俺はそう答える。
「わかった、何かあったら言ってね」
「ありがとうございます」
けれども、その後も、打ち込んで書いては消し、書いては消し、を繰り返す。こんなに、難しいものだとは思わなかった。プロットも書いたはず。キャラクターもこんな人だ、って分かっているのに。
詰まってしまったのは起承転結の転の部分。仲良くなった月山と神山がお花見に行くことになる。しかし、途中で雨が降ってしまった。雨宿りをする二人。そして、お花見をすることが出来る。その間の展開が全く思いつかなかった。雨が止んでただお花見。を予定していたけれども、それだけだとなんだか物足りなくって。
「ん~……。どうしようか……」
家に帰ってからも、ずっとその事が頭から離れない。お風呂に入っている時も、夜眠る前も、朝ご飯を食べている時も、授業中も、ずーっと、どうしようかを考えてしまっていた。
――
「大丈夫か~?」
目の前で手がひらひらと振られる。その動きで俺は我に返った。アプリが開かれた時みたいに思考が戻ってくる。
「あれ、小澤、どうした?」
「どうした、じゃないって。さっきから話しかけてるのに上の空なままだったから」
「え、ごめん。で、何の話してた?」
「いや、俺の話は別にいいんだけど……。大丈夫か? 体調が悪いのか?」
「体調は大丈夫。その、今書いている小説がなかなか思い浮かばなくって」
「なるほどな~。お前今すげーいい顔してる」
「いい顔? 悩んでるのに?」
小澤は言う。悩んでる顔がいい顔。どういうことだろうか。
「そう。なんか、面白い男になってきた、って感じがする。だって、今までこんな何かに夢中になってたり、こんな真剣な顔になった星原、見たことねえもん」
「そんなに?」
「ああ。そんなに」
小澤はどこか楽しそうに笑っている。友達の変化を見ているのが楽しい、みたいに。あまり意識はしていなかったけれど、もしかしたらそうなのかもしれない。
「いい案が思いついたみたいだね」
「は、はい……! 先輩のおかげです。ありがとうございます」
「僕のおかげじゃないよ。星原くんが頑張ったからだよ」
仮のタイトルは直球に「高校生二人がお花見に行く話」にした。プロット表の締め切りは二週間後。と聞くと長いかもしれないけれど、ゴールデンウィークも挟むからあまり時間はない。プロットは顧問の本田先生に見せることになっていた。
作業を初めて5分ほど経った頃だった。先輩に「星原くん」と名前を呼ばれる。
「な、なんでしょうか」
「もしかして手書きよりもパソコンで打つ方が楽かな?」
印刷したプロットを書き写した俺を見た先輩が言う。
「そうですね。この、プロットの前のメモみたいなのはパソコンで作りました」
高校入学以前にも、兄貴のお下がりのパソコンを使わせてもらっていた。もちろん文章を打つというよりは、ネットサーフィンの用途だけれど。あまりがっつり文章を打つ、という経験がなかったからあまり分からなかったけど、文章を打つのはパソコンの方が楽かもしれない。
「それならこっち来てパソコン使う?」
先輩は先輩の隣の席をぽんぽん、と軽く叩く。つまり、これは、俺が先輩の隣に来る、ということ? 俺の身体に緊張が走る。
「え、いいんですか?」
「うん。最新鋭、ではないけれど、文字を打つのには支障がないし、もしよかったらパソコン使って。プロットのテンプレートもあるし、それコピーして入力したらいいと思う」
少し答えはかみ合っていない。俺は先輩の隣に来てもいいんですか、と言う意味でいいんですか、と言ったけれども、先輩は「パソコンを使っていいんですか?」という意味にとったみたいだ。
先輩はニコニコしている、まるで歓迎するように。
「そ、それじゃあ、失礼します」
「はい。いらっしゃい」
そして俺は先輩の隣に座る。ふわっと柔らかいシトラスの匂いがする。多分、制汗剤。俺の体温が上がったのが分かった。それこそ、隣に超有名芸能人が座ってる、みたいな感覚が俺の身体に走っている。俺、この状況で執筆できるかな。心臓の跳ねる鼓動を、静まれ、と頭の中で念じながら、俺は、パソコンの電源を付けて、文字を打ち始めた。少し起動が遅かったけれども、打つことには全く支障がなかった。
「キーボード打つの、早いんだね」
「そ、そうでしょうか……」
高校入学の前は、兄貴のパソコンを使っていたから、打つのは速いほうなのかもしれない。けれどもドキドキに引きずられているのか、いつもよりも打つスピードは遅い。その間に、先輩は、さらさらとペンを動かしている。先輩のペンはなんかすごく高そうな万年筆だった。俺はつい、ペンの方に視線を向けてしまう。
「わ……」
紙のプロット表の上に文字が浮かびあがる。まるで魔法のよう。この様子をSNSのショート動画とかに投稿したら絶対にバズるだろうな、というくらいなめらかで美しい。つい視線を向けてしまう。プロット表を書いている、という動きなのに。この間まで向かい側にいたけれども自分の方のプロットが手一杯で気づかなかった。隣にいるから今、はっきりその綺麗さが分かった。
「どうしたの?」
「せ、先輩、文字、すごく綺麗ですね」
「そうかな? ありがとう」
それこそ文豪の博物館に置いていてもおかしくないくらいの綺麗な文字。つい、じっと眺めていたくなる。けれども、俺もちゃんとやらないといけない。俺もプロット表に向き合って書く作業をする。平常心、と頭の中で唱えて、俺はぱちぱちとキーボードを打ち込んでいく。
『高校生二人がお花見に行く話』の内容は主人公、月山(つきやま)と神山(かみやま)が同じクラスになったことをきっかけに、一緒にお花見に行く話。月山はちょっと俺に似せたところはある。月山はクラスでも目立たない男。神山は超優等生でモテモテのイケメン。
月山がある日神山の落とし物を拾ったことがきっかけで仲良くなる。そして、二人でお花見に行くことになる。そして紆余曲折ありながらも楽しく過ごす、という話だ。
「ふふ」
その時、先輩が微かな笑い声を漏らした。俺は思わず顔を先輩の方に向けてしまう。
「え、えっと。俺、なんか変なこと書いてました?」
「ううん、星原くんの笑顔が素敵だなって思って」
「え、笑顔、ですか……?」
俺は顔をぺたぺたと触る。笑顔になっている自覚が全くなかったからびっくりした。それこそ、「アンドロイドの星原」と言われているのに。
「楽しそうに書いていて、いいね」
「は、はい……」
無表情、とは言われたことがあるけれど、笑顔、になっているとは思っていなかった。
その言葉通り、先輩と二人、楽しくプロットを作っていた。
――
そして4月末。プロットの締め切り日。俺と先輩は職員室の本田先生の元にいた。本田先生にプロットを見てもらうために。文芸部ではプロットを書き終わった段階、そして大まかに書いた段階で一度顧問の本田先生に見てもらう必要がある。
「それじゃあ、まず、成神くんから見せてもらうね。成神くんに対してちょっと話したいことがあるから、一度外に出てもらってもいいかな。終わったらまた呼びに来るから」
「わかりました」
そして俺は一度職員室から出た。その間に俺は本田先生に渡すプロットを何度か眺める。とりあえずこれからどうなるかは分からないけれど形になった、という感じだ。
俺が職員室から出て、10分くらい経った頃に成神先輩が職員室の外に出た俺のことを呼びに来てくれた。
「先輩、お疲れ様です。何のお話をされてたんですか?」
「……えっと、僕のプロットと、そして今後の予定に関しての話、かな」
「そうなんですね、えっと差し支えなければ……」
先輩が言い淀むようにして言ったから、俺は、少し気になって、訊ねようとした。
「ごめんね! 星原くん! もうすぐ緊急の会議が入っちゃいそうで……。ちょっと急いでもらってもいいかな……!」
「あ、す、すみません……!」
けれども、本田先生が少し慌てた様子で俺を呼びに来たから、俺は急いで職員室の中へと入った。
「ごめんね、今から読むからね」
「お、お願いします……!」
先生は眼鏡のツルを持って眼鏡を動かしながら俺のプロット表の文字を眺めている。老眼みたいで、少し見えにくそうだった。
一体どんな評価になるんだろう。書き直し、とかになったりするのかな……。俺は眼鏡を動かしている先生を緊張しながら眺めていた。そして、先生の手が止まり、先生は眼鏡をかけ直す。
「素敵な話だね。それじゃあこれで進めてもらってもいいかな」
「は、はい」
にこりと笑いながら先生は俺にプロット表を返してくれた。だめだ、って突き返されなくて俺は安心する。先生はにこにこしていた。
「ところで、この神山って子、とても魅力的でいいね」
「そ、そうでしょうか」
「うん、すごく生き生き書けてるよ」
「あ、ありがとうございます」
神山は先輩をモデルにしたキャラクター。だから、なんだか褒められるのは、嬉しいような、俺の先輩への想いが出されてなんだか恥ずかしいような、そんな感覚が走った。
その感覚のまま、俺は職員室の外に出る。先輩が待っていてくれた。俺は先輩の元に向かう。
「待っていただいてありがとうございます」
「ううん、大丈夫。プロット、どうだった?」
「はい、OKでした!」
「僕もだよ。それじゃあ、これから部室で書き始めようか」
「わかりました……!」
そして、俺達は本文を書く作業へと移ることになった。先輩の隣、俺は文章をぱちぱちと打ち込んだ。けれども、俺ばかりパソコンを使っていていいのだろうか。
「先輩、あの、パソ……」
俺がそれを訊ねようとした時、先輩は隣にはいなくて、立ち上がっていた。そして、何かを持って席に戻って来る。その何か、を置いた時にどん、と音がした。
「こ、これは……?」
先輩の目の前にあったのは原稿用紙とざら紙だった。それこそ、週刊漫画くらいの熱さがある。
「下書き用のざら紙と原稿用紙だよ。僕はいつもこれに書いて、完成稿を入力しているんだ」
「げ、原稿用紙に……!? 時間かかんないんですか?」
「まあ、時間はかかるけれど、紙に書くのが好きだからね。
そして、先輩は原稿用紙に手描きで原稿を書き始めた。さっきプロット表に書いていたように、原稿用紙の上に隣にいるから余計にそれが見えてしまう。
心地のいい音が部屋の中に響いている。ちら、と先輩の方に視線を向ける。先輩の口角が上がったり、下がったり。なんだか眺めているのが楽しい。感情移入しているのかな。どんな話を書いているのかな。あんまりガン見すると迷惑だろうから、ちらちらと眺めてしまっている。先輩の表情が変わるのを眺めてしまっている。
「ん、星原くん、どうしたの? 何か言いたいことがあったりする?」
「い、いえ、なんでもないです。すみません」
俺は何事もなかったかのようにパソコンの画面に視線を向ける。先輩に気づかれてしまった。ちょっと恥ずかしさ、みたいな感情が出てくる。
「もし何か言いたいことがあったら、作業中でもいつでも話しかけていいからね。おしゃべりを長い時間するのはよくないけど、もし、息抜きとかしたくなったらいつでも言って」
「わかりました。ありがとうございます」
先輩、やっぱり優しいな。美形で優しい。モテるのも分かる気がする。そんな先輩とこうして二人きりでいられるの、やっぱり贅沢だな。と思った。
カリカリとした音。カタカタとしたパソコンのキーボードの音が交わっている。落ち着いた空気が流れている。こうして、先輩と二人で過ごす時間が、楽しかった。
――
締め切りまで残りはあと2週間ほど。部活の中の限られた時間で制作をしているから、先輩とおしゃべりをしている暇はない。先輩がペンを走らせる音と、俺のキーボードの音が響き続けている。
「……」
「……」
けれども、俺のキーボードの音がだんだんと遅くなって、そして、ついには、止まってしまった。
「うーん……」
途中まではすらすら書けていたのに、止まってしまった。展開も、これからどうする、は決まっているのに、何も書けなくなってしまった。プロットはしっかり書いたはずなのに、なんだかしっくり来ない気がして。うまく書けなくなってしまった。
「どうしたの、大丈夫?」
先輩が俺のことを心配してくれた。
「多分、大丈夫です」
きっとこれは一過性のものだと思って、俺はそう答える。
「わかった、何かあったら言ってね」
「ありがとうございます」
けれども、その後も、打ち込んで書いては消し、書いては消し、を繰り返す。こんなに、難しいものだとは思わなかった。プロットも書いたはず。キャラクターもこんな人だ、って分かっているのに。
詰まってしまったのは起承転結の転の部分。仲良くなった月山と神山がお花見に行くことになる。しかし、途中で雨が降ってしまった。雨宿りをする二人。そして、お花見をすることが出来る。その間の展開が全く思いつかなかった。雨が止んでただお花見。を予定していたけれども、それだけだとなんだか物足りなくって。
「ん~……。どうしようか……」
家に帰ってからも、ずっとその事が頭から離れない。お風呂に入っている時も、夜眠る前も、朝ご飯を食べている時も、授業中も、ずーっと、どうしようかを考えてしまっていた。
――
「大丈夫か~?」
目の前で手がひらひらと振られる。その動きで俺は我に返った。アプリが開かれた時みたいに思考が戻ってくる。
「あれ、小澤、どうした?」
「どうした、じゃないって。さっきから話しかけてるのに上の空なままだったから」
「え、ごめん。で、何の話してた?」
「いや、俺の話は別にいいんだけど……。大丈夫か? 体調が悪いのか?」
「体調は大丈夫。その、今書いている小説がなかなか思い浮かばなくって」
「なるほどな~。お前今すげーいい顔してる」
「いい顔? 悩んでるのに?」
小澤は言う。悩んでる顔がいい顔。どういうことだろうか。
「そう。なんか、面白い男になってきた、って感じがする。だって、今までこんな何かに夢中になってたり、こんな真剣な顔になった星原、見たことねえもん」
「そんなに?」
「ああ。そんなに」
小澤はどこか楽しそうに笑っている。友達の変化を見ているのが楽しい、みたいに。あまり意識はしていなかったけれど、もしかしたらそうなのかもしれない。