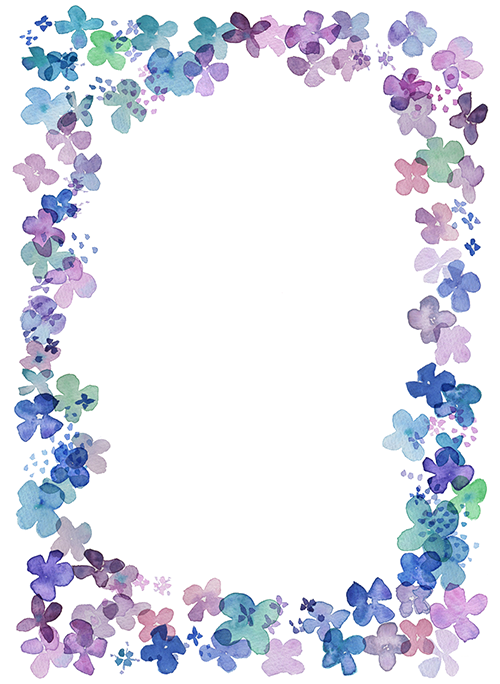ついに日曜日、歓迎会の日を迎えた。
「……5時」
いつも目覚ましの鳴り響く少し前、もしくは鳴ってから起きるのに、今日は随分と早く目を覚ましてしまった。昨日はなんだかどきどきして、上手く眠れなかったのに。まるで遠足の次の日、みたいな感じ。遠足前とかそこそこ楽しみではあったけれど、今まで眠れなくなる、なんてことなかったのに。早く起きたから、いつもよりもずっと早い時間に俺は制服に着替えた。
「歓迎会、は部費を使っているんだ。部活動の一環、ってことになるね。だから、日曜日ではあるけれど、制服を着てきてほしいんだ」
金曜日に先輩に言われていた。その言葉通りに、制服に着替えた俺は、朝ごはんを食べて、そしてスマートフォンを眺めながら時間を潰した。出かける時間になって、俺は玄関へと向かう。9時10分。その時に遅起きした母さんがやって来る。母さんは仕事が休みの日はいつも遅く起きているから。
「あら、春男。制服着てどこ行くの? 今日は休みじゃないの?」
「休みだけど出かけてくる」
「誰と? 小澤くん達と?」
「違う、部活の先輩と一緒に出かけてくる」
俺が部活の先輩、と言った瞬間、母さんは目を丸くした。
「…………えええええっ!?」
母さんは、まるでアニメとか漫画みたいな反応みたいに、数秒遅れて驚いた声を上げる。そして、俺の肩をがっしりと掴む。
「部活!? 春男、部活に入ったの? 帰宅部って言ってたのに!? 何部!?」
「う、うん……、えっと、その、文芸部……」
「文芸部!? 突然どうして……!?」
「い、いや……、まあ、いろいろあって、文章、書きたい、って思って……」
さすがに先輩の話はできないからそう言った。
「そうなのね……! まさかあの無気力でリアクションの薄いなんにも興味もってません、みたいな春男が、自分から部活ねえ……。その先輩、って人に感謝しなきゃ……」
「母さん、なかなか失礼だよそれは」
「ごめんごめん。でも、春男がそんな風に何かやりたいことを見つけるなんて嬉しくって……。文章、書いたら見せてね」
「まあ、そのうち、ね」
母さんはちょっと感動してる感じだ。流石に、俺の思いどーん! みたいなあの文章を母さんに見せるのは少し恥ずかしくて、ぼかすような返事をする。けれども、母さんはなんだか嬉しそうな顔をしていた。
――
待ち合わせ場所の学校の最寄りに着いた。スマートフォンを見る。待ち合わせは10時。気持ちがはやりすぎて、30分も前に着いてしまった。
ちょうどスマートフォンの通知が届いた。
“あと10分くらいで着くよ🚃”
先輩、絵文字使うんだ。なんだか意外。かわいいな。小澤とか父さん母さんも絵文字いっぱいのLIMEを送ってくるのに。そういうのとはまた違った感覚。
そんなことを思いながら、俺は、“はい、分かりました”と俺は随分と味気のない返事を返す。いつもこんな感じ。兄貴には「取引先メールみたいだ」って言われるような感じだ。
そして、しばらくして、先輩がやってきた。柔らかな髪をさらさらと揺らしながらこちらにやってくる。やっぱり綺麗だと思った。
「お疲れ様、星原くん。待たせてごめんね」
背の高い先輩は少しかがんで俺に目を合わせる。濃い琥珀色の瞳が俺に合わせられる。どきどきしてしまった。
「い、いえ、全然待っていません! 大丈夫です!」
うわずった声の俺の答えに先輩は柔らかく笑みを浮かべる。やっぱり、綺麗な人だな、と思った。
「それじゃあ、行こうか」
「は、はい……!」
これからの予定は駅のすぐそばにあるスーパーに行ってお菓子とか飲み物を買うことになっている。
スーパーの中に入った俺達。俺はカートを押しつつ、やっぱり先輩をちらちら見てしまう。俺よりも10センチ以上高い背丈。歩いているとさらさらとなびく髪。本当に王子様みたいで綺麗な人だと思う。あと、最初に助けてくれた時のように、先輩は優しいし俺を気遣ってくれる。俺の先輩に対しての想いになんて名前が付けられるのかは分からない。小澤の言うような推し、なのか、どうなのか。でも、先輩のことを人間として好き、という感情は抱いていた。あと、美しい人だな、ということも。
「星原くん」
「はい、なんでしょうか?」
「星原くんはどんなお菓子が好き?」
「お、お菓子、ですか? お菓子なら、なんでも好きですね。和菓子とか洋菓子とかなんでも。どうしてでしょうか?」
「今日は星原くんの歓迎会だからね。星原くんの好きなお菓子、買いたいなって思って。何がいい、とかある?」
「そ、そうですね。お菓子なら、何でも好きです。和菓子とか、お花見だから、えっと、お団子とか、桜餅とかも、よさそうな気がします。先輩はどういうお菓子が好きでしょう?」
なんか妙に緊張して、ちゃんと言われた答えを返せてないような気がする。けれども先輩はそんな俺を柔らかく見つめて笑う。心臓がドキリとした。
「分かった。じゃあ、普通のお菓子に加えてそういうのも買おうか。僕はみたらし団子が好きかな」
「は、はい。じゃあ、それも、買いましょうか」
どこか緊張しながら返すと、先輩が微笑んでくれた。先輩のこと、推し、かどうかは分からないけれど、ファンサービスを返してもらって喜んでいた小澤の気持ちがちょっと分かる気がした。そしてお菓子とか飲み物とか、あと軽食のおにぎりとかも買って、俺達は駅から徒歩10分の公園へと向かった。
「わ……!」
つい声を出してしまった。綺麗な桜が公園の中を彩っていたから。
公園に辿り着く。桜が公園全体を彩るように咲いていた。この辺りは寒い地方だから、まだ桜がきちんと残っていた。
「綺麗ですね……」
「そうだね。桜、残ってよかった。まるで桜のドームの中にいるみたいだね」
「は、はい。先輩の今の言葉、すごく綺麗な表現ですね」
「ありがとう。そう言ってくれて嬉しいよ」
柔らかく笑う先輩の表情はやっぱり美しくて、俺の心臓が跳ねた。
少し風は強めだけれども。ぽかぽかとしていて、温かな桜の匂いが混ざった空気が俺と先輩を包み込んでいる。春休み中の4月頭がピークだったのか、そこまで混んでもいない。俺達は、公園の真ん中の辺り、桜に囲まれるようにしてレジャーシートを敷いた。
そして、レジャーシートの上に買ってきたものを並べて広げる。スナック菓子におまんじゅう。みたらし団子。あと、おにぎりとかサンドイッチとか、ちょっとした軽食。まるでピクニックみたいだ。そして、並べ終えると、先輩と俺は正座して向かい合った。先輩の濃い琥珀色の瞳がゆらゆらと揺れている。そこにどこかぽーっとした俺の顔が映っている。
「星原くん。改めて、文芸部に入ってくれてありがとう」
「はい。こちらこそ、入部させていただいて、ありがとうございました」
「頑張ってくれてとっても嬉しかったよ。これから、よろしくね」
「は、はい……! よろしくお願いします!」
レジャーシートの上、俺は土下座みたいな感じでよろしくお願いします、を口にした。
「ふふ、なんだか結婚の挨拶みたいだね」
「け、けっこん、ですか……」
先輩の言葉に俺の身体が少し熱くなった。けれども先輩はあまり深い意味がなさそうに笑っていた。俺一人だけ変に意識してるみたいだ。いや、でも、これ、なんて気持ちだろうか。
「それじゃあ、食べようか」
「は、はい」
俺達は、レジャーシートの上に並べた先ほど買ってきたものを食べ始めた。俺はまず最初におにぎりを食べ、先輩はみたらし団子を食べている。一口が小さめ先輩はすごく品のある食べ方をしていて、俺は食べている最中も、ついちらちらと視線を向けてしまった。
「星原くん」
「な、なんでしょうか」
「星原くんは、文章を書くことは、好き?」
「その、まだ、分からないです。読書感想文、みたいな宿題で出されるものはノリノリ、とは真逆でしたし、でも……」
「でも?」
「でも、その、この間、その、テストの文章を書いていた時は、すごく、楽しかったです。そして、これから、もっと書きたいな、とも思っていて……。だから、これから、文章を書くことを、好きになれたらいいなあって思ってます」
俺の答えに先輩は柔らかく口角を上げてくれた。
「嬉しい答え、ありがとう。ものを始めることは“好き”からがいいって言うからね。好きなものを書くのが一番だよ。好きなものを、これからたくさん書いて欲しいな」
「は、はい」
これから俺は、どんな文章を書いていくんだろう。楽しみになった。俺達は買ってきたものを談笑しながら食べていた。そんな中で、俺は一つ気になったことがあった。先輩はどうして文芸部にいて、文章を書いているんだろう、と思った。
「そういえば、先輩は、どうして文章を書かれるんですか?」
「ああ、僕はね……っ……!」
「わっ……!」
先輩は答えを言おうとしたけれども、その声が途中で止まってしまった。俺の口からも、声が出てしまう。びゅうう、と勢いよく、強い風が吹いたから。残っている桜の花びらを全て持っていってしまうのでは、って思うくらいの強い風。
「すごい風でしたね……」
お互い顔を見合わせる。先輩は少しきょとん、としたような表情を俺の方に向けていた。 そして、俺の方に、先輩が身体を近づけ始める。
「えっ……!?」
「ごめんね、ちょっといい?」
俺の身体が硬直する。キス出来るくらいの距離に、先輩の顔と、そして手が近づく。まるで恋愛ドラマのワンシーンみたいに。俺の心拍が、ひどく乱れて、そして、ばくばくと激しく拍動する。俺は思わず目を閉じてしまった。
しばらくして、穏やかな声で「星原くん。大丈夫だよ」と呼ばれた。目を開けると、指先で桜の花びらをつまんだ先輩がいた。
「驚かせてごめんね。星原くんの前髪に桜の花びらがついていたんだ」
「そ、そうだったんですね……、あ、ありがとう、ございました……」
キスでもなんでもなく、俺の前髪についた花びらを取ってくれただけだった。けれども、妙にドキドキしてしまって、ふわふわとした感情になっている。この感情を、そのまま書き記したい、と思った。その後も、談笑を続けていたけれど、「さっきのことを書きたい」で頭がいっぱいになっていた。
歓迎会の時間は甘い感情のままに過ぎていった。
――
「どうだった? 今日」
「はい。すごく、楽しかったです」
「よかったよ。楽しんでもらえて」
先輩は俺の言葉に先輩は目を細める。俺の中には一つ、やりたいことが出てきた。これを言い出すのは少し恥ずかしいかもしれないけれど、やりたい、でいっぱいになっていた。
「あの、先輩」
「ん?」
「その、今日のお花見を元にした話、書いてもいいですか? その、先輩をモデルにしたくて」
さすがに、「先輩に桜の花びらを取ってもらって嬉しかった」をそのまま書くことはできないけれど、先輩と一緒に過ごせて楽しかった、とか食べたものが美味しかった、っていう話とかを、書きたいなって思って。
「もちろん! モデルだなんて光栄だよ。嬉しいな」
「あ、ありがとうございます……!」
書くの楽しみだな。つい少しまで、あんなに詰まっていたのが嘘みたいに、書きたいものがたくさん思い浮かんでいた。
――
俺は帰ってから、高校の入学祝いにもらって、設定だけをした新品のパソコンを開いた。
プロット表は部室においてきてしまったけれども、頭の中に浮かんだものを、一秒でも早く打ち込みたかった。文章作成ソフトを開いて、「お花見」とタイトルを打ち込んだファイルを作成する。小説、とも詩とも言えない、殴り書きメモ、みたいなのを作成する。忘れないうちに作りたい、って思って。
“4月の半ばのある日、僕、が出会ったのは、優しい、男の人だった”
さすがに先輩をそのまま出すのはまずいから、同級生の二人がお花見に行く話を書くことにした。
先輩みたいな文章を。今日の楽しかったことを、先輩みたいな、優しい話を……。
俺の頭の中には、先輩の文章と、先輩の笑顔とか、今日のお花見を一緒に混ぜた柔らかなものがいっぱいになっていた。
「……5時」
いつも目覚ましの鳴り響く少し前、もしくは鳴ってから起きるのに、今日は随分と早く目を覚ましてしまった。昨日はなんだかどきどきして、上手く眠れなかったのに。まるで遠足の次の日、みたいな感じ。遠足前とかそこそこ楽しみではあったけれど、今まで眠れなくなる、なんてことなかったのに。早く起きたから、いつもよりもずっと早い時間に俺は制服に着替えた。
「歓迎会、は部費を使っているんだ。部活動の一環、ってことになるね。だから、日曜日ではあるけれど、制服を着てきてほしいんだ」
金曜日に先輩に言われていた。その言葉通りに、制服に着替えた俺は、朝ごはんを食べて、そしてスマートフォンを眺めながら時間を潰した。出かける時間になって、俺は玄関へと向かう。9時10分。その時に遅起きした母さんがやって来る。母さんは仕事が休みの日はいつも遅く起きているから。
「あら、春男。制服着てどこ行くの? 今日は休みじゃないの?」
「休みだけど出かけてくる」
「誰と? 小澤くん達と?」
「違う、部活の先輩と一緒に出かけてくる」
俺が部活の先輩、と言った瞬間、母さんは目を丸くした。
「…………えええええっ!?」
母さんは、まるでアニメとか漫画みたいな反応みたいに、数秒遅れて驚いた声を上げる。そして、俺の肩をがっしりと掴む。
「部活!? 春男、部活に入ったの? 帰宅部って言ってたのに!? 何部!?」
「う、うん……、えっと、その、文芸部……」
「文芸部!? 突然どうして……!?」
「い、いや……、まあ、いろいろあって、文章、書きたい、って思って……」
さすがに先輩の話はできないからそう言った。
「そうなのね……! まさかあの無気力でリアクションの薄いなんにも興味もってません、みたいな春男が、自分から部活ねえ……。その先輩、って人に感謝しなきゃ……」
「母さん、なかなか失礼だよそれは」
「ごめんごめん。でも、春男がそんな風に何かやりたいことを見つけるなんて嬉しくって……。文章、書いたら見せてね」
「まあ、そのうち、ね」
母さんはちょっと感動してる感じだ。流石に、俺の思いどーん! みたいなあの文章を母さんに見せるのは少し恥ずかしくて、ぼかすような返事をする。けれども、母さんはなんだか嬉しそうな顔をしていた。
――
待ち合わせ場所の学校の最寄りに着いた。スマートフォンを見る。待ち合わせは10時。気持ちがはやりすぎて、30分も前に着いてしまった。
ちょうどスマートフォンの通知が届いた。
“あと10分くらいで着くよ🚃”
先輩、絵文字使うんだ。なんだか意外。かわいいな。小澤とか父さん母さんも絵文字いっぱいのLIMEを送ってくるのに。そういうのとはまた違った感覚。
そんなことを思いながら、俺は、“はい、分かりました”と俺は随分と味気のない返事を返す。いつもこんな感じ。兄貴には「取引先メールみたいだ」って言われるような感じだ。
そして、しばらくして、先輩がやってきた。柔らかな髪をさらさらと揺らしながらこちらにやってくる。やっぱり綺麗だと思った。
「お疲れ様、星原くん。待たせてごめんね」
背の高い先輩は少しかがんで俺に目を合わせる。濃い琥珀色の瞳が俺に合わせられる。どきどきしてしまった。
「い、いえ、全然待っていません! 大丈夫です!」
うわずった声の俺の答えに先輩は柔らかく笑みを浮かべる。やっぱり、綺麗な人だな、と思った。
「それじゃあ、行こうか」
「は、はい……!」
これからの予定は駅のすぐそばにあるスーパーに行ってお菓子とか飲み物を買うことになっている。
スーパーの中に入った俺達。俺はカートを押しつつ、やっぱり先輩をちらちら見てしまう。俺よりも10センチ以上高い背丈。歩いているとさらさらとなびく髪。本当に王子様みたいで綺麗な人だと思う。あと、最初に助けてくれた時のように、先輩は優しいし俺を気遣ってくれる。俺の先輩に対しての想いになんて名前が付けられるのかは分からない。小澤の言うような推し、なのか、どうなのか。でも、先輩のことを人間として好き、という感情は抱いていた。あと、美しい人だな、ということも。
「星原くん」
「はい、なんでしょうか?」
「星原くんはどんなお菓子が好き?」
「お、お菓子、ですか? お菓子なら、なんでも好きですね。和菓子とか洋菓子とかなんでも。どうしてでしょうか?」
「今日は星原くんの歓迎会だからね。星原くんの好きなお菓子、買いたいなって思って。何がいい、とかある?」
「そ、そうですね。お菓子なら、何でも好きです。和菓子とか、お花見だから、えっと、お団子とか、桜餅とかも、よさそうな気がします。先輩はどういうお菓子が好きでしょう?」
なんか妙に緊張して、ちゃんと言われた答えを返せてないような気がする。けれども先輩はそんな俺を柔らかく見つめて笑う。心臓がドキリとした。
「分かった。じゃあ、普通のお菓子に加えてそういうのも買おうか。僕はみたらし団子が好きかな」
「は、はい。じゃあ、それも、買いましょうか」
どこか緊張しながら返すと、先輩が微笑んでくれた。先輩のこと、推し、かどうかは分からないけれど、ファンサービスを返してもらって喜んでいた小澤の気持ちがちょっと分かる気がした。そしてお菓子とか飲み物とか、あと軽食のおにぎりとかも買って、俺達は駅から徒歩10分の公園へと向かった。
「わ……!」
つい声を出してしまった。綺麗な桜が公園の中を彩っていたから。
公園に辿り着く。桜が公園全体を彩るように咲いていた。この辺りは寒い地方だから、まだ桜がきちんと残っていた。
「綺麗ですね……」
「そうだね。桜、残ってよかった。まるで桜のドームの中にいるみたいだね」
「は、はい。先輩の今の言葉、すごく綺麗な表現ですね」
「ありがとう。そう言ってくれて嬉しいよ」
柔らかく笑う先輩の表情はやっぱり美しくて、俺の心臓が跳ねた。
少し風は強めだけれども。ぽかぽかとしていて、温かな桜の匂いが混ざった空気が俺と先輩を包み込んでいる。春休み中の4月頭がピークだったのか、そこまで混んでもいない。俺達は、公園の真ん中の辺り、桜に囲まれるようにしてレジャーシートを敷いた。
そして、レジャーシートの上に買ってきたものを並べて広げる。スナック菓子におまんじゅう。みたらし団子。あと、おにぎりとかサンドイッチとか、ちょっとした軽食。まるでピクニックみたいだ。そして、並べ終えると、先輩と俺は正座して向かい合った。先輩の濃い琥珀色の瞳がゆらゆらと揺れている。そこにどこかぽーっとした俺の顔が映っている。
「星原くん。改めて、文芸部に入ってくれてありがとう」
「はい。こちらこそ、入部させていただいて、ありがとうございました」
「頑張ってくれてとっても嬉しかったよ。これから、よろしくね」
「は、はい……! よろしくお願いします!」
レジャーシートの上、俺は土下座みたいな感じでよろしくお願いします、を口にした。
「ふふ、なんだか結婚の挨拶みたいだね」
「け、けっこん、ですか……」
先輩の言葉に俺の身体が少し熱くなった。けれども先輩はあまり深い意味がなさそうに笑っていた。俺一人だけ変に意識してるみたいだ。いや、でも、これ、なんて気持ちだろうか。
「それじゃあ、食べようか」
「は、はい」
俺達は、レジャーシートの上に並べた先ほど買ってきたものを食べ始めた。俺はまず最初におにぎりを食べ、先輩はみたらし団子を食べている。一口が小さめ先輩はすごく品のある食べ方をしていて、俺は食べている最中も、ついちらちらと視線を向けてしまった。
「星原くん」
「な、なんでしょうか」
「星原くんは、文章を書くことは、好き?」
「その、まだ、分からないです。読書感想文、みたいな宿題で出されるものはノリノリ、とは真逆でしたし、でも……」
「でも?」
「でも、その、この間、その、テストの文章を書いていた時は、すごく、楽しかったです。そして、これから、もっと書きたいな、とも思っていて……。だから、これから、文章を書くことを、好きになれたらいいなあって思ってます」
俺の答えに先輩は柔らかく口角を上げてくれた。
「嬉しい答え、ありがとう。ものを始めることは“好き”からがいいって言うからね。好きなものを書くのが一番だよ。好きなものを、これからたくさん書いて欲しいな」
「は、はい」
これから俺は、どんな文章を書いていくんだろう。楽しみになった。俺達は買ってきたものを談笑しながら食べていた。そんな中で、俺は一つ気になったことがあった。先輩はどうして文芸部にいて、文章を書いているんだろう、と思った。
「そういえば、先輩は、どうして文章を書かれるんですか?」
「ああ、僕はね……っ……!」
「わっ……!」
先輩は答えを言おうとしたけれども、その声が途中で止まってしまった。俺の口からも、声が出てしまう。びゅうう、と勢いよく、強い風が吹いたから。残っている桜の花びらを全て持っていってしまうのでは、って思うくらいの強い風。
「すごい風でしたね……」
お互い顔を見合わせる。先輩は少しきょとん、としたような表情を俺の方に向けていた。 そして、俺の方に、先輩が身体を近づけ始める。
「えっ……!?」
「ごめんね、ちょっといい?」
俺の身体が硬直する。キス出来るくらいの距離に、先輩の顔と、そして手が近づく。まるで恋愛ドラマのワンシーンみたいに。俺の心拍が、ひどく乱れて、そして、ばくばくと激しく拍動する。俺は思わず目を閉じてしまった。
しばらくして、穏やかな声で「星原くん。大丈夫だよ」と呼ばれた。目を開けると、指先で桜の花びらをつまんだ先輩がいた。
「驚かせてごめんね。星原くんの前髪に桜の花びらがついていたんだ」
「そ、そうだったんですね……、あ、ありがとう、ございました……」
キスでもなんでもなく、俺の前髪についた花びらを取ってくれただけだった。けれども、妙にドキドキしてしまって、ふわふわとした感情になっている。この感情を、そのまま書き記したい、と思った。その後も、談笑を続けていたけれど、「さっきのことを書きたい」で頭がいっぱいになっていた。
歓迎会の時間は甘い感情のままに過ぎていった。
――
「どうだった? 今日」
「はい。すごく、楽しかったです」
「よかったよ。楽しんでもらえて」
先輩は俺の言葉に先輩は目を細める。俺の中には一つ、やりたいことが出てきた。これを言い出すのは少し恥ずかしいかもしれないけれど、やりたい、でいっぱいになっていた。
「あの、先輩」
「ん?」
「その、今日のお花見を元にした話、書いてもいいですか? その、先輩をモデルにしたくて」
さすがに、「先輩に桜の花びらを取ってもらって嬉しかった」をそのまま書くことはできないけれど、先輩と一緒に過ごせて楽しかった、とか食べたものが美味しかった、っていう話とかを、書きたいなって思って。
「もちろん! モデルだなんて光栄だよ。嬉しいな」
「あ、ありがとうございます……!」
書くの楽しみだな。つい少しまで、あんなに詰まっていたのが嘘みたいに、書きたいものがたくさん思い浮かんでいた。
――
俺は帰ってから、高校の入学祝いにもらって、設定だけをした新品のパソコンを開いた。
プロット表は部室においてきてしまったけれども、頭の中に浮かんだものを、一秒でも早く打ち込みたかった。文章作成ソフトを開いて、「お花見」とタイトルを打ち込んだファイルを作成する。小説、とも詩とも言えない、殴り書きメモ、みたいなのを作成する。忘れないうちに作りたい、って思って。
“4月の半ばのある日、僕、が出会ったのは、優しい、男の人だった”
さすがに先輩をそのまま出すのはまずいから、同級生の二人がお花見に行く話を書くことにした。
先輩みたいな文章を。今日の楽しかったことを、先輩みたいな、優しい話を……。
俺の頭の中には、先輩の文章と、先輩の笑顔とか、今日のお花見を一緒に混ぜた柔らかなものがいっぱいになっていた。