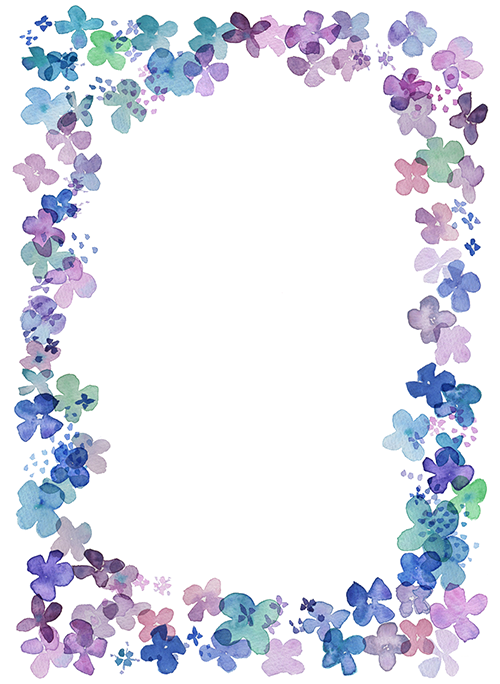書き上げた原稿をリュックサックの中に仕舞い、寝不足のまま、俺は学校へと向かった。
「おはよう……。小澤……」
「あ、星原。おは……」
小澤はおはよう、を途中で止めて、ぎょっとした顔で俺の方に視線を向けた。まあ、そうだと思う。俺の今の顔、多分、「一睡もしてません」みたいな顔だと思うから。
「お、おい……、大丈夫か? クマすごいぞ?」
「いや、まあ、いろいろあって」
「そ、そっか……」
眠いけど、頭の中は、寝不足ハイテンション、って感じで妙に元気ではあった。それでも、一日中、放課後のことを考えてしまっていた。先輩は俺の原稿をどんな風に見てくれるんだろう……。それがひどく気になってしまった。
――
ようやく、という感じの、いつもよりも長く感じるような時間を過ごした後、放課後になった。昨日とはまた別の緊張を味わいながら、文芸部の部室の扉をノックする。
「ほ、星原くん……。いらっしゃい」
出てきた先輩は、随分と驚いた顔をしていた。その驚きは、「本当に書いて来る人がいたんだ」みたいな感じの雰囲気だった。
「原稿、書いてきました。これが、俺の今の精一杯です」
卒業式の証書授与みたいな感じで、俺は書いた原稿を先輩に渡す。
「あ、ありがとう……。それじゃあ、今から読ませてもらうね。部室に入ってもらっていいかな?」
先輩は驚いた顔のまま、俺の原稿を受け取った。
「わ、わかりました」
俺は緊張を含んだまま口にする。そして俺達は昨日と同じように向かい合って座った。そして先輩が「それじゃあ、読ませてもらうね」と言って、俺の原稿を読み始めた。緊張がさらに強まっていく。
「……」
「……」
俺と先輩、それぞれの、ひそめるような息づかいと、先輩がぱさぱさと紙をめくる音だけが、文芸部の部室の中に響いている。先輩は俺の原稿を食い入るようにして見つめている。一文字の抜けもないように、じ、っと。真剣な表情で。
先輩が、読み終わった瞬間、これから、どうなるかが決まる。どうなるんだろう、という緊張はある。でも、結果がどっちにしろ、ちょっとすっきりした気持ちはあった。今まで味わったことのない熱量を、ぶつけられたような気がしたから。小中の卒業式でも全然泣かなかったし、部活も帰宅部だった。行事とかも気を抜いていたわけでもないけれど、全力を注ぐ、みたいな気持ちではなかった気がする。こんな風に達成感を味わったのは、初めてかもしれないから。
そして、先輩は、最後の原稿用紙をぱさ、と一番後ろに持っていく。原稿用紙が、俺が渡した時と同じ順番になる。先輩はなんていうんだろう。
「ふふっ……」
先輩は、緊張を緩ませるようにして、笑い声を漏らした。綺麗に笑っているなあ、と思う。けれども、この笑いに、何を意味するのかは分からない。OKなのかNGなのか。分からない笑み。でも、あの原稿に笑う要素、あった? あまりに下手すぎて、とか? それともあまりにもおかしなことを書いてた、とか?
「そ、その、すみません。下手、でしたよね。それとも何かおかしなことを?」
先輩が笑った理由が分からず、俺は少し混乱しながら先輩に訊ねた。先輩は柔らかく首を横に振った。
「ごめんね、下手、とかおかしなことを書いていたから笑ったんじゃないんだ。素直で、真っ直ぐで、素敵だなあ、って思って」
「え……?」
先輩が原稿を持ったまま立ち上がり、俺の隣に来た。そして、俺にゆっくりと視線を合わせる。穏やかで美しいと間違いなく言い表せる笑み。先輩の濃い琥珀色の瞳に、文芸部の部室に入って来る、夕日の光の色が混ざり合って、夕暮れ時の海のように揺らめいている。息を飲むほどに綺麗だ。
「今まで文芸部に入ろうとテストをした子達は、みんな、何かしらのずるをして、自分の言葉じゃない言葉で紡いでいた。けれども、星原くんは真っ直ぐに頑張って素敵な作品を書いてくれた」
先輩が俺の方にそっと手を伸ばした。そのまま、すう、と柔らかく俺の目の下を撫でた。どきりと俺の心臓が跳ねる。
「こうして、クマを作ってくれるまでに、頑張ってくれたんだね。無理させてしまってごめんね、ありがとう」
そのまま、柔らかく、俺の頬に柔らかく触れる。俺の体温よりも少し冷えた先輩の指の感触が走る。先輩の濃い琥珀色の瞳に映っている俺の姿は、ぽっかりと少し口を開けた、戸惑った表情だった。自分であまりしたことのない表情をしている。そして、全身がぶわりと熱くなっている。
「え、えっとっ……、あの、 先輩!?」
俺はしどろもどろになりながら先輩に問いかけた。あまりに驚いて。自分でもこんな反応したことがない。すると、先輩は少しはっとした表情で、手を離す。俺は先輩に触れられたところを軽く手で押さえる。ひどく熱くなっていた。
「あ、ごめんね。…………。星原くんがこんな風に頑張ってくれたのが嬉しくて。つい。嫌な思いをさせてしまったね」
「そ、そうなんですね。いや、ぜんぜん、嫌じゃ……その、ありがとう、ございます……」
先輩は何かを誤魔化すように言う。俺もどきどきした感情を誤魔化すように答えた。俺ももちゃもちゃと上手く言えないまま口にする。
それは、自分が作ったものを褒められたから嬉しい、のか、こうして憧れの先輩との距離が近づいたからか。それとも、別の気持ちなのか、分からない。名前をどう付ければいいのか分からない気持ち、がさらに名前が付けられなくなっている。そして、先輩は再び文章に視線を向けた。愛おしいものを見るような視線。俺の心臓がどきりと跳ねた。
「それにしても、この、“あなた”はすごく幸せ者だね」
「え……?」
「この文章は、まるで、ラブレターみたいに熱がこもっていてとても素敵だと思ったんだ」
「らっ……!?」
「真っ直ぐに、自分の中のものを煮詰めて作った文章。とても素敵だよ。僕は星原くんの書いた文章をもっと見てみたい、と思った」
「あ、ありがとうございます」
俺は嬉しさと、そして、まだ名前の付けられない気持ちのまま、礼を言うことしかできなかった。
「それで、入部、に関しての話だけど、入部する気持ちはある?」
「は、はい……! あ、あの、その、動機は、先輩に憧れて、だったんですけれど、その、今日この文章を書いてすごく楽しかったので、入りたいです……!」
俺の答えに先輩はにこやかな笑みを浮かべた。
「これから顧問の本田先生のところに行こうと思う。先生がだめって言っても僕から頭を下げて入部させてもらえるようにするよ。でも、この文章だったら、先生もOKしてくれると思う」
「あ、ありがとうございます」
先輩がそんな風に言い切ってくれるとは思わなかった。けれども、そう言ってくれるのは嬉しかった。
そして、俺と先輩は、顧問の本田和宏先生がいる職員室に向かって、本田先生に原稿を渡した。本田先生は国語を担当する穏やかで物腰柔らかなおじいちゃん先生だ。本田先生は俺の原稿をじっと眺めている。さっきの先輩と同じように。職員室の中、緊張が走っていた。
「お疲れ様。よく頑張ったね」
本田先生は原稿を読み終わった後、机の中から先生のはんこが入った入部届けを渡してくれた。
「あ、ありがとうございます……!」
それを俺は記入して、先生に再び手渡す。先生はそれを受け取ってくれた。それは、つまり、俺の入部が正式に決まった、ということだ。
「入部おめでとう。これからよろしくね」
「はい。よろしくお願いします」
文芸部の部室に戻り、俺達は改めて挨拶をした。改めて部室の中をじっと眺めていると、
本棚の中にさっきは気づかなかったけれどもいくつかの冊子があった。文芸部の部誌みたいだ。もしかして先輩の作品もこの中にあるのかもしれない。気になった。
「先輩は、どういった作品を作るんですか?」
「そうだね。星原くんの作品を見たのに、僕の作品を見せないと不公平だよね。僕が書いた作品が載っている部誌、見せるね」
先輩は昨日原稿用紙を出した部室の奥の本棚へと向かう。ここには文芸部のいろいろなものが入っているみたいだ。そして、何か冊子を持って戻ってきた。その冊子には、A4コピー用紙が真ん中で閉じてある冊子。遠足のしおりの豪華版、という感じだ。そこには「セツナ」とか「まんじゅう太郎」とか、おそらくペンネームであろう共に作品のタイトルがあった。先輩の名前、どれだろう。
「先輩のペンネームってどれですか?」
「比翼、という名前が僕のペンネームだよ」
「比翼……。なんだかかっこいいお名前ですね……」
「比翼連理、という言葉があってね。僕の“連理”って名前はそこからつけられたらしい。亡くなった祖父が付けてくれたんだ」
「そうなんですね……」
比翼連理。あまり聞き馴染みのない言葉だ。後で調べよう、と思った。俺は先輩に言われた通り「比翼」という名前のページを開き、読み始めた。
「っ……!?」
瞬間、俺の身体が硬直してしまった。それこそ、俺の身体に強烈な衝撃が走る。先輩と出会った時と同じくらいの強烈な衝撃が。
「どうしたの? 大丈夫?」
「あ、あの、先輩の作品、お家で、じっくり読ませてもらってもいいですか?」
「うん。もちろんいいよ。もしかして、気に入ってくれた?」
「は、はい!」
「そっかそっか。それなら、他の部誌もあるけどどう?」
「は、はい。読みたいです!」
先輩からいくつか部誌を借りる。数日退屈しなさそう、ってくらいの量。
「本格的な部活動は来週からだからね。土日でゆっくり読んでもらえたら嬉しいよ」
「ありがとうございます!」
俺は、家に帰った後、食事と風呂に急いで入って、先輩の作品をじっくりと読んだ。正直、教科書に載っている文章とか、文字が並んでいる本って、退屈なものだって遠ざけてしまっていた。けれども、先輩の作品は、すっごく面白かった。恋愛をテーマにした小説。相手はに面白い作品、読んだことがない、って思うくらいに面白い。そして文章もとてつもなく美しかった。こんな文章を書きたいな、って思うような美しい文章。恋愛、がまだわからないし先輩への想いもわからない。けれども、先輩の文章が、作品が好きだ、ということは確かだった。
「はあ……」
ベッドの上に大の字になる。俺の心臓がすごくドキドキしている。その、先輩本人に対してともまた違うドキドキ。そのドキドキを味わっていたら、俺の身体にあまり味わったことのない感覚が走っていた。そのままぼんやりと天井を見ている。なんだか天井がぼやけている。疲れ目かな。視力は悪いわけじゃないんだけど。
「……。え」
俺の口から間抜けな声が出る。俺の目からつう、と涙がこぼれて、そしてシーツの上に落ちていた。ちょっとびっくりしてしまった。幼稚園とか小学生の頃とかは泣いていたけれど、中学校に上がった頃からは泣くこと、というか大きく感情を動かすこと自体があまりなかった。玉ねぎを切って泣く、とか強い風が吹いて、とかはよくあったけれど、まさか、こんな風に泣くとは思わなかった。
「すごいなあ、先輩」
先輩の作った作品に、先輩に、俺は、知らない感情を教えてもらって、そして、あまり動かない感情を、動かしてもらっている。今日、先輩のところに行ったら、また先輩の作品、読めるかな。今日も部活に行って、先輩の話、読ませてもらおう。
俺は先輩の文章を瞳に焼き付けるようにして、ページを閉じた。比翼、さん。
そこで、俺は先輩の名づけの由来、である「比翼連理」の意味をまだ調べていなかったことを思い出す。
「そういえば、比翼連理、ってどういう意味だろう」
俺はスマートフォンの辞書で検索して調べる。調べるとすぐに出てきた。
「……!」
その文字列を見た瞬間、俺の身体がぶわりと熱くなってしまった。そういう意味があるとは思っていなかったから。
俺、先輩のこと、好きなのかな……。でも、まだ、先輩のことをきちんと知らない。それでも、俺の頭の中で、先輩の姿が浮かんでいた。
次の日。
「大丈夫か?」
教室に入って最初に小澤に言われたことがそれだった。
「な、何が……?」
「なんか、さらに悪化してないか?」
「まあ、ちょっと寝不足で……」
「星原が寝不足……。珍しいな……。テスト勉強とか結構すぐ諦めて寝てたのに」
「ま、まあ、いろいろあって……」
その後、小澤に文芸部に入部することを話した。来週から本格的に部活が始まる、という話もした。
「へえ! よかったじゃん!」
「う、うん……!」
「でもさ、星原、文章あんま興味ない感じだったろ? 着いていけそうなのか?」
「その、あの、入部テストみたいなので文章書いたんだけど、それが、なんか、楽しかったから……。それに、先輩の文章、すごくって……」
「へえ、お前、ほんと先輩ガチ推しって感じだな……」
「え、えっと……、推し、なのかな……。その、憧れって感じで……! その、ほんとにすごい人だから、俺も、先輩みたいな文章書きたいなって……思って」
「そっかそっか……! なんか変わったな! 楽しめよ!」
「うわっ、」
小澤に背中をばしっと叩かれる。楽しんでいる、というか、喝を入れられるというか。なんだか、応援されているかのようで嬉しかった。
本格的な部活動は来週、ではあるけれど、はやる気持ちが抑えられなくて、俺は文芸部の部室へと向かった。今日はまだ仮入部期間、ではあるけれど、先輩に会いに。というか先輩の作品を読んで感じたあの気持ちを伝えずにはいられなくって。口元に笑みが浮かんでいるのが分かる。自分でもこんな表情を浮かべられるなんて思わなかった。
「失礼します……!」
「ほ、星原くん、どうしたの!?」
放課後、部室の入り口、先輩はびっくりしたような表情を浮かべる。本格的な部活動が始まるのは来週の月曜日だから、今日来るとは思っていなかったのかもしれない。
「すみません。突然お邪魔して。あの、先輩、部誌、ありがとうございました! 部誌、本当にすごかったです! 先輩の作品、もっと読ませていただきたいです!」
俺は興奮気味に口にする。今まで、こんな風な話し方、したことがなかったかもしれない。先輩の話がもっと読みたかった。
「だめだよ」
「えっ……」
先輩は眉間に皺を寄せた、少し険しい顔をしながら言う。俺の口から、動揺した声が漏れてしまう。もしかして、俺、まずいことを言ってしまった?
けれども先輩は、険しい表情をすぐに柔らかくして、そのまま、俺に視線を合わせるようにかがむ。かがんだ後、少し手を伸ばして、俺の目の下をそっと撫でた。先輩の体温が伝わってくる。俺の体温がぶわ、と上がるような感覚になる。
「星原くん、今日も寝てないよね? クマ、もっと濃くなってるよ」
「あ、は、はい」
一昨日はあの作品を書いていて寝てなかった。今日は、先輩の作品を書くので寝ていなかった。二日連続でほぼ徹夜状態。小澤にも言われたように。
「僕の作品を褒めてくれたのは嬉しい。でも、やっぱり、ちゃんと休んで欲しいな」
先輩の視線は、小さな子どもに言い聞かせる、みたいな視線で。それでいてひどく優しい視線だった。柔らかな表情。俺の心臓がさらに跳ねる。
「今日はお家に帰って、ゆっくり休んで欲しいな。そしたら、僕の作った作品を他にも読んでもらいたいな」
「あ、ありがとう、ございます!」
「来週、一緒に活動できるのを、楽しみに待ってるよ」
「は、はい」
先輩は俺を気遣うように口にしてくれた。その優しさが、俺の心に染み入るようだった。なんというか、心配されるありがたさと同時に、なんだか、嬉しさみたいな感覚が俺の身体に走っていた。今まで、あまり感じたことのない感覚だった。
「おはよう……。小澤……」
「あ、星原。おは……」
小澤はおはよう、を途中で止めて、ぎょっとした顔で俺の方に視線を向けた。まあ、そうだと思う。俺の今の顔、多分、「一睡もしてません」みたいな顔だと思うから。
「お、おい……、大丈夫か? クマすごいぞ?」
「いや、まあ、いろいろあって」
「そ、そっか……」
眠いけど、頭の中は、寝不足ハイテンション、って感じで妙に元気ではあった。それでも、一日中、放課後のことを考えてしまっていた。先輩は俺の原稿をどんな風に見てくれるんだろう……。それがひどく気になってしまった。
――
ようやく、という感じの、いつもよりも長く感じるような時間を過ごした後、放課後になった。昨日とはまた別の緊張を味わいながら、文芸部の部室の扉をノックする。
「ほ、星原くん……。いらっしゃい」
出てきた先輩は、随分と驚いた顔をしていた。その驚きは、「本当に書いて来る人がいたんだ」みたいな感じの雰囲気だった。
「原稿、書いてきました。これが、俺の今の精一杯です」
卒業式の証書授与みたいな感じで、俺は書いた原稿を先輩に渡す。
「あ、ありがとう……。それじゃあ、今から読ませてもらうね。部室に入ってもらっていいかな?」
先輩は驚いた顔のまま、俺の原稿を受け取った。
「わ、わかりました」
俺は緊張を含んだまま口にする。そして俺達は昨日と同じように向かい合って座った。そして先輩が「それじゃあ、読ませてもらうね」と言って、俺の原稿を読み始めた。緊張がさらに強まっていく。
「……」
「……」
俺と先輩、それぞれの、ひそめるような息づかいと、先輩がぱさぱさと紙をめくる音だけが、文芸部の部室の中に響いている。先輩は俺の原稿を食い入るようにして見つめている。一文字の抜けもないように、じ、っと。真剣な表情で。
先輩が、読み終わった瞬間、これから、どうなるかが決まる。どうなるんだろう、という緊張はある。でも、結果がどっちにしろ、ちょっとすっきりした気持ちはあった。今まで味わったことのない熱量を、ぶつけられたような気がしたから。小中の卒業式でも全然泣かなかったし、部活も帰宅部だった。行事とかも気を抜いていたわけでもないけれど、全力を注ぐ、みたいな気持ちではなかった気がする。こんな風に達成感を味わったのは、初めてかもしれないから。
そして、先輩は、最後の原稿用紙をぱさ、と一番後ろに持っていく。原稿用紙が、俺が渡した時と同じ順番になる。先輩はなんていうんだろう。
「ふふっ……」
先輩は、緊張を緩ませるようにして、笑い声を漏らした。綺麗に笑っているなあ、と思う。けれども、この笑いに、何を意味するのかは分からない。OKなのかNGなのか。分からない笑み。でも、あの原稿に笑う要素、あった? あまりに下手すぎて、とか? それともあまりにもおかしなことを書いてた、とか?
「そ、その、すみません。下手、でしたよね。それとも何かおかしなことを?」
先輩が笑った理由が分からず、俺は少し混乱しながら先輩に訊ねた。先輩は柔らかく首を横に振った。
「ごめんね、下手、とかおかしなことを書いていたから笑ったんじゃないんだ。素直で、真っ直ぐで、素敵だなあ、って思って」
「え……?」
先輩が原稿を持ったまま立ち上がり、俺の隣に来た。そして、俺にゆっくりと視線を合わせる。穏やかで美しいと間違いなく言い表せる笑み。先輩の濃い琥珀色の瞳に、文芸部の部室に入って来る、夕日の光の色が混ざり合って、夕暮れ時の海のように揺らめいている。息を飲むほどに綺麗だ。
「今まで文芸部に入ろうとテストをした子達は、みんな、何かしらのずるをして、自分の言葉じゃない言葉で紡いでいた。けれども、星原くんは真っ直ぐに頑張って素敵な作品を書いてくれた」
先輩が俺の方にそっと手を伸ばした。そのまま、すう、と柔らかく俺の目の下を撫でた。どきりと俺の心臓が跳ねる。
「こうして、クマを作ってくれるまでに、頑張ってくれたんだね。無理させてしまってごめんね、ありがとう」
そのまま、柔らかく、俺の頬に柔らかく触れる。俺の体温よりも少し冷えた先輩の指の感触が走る。先輩の濃い琥珀色の瞳に映っている俺の姿は、ぽっかりと少し口を開けた、戸惑った表情だった。自分であまりしたことのない表情をしている。そして、全身がぶわりと熱くなっている。
「え、えっとっ……、あの、 先輩!?」
俺はしどろもどろになりながら先輩に問いかけた。あまりに驚いて。自分でもこんな反応したことがない。すると、先輩は少しはっとした表情で、手を離す。俺は先輩に触れられたところを軽く手で押さえる。ひどく熱くなっていた。
「あ、ごめんね。…………。星原くんがこんな風に頑張ってくれたのが嬉しくて。つい。嫌な思いをさせてしまったね」
「そ、そうなんですね。いや、ぜんぜん、嫌じゃ……その、ありがとう、ございます……」
先輩は何かを誤魔化すように言う。俺もどきどきした感情を誤魔化すように答えた。俺ももちゃもちゃと上手く言えないまま口にする。
それは、自分が作ったものを褒められたから嬉しい、のか、こうして憧れの先輩との距離が近づいたからか。それとも、別の気持ちなのか、分からない。名前をどう付ければいいのか分からない気持ち、がさらに名前が付けられなくなっている。そして、先輩は再び文章に視線を向けた。愛おしいものを見るような視線。俺の心臓がどきりと跳ねた。
「それにしても、この、“あなた”はすごく幸せ者だね」
「え……?」
「この文章は、まるで、ラブレターみたいに熱がこもっていてとても素敵だと思ったんだ」
「らっ……!?」
「真っ直ぐに、自分の中のものを煮詰めて作った文章。とても素敵だよ。僕は星原くんの書いた文章をもっと見てみたい、と思った」
「あ、ありがとうございます」
俺は嬉しさと、そして、まだ名前の付けられない気持ちのまま、礼を言うことしかできなかった。
「それで、入部、に関しての話だけど、入部する気持ちはある?」
「は、はい……! あ、あの、その、動機は、先輩に憧れて、だったんですけれど、その、今日この文章を書いてすごく楽しかったので、入りたいです……!」
俺の答えに先輩はにこやかな笑みを浮かべた。
「これから顧問の本田先生のところに行こうと思う。先生がだめって言っても僕から頭を下げて入部させてもらえるようにするよ。でも、この文章だったら、先生もOKしてくれると思う」
「あ、ありがとうございます」
先輩がそんな風に言い切ってくれるとは思わなかった。けれども、そう言ってくれるのは嬉しかった。
そして、俺と先輩は、顧問の本田和宏先生がいる職員室に向かって、本田先生に原稿を渡した。本田先生は国語を担当する穏やかで物腰柔らかなおじいちゃん先生だ。本田先生は俺の原稿をじっと眺めている。さっきの先輩と同じように。職員室の中、緊張が走っていた。
「お疲れ様。よく頑張ったね」
本田先生は原稿を読み終わった後、机の中から先生のはんこが入った入部届けを渡してくれた。
「あ、ありがとうございます……!」
それを俺は記入して、先生に再び手渡す。先生はそれを受け取ってくれた。それは、つまり、俺の入部が正式に決まった、ということだ。
「入部おめでとう。これからよろしくね」
「はい。よろしくお願いします」
文芸部の部室に戻り、俺達は改めて挨拶をした。改めて部室の中をじっと眺めていると、
本棚の中にさっきは気づかなかったけれどもいくつかの冊子があった。文芸部の部誌みたいだ。もしかして先輩の作品もこの中にあるのかもしれない。気になった。
「先輩は、どういった作品を作るんですか?」
「そうだね。星原くんの作品を見たのに、僕の作品を見せないと不公平だよね。僕が書いた作品が載っている部誌、見せるね」
先輩は昨日原稿用紙を出した部室の奥の本棚へと向かう。ここには文芸部のいろいろなものが入っているみたいだ。そして、何か冊子を持って戻ってきた。その冊子には、A4コピー用紙が真ん中で閉じてある冊子。遠足のしおりの豪華版、という感じだ。そこには「セツナ」とか「まんじゅう太郎」とか、おそらくペンネームであろう共に作品のタイトルがあった。先輩の名前、どれだろう。
「先輩のペンネームってどれですか?」
「比翼、という名前が僕のペンネームだよ」
「比翼……。なんだかかっこいいお名前ですね……」
「比翼連理、という言葉があってね。僕の“連理”って名前はそこからつけられたらしい。亡くなった祖父が付けてくれたんだ」
「そうなんですね……」
比翼連理。あまり聞き馴染みのない言葉だ。後で調べよう、と思った。俺は先輩に言われた通り「比翼」という名前のページを開き、読み始めた。
「っ……!?」
瞬間、俺の身体が硬直してしまった。それこそ、俺の身体に強烈な衝撃が走る。先輩と出会った時と同じくらいの強烈な衝撃が。
「どうしたの? 大丈夫?」
「あ、あの、先輩の作品、お家で、じっくり読ませてもらってもいいですか?」
「うん。もちろんいいよ。もしかして、気に入ってくれた?」
「は、はい!」
「そっかそっか。それなら、他の部誌もあるけどどう?」
「は、はい。読みたいです!」
先輩からいくつか部誌を借りる。数日退屈しなさそう、ってくらいの量。
「本格的な部活動は来週からだからね。土日でゆっくり読んでもらえたら嬉しいよ」
「ありがとうございます!」
俺は、家に帰った後、食事と風呂に急いで入って、先輩の作品をじっくりと読んだ。正直、教科書に載っている文章とか、文字が並んでいる本って、退屈なものだって遠ざけてしまっていた。けれども、先輩の作品は、すっごく面白かった。恋愛をテーマにした小説。相手はに面白い作品、読んだことがない、って思うくらいに面白い。そして文章もとてつもなく美しかった。こんな文章を書きたいな、って思うような美しい文章。恋愛、がまだわからないし先輩への想いもわからない。けれども、先輩の文章が、作品が好きだ、ということは確かだった。
「はあ……」
ベッドの上に大の字になる。俺の心臓がすごくドキドキしている。その、先輩本人に対してともまた違うドキドキ。そのドキドキを味わっていたら、俺の身体にあまり味わったことのない感覚が走っていた。そのままぼんやりと天井を見ている。なんだか天井がぼやけている。疲れ目かな。視力は悪いわけじゃないんだけど。
「……。え」
俺の口から間抜けな声が出る。俺の目からつう、と涙がこぼれて、そしてシーツの上に落ちていた。ちょっとびっくりしてしまった。幼稚園とか小学生の頃とかは泣いていたけれど、中学校に上がった頃からは泣くこと、というか大きく感情を動かすこと自体があまりなかった。玉ねぎを切って泣く、とか強い風が吹いて、とかはよくあったけれど、まさか、こんな風に泣くとは思わなかった。
「すごいなあ、先輩」
先輩の作った作品に、先輩に、俺は、知らない感情を教えてもらって、そして、あまり動かない感情を、動かしてもらっている。今日、先輩のところに行ったら、また先輩の作品、読めるかな。今日も部活に行って、先輩の話、読ませてもらおう。
俺は先輩の文章を瞳に焼き付けるようにして、ページを閉じた。比翼、さん。
そこで、俺は先輩の名づけの由来、である「比翼連理」の意味をまだ調べていなかったことを思い出す。
「そういえば、比翼連理、ってどういう意味だろう」
俺はスマートフォンの辞書で検索して調べる。調べるとすぐに出てきた。
「……!」
その文字列を見た瞬間、俺の身体がぶわりと熱くなってしまった。そういう意味があるとは思っていなかったから。
俺、先輩のこと、好きなのかな……。でも、まだ、先輩のことをきちんと知らない。それでも、俺の頭の中で、先輩の姿が浮かんでいた。
次の日。
「大丈夫か?」
教室に入って最初に小澤に言われたことがそれだった。
「な、何が……?」
「なんか、さらに悪化してないか?」
「まあ、ちょっと寝不足で……」
「星原が寝不足……。珍しいな……。テスト勉強とか結構すぐ諦めて寝てたのに」
「ま、まあ、いろいろあって……」
その後、小澤に文芸部に入部することを話した。来週から本格的に部活が始まる、という話もした。
「へえ! よかったじゃん!」
「う、うん……!」
「でもさ、星原、文章あんま興味ない感じだったろ? 着いていけそうなのか?」
「その、あの、入部テストみたいなので文章書いたんだけど、それが、なんか、楽しかったから……。それに、先輩の文章、すごくって……」
「へえ、お前、ほんと先輩ガチ推しって感じだな……」
「え、えっと……、推し、なのかな……。その、憧れって感じで……! その、ほんとにすごい人だから、俺も、先輩みたいな文章書きたいなって……思って」
「そっかそっか……! なんか変わったな! 楽しめよ!」
「うわっ、」
小澤に背中をばしっと叩かれる。楽しんでいる、というか、喝を入れられるというか。なんだか、応援されているかのようで嬉しかった。
本格的な部活動は来週、ではあるけれど、はやる気持ちが抑えられなくて、俺は文芸部の部室へと向かった。今日はまだ仮入部期間、ではあるけれど、先輩に会いに。というか先輩の作品を読んで感じたあの気持ちを伝えずにはいられなくって。口元に笑みが浮かんでいるのが分かる。自分でもこんな表情を浮かべられるなんて思わなかった。
「失礼します……!」
「ほ、星原くん、どうしたの!?」
放課後、部室の入り口、先輩はびっくりしたような表情を浮かべる。本格的な部活動が始まるのは来週の月曜日だから、今日来るとは思っていなかったのかもしれない。
「すみません。突然お邪魔して。あの、先輩、部誌、ありがとうございました! 部誌、本当にすごかったです! 先輩の作品、もっと読ませていただきたいです!」
俺は興奮気味に口にする。今まで、こんな風な話し方、したことがなかったかもしれない。先輩の話がもっと読みたかった。
「だめだよ」
「えっ……」
先輩は眉間に皺を寄せた、少し険しい顔をしながら言う。俺の口から、動揺した声が漏れてしまう。もしかして、俺、まずいことを言ってしまった?
けれども先輩は、険しい表情をすぐに柔らかくして、そのまま、俺に視線を合わせるようにかがむ。かがんだ後、少し手を伸ばして、俺の目の下をそっと撫でた。先輩の体温が伝わってくる。俺の体温がぶわ、と上がるような感覚になる。
「星原くん、今日も寝てないよね? クマ、もっと濃くなってるよ」
「あ、は、はい」
一昨日はあの作品を書いていて寝てなかった。今日は、先輩の作品を書くので寝ていなかった。二日連続でほぼ徹夜状態。小澤にも言われたように。
「僕の作品を褒めてくれたのは嬉しい。でも、やっぱり、ちゃんと休んで欲しいな」
先輩の視線は、小さな子どもに言い聞かせる、みたいな視線で。それでいてひどく優しい視線だった。柔らかな表情。俺の心臓がさらに跳ねる。
「今日はお家に帰って、ゆっくり休んで欲しいな。そしたら、僕の作った作品を他にも読んでもらいたいな」
「あ、ありがとう、ございます!」
「来週、一緒に活動できるのを、楽しみに待ってるよ」
「は、はい」
先輩は俺を気遣うように口にしてくれた。その優しさが、俺の心に染み入るようだった。なんというか、心配されるありがたさと同時に、なんだか、嬉しさみたいな感覚が俺の身体に走っていた。今まで、あまり感じたことのない感覚だった。