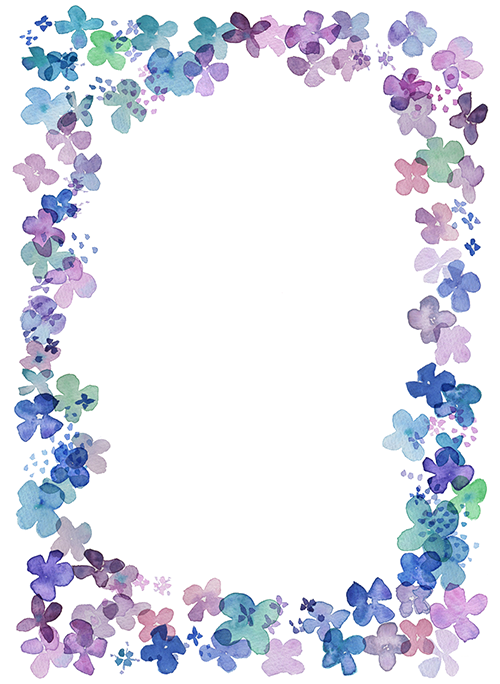小澤が先輩の部活の情報を手に入れてくれた日の放課後、俺は、先輩がいると噂の、校舎から30メートルほど離れた部室棟へと向かっていた。部活見学もあと3日で終わり。あまり惹かれる部活動はなくて、俺は帰宅部のつもりだった。けど、どうしても、先輩に会ってみたくて、俺は文芸部に行くことに決めた。
「大丈夫そうか? オレ、ついてくか? バド部の第二体育館、部室棟のもっと先だからさ」
「だ、大丈夫、一人で行けるから」
「でも、右手と右足一緒に出てるぞ?」
「た、多分、大丈、夫、」
「こんな星原、初めて見たな……。学芸会でも入学式でも運動会でも緊張してなかったのに……。表情筋、別の意味でガチガチだな……。」
「そりゃあ、先輩に会いに行くから……」
「まあ、そうだよな……。俺も、推しの握手会に行く時はめっちゃ緊張するからなあ……」
俺は、運動会の緊張した行進みたいな歩き方で進んでいく。確かに、人生の中でこんなに緊張した瞬間はなかった。運動会も学芸会も、周りが緊張したり盛り上がっている中、やっぱり一人だけ「アンドロイド」みたいな反応をしてしまっていた。
「……でも、貴公子がいる、ってのに、文芸部の話って訊かねえんだよな。不思議なくらい」
「そうなの?」
「入ってる奴の話も、入ろうとしている奴の話も知らないんだよな。貴公子が文芸部にいるって話してた奴もその他の文芸部員のこと知らないみたいで。変な話なんだけど」
「そうなんだ……」
「あ、ただ、なんか揉めてた、みたいな話と、入部するのがめっちゃむずいらしい、みたいなことは言ってた」
「なるほど……」
文芸部。全部の部活動について書かれている部活紹介のパンフレットには、「よろしくお願いします」しか書いていなかった。部活動勧誘を積極的にやってる、って感じでもなかった。人数は3年生が5人、2年生が1人。この1人、が先輩なんだと思う。部員はいるみたい。でも、「うちの部活に入ってください!」みたいな宣伝をしている人を一人も見かけなかった。
「もし、活動方針が合えば入るのか?」
「入る、かもしれない」
「星原、ちなみに文章は好きなのか?」
「わかんないな。小学校くらいの頃のお話づくりは好きだった。けど読書感想文とかは埋めるのがやっと」
「小説書いたりは?」
「授業とかではやった。楽しかった」
「授業以外は?」
「……」
「本が好きとかは」
「漫画とかは読む」
「小説とか新書とかは」
「……」
「完全に先輩目当てって感じだな」
「うん、そうだね」
そんな風に話をしていたら文芸部の部室がある部室棟にたどり着いた。小澤とはここでお別れだ。
「ここだな」
「う、うん。小澤、ここまで着いてきてくれてありがとう」
「ああ! 確か、文芸部の部室は部室棟の三階だ、って言ってた。 じゃあな、頑張れよ!」
「うん」
そして俺は、部室棟の中へと入っていく。辿り着くまでに何度か「カードゲーム部いいですよ!」「手芸部入りませんか!」みたいな歓迎を受けつつ、俺は三階までたどり着いた。
「……ここだ」
三階の端に文芸部室はあった。白い引き戸。「文芸部」と達筆な文字で書いてある木製のプレートが引っかかっているだけ。妙にそこだけ静か。他の部活みたいに勧誘される気配はない。勧誘、どころか歓迎されているような雰囲気もない。本当にここに、すごく人気なあの先輩がいるのだろうか、と思うくらいの静かさ。
俺の身体にそれでも、俺は、もう一度先輩に会ってみたいし、話してみたい。そして、しばらくした後、俺は意を決して、こんこん、と文芸部の扉をノックした。
「はい」
低く柔らかい声の返事が返ってくる。先輩の声。どきどきと心臓が跳ねる。俺が、そのどきどきに浸っていたら、がらりと音がして、扉が開かれた。そして、扉の向こうから出てきたのはあの先輩だった。俺の口から声が漏れてしまう。そして、先輩の視線が俺の方に向けられる。すると、先輩は、柔らかく口角を上げた。
「あ、あの時の1年生くん。学校には慣れた?」
「は、はい……! お、お久しぶりです……! あの時はありがとうございました!」
「とんでもない。元気そうでよかったよ」
先輩、俺のこと、覚えてくれたんだ……! なんだか嬉しくなる。それこそ小澤が推しのアイドルのイベントに行って、「推しが認知してくれた!」みたいに嬉しそうに言っていたのを思い出した。それと同じ気持ちなのかもしれない。表情に出ているかどうかは分からないけれど、俺の口角が上がったのが分かった。
「こんなところまで来て、どうしたの?」
「あの、ぶ、文芸部の見学をしたくて……」
俺の言葉に先輩は少し驚いたような顔をする。そのまま、少し、何かに迷ったかのような表情を浮かべた。けれども、その表情はすぐに再びふわりとした、それこそ、貴公子とか王子様、と言い表せるような笑顔になった。俺の心臓がとくりと甘く跳ねる。
「そっか。それじゃあ話を訊きたいから、入ってもらってもいい?」
「あ、ありがとうございます……!」
先輩の後をついて俺は文芸部の部室に入らせてもらった。
入った瞬間に、紙とインクのような匂いがする。文芸部の部室は普段授業を受けている教室の半分くらいの広さ。白いカーテンで光量は抑えられているけれども日当たりのいい部屋だということが分かる。文芸部の部室の入り口そばには壁に寄せられているようにローラーで動くホワイトボードと本棚がある。部屋の中にはグループ学習をする時みたいに、机が4つくっつけられていた。そのうちの一つ、俺から見て左側の席には、漫画家が使うようなインクの瓶と万年筆らしきペンが置かれていて、その隣にはデスクトップパソコンが置かれていた。文芸部の部室、という感じの空間だった。
「それじゃあ、ここに座ってもらっていいかな?」
「は、はい」
先輩が指差したのは万年筆とインクが乗せられている席の向かい側。先輩は俺と向かい合うようにして座った。
俺は、緊張しながら、すこし俯きがちに先輩を見る。ドキドキしていて、どこを見たらいいのか分からない。挙動不審になってしまう。こうして向かいあっているのは、なんだか二者面談とか面接みたいな構図だ。ただ、二者面談とか面接とかとは別の意味で緊張してしまっている。
「それじゃあ、名前、教えてもらってもいいかな?」
「い、い、1年6組の、ほ、星原春男です。よろしくお願いします!」
「星原くんって言うんだね。僕は2年1組、成神連理(なるかみれんり)。文芸部の部長をしているよ。よろしくね」
「よ、よろしくお願いします」
ぺこりと礼をして、俺は先輩に視線を向ける。きらきらとしたぱっちりとした瞳は部屋の中に入る柔らかな光できらきらと波のように揺れている。柔らかく孤を描く唇。目鼻立ちのはっきりとした造形美、と言わんばかりの顔。改めて見ると本当に綺麗な顔をしていると思うと同時に心臓が跳ねる。今まで芸能人とかアイドルとか「美人だなあ」「かっこいいなあ」と思ったことはあるけれども、こんな感情になったことはなかった。やっぱり、推し、とはまた違った感情なのかもしれない。なんて名前の感情なんだろう。
「それじゃあ、早速この部活に関して説明するね」
「はい。お願いします」
「文芸部はその名前の通り、文章を書く部活。小説やエッセイ、詩や短歌……文章に関係ある創作をするんだ。毎週月曜日から金曜日までこの部室で活動をしているよ。……部活紹介のパンフレットを見ても分かるように籍を置いている部員、は何人かいるけれども今この部室に毎日来ている部員は僕一人かな」
「そうなんですね」
「それで、この部活に来てくれた、ってことは、文章に興味があるってことだよね。星原くんはどんな文章を作りたいの?」
「え、えっと……、あまり、文章には、詳しくなくって。それで、どんな文章を作りたいか、もまだ、分からないんですけれど、そ、その、先輩に、憧れていて、ここに来たんです」
俺は、バカ正直にそんな風に言ってしまった。しどろもどろになっている。こんなこと初めて。嘘でも、いつものように抑揚薄く、「文芸に興味があります」とか言えた方がよかったかもしれない。けれども、先輩を前にして、ひどく緊張していて、そんな風に言う余裕はなくなってしまった。
「……」
俺の答えに、先輩の孤を描いていた唇がすっと真っ直ぐになる。やっぱり、よくなかったよね。こんな邪な理由。
「あ、あの……、すみま、」
「なるほど……。ありがとう。僕に憧れてくれて」
なんだか申し訳なくなってしまって、俺は謝罪の言葉を口にしようとする。けれども、俺の答えを遮るように先輩は言った。ありがとう、という言葉は入っているけれども、その声はなんだかひんやりとしている。やっぱり、動機が不純過ぎるよね……? そして、先輩は立ち上がり、文芸部の部室の中にある本棚を開ける。そして何かを手に取り、戻ってくる。戻ってきた先輩は、その持ってきた何か、を俺の目の前に差し出すようにして置いた。
「え……?」
俺の目の前に置かれたのは、紙の束。原稿用紙。10枚はある。これまでの夏休みの宿題の読書感想文でも結構な量の原稿用紙が渡されていた。でも、それよりもずっと多い。
「これから星原くんにはテストを受けてもらうよ」
「て、テスト、ですか……!?」
「そう。いろいろあって、文芸部に入部したい人にはテストをしてもらうことに決めたんだ。部活に見学に来て、入りたいと思っている人全員にこのテストをして部長である僕と、本田先生がOKを出したら入部が認められるんだ」
「そうなんですね。それで、テスト、っていうのは、どういうことをするんですか?」
「内容に関してはシンプル。この原稿用紙を明日までに埋めてきてほしいんだ」
「あ、明日!? ですか!?」
俺は交互に原稿用紙と先輩に視線を向ける。この量の原稿用紙を明日までに埋めてくる!? 夏休みの宿題でもこんな量の原稿用紙を埋めてくる、と言う課題はなかった。今まで味わったことのない強烈な感覚が走る。
「そう。詩・物語・短歌・どんな形式でもいいから、この原稿用紙を埋めてきて欲しいんだ。念のために言っておくけれども、埋める、と言っても、漢字練習とか、意味のない文字の羅列を書いたり、AIに頼ったり誰かの作品をまるっと写して、みたいなのはもちろんだめだからね」
「は、はい……。わ、わかり、ました……。あの、ちなみに、今まで、このテストに合格出来た人は……?」
「いないよ」
「…………」
そりゃあ、この量を明日までに、っていうのはなかなかの無理難題。合格出来た人がいないテストが俺に課されている。小澤は「入るのが難しい」みたいなことを言っていたけれど、まさか、こんなことが起こるなんて思っていなかった。
「じゃあ、今日の部活動はおしまい。またね。明日、楽しみにしているよ」
そして先輩は、ニコニコとした柔らかい笑みで、俺に対して手を振る。俺は先輩の笑顔とは対象的に、危機感でいっぱいだった。
「は、はい……。分かりました。失礼します」
俺は文芸部の部室を出ざるを得なかった。随分と困ったことになってしまった。一体どうしよう。手元の原稿用紙を見ながら途方に暮れていた。
―――
「うーん、困ったな」
夜10時。呻くように俺は口にした。俺の身体に、味わったことのないような強烈な焦りが走っている。俺の目の前には真っ白い原稿用紙。一文字も埋められていなかった。
「一体、何を書けばいいんだろう」
文芸部の部室を出てからずーっと考えている。けど、何も出てこない。日記、は三行で終わってしまう。これまであったこと……、も、なんとか1枚埋められる、くらい。小説、なんて書いたこともない。詩に短歌、も、授業でうんうん言いながら書いたくらい。俺には詩も小説も文才は何にもない。どうすればいいんだろう……。
「はあ……」
溜息をつく。この状況を切り抜ける手段は思い着かない。最近観たバトルアニメではいろんな手段で切り抜けていた。だましたり、ハッタリをしたり。でも、騙すのは違う。それに、先輩もずるしちゃだめ、と言っていた。もちろんする気はないけれど。
何も思いつかない。どうすればいいんだろう。
「諦めた方が、いいのかな」
このまま諦めて、「書けませんでした」って真っ白のまま提出して、先輩を遠くから眺めているのが、一番楽なのかもしれない。あんなに人気の先輩だ。それに、不埒な動機で行ったんだ。だから、さっき、見学に行った時に話せただけでも、奇跡なのかもしれない。
どうすればいいんだろう。そのまま、俺は原稿用紙の上にべったりと突っ伏してしまった。
「先輩のことだったら、いっぱい、書けそうな気がするんだけどな」
口に出した瞬間だった。漫画だったら、頭の上で電球が点いたかのような、そんな感覚が走る。
「先輩の、ことを?」
先輩に対しての名前を付けられない想いを、書く。そんな風に、書くなんてこと、できるのかな。文章が得意、というわけじゃないけれど。けれども、今、この原稿用紙を埋めることが出来る方法って、それしかないような気がする。どうなるかは分からないけれど
「先輩のこと、書いてみようかな」
そして、俺はいつも使っているプラスチックのシャープペンを持って書き始めた。
“この気持ちの名前を知りたい”
そんな書き出しで、原稿用紙の一行目が始まった。そのまま俺は書いていく。
あなたのことをたくさん知りたい
好きなものはなんなんだろう。きらいなものはなんだろう。
そんなことを、何も知らない。
あなたと、たくさんしゃべってみたい。
だから、あなたのことを、もっと知りたい。
「っ、これ、かなり恥ずかしいな……」
妙な恥ずかしさ、と言えばいいのか、照れ、みたいなのを味わっている。顔が熱くなっている。マラソンで走った後よりもずっと身体が熱い。生きていてあまり感じたことのない感覚だ。それでも俺は書き進めていく。
あなたのきれいなところも汚いところもみてみたい。
あなたの身体の中を、ドアみたいに開いて、見ることが出来たらいいのに。
あなたのことを知って、あなたへの想いに、早く名前を付けたい。
……
俺の身体の熱は激しくなっていくばかり。恥ずかしさも増していくばかり。けど、先輩への思いをぶつけるように、無我夢中で、俺はペンを動かす。
憧れの先輩のいろんなことを見たい、知りたい、みたいな話を作っていく。エッセイなんだかポエムなんだか小説なんだかも分からないような、謎の文章。 でも、今の俺の出来る精一杯がこの文章だった。
「…………でも、ちょっと楽しいかも」
そんなことをつい呟いてしまった。これが全く興味のない読書感想文、とかだったら、一枚も埋めないうちにギブアップしていたかもしれない。でも、こうして、先輩のことを書いていくのは、なんだか、楽しかった。それこそ、小澤が推しにファンレターを書いているのを見たことがある。すごく楽しそうにしていた。それと同じ気持ちなのかもしれない。
――
カーテンの隙間から入り込んで来る光が、夜の光から朝の光になった。ちゅんちゅんと、すずめのさえずりが聞こえてくる。
「……。でき、た……」
徹夜をして、10枚の原稿用紙の最後の一行まで書き込んだ。先輩に対しての、まだ名前の分からない想いを全て詰め込むようにして。思えばテスト勉強も、受験勉強も、こんなに真剣にやらなかったかもしれない。こんなに、頑張れるとは、思わなかった。知らない自分、を見つけたような気がした。
「…………楽しかった、な」
達成感と共に、そんな言葉が口から出て来る。もっと、書いてみたいな、という想いが湧き上がる。文芸部に入って、書きたいな、という想いが。
「大丈夫そうか? オレ、ついてくか? バド部の第二体育館、部室棟のもっと先だからさ」
「だ、大丈夫、一人で行けるから」
「でも、右手と右足一緒に出てるぞ?」
「た、多分、大丈、夫、」
「こんな星原、初めて見たな……。学芸会でも入学式でも運動会でも緊張してなかったのに……。表情筋、別の意味でガチガチだな……。」
「そりゃあ、先輩に会いに行くから……」
「まあ、そうだよな……。俺も、推しの握手会に行く時はめっちゃ緊張するからなあ……」
俺は、運動会の緊張した行進みたいな歩き方で進んでいく。確かに、人生の中でこんなに緊張した瞬間はなかった。運動会も学芸会も、周りが緊張したり盛り上がっている中、やっぱり一人だけ「アンドロイド」みたいな反応をしてしまっていた。
「……でも、貴公子がいる、ってのに、文芸部の話って訊かねえんだよな。不思議なくらい」
「そうなの?」
「入ってる奴の話も、入ろうとしている奴の話も知らないんだよな。貴公子が文芸部にいるって話してた奴もその他の文芸部員のこと知らないみたいで。変な話なんだけど」
「そうなんだ……」
「あ、ただ、なんか揉めてた、みたいな話と、入部するのがめっちゃむずいらしい、みたいなことは言ってた」
「なるほど……」
文芸部。全部の部活動について書かれている部活紹介のパンフレットには、「よろしくお願いします」しか書いていなかった。部活動勧誘を積極的にやってる、って感じでもなかった。人数は3年生が5人、2年生が1人。この1人、が先輩なんだと思う。部員はいるみたい。でも、「うちの部活に入ってください!」みたいな宣伝をしている人を一人も見かけなかった。
「もし、活動方針が合えば入るのか?」
「入る、かもしれない」
「星原、ちなみに文章は好きなのか?」
「わかんないな。小学校くらいの頃のお話づくりは好きだった。けど読書感想文とかは埋めるのがやっと」
「小説書いたりは?」
「授業とかではやった。楽しかった」
「授業以外は?」
「……」
「本が好きとかは」
「漫画とかは読む」
「小説とか新書とかは」
「……」
「完全に先輩目当てって感じだな」
「うん、そうだね」
そんな風に話をしていたら文芸部の部室がある部室棟にたどり着いた。小澤とはここでお別れだ。
「ここだな」
「う、うん。小澤、ここまで着いてきてくれてありがとう」
「ああ! 確か、文芸部の部室は部室棟の三階だ、って言ってた。 じゃあな、頑張れよ!」
「うん」
そして俺は、部室棟の中へと入っていく。辿り着くまでに何度か「カードゲーム部いいですよ!」「手芸部入りませんか!」みたいな歓迎を受けつつ、俺は三階までたどり着いた。
「……ここだ」
三階の端に文芸部室はあった。白い引き戸。「文芸部」と達筆な文字で書いてある木製のプレートが引っかかっているだけ。妙にそこだけ静か。他の部活みたいに勧誘される気配はない。勧誘、どころか歓迎されているような雰囲気もない。本当にここに、すごく人気なあの先輩がいるのだろうか、と思うくらいの静かさ。
俺の身体にそれでも、俺は、もう一度先輩に会ってみたいし、話してみたい。そして、しばらくした後、俺は意を決して、こんこん、と文芸部の扉をノックした。
「はい」
低く柔らかい声の返事が返ってくる。先輩の声。どきどきと心臓が跳ねる。俺が、そのどきどきに浸っていたら、がらりと音がして、扉が開かれた。そして、扉の向こうから出てきたのはあの先輩だった。俺の口から声が漏れてしまう。そして、先輩の視線が俺の方に向けられる。すると、先輩は、柔らかく口角を上げた。
「あ、あの時の1年生くん。学校には慣れた?」
「は、はい……! お、お久しぶりです……! あの時はありがとうございました!」
「とんでもない。元気そうでよかったよ」
先輩、俺のこと、覚えてくれたんだ……! なんだか嬉しくなる。それこそ小澤が推しのアイドルのイベントに行って、「推しが認知してくれた!」みたいに嬉しそうに言っていたのを思い出した。それと同じ気持ちなのかもしれない。表情に出ているかどうかは分からないけれど、俺の口角が上がったのが分かった。
「こんなところまで来て、どうしたの?」
「あの、ぶ、文芸部の見学をしたくて……」
俺の言葉に先輩は少し驚いたような顔をする。そのまま、少し、何かに迷ったかのような表情を浮かべた。けれども、その表情はすぐに再びふわりとした、それこそ、貴公子とか王子様、と言い表せるような笑顔になった。俺の心臓がとくりと甘く跳ねる。
「そっか。それじゃあ話を訊きたいから、入ってもらってもいい?」
「あ、ありがとうございます……!」
先輩の後をついて俺は文芸部の部室に入らせてもらった。
入った瞬間に、紙とインクのような匂いがする。文芸部の部室は普段授業を受けている教室の半分くらいの広さ。白いカーテンで光量は抑えられているけれども日当たりのいい部屋だということが分かる。文芸部の部室の入り口そばには壁に寄せられているようにローラーで動くホワイトボードと本棚がある。部屋の中にはグループ学習をする時みたいに、机が4つくっつけられていた。そのうちの一つ、俺から見て左側の席には、漫画家が使うようなインクの瓶と万年筆らしきペンが置かれていて、その隣にはデスクトップパソコンが置かれていた。文芸部の部室、という感じの空間だった。
「それじゃあ、ここに座ってもらっていいかな?」
「は、はい」
先輩が指差したのは万年筆とインクが乗せられている席の向かい側。先輩は俺と向かい合うようにして座った。
俺は、緊張しながら、すこし俯きがちに先輩を見る。ドキドキしていて、どこを見たらいいのか分からない。挙動不審になってしまう。こうして向かいあっているのは、なんだか二者面談とか面接みたいな構図だ。ただ、二者面談とか面接とかとは別の意味で緊張してしまっている。
「それじゃあ、名前、教えてもらってもいいかな?」
「い、い、1年6組の、ほ、星原春男です。よろしくお願いします!」
「星原くんって言うんだね。僕は2年1組、成神連理(なるかみれんり)。文芸部の部長をしているよ。よろしくね」
「よ、よろしくお願いします」
ぺこりと礼をして、俺は先輩に視線を向ける。きらきらとしたぱっちりとした瞳は部屋の中に入る柔らかな光できらきらと波のように揺れている。柔らかく孤を描く唇。目鼻立ちのはっきりとした造形美、と言わんばかりの顔。改めて見ると本当に綺麗な顔をしていると思うと同時に心臓が跳ねる。今まで芸能人とかアイドルとか「美人だなあ」「かっこいいなあ」と思ったことはあるけれども、こんな感情になったことはなかった。やっぱり、推し、とはまた違った感情なのかもしれない。なんて名前の感情なんだろう。
「それじゃあ、早速この部活に関して説明するね」
「はい。お願いします」
「文芸部はその名前の通り、文章を書く部活。小説やエッセイ、詩や短歌……文章に関係ある創作をするんだ。毎週月曜日から金曜日までこの部室で活動をしているよ。……部活紹介のパンフレットを見ても分かるように籍を置いている部員、は何人かいるけれども今この部室に毎日来ている部員は僕一人かな」
「そうなんですね」
「それで、この部活に来てくれた、ってことは、文章に興味があるってことだよね。星原くんはどんな文章を作りたいの?」
「え、えっと……、あまり、文章には、詳しくなくって。それで、どんな文章を作りたいか、もまだ、分からないんですけれど、そ、その、先輩に、憧れていて、ここに来たんです」
俺は、バカ正直にそんな風に言ってしまった。しどろもどろになっている。こんなこと初めて。嘘でも、いつものように抑揚薄く、「文芸に興味があります」とか言えた方がよかったかもしれない。けれども、先輩を前にして、ひどく緊張していて、そんな風に言う余裕はなくなってしまった。
「……」
俺の答えに、先輩の孤を描いていた唇がすっと真っ直ぐになる。やっぱり、よくなかったよね。こんな邪な理由。
「あ、あの……、すみま、」
「なるほど……。ありがとう。僕に憧れてくれて」
なんだか申し訳なくなってしまって、俺は謝罪の言葉を口にしようとする。けれども、俺の答えを遮るように先輩は言った。ありがとう、という言葉は入っているけれども、その声はなんだかひんやりとしている。やっぱり、動機が不純過ぎるよね……? そして、先輩は立ち上がり、文芸部の部室の中にある本棚を開ける。そして何かを手に取り、戻ってくる。戻ってきた先輩は、その持ってきた何か、を俺の目の前に差し出すようにして置いた。
「え……?」
俺の目の前に置かれたのは、紙の束。原稿用紙。10枚はある。これまでの夏休みの宿題の読書感想文でも結構な量の原稿用紙が渡されていた。でも、それよりもずっと多い。
「これから星原くんにはテストを受けてもらうよ」
「て、テスト、ですか……!?」
「そう。いろいろあって、文芸部に入部したい人にはテストをしてもらうことに決めたんだ。部活に見学に来て、入りたいと思っている人全員にこのテストをして部長である僕と、本田先生がOKを出したら入部が認められるんだ」
「そうなんですね。それで、テスト、っていうのは、どういうことをするんですか?」
「内容に関してはシンプル。この原稿用紙を明日までに埋めてきてほしいんだ」
「あ、明日!? ですか!?」
俺は交互に原稿用紙と先輩に視線を向ける。この量の原稿用紙を明日までに埋めてくる!? 夏休みの宿題でもこんな量の原稿用紙を埋めてくる、と言う課題はなかった。今まで味わったことのない強烈な感覚が走る。
「そう。詩・物語・短歌・どんな形式でもいいから、この原稿用紙を埋めてきて欲しいんだ。念のために言っておくけれども、埋める、と言っても、漢字練習とか、意味のない文字の羅列を書いたり、AIに頼ったり誰かの作品をまるっと写して、みたいなのはもちろんだめだからね」
「は、はい……。わ、わかり、ました……。あの、ちなみに、今まで、このテストに合格出来た人は……?」
「いないよ」
「…………」
そりゃあ、この量を明日までに、っていうのはなかなかの無理難題。合格出来た人がいないテストが俺に課されている。小澤は「入るのが難しい」みたいなことを言っていたけれど、まさか、こんなことが起こるなんて思っていなかった。
「じゃあ、今日の部活動はおしまい。またね。明日、楽しみにしているよ」
そして先輩は、ニコニコとした柔らかい笑みで、俺に対して手を振る。俺は先輩の笑顔とは対象的に、危機感でいっぱいだった。
「は、はい……。分かりました。失礼します」
俺は文芸部の部室を出ざるを得なかった。随分と困ったことになってしまった。一体どうしよう。手元の原稿用紙を見ながら途方に暮れていた。
―――
「うーん、困ったな」
夜10時。呻くように俺は口にした。俺の身体に、味わったことのないような強烈な焦りが走っている。俺の目の前には真っ白い原稿用紙。一文字も埋められていなかった。
「一体、何を書けばいいんだろう」
文芸部の部室を出てからずーっと考えている。けど、何も出てこない。日記、は三行で終わってしまう。これまであったこと……、も、なんとか1枚埋められる、くらい。小説、なんて書いたこともない。詩に短歌、も、授業でうんうん言いながら書いたくらい。俺には詩も小説も文才は何にもない。どうすればいいんだろう……。
「はあ……」
溜息をつく。この状況を切り抜ける手段は思い着かない。最近観たバトルアニメではいろんな手段で切り抜けていた。だましたり、ハッタリをしたり。でも、騙すのは違う。それに、先輩もずるしちゃだめ、と言っていた。もちろんする気はないけれど。
何も思いつかない。どうすればいいんだろう。
「諦めた方が、いいのかな」
このまま諦めて、「書けませんでした」って真っ白のまま提出して、先輩を遠くから眺めているのが、一番楽なのかもしれない。あんなに人気の先輩だ。それに、不埒な動機で行ったんだ。だから、さっき、見学に行った時に話せただけでも、奇跡なのかもしれない。
どうすればいいんだろう。そのまま、俺は原稿用紙の上にべったりと突っ伏してしまった。
「先輩のことだったら、いっぱい、書けそうな気がするんだけどな」
口に出した瞬間だった。漫画だったら、頭の上で電球が点いたかのような、そんな感覚が走る。
「先輩の、ことを?」
先輩に対しての名前を付けられない想いを、書く。そんな風に、書くなんてこと、できるのかな。文章が得意、というわけじゃないけれど。けれども、今、この原稿用紙を埋めることが出来る方法って、それしかないような気がする。どうなるかは分からないけれど
「先輩のこと、書いてみようかな」
そして、俺はいつも使っているプラスチックのシャープペンを持って書き始めた。
“この気持ちの名前を知りたい”
そんな書き出しで、原稿用紙の一行目が始まった。そのまま俺は書いていく。
あなたのことをたくさん知りたい
好きなものはなんなんだろう。きらいなものはなんだろう。
そんなことを、何も知らない。
あなたと、たくさんしゃべってみたい。
だから、あなたのことを、もっと知りたい。
「っ、これ、かなり恥ずかしいな……」
妙な恥ずかしさ、と言えばいいのか、照れ、みたいなのを味わっている。顔が熱くなっている。マラソンで走った後よりもずっと身体が熱い。生きていてあまり感じたことのない感覚だ。それでも俺は書き進めていく。
あなたのきれいなところも汚いところもみてみたい。
あなたの身体の中を、ドアみたいに開いて、見ることが出来たらいいのに。
あなたのことを知って、あなたへの想いに、早く名前を付けたい。
……
俺の身体の熱は激しくなっていくばかり。恥ずかしさも増していくばかり。けど、先輩への思いをぶつけるように、無我夢中で、俺はペンを動かす。
憧れの先輩のいろんなことを見たい、知りたい、みたいな話を作っていく。エッセイなんだかポエムなんだか小説なんだかも分からないような、謎の文章。 でも、今の俺の出来る精一杯がこの文章だった。
「…………でも、ちょっと楽しいかも」
そんなことをつい呟いてしまった。これが全く興味のない読書感想文、とかだったら、一枚も埋めないうちにギブアップしていたかもしれない。でも、こうして、先輩のことを書いていくのは、なんだか、楽しかった。それこそ、小澤が推しにファンレターを書いているのを見たことがある。すごく楽しそうにしていた。それと同じ気持ちなのかもしれない。
――
カーテンの隙間から入り込んで来る光が、夜の光から朝の光になった。ちゅんちゅんと、すずめのさえずりが聞こえてくる。
「……。でき、た……」
徹夜をして、10枚の原稿用紙の最後の一行まで書き込んだ。先輩に対しての、まだ名前の分からない想いを全て詰め込むようにして。思えばテスト勉強も、受験勉強も、こんなに真剣にやらなかったかもしれない。こんなに、頑張れるとは、思わなかった。知らない自分、を見つけたような気がした。
「…………楽しかった、な」
達成感と共に、そんな言葉が口から出て来る。もっと、書いてみたいな、という想いが湧き上がる。文芸部に入って、書きたいな、という想いが。