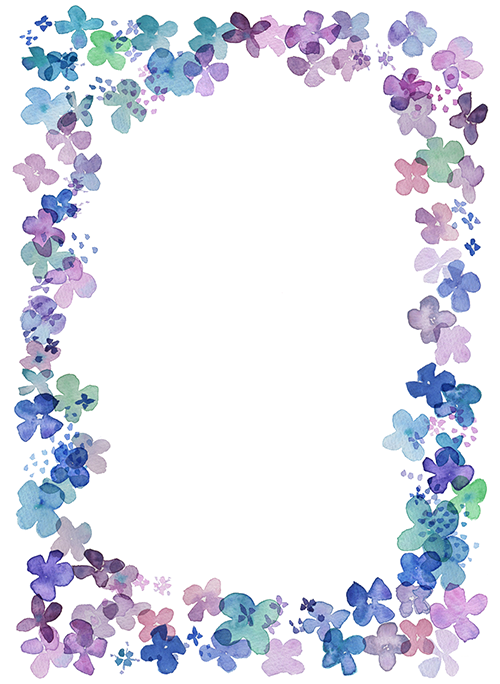2月のある日のことだった。
「春男、いってらっしゃい」
「いってきます」
俺が出したあの小説が、大賞を取った。そのお祝い、をする。というか、デート。最寄り駅で待ち合わせ。駅で待ち合わせをして、一緒に行くことになった。
二人で道を歩いている。その距離は付き合う前よりもずっとずっと近い。
「先輩、今日はありがとうございます……。あ、違う、先輩、じゃない……、その、連理、さん……」
学校とか、部活動では「先輩」呼びでこのスタンスを崩していない。「部活では恋愛をしない」ということにしているから。その代わり、こうして、学校ではないところでは、「連理さん」「春男くん」と呼びあっている。
「それにしても、まさか、廃部にならない、とはね」
「はい。ちょっとびっくりですね」
俺がこの賞を取ったことによって、廃部は免れることになった。というのも、俺が取った「想いの文学賞」の話題が大々的に取り上げられて、「文芸部に入りたい」という真面目な希望者が学校の中からも、それだけではなく、受験生からも問い合わせが殺到したらしい。それで、部活動は存続することになった。
「一緒に切磋琢磨出来る人が欲しかったんだ」
「え?」
「どうして僕が文章を書いているか、っていう話。そういえば、どうしてか、言いそびれてしまったなって思ってね」
先輩と歓迎会に行った日に俺が訊いたけれど、風が吹いて結局聞きそびれてしまったな、と思い出す。
「もちろん、文章を書くのが好きだ、というのもある」
先輩は柔らかな表情で、俺の方に視線を向けた。
「そして、贅沢かもしれないけれど、きらきらした目で読んでくれる人が欲しかった。そういう人が欲しくて、僕は書いていたんだと思う」
「だから、春男くんの存在は嬉しかった」
「先輩……」
そして、先輩が俺の手をぎゅ、と握る。
「これからも、春男くんと一緒に文章を書いていきたいな」
「はい……!」
二人、手を繋いで歩いていった。
「春男、いってらっしゃい」
「いってきます」
俺が出したあの小説が、大賞を取った。そのお祝い、をする。というか、デート。最寄り駅で待ち合わせ。駅で待ち合わせをして、一緒に行くことになった。
二人で道を歩いている。その距離は付き合う前よりもずっとずっと近い。
「先輩、今日はありがとうございます……。あ、違う、先輩、じゃない……、その、連理、さん……」
学校とか、部活動では「先輩」呼びでこのスタンスを崩していない。「部活では恋愛をしない」ということにしているから。その代わり、こうして、学校ではないところでは、「連理さん」「春男くん」と呼びあっている。
「それにしても、まさか、廃部にならない、とはね」
「はい。ちょっとびっくりですね」
俺がこの賞を取ったことによって、廃部は免れることになった。というのも、俺が取った「想いの文学賞」の話題が大々的に取り上げられて、「文芸部に入りたい」という真面目な希望者が学校の中からも、それだけではなく、受験生からも問い合わせが殺到したらしい。それで、部活動は存続することになった。
「一緒に切磋琢磨出来る人が欲しかったんだ」
「え?」
「どうして僕が文章を書いているか、っていう話。そういえば、どうしてか、言いそびれてしまったなって思ってね」
先輩と歓迎会に行った日に俺が訊いたけれど、風が吹いて結局聞きそびれてしまったな、と思い出す。
「もちろん、文章を書くのが好きだ、というのもある」
先輩は柔らかな表情で、俺の方に視線を向けた。
「そして、贅沢かもしれないけれど、きらきらした目で読んでくれる人が欲しかった。そういう人が欲しくて、僕は書いていたんだと思う」
「だから、春男くんの存在は嬉しかった」
「先輩……」
そして、先輩が俺の手をぎゅ、と握る。
「これからも、春男くんと一緒に文章を書いていきたいな」
「はい……!」
二人、手を繋いで歩いていった。