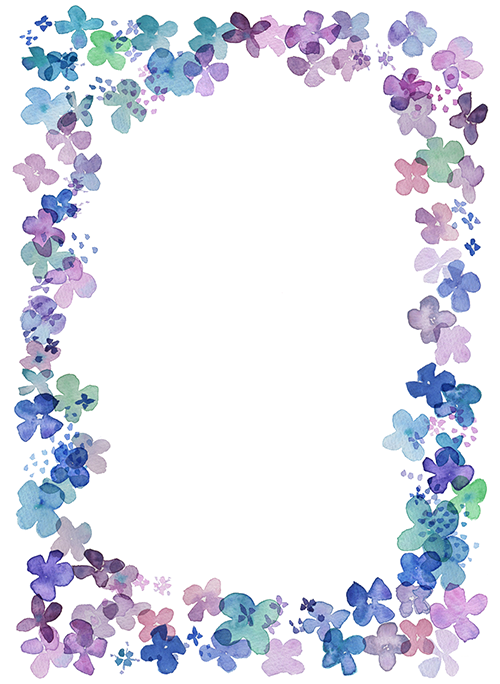次の日の昼休み、俺は小澤と一緒に、外のベンチで二人、昼ごはんを食べていた。視界の端で購買のホットドッグを囓っている小澤が見える。俺は弁当箱の蓋を開け、箸を持ったままぼーっと固まってしまっていた。昨日のことが頭から離れなくてぼんやりしている。
「星原~」
「何?」
「今日、なんかぼーっとしてないか? なんかフリーズしたパソコンみたいになってるぞ。大丈夫か? 何か悩んでることでもあるのか? 飯も全然減ってないし……。熱でもあるのか?」
「いや、多分大丈夫、」
「大丈夫って感じじゃねえぞ」
今のこの感情。なんて言い表せばいいんだろうか。ぼんやりとした頭で俺は考える。そしてしばらく頭の中で考えた後、ようやく出せる準備が整った。
「あのさ、誰かのことが頭から離れなくなる時、ってある?」
「え……、突然どうしたんだよ」
「まあ、いろいろあって。小澤はある?」
「そうだな。推しのトワちゃんのことずーっと考えてることはあるぞ。特にライブ前とか接近戦の前とか」
「推し……。かあ……」
小澤の言葉で、ちょっとしっくり来たような気がした。ちょっと助けてもらっただけの相手を「恋」というよりはなんとなく納得が出来る。ただ、完璧に、「推し」と言い切ってしまうのも少し違う気がする。アイドルとか芸能人と近づきたい、ともまた違う感覚。もっと深く知りたい、みたいなそんな感じ。
「誰かいるのか? そういう人?」
「う、うん……、その、まだよくは分かってないんだけど、多分、うちの学校の人」
「どんな感じの人? 可愛い、とかかっこいい、とか」
「いや……、多分、先輩……。すごくきれいな人って、知ってたりする?」
小澤は有名人と情報収集が大好き。SNSとかも呟かないアカウントをいくつも持っている。「推しのアイドル、トワちゃんの情報収集用」と「芸能人の情報収集用」と「身内用」と「学校用」と「アニメ用」といくつも持っているくらい。LIMEをフル活用してるしコミュ力も高い。だから、俺の知らない学校情報を結構知っている。
「うーん、先輩だとチア部2年の城崎(しろさき)先輩とか?」
「……どなた?」
「あ、有名人だけど知らない感じか。城崎セリカ先輩。超美人の先輩。SNSのフォロワー万超えだとか、大手の事務所からスカウト来てる、とか、かなり噂になってる」
「ごめん、その人は知らない」
「そうか。じゃあ、他に特徴はあるか?」
「えっと、男の先輩で、背が高くてすっごい美形な人。なんとなく、王子様って感じの人」
「あー、そっちか! 男の先輩ね! なら多分だけど、貴公子!」
「貴公子?」
「貴公子、ってあだ名がついてて、めっちゃモテるって噂の二年生の先輩。その先輩かも。名前は、確か、成神先輩、だったような……。貴公子って呼ばれてるから、フルネームわかんねえんだよな」
貴公子、というあだ名、なんとなくピッタリハマる。昨日会った時のあの姿が思い出されて、俺の心臓が跳ねた。柔らかなふわふわの茶色い髪。濃い琥珀色の、まるで夕日みたいなきらきらした瞳。柔らかな笑顔。心臓がドキドキと跳ねる。なんだろう、この感情。
「もしかして、その人かも」
「そっか!」
俺が答えると、小澤はもぐもぐと残りのホットドッグをほおばってそのままココアで流し込んだ。まるで何かにせき立てられる、みたいに。
「それじゃあ、行ってみるか。3階!」
「えっ……!? と、突然、どうして……!?」
「2年生の教室があるだろ? もしかしたら、貴公子がいるかもしれねえし、城崎先輩にも会えるかもしれない……! それに、バスケ部の爆美女、空井先輩に、茶道部のエース美女、村雨先輩が見れるかもしれない……! あわよくば喋れるかもしれない!」
「な、なるほど」
小澤の話し方は、「芸能人が撮影に来てるから撮影現場に行く」みたいなそんな感じ。多分小澤の目的は俺が目的としているあの先輩ではなくて、城崎先輩だと思う。けれども、そうやってついてきてくれるのは心強いかもしれない。俺も、急いで弁当を食べ、三階へと向かった。
――
俺達は外のベンチから教室に入り、三階の教室へと上がっていった。階段を登り切り、廊下を二人で踏みしめた瞬間だった。
「あ!」
俺は思わず声を出す。思いのほかすぐにその先輩は見つかった。廊下の真ん中辺りにいた背の高い先輩。ふわふわの柔らかそうな茶髪。綺麗な横顔。あの先輩が廊下で一番目立っていた。
「あの人?」
「うん、あの人!」
けど……。
先輩は廊下で、たくさんの女の子達に囲まれていた。今日は特に何にもない日だというのにまるでイベント事のように。声は聞こえないけれども、女の子たちと談笑しているみたいだ。
芸能人とか野球選手にサインや握手を求めて近づいている光景を見たことがある。それ
が、今目の前で起こっている。近づくことすら難しい雰囲気。
「喋るどころか近づくのも大変そうだな……」
「そう、だね」
「あ、先輩のそばに城崎先輩いるな。それに野球部の大人気マネージャーの空井先輩に、去年文化祭の彼女にしたいランキング1位だった村雨先輩もいるぜ……。貴公子、やっぱりモテるんだな……」
あの先輩の周りには、女の人達がたくさん集まっていた。1軍、っていうのはああ人達のことを言うんだろうな、みたいな、オシャレで綺麗で目立ちそうな人達がたくさん。この状況で話し掛けに行けるわけがない。圧倒されてしまう。
「……」
俺の入る場所はありません、と言われているみたいな状況が、俺の目の前に広がっていた。
しばらくその場に立っていると、予鈴のチャイムが鳴り、先輩と、女の子達はそれぞれの教室に戻っていった。何も出来ないまま時間が終わってしまった
「俺達も戻るか……」
「うん」
午後の授業を受けながらぼんやりと考える。戦果はほとんどない状態。でも、戦果なし、では、あったけれど、先輩のことが、頭の中から離れなかった。
むしろ、ああして、もう一度、見たことで、先輩に対しての興味が沸いてくる。俺も、先輩としゃべってみたい。先輩と過ごしてみたい。それは、小澤とか友達と長い時間過ごしてみたい、という感覚ではない。推し、に近いものかもしれない。恋かはどうかはまだ分からない。
――
「今日もすごいな……。いや、昨日も一昨日もすごかったけど……」
「そうだね、」
それから昼休み、毎日のように、三階の廊下に行ったけれど、先輩は毎回誰かしらに囲まれていた。女の子たちもだし、男友達らしき人も。先輩はまるで芸能人のような人気者。話しかけに行くことも難しくて、悶々と過ごしていた。
先輩に対しては今まで抱いたことのない感情を抱いている。けれども、俺は先輩のことをほとんど知らない。2年生で、貴公子と呼ばれていて、めちゃくちゃモテる先輩、ということだけ。部活も分からない。小澤も興味の範疇ではないから、先輩に対しては詳しいことを知らなかったみたいだ。
けれども、入学してから10日ほどが経ったある日、変化が訪れた。
「文芸部!」
朝登校するなり、小澤が目を輝かせて俺のところに言いに来た。まるで芸能人のスクープを掴んだかのように。けど、俺は戸惑ってしまった。
「え? 小澤、バドミントン部に入るんじゃないの?」
小澤は小学校からずっとバドミントンをやっていた。それに、昨日までも喜々してバドミントン部の仮入部に行っていた。それなのに突然文芸部、って言い出すなんて、どうしたんだろう。
「貴公子の部活、文芸部なんだって! バド部の先輩が言ってた!」
「え、」
突然の先輩の手がかりに、俺は驚きと嬉しさが混じた感情を抱いていた。