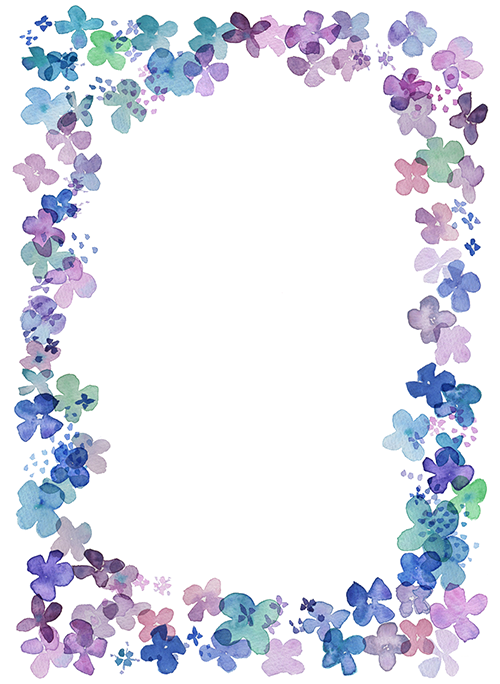修学旅行から数日が経った。もう12月に入っている。一時間目に当たる時間、俺達は体育館の中にいた。冷たい空気に覆われた体育館の中、冷えた空気が広がっている。
先輩達2年生が修学旅行で帰って来るから、そのタイミングで全校集会が開かれる。先輩の方をちらちら見てしまう。成神先輩は隣の列の一番後ろ。他にも女の子たちがちらちらと先輩の方に視線を向けていた。前の方にいる城崎先輩も、先輩をちらちらと見ているのが分かった。
城崎先輩、自由行動で一緒だったって話だ。もしかしたら、先輩と、距離が近づいていたのかもしれない。先輩と、手とか、繋いだりしてたのかもしれない。脳裏に浮かんだのは、先輩と、城崎先輩が手を繋いでいる姿。文化祭の時よりも鮮明に見えてしまった。文芸部が廃部になる、っていうのもあって。ああ、きっと、お似合いだ。美男美女カップル。ぎゅう、と胸が締め付けられる。……、あれ?
「……っ」
胸が締め付けられている。物理的に。思わず胸を押さえてしまった。気持ち悪い、吐きそう。心臓が異常に激しく鼓動している。俺の身体に一体視界が狭まっていく。どういう、こと……? 目の前が真っ暗になる。何も見えない。そのまま、身体が前のめりに倒れていく。まるで、あの日のように。でも、先輩は、いない。
「星原くん!?」
けれども、地面に激突する直前で、誰かに身体を支えられた。まるで、あの日のように。それでも、今のこの状態では、それが、誰の声か判別することはできなかった。
「星原、大丈夫か!?」
「星原くん!」
それにつられるように、悲鳴のような、ざわざわとした声が聞こえてくる。言葉を出したいのに、まるで喉に何かが貼り付いているようで、言葉が出てこない。そのまま、俺の意識が、現実じゃないものに、引きずられていった。覚えているのは、誰かの身体の感触と、誰かに俺の身体全体が持ち上げられているかのような感覚だった。
「……」
気が付けば、俺は保健室のベッドの上にいた。先輩は俺の枕元に座っていた。すごく不安そうな顔で俺のことを覗き込んでいる。
「星原くん!? 大丈夫? 痛いとか苦しいとかない?」
いつも柔らかく喋る先輩にしては珍しい、せき立てるような。ひどく勢いの強い声だった。怒っている、というわけではなくって、俺を心配しているような声。
「……。は、はい……。俺は、大丈夫です。あの、俺は、一体……」
上半身を起こす。先輩と目が合った。それでも先輩の不安そうな表情は完全に消えていない。
「先生曰く、寝不足と脳貧血。熱はないって言っていたんだ。先生は用事で一時間くらい席を外すみたいだよ。少し心配だから、僕がそばにいさせてもらうことになったんだ」
「……そうなんですね。もしかして、先輩が、保健室まで運んで来てくださったんですか?」
「そうだよ」
「すみません、ご迷惑、おかけしてしまって……」
「そのことは気にしないで大丈夫」
先輩の不安そうな表情は、少し険しい表情となった。それでも、俺を心配してくれているんだと分かる。
「星原くん、また、眠らないで書いてたの?」
「……はい」
「……、頑張り過ぎるのは、星原くんのよくないところだからね」
そっと、俺の目の下をゆっくりと撫でられる。先輩の少し冷たい指の感触が俺の身体に伝わる。ああ、こうして、撫でてもらえるのは、いつまでだろう。城崎先輩とはどうなったんだろう。廃部になったら、こうして、先輩と一緒にいられる時間は、なくなるんだろうな……。
「っ……!? 星原くん!」
先輩の焦ったような声が聞こえてくる。今まで我慢をしていたものが、決壊するように溢れ出てしまった。ぼろぼろと涙が溢れて、シーツの上にこんな風に泣いたのって、いつぶりだっけ。
「どうしたの? やっぱり、体調、つらい? 保険の先生よんでくる?」
俺は首を横に振る。涙の混じった声で俺は「不安、なんです」と口にした。
「不安? 何が……?」
「……」
その不安を口にすることが出来ず。俺は泣いたまま、先輩から視線を背けて俯いた。さらにぼたぼたと涙がシーツの上に落ちていく。
「星原くん。僕の方を見て」
先輩が柔らかい声で言う。けれども、俺の顔は動かなくて。
「星原くん」
もう一度、俺の名前を呼ばれる。涙でぼやけた視線ではあるけれど、先輩の綺麗な顔の輪郭は見える。ああ、やっぱり、綺麗だな。
「もしも、僕に言えることだったら、何でも言って。話せば、楽になるのかもしれないから」
本当に、それを言っていいかな。この言葉を言ったら、この関係が壊れてしまうかもしれない。不安で仕方がない。
「なんでも、いいん、ですか……?」
「ああ、なんでも、いいよ。星原くんの事だったら、何でも、訊きたい」
真っ白い保健室。昼の陽の光が入ってくる。きらきらとしていた。先輩ともうすぐいられなくなってしまうのかもしれない。
「……、せんぱい、と、はなれたく、ない、です……」
「え?」
「部活が、廃部になるって、訊いて、す、み、ません。その、前に、言っていた、言いたいこと、みたいなのが、そういうことかなって思って……」
俺の心臓がバクバクと言っている。言う度に心臓が出てしまいそうだ。こんな感覚、味わったことがない。俺が不安がっているのは、それだけじゃない。でも、もう押さえることが出来なかった。
「あの、本当に、これ、迷惑だったら、すみません。その、俺は、先輩のことが、好き、なんです……。それは、きっと、その部活の、後輩、よりも先に進みたい、という感情、なんです……」
言ったら終わり、みたいなことが、一気に、溢れるように出て来る。ぐちゃぐちゃになりながら、支離滅裂になりながら、俺は、そんなことを口にした。
「……、おれは、その、せんぱい、にとっては、文芸部の、部員で、……、でも、俺は、それ以上の、ことを、先輩に、求めてしまって……。でも、城崎先輩が、いるからって、想って……。」
まるで小さな子どもみたいにぼろぼろ泣きながら、そんなことを口にした。涙で霞んで、先輩の姿はもう見えていなかった。頭がうまく回らなくって、俺の口から「えっと」とかしゃくりあげる声しか出てこなくなる。
「……星原くん」
そして、先輩があの日みたいに抱きしめてくれた。あの日みたいな、支える、って感じの抱き方じゃなくて、ちゃんと意志を持って抱きしめてくれていた。
「不安な気持ちにさせてしまったみたいでごめんね」
抱きしめたまま、先輩は、俺の背中を柔らかく撫でてくれた。その感触と、先輩の体温が心地いい。そして、先輩は柔らかく背中を撫でていてくれた。
「それじゃあ、一つずつ、星原くんの不安を解消していこうね」
「……はい」
「まず、城崎さんとの関係に関して。彼女とはクラスと、修学旅行の班が同じだった。確かに、城崎さんから、僕のことが好きで、付き合って欲しい、ということを。けれども、城崎さんの告白に関しては、お断りさせてもらったよ」
「え、っと、どうして……」
衝撃で、俺の涙が止まりはじめる。あんなに綺麗な人で、仲よさそうにしゃべっていたのに。
「確かに、話をしたこともあるし慕ってくれていた。けれども、僕は城崎さんのことをクラスメイトや友人、としては接することは出来ても、それ以上の気持ちに、応えられないと思ったんだ」
「そう、だったんですね……」
「それじゃあ、これから僕が言いたいことは二つあるんだ。一つ目は部活に関して」
「はい……」
「文芸部が廃部になることは決まっているんだ。廃部に関しては、僕がきちんと言わなくて、不安にさせてしまったと思う。本当にごめんね」
「あの、廃部になることって、もう、決まってるんですか?」
「そうだね。星原くんが部活に来る前から、そういう話は出ていたんだ」
「え……?」
「僕が入学する前の文芸部は、作品作りもままならないくらいひどく緩い部活だったんだ。そのせいもあって、僕が入ってからも、僕以外真面目にやりたい、という人がいなかったんだ。話し合いをしたけれどもなかなかうまくいかなくてね。そして、最終的には、ちゃんと作品を作りたい、という意志を持って残ったのが僕一人だけになってしまった。それが今年の3月。2年生の部員は全員退部して、3年生の部員は籍だけ残すことになった。もうそこで、廃部は決まってしまったようなものだった。ただ、どうしても文芸部の活動がしたくて、今年の部活の期間だけ」
「そう、だったんですね……」
そして、先輩はひどく穏やかな視線を俺に向けてくれていた。
「本当はね、星原くんが来る前に、廃部を受け入れて、終わりにしようと思っていたんだ」
「え……?」
「確かに僕目当てで来た子もいた。部活の外、であれば僕目当てでも対応したけれども、部活に、そんなうわついた気持ちを持ち込んで欲しくはなかった。だから、きっと、星原くんも、冷やかしか何かだろう、と正直思ってしまったんだ。星原くんが」
「……。すみません。冷やかし、というか“先輩に会いたい”みたいな邪な気持ちで部活に来ました……」
「なんとなくそれは分かっていたよ。けれどもね、その子達と星原くんの違うところは、ちゃんとテストをクリアしてくれたところだ」
「え……」
「星原くんの頑張りを見て、そして、星原くんの文章を見て、もう少し、この部活で、星原くんと一緒にやりたい、と思ったんだ。あんなに頑張って文章を書いてきてくれたのは星原くんだけ、だったからね」
「先輩……」
「そして、星原くんは、ちゃんと、文章も好きになっていた。星原くんの文章はとても素敵だった。今も頑張っている。けれども、星原くんの文章はね、情熱に溢れていて、まっすぐで、素直だった。僕みたいなのを書きたい、って言ってくれたけれども、ちゃんと、そこに自分の色を付けようとしている。僕の文章を頭に置きながらも、自分のえがきたいものをちゃんと描こうとしている。何よりも、悩んだり、苦しんだり、楽しそうに書く星原くんを見ていると、僕も頑張ろう、という気持ちになっていた」
先輩はふわりと俺の方に柔らかく視線を向けてくれる。その瞳は、まるで、愛おしいものを見つめているような視線。ドキドキと心拍が高鳴った。
「あと、星原くんと過ごしているのは純粋に楽しいんだ」
「た、楽しい、ですか……?」
「最初は、あまり表情の変わらない子かな、と思ったんだ。けれどもね、それは、僕の思い違いだった」
「そ、そうですか……?」
「星原くんのくるくる変わる表情を見ているのは楽しいし、一生懸命に頑張ってくれる星原くんの姿は素敵だ。そして、何かを食べるちょっと子どもっぽい顔も、僕のことが好きなんだって伝わってくる姿も、どれもとても愛おしいんだ」
「…………、えっと……、その、先輩……、!? その、あのっ……、好きってっ……!?」
「そうだよ。二つ目に言いたかったこと。僕は君のことがずっと好きだった」
先輩は柔らかな表情で俺の方に視線を向ける。
「あの日、僕にあの文章を見せてくれた時から、僕は、星原くんのことが好きだったのかもしれない」
「え……?」
「でも、この関係が変わってしまうのが怖くてね、なかなか、言い出すことが出来なかったんだ。この関係が、壊れてしまうくらいであったら、何もしない方がいいんじゃないかと思ってね」
「……そう、なんですね……。俺も、です……」
先輩も、俺と同じだった。それは、先輩の引き出してくれた表情だった。俺の知らない感情を、先輩が、教えてくれた。
「ちゃんと俺が言わずに、つらい想いをさせてしまったみたいで、本当にごめんね」
「っ……!」
そのまま、先輩はぎゅう、と俺のことをさらに強く抱きしめてくれた。
「これが、僕の気持ちだ」
そして、先輩は腕の力を緩めて、その手を、僕の頬を包み込むように触れた。先輩の、少し低い指先の温度が頬に伝わる。花火大会の時の手の温度。書き記せないくらい。どきどきしている。俺も、その動きを受け入れた。
「俺も、先輩が、好きです……」
目の前で、先輩が笑っていた。ふわりとした柔らかい微笑み。
「そして、二つ目のこと。文芸部が廃部になる。けれども、僕は、もう一度、文芸部を立て直したいと思っているんだ」
「そ、そうなんですか……!」
「そんなことを言うと、重いと感じてしまうんじゃないか、って思ってしまったんだ」
「そ、そんなこと、ないです……。うれしいです……。先輩がそう言ってくれるなんて……」
先輩はふわりと俺に柔らかい微笑みを向けた。
「ついてきて、くれるかな」
「は、はい……!」
頷いた時の先輩は、すごく綺麗な笑顔を浮かべていた。
先輩達2年生が修学旅行で帰って来るから、そのタイミングで全校集会が開かれる。先輩の方をちらちら見てしまう。成神先輩は隣の列の一番後ろ。他にも女の子たちがちらちらと先輩の方に視線を向けていた。前の方にいる城崎先輩も、先輩をちらちらと見ているのが分かった。
城崎先輩、自由行動で一緒だったって話だ。もしかしたら、先輩と、距離が近づいていたのかもしれない。先輩と、手とか、繋いだりしてたのかもしれない。脳裏に浮かんだのは、先輩と、城崎先輩が手を繋いでいる姿。文化祭の時よりも鮮明に見えてしまった。文芸部が廃部になる、っていうのもあって。ああ、きっと、お似合いだ。美男美女カップル。ぎゅう、と胸が締め付けられる。……、あれ?
「……っ」
胸が締め付けられている。物理的に。思わず胸を押さえてしまった。気持ち悪い、吐きそう。心臓が異常に激しく鼓動している。俺の身体に一体視界が狭まっていく。どういう、こと……? 目の前が真っ暗になる。何も見えない。そのまま、身体が前のめりに倒れていく。まるで、あの日のように。でも、先輩は、いない。
「星原くん!?」
けれども、地面に激突する直前で、誰かに身体を支えられた。まるで、あの日のように。それでも、今のこの状態では、それが、誰の声か判別することはできなかった。
「星原、大丈夫か!?」
「星原くん!」
それにつられるように、悲鳴のような、ざわざわとした声が聞こえてくる。言葉を出したいのに、まるで喉に何かが貼り付いているようで、言葉が出てこない。そのまま、俺の意識が、現実じゃないものに、引きずられていった。覚えているのは、誰かの身体の感触と、誰かに俺の身体全体が持ち上げられているかのような感覚だった。
「……」
気が付けば、俺は保健室のベッドの上にいた。先輩は俺の枕元に座っていた。すごく不安そうな顔で俺のことを覗き込んでいる。
「星原くん!? 大丈夫? 痛いとか苦しいとかない?」
いつも柔らかく喋る先輩にしては珍しい、せき立てるような。ひどく勢いの強い声だった。怒っている、というわけではなくって、俺を心配しているような声。
「……。は、はい……。俺は、大丈夫です。あの、俺は、一体……」
上半身を起こす。先輩と目が合った。それでも先輩の不安そうな表情は完全に消えていない。
「先生曰く、寝不足と脳貧血。熱はないって言っていたんだ。先生は用事で一時間くらい席を外すみたいだよ。少し心配だから、僕がそばにいさせてもらうことになったんだ」
「……そうなんですね。もしかして、先輩が、保健室まで運んで来てくださったんですか?」
「そうだよ」
「すみません、ご迷惑、おかけしてしまって……」
「そのことは気にしないで大丈夫」
先輩の不安そうな表情は、少し険しい表情となった。それでも、俺を心配してくれているんだと分かる。
「星原くん、また、眠らないで書いてたの?」
「……はい」
「……、頑張り過ぎるのは、星原くんのよくないところだからね」
そっと、俺の目の下をゆっくりと撫でられる。先輩の少し冷たい指の感触が俺の身体に伝わる。ああ、こうして、撫でてもらえるのは、いつまでだろう。城崎先輩とはどうなったんだろう。廃部になったら、こうして、先輩と一緒にいられる時間は、なくなるんだろうな……。
「っ……!? 星原くん!」
先輩の焦ったような声が聞こえてくる。今まで我慢をしていたものが、決壊するように溢れ出てしまった。ぼろぼろと涙が溢れて、シーツの上にこんな風に泣いたのって、いつぶりだっけ。
「どうしたの? やっぱり、体調、つらい? 保険の先生よんでくる?」
俺は首を横に振る。涙の混じった声で俺は「不安、なんです」と口にした。
「不安? 何が……?」
「……」
その不安を口にすることが出来ず。俺は泣いたまま、先輩から視線を背けて俯いた。さらにぼたぼたと涙がシーツの上に落ちていく。
「星原くん。僕の方を見て」
先輩が柔らかい声で言う。けれども、俺の顔は動かなくて。
「星原くん」
もう一度、俺の名前を呼ばれる。涙でぼやけた視線ではあるけれど、先輩の綺麗な顔の輪郭は見える。ああ、やっぱり、綺麗だな。
「もしも、僕に言えることだったら、何でも言って。話せば、楽になるのかもしれないから」
本当に、それを言っていいかな。この言葉を言ったら、この関係が壊れてしまうかもしれない。不安で仕方がない。
「なんでも、いいん、ですか……?」
「ああ、なんでも、いいよ。星原くんの事だったら、何でも、訊きたい」
真っ白い保健室。昼の陽の光が入ってくる。きらきらとしていた。先輩ともうすぐいられなくなってしまうのかもしれない。
「……、せんぱい、と、はなれたく、ない、です……」
「え?」
「部活が、廃部になるって、訊いて、す、み、ません。その、前に、言っていた、言いたいこと、みたいなのが、そういうことかなって思って……」
俺の心臓がバクバクと言っている。言う度に心臓が出てしまいそうだ。こんな感覚、味わったことがない。俺が不安がっているのは、それだけじゃない。でも、もう押さえることが出来なかった。
「あの、本当に、これ、迷惑だったら、すみません。その、俺は、先輩のことが、好き、なんです……。それは、きっと、その部活の、後輩、よりも先に進みたい、という感情、なんです……」
言ったら終わり、みたいなことが、一気に、溢れるように出て来る。ぐちゃぐちゃになりながら、支離滅裂になりながら、俺は、そんなことを口にした。
「……、おれは、その、せんぱい、にとっては、文芸部の、部員で、……、でも、俺は、それ以上の、ことを、先輩に、求めてしまって……。でも、城崎先輩が、いるからって、想って……。」
まるで小さな子どもみたいにぼろぼろ泣きながら、そんなことを口にした。涙で霞んで、先輩の姿はもう見えていなかった。頭がうまく回らなくって、俺の口から「えっと」とかしゃくりあげる声しか出てこなくなる。
「……星原くん」
そして、先輩があの日みたいに抱きしめてくれた。あの日みたいな、支える、って感じの抱き方じゃなくて、ちゃんと意志を持って抱きしめてくれていた。
「不安な気持ちにさせてしまったみたいでごめんね」
抱きしめたまま、先輩は、俺の背中を柔らかく撫でてくれた。その感触と、先輩の体温が心地いい。そして、先輩は柔らかく背中を撫でていてくれた。
「それじゃあ、一つずつ、星原くんの不安を解消していこうね」
「……はい」
「まず、城崎さんとの関係に関して。彼女とはクラスと、修学旅行の班が同じだった。確かに、城崎さんから、僕のことが好きで、付き合って欲しい、ということを。けれども、城崎さんの告白に関しては、お断りさせてもらったよ」
「え、っと、どうして……」
衝撃で、俺の涙が止まりはじめる。あんなに綺麗な人で、仲よさそうにしゃべっていたのに。
「確かに、話をしたこともあるし慕ってくれていた。けれども、僕は城崎さんのことをクラスメイトや友人、としては接することは出来ても、それ以上の気持ちに、応えられないと思ったんだ」
「そう、だったんですね……」
「それじゃあ、これから僕が言いたいことは二つあるんだ。一つ目は部活に関して」
「はい……」
「文芸部が廃部になることは決まっているんだ。廃部に関しては、僕がきちんと言わなくて、不安にさせてしまったと思う。本当にごめんね」
「あの、廃部になることって、もう、決まってるんですか?」
「そうだね。星原くんが部活に来る前から、そういう話は出ていたんだ」
「え……?」
「僕が入学する前の文芸部は、作品作りもままならないくらいひどく緩い部活だったんだ。そのせいもあって、僕が入ってからも、僕以外真面目にやりたい、という人がいなかったんだ。話し合いをしたけれどもなかなかうまくいかなくてね。そして、最終的には、ちゃんと作品を作りたい、という意志を持って残ったのが僕一人だけになってしまった。それが今年の3月。2年生の部員は全員退部して、3年生の部員は籍だけ残すことになった。もうそこで、廃部は決まってしまったようなものだった。ただ、どうしても文芸部の活動がしたくて、今年の部活の期間だけ」
「そう、だったんですね……」
そして、先輩はひどく穏やかな視線を俺に向けてくれていた。
「本当はね、星原くんが来る前に、廃部を受け入れて、終わりにしようと思っていたんだ」
「え……?」
「確かに僕目当てで来た子もいた。部活の外、であれば僕目当てでも対応したけれども、部活に、そんなうわついた気持ちを持ち込んで欲しくはなかった。だから、きっと、星原くんも、冷やかしか何かだろう、と正直思ってしまったんだ。星原くんが」
「……。すみません。冷やかし、というか“先輩に会いたい”みたいな邪な気持ちで部活に来ました……」
「なんとなくそれは分かっていたよ。けれどもね、その子達と星原くんの違うところは、ちゃんとテストをクリアしてくれたところだ」
「え……」
「星原くんの頑張りを見て、そして、星原くんの文章を見て、もう少し、この部活で、星原くんと一緒にやりたい、と思ったんだ。あんなに頑張って文章を書いてきてくれたのは星原くんだけ、だったからね」
「先輩……」
「そして、星原くんは、ちゃんと、文章も好きになっていた。星原くんの文章はとても素敵だった。今も頑張っている。けれども、星原くんの文章はね、情熱に溢れていて、まっすぐで、素直だった。僕みたいなのを書きたい、って言ってくれたけれども、ちゃんと、そこに自分の色を付けようとしている。僕の文章を頭に置きながらも、自分のえがきたいものをちゃんと描こうとしている。何よりも、悩んだり、苦しんだり、楽しそうに書く星原くんを見ていると、僕も頑張ろう、という気持ちになっていた」
先輩はふわりと俺の方に柔らかく視線を向けてくれる。その瞳は、まるで、愛おしいものを見つめているような視線。ドキドキと心拍が高鳴った。
「あと、星原くんと過ごしているのは純粋に楽しいんだ」
「た、楽しい、ですか……?」
「最初は、あまり表情の変わらない子かな、と思ったんだ。けれどもね、それは、僕の思い違いだった」
「そ、そうですか……?」
「星原くんのくるくる変わる表情を見ているのは楽しいし、一生懸命に頑張ってくれる星原くんの姿は素敵だ。そして、何かを食べるちょっと子どもっぽい顔も、僕のことが好きなんだって伝わってくる姿も、どれもとても愛おしいんだ」
「…………、えっと……、その、先輩……、!? その、あのっ……、好きってっ……!?」
「そうだよ。二つ目に言いたかったこと。僕は君のことがずっと好きだった」
先輩は柔らかな表情で俺の方に視線を向ける。
「あの日、僕にあの文章を見せてくれた時から、僕は、星原くんのことが好きだったのかもしれない」
「え……?」
「でも、この関係が変わってしまうのが怖くてね、なかなか、言い出すことが出来なかったんだ。この関係が、壊れてしまうくらいであったら、何もしない方がいいんじゃないかと思ってね」
「……そう、なんですね……。俺も、です……」
先輩も、俺と同じだった。それは、先輩の引き出してくれた表情だった。俺の知らない感情を、先輩が、教えてくれた。
「ちゃんと俺が言わずに、つらい想いをさせてしまったみたいで、本当にごめんね」
「っ……!」
そのまま、先輩はぎゅう、と俺のことをさらに強く抱きしめてくれた。
「これが、僕の気持ちだ」
そして、先輩は腕の力を緩めて、その手を、僕の頬を包み込むように触れた。先輩の、少し低い指先の温度が頬に伝わる。花火大会の時の手の温度。書き記せないくらい。どきどきしている。俺も、その動きを受け入れた。
「俺も、先輩が、好きです……」
目の前で、先輩が笑っていた。ふわりとした柔らかい微笑み。
「そして、二つ目のこと。文芸部が廃部になる。けれども、僕は、もう一度、文芸部を立て直したいと思っているんだ」
「そ、そうなんですか……!」
「そんなことを言うと、重いと感じてしまうんじゃないか、って思ってしまったんだ」
「そ、そんなこと、ないです……。うれしいです……。先輩がそう言ってくれるなんて……」
先輩はふわりと俺に柔らかい微笑みを向けた。
「ついてきて、くれるかな」
「は、はい……!」
頷いた時の先輩は、すごく綺麗な笑顔を浮かべていた。