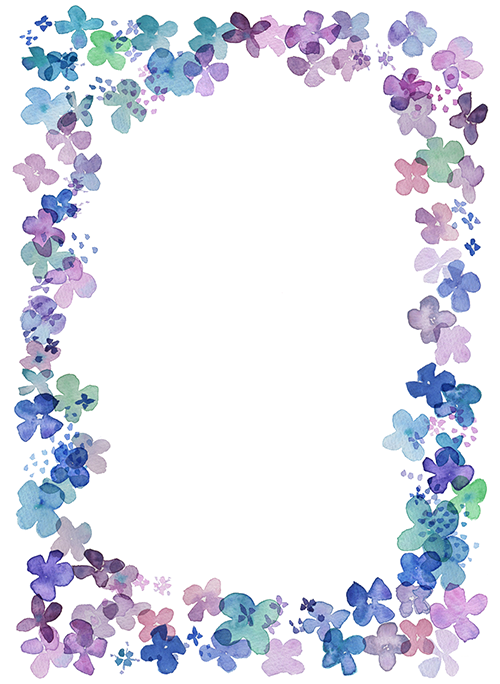もう一人の先生が職員室に入っていったタイミングで、俺は慌てながら本田先生に訊ねた。
「ほ、本田先生っ……!? 文芸部が今年で、終わりって、どういうことですか……!?」
俺は強烈な動揺の声を出しながら本田先生に訊ねた。本田先生は少し驚いたような表情を浮かべている。
「成神くんから何も訊いてないかい?」
「は、はい……、なんにも……」
本田先生は驚きの表情から、ひどく神妙な表情へと変わる。口をもごもごとさせて、すごく言い出しにくそうに。そして、しばらくそんな動きをした後に、口を開いた。
「あのね、文芸部は今年度――来年の3月に廃部になる予定なんだ」
「えっ……!? は、廃部、ですか……?」
「3年生の籍を置いている子達は籍は置いているけれども部活には参加しなかった。こうして10月になったけれども、部員が新しく入ることはなかった。だから、ね……」
「そ、そんな……」
「廃部の話はね、4月頃から決まってたんだ。4月頃から何度もいろいろと話し合って、成神くんが粘ってくれてはいたけれど、やっぱり覆らなかったんだ」
「………」
もしかして、4月、先生にプロット表を見せる時に喋っていたのは、度々先生に呼ばれていたのは、その話をするため、だったかもしれない。
「だから、活動内容も、文化祭以降はあまりはっきりとした活動内容は組み立てられなくてね」
「そう、なんですね……」
「来月の3月までは部活はあるからね。その間にこれからどうするか、考えておいて」
本田先生は優しく言う。けれども、俺の動揺は落ち着くことがなかった。
―――
家に帰ってからも、廃部、ということが頭から離れなかった。
“本田先生から廃部になる、って訊きました。部活、なくなっちゃうんですか?”
俺は先輩に打ち込んで消して、を繰り返す。しかし、送信ボタンを押そうとしたところで、その手が止まってしまう。
「部活が廃部になったら、俺、先輩との接点、あるのかな……」
つい、呟いてしまった。同じクラスでもなんでもない。
この部活が、なくなったら、先輩との繋がりもなくなってしまうかもしれない。先輩と全くしゃべらなくなってしまうのかもしれない。先輩だったら、俺じゃなくても、きっといい人がいると思う。
「……」
時間だけが、過ぎていく。ぱちぱちとキーボードを打ち込んでいく。停滞、みたいな期間だ。予定が何もない期間。何も考えずに、無心で手だけを動かした。手を動かしている時だけは、何も考えずに済むから。
「どうしたの? 最近、すごく元気がないけれど……」
「いえ、なんでも……」
この関係性が変わってしまうことが怖くて、訊ねることが出来なかった。そのまま、一ヶ月が経ってしまった。それまでと、何も変わらない日々が過ぎていった。
――
11月半ば、修学旅行が近づいてきた。先輩は修学旅行の事前打ち合わせみたいなのがあって、そして、二年生はテストが前倒しで行われる。だから、今日が、テスト前に先輩と会える最後の部活。
俺はプロットに沿って作品を書いていた。想いの文学賞に出す作品。内容は、高校の先輩に片思いをする子の話だ。進んではいるけれども、俺はどこかうわの空という感じで執筆をしていた。
「そうだ。星原くん」
「は、はい……。何でしょうか」
「修学旅行から帰ってきたら、きちんと、言わせてほしいことがあるんだ。いい?」
「い、言わせて欲しい、ことですか?」
「うん。文化祭の日から、ずっと、言おうと思って、言えなかったことだよ」
俺の中に、きっと、廃部のこと。あとは、城崎先輩のこと、かもしれない。
そして、部活終わりの時間になる。部室の前、先輩が部室棟の鍵を返してくれるからって、少し前を歩いていた時だった。
「それじゃあ、また、部活明けに、会おうね」
「あ、あの……、ま、待ってください……!」
別れる直前、俺はつい先輩を呼び止めてしまった。
「ん? どうしたの?」
先輩、城崎先輩のことはどう思ってるんですか?
部活、廃部になってしまうんですか?
もし、廃部になったら、俺は……
「星原くん……?」
先輩の口からひどく戸惑った声が出てきていた。先輩に訊ねようとしていたのに、俺は、思わず先輩に後ろ抱き、してしまっていた。
「すみません……、その、別れの前に、抱きしめるシーン、みたいなのがあって……」
もしかしたら、先輩とは、近いうちになってしまうのかもしれない。そう思うと、こうせずにはいられなかった。そんな風に誤魔化さなくてもよかったらいいのに。
今まで、こんな感情、知らなかった。
「大丈夫、修学旅行からちゃんと帰って来るからね。今生の別れじゃないから」
「す、すみません……」
「お土産、ちゃんと買ってくるからね」
先輩は俺のことを優しく撫でてくれる。ふわふわとした優しい手付き。でも、俺は安心することは出来なかった。
――
部屋の中、カタカタとキーボードの音が響いている。
テストが終わった後、俺は全てを忘れるために、ひたすらに文字を打ち込んだ。「想いの文学賞」に出す小説を寝ないで書いていた。起きている間、こうやって打ち込めば、それ以外のことを考えなくて済むから。
「…………」
机の上にペンが置いてある。先輩から貰ったシャープペン。
アルミのボディに映る俺の顔は、歪んでいる。泣きそうな表情をしていた。こんなに悲しいこと、今まであっただろうか。
「先輩と離れたら、この想いって、どうすればいいんだろう」
俺の口からなんだか悲しい響きの言葉が出て来る。それこそ、先輩には言わないでおいた方がいいのかな。
そして俺が書いていたのは、卒業と共に離れてしまう作品。先輩に対しての想いを抱いていた。
“一緒に、いたいよ”
“あなたとずーっと一緒に”
“いつか、離れてしまう時が来ても、ずっと一緒にいたい”
画面の向こうには、そんな言葉が載せられていた。それは、登場人物のセリフではあったけれど、俺の思いをそのままぶつけているかのような言葉だった。
「ほ、本田先生っ……!? 文芸部が今年で、終わりって、どういうことですか……!?」
俺は強烈な動揺の声を出しながら本田先生に訊ねた。本田先生は少し驚いたような表情を浮かべている。
「成神くんから何も訊いてないかい?」
「は、はい……、なんにも……」
本田先生は驚きの表情から、ひどく神妙な表情へと変わる。口をもごもごとさせて、すごく言い出しにくそうに。そして、しばらくそんな動きをした後に、口を開いた。
「あのね、文芸部は今年度――来年の3月に廃部になる予定なんだ」
「えっ……!? は、廃部、ですか……?」
「3年生の籍を置いている子達は籍は置いているけれども部活には参加しなかった。こうして10月になったけれども、部員が新しく入ることはなかった。だから、ね……」
「そ、そんな……」
「廃部の話はね、4月頃から決まってたんだ。4月頃から何度もいろいろと話し合って、成神くんが粘ってくれてはいたけれど、やっぱり覆らなかったんだ」
「………」
もしかして、4月、先生にプロット表を見せる時に喋っていたのは、度々先生に呼ばれていたのは、その話をするため、だったかもしれない。
「だから、活動内容も、文化祭以降はあまりはっきりとした活動内容は組み立てられなくてね」
「そう、なんですね……」
「来月の3月までは部活はあるからね。その間にこれからどうするか、考えておいて」
本田先生は優しく言う。けれども、俺の動揺は落ち着くことがなかった。
―――
家に帰ってからも、廃部、ということが頭から離れなかった。
“本田先生から廃部になる、って訊きました。部活、なくなっちゃうんですか?”
俺は先輩に打ち込んで消して、を繰り返す。しかし、送信ボタンを押そうとしたところで、その手が止まってしまう。
「部活が廃部になったら、俺、先輩との接点、あるのかな……」
つい、呟いてしまった。同じクラスでもなんでもない。
この部活が、なくなったら、先輩との繋がりもなくなってしまうかもしれない。先輩と全くしゃべらなくなってしまうのかもしれない。先輩だったら、俺じゃなくても、きっといい人がいると思う。
「……」
時間だけが、過ぎていく。ぱちぱちとキーボードを打ち込んでいく。停滞、みたいな期間だ。予定が何もない期間。何も考えずに、無心で手だけを動かした。手を動かしている時だけは、何も考えずに済むから。
「どうしたの? 最近、すごく元気がないけれど……」
「いえ、なんでも……」
この関係性が変わってしまうことが怖くて、訊ねることが出来なかった。そのまま、一ヶ月が経ってしまった。それまでと、何も変わらない日々が過ぎていった。
――
11月半ば、修学旅行が近づいてきた。先輩は修学旅行の事前打ち合わせみたいなのがあって、そして、二年生はテストが前倒しで行われる。だから、今日が、テスト前に先輩と会える最後の部活。
俺はプロットに沿って作品を書いていた。想いの文学賞に出す作品。内容は、高校の先輩に片思いをする子の話だ。進んではいるけれども、俺はどこかうわの空という感じで執筆をしていた。
「そうだ。星原くん」
「は、はい……。何でしょうか」
「修学旅行から帰ってきたら、きちんと、言わせてほしいことがあるんだ。いい?」
「い、言わせて欲しい、ことですか?」
「うん。文化祭の日から、ずっと、言おうと思って、言えなかったことだよ」
俺の中に、きっと、廃部のこと。あとは、城崎先輩のこと、かもしれない。
そして、部活終わりの時間になる。部室の前、先輩が部室棟の鍵を返してくれるからって、少し前を歩いていた時だった。
「それじゃあ、また、部活明けに、会おうね」
「あ、あの……、ま、待ってください……!」
別れる直前、俺はつい先輩を呼び止めてしまった。
「ん? どうしたの?」
先輩、城崎先輩のことはどう思ってるんですか?
部活、廃部になってしまうんですか?
もし、廃部になったら、俺は……
「星原くん……?」
先輩の口からひどく戸惑った声が出てきていた。先輩に訊ねようとしていたのに、俺は、思わず先輩に後ろ抱き、してしまっていた。
「すみません……、その、別れの前に、抱きしめるシーン、みたいなのがあって……」
もしかしたら、先輩とは、近いうちになってしまうのかもしれない。そう思うと、こうせずにはいられなかった。そんな風に誤魔化さなくてもよかったらいいのに。
今まで、こんな感情、知らなかった。
「大丈夫、修学旅行からちゃんと帰って来るからね。今生の別れじゃないから」
「す、すみません……」
「お土産、ちゃんと買ってくるからね」
先輩は俺のことを優しく撫でてくれる。ふわふわとした優しい手付き。でも、俺は安心することは出来なかった。
――
部屋の中、カタカタとキーボードの音が響いている。
テストが終わった後、俺は全てを忘れるために、ひたすらに文字を打ち込んだ。「想いの文学賞」に出す小説を寝ないで書いていた。起きている間、こうやって打ち込めば、それ以外のことを考えなくて済むから。
「…………」
机の上にペンが置いてある。先輩から貰ったシャープペン。
アルミのボディに映る俺の顔は、歪んでいる。泣きそうな表情をしていた。こんなに悲しいこと、今まであっただろうか。
「先輩と離れたら、この想いって、どうすればいいんだろう」
俺の口からなんだか悲しい響きの言葉が出て来る。それこそ、先輩には言わないでおいた方がいいのかな。
そして俺が書いていたのは、卒業と共に離れてしまう作品。先輩に対しての想いを抱いていた。
“一緒に、いたいよ”
“あなたとずーっと一緒に”
“いつか、離れてしまう時が来ても、ずっと一緒にいたい”
画面の向こうには、そんな言葉が載せられていた。それは、登場人物のセリフではあったけれど、俺の思いをそのままぶつけているかのような言葉だった。