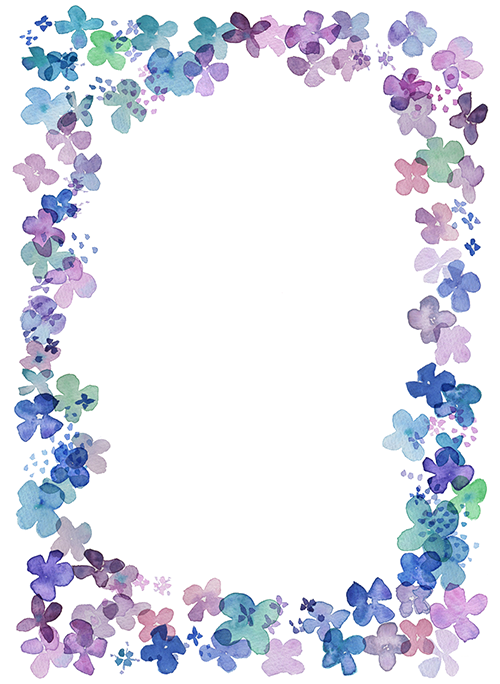そして、また変わらない日常が始まっていった。カリカリと文章を書いている。文化祭の後に一本小説を書いた後10月は本を読んだり、各自の活動となっていた。
その日、俺は本田先生に呼び出されていて、部活に行く前に、職員室にいた。
「想いの小説賞、ですか?」
「ああ、星原くんの小説に似合うだろうなあ、と思ってね」
先生が呼び出したのは、“想いの小説賞”に出してみないか。という誘いだった。先生は申し込み用紙付きのチラシを渡してくれた。
「ありがとうございます」
チラシを読みながら部室へと向かう。題材はなんでもOK。喜怒哀楽の想い、をぶつけろ、というコンテストだった。テーマは自由。締切りは11月末。入賞者は都心のホテルに泊まっての表彰式があり、そして書籍化も検討される、らしい。1学期のテストの時に読んだあの本は、もしかしたらこの賞を取った作品なのかもしれない。なんだかおもしろそう。出してみよう、と思いながら、俺は文芸部の部室へと向かった。
「あ……」
部室の前、先輩と仲良しそうに喋っている城崎さんがいた。胸の中にじくじくとした感覚が走っていた。城崎さんはキラキラとした笑顔で喋っている。そして、手を振って、階段を降りていった。俺は、城崎先輩に気づかれないように、城崎先輩が部室棟の階段を降りていって、その場を去った後に先輩の元へと向かった。
「星原くん。こんにちは」
「す、すみません……、その、あの、遅くなってしまって」
「うん。大丈夫だよ」
「あの、先ほど、城崎先輩とは何のお話を……」
「ああ、修学旅行関係の話をしていたんだ。来月が修学旅行だからね」
「そ、そうなんですね……」
「城崎さんに何か用があったの?」
「い、いえ……、なんでも……」
先輩は、ただ事実を述べるように口にしていた。そこから、先輩の感情は読み取れない。城崎さんに惚れている、という感じでもなさそう。けれども、やっぱり他の女性と話す、というのは、少し、胸が痛んだ。
俺は先生にもらった応募用紙を記入する。先輩はその横で、お揃いのシャープペンを使ってプロットを記入していた。
「想いの文学賞、出すの?」
「は、はい……。出すつもりです」
「そうなんだね。頑張ってね」
「あ、ありがとうございます……」
申込用紙を書いた後、俺もプロットを作り始めた。想いの文学賞用のプロットを。でも、城崎先輩のことをずっと考えてしまっていた。申込用紙を本田先生に渡そうとしたけれど、本田先生は今日は早く帰ってしまったみたいで、出すことはできなかった。明日出そう、と思った。
その日一日、城崎先輩のことが頭から離れなかった。
―――
「星原。大丈夫か~。星原~」
「あ、ごめん」
昼時、小澤に手を目の前で振られて、俺は気が付いた。弁当箱を持ったままぼーっとしてしまっていたみたいだ。頭の中にあったのは、城崎先輩だった。
「星原、またぼーっとしてるぞ。具合、悪いのか?」
「……あのさ、小澤。もしも超平凡でなんの面白みもない子と、クラスのマドンナの超美人、どっちと付き合いたい?」
「え、付き合うんだったら……? 性格とかにもよるかな。でも、クラスのマドンナの超美人だったら、その、後者に誘惑されるかもしれねえ」
「……。やっぱり、そうなるよね」
「どうしたんだ?」
「……。先輩が、城崎先輩と、距離が近い気がして……」
「なるほどなあ……。城崎先輩が相手、かあ……」
小澤はひどく言い淀んでいる。「うーん」とか「えーと」とかすごく言いにくそうだった。そりゃあ言いにくいと思う。
「まあ、応援してるからな。頑張れ」
「うん……」
しばらくの迷ったような声の後に、そういう、無難な答えが返ってきた。俺が小澤の立場で、同じ質問をされたら、同じように答えてしまうと思う。けれども、なんだか、現実を突きつけられているような感覚があった。
そして、落ち着かないままに俺は午後の授業を受けていた。今日何度目か分からずに、筆箱を開けた時だった。
筆箱の中、形も何もかもが同じ銀色のシャーペンが二本。
「あ……」
昨日の部活、先輩のシャープペンを持ってきてしまったみたいだ。まさか、この時間まで気づかなかったとは。あまりにもぼーっとしてたみたいだ。部活で渡せばいいとは思うけれど、消しゴムだ。授業の行間休み、俺は先輩の教室――2年1組の教室へと向かった。下心は全くなく、さすがに俺が持っているわけにはいかないから。
3階の教室。休み時間ではないから、先輩を囲んで……、というのはなかった。
「失礼します……」
きょろきょろと先輩を探す。すると、俺の方にぱたぱたと近づいてきた。城崎先輩が。
「ああ、もしかして文芸部の子かな! どうしたの?」
「あの、間違って成神先輩のシャープペンを持っていってしまって……」
「あ、レンくんね。今、文芸部の先生に呼ばれてていないから、会うから渡しておくよ!」
城崎先輩は、俺の手にあったシャープペンをひょい、と手に取ってしまった。それは、親切心、というよりも、先輩と喋るチャンスが欲しい、とか悪く言えば牽制、という感じが近かった。まあ、俺は、恋のライバルとして認識すらされていないだろうけれど。
そのまま俺は、その場から離れることしか出来なかった。
二階の廊下を、とぼとぼと、という感じで歩いていた時だった。
「城崎ちゃんってさ、貴公子のこと好きなのかな」
そんな声が聞こえて思わず立ち止まってしまう。盗み聞き、よくないことだ、と分かっていても、つい、立ち止まって、聞き耳をたててしまった。
「狙ってるんじゃない? 貴公子とおんなじ班になりたい、って言ってたからさ~」
「まあ、城崎ちゃんだったらいけんじゃない? 可愛いからね~」
俺の心が、さらに押しつぶされそうだった。俺が隣にいるよりも、あんなに綺麗な先輩と付き合えるんだったら、幸せだと思う。
俺みたいな平凡で感情が薄っぺらくて、面白みのない男よりも絶対いい、と思った。
部活の時間も、やっぱり全然落ち着かなかった。先輩は今日は修学旅行の打ち合わせがあるから、遅く来る。一人の部室、俺は、どこか心ここにあらず、という感じで作業をしていた。
「……、くん、」
「え……?」
「星原くん」
先輩の声が聞こえてくる。先輩はずっと俺のことを呼んでいたみたいだ。先輩は心配そうに俺のことを覗き込んでいる。
「大丈夫? 具合、悪い?」
「い、いえ……」
「さっきは消しゴムありがとう。城崎さんから、わざわざ持ってきてくれた、って訊いたよ」
「すみません、元々は俺が間違ってしまって……。先輩?」
俺の言葉が止まる。先輩の表情が、俺を見つめるような表情になっていたから。
「どうしたの? 何か悩んでる? 嫌なこととか、あった? あんまり、顔色よくないよ?」
「えっと……。
先輩が俺の方にそっと手を伸ばす。そして、そっと髪をかきあげて、俺の額に先輩の手を当てた。先輩と、同じくらいの温度が俺の手に伝わる。
「えっ……」
「……、熱とかは、ないね……」
「今、季節の変わり目とかで、疲れちゃってるかな」
「い、いえ……! だ、大丈夫です……!」
「星原くんが調子が悪いのは、僕も心配だよ」
先輩は心配そうな顔で俺の方を見つめている。
「すみません。大丈夫ですので……」
「そっか。なら、いいんだけど。あんまり、無理しないでね」
「は、はい……」
そして、部活が終わる。プロットが出来上がった。俺は一度先生にプロットを見せに行こうとした時だった。
「あの、文芸部の件ですが……」
「そうだね、文芸部も、今年で終わりですからね……」
俺の耳に間違いなく聞こえてきた。今年で終わり、という言葉。終わり、ってどういうことなんだろう。俺の身体に強烈な焦りが走る。心臓の拍動がひどく乱れていた。
その日、俺は本田先生に呼び出されていて、部活に行く前に、職員室にいた。
「想いの小説賞、ですか?」
「ああ、星原くんの小説に似合うだろうなあ、と思ってね」
先生が呼び出したのは、“想いの小説賞”に出してみないか。という誘いだった。先生は申し込み用紙付きのチラシを渡してくれた。
「ありがとうございます」
チラシを読みながら部室へと向かう。題材はなんでもOK。喜怒哀楽の想い、をぶつけろ、というコンテストだった。テーマは自由。締切りは11月末。入賞者は都心のホテルに泊まっての表彰式があり、そして書籍化も検討される、らしい。1学期のテストの時に読んだあの本は、もしかしたらこの賞を取った作品なのかもしれない。なんだかおもしろそう。出してみよう、と思いながら、俺は文芸部の部室へと向かった。
「あ……」
部室の前、先輩と仲良しそうに喋っている城崎さんがいた。胸の中にじくじくとした感覚が走っていた。城崎さんはキラキラとした笑顔で喋っている。そして、手を振って、階段を降りていった。俺は、城崎先輩に気づかれないように、城崎先輩が部室棟の階段を降りていって、その場を去った後に先輩の元へと向かった。
「星原くん。こんにちは」
「す、すみません……、その、あの、遅くなってしまって」
「うん。大丈夫だよ」
「あの、先ほど、城崎先輩とは何のお話を……」
「ああ、修学旅行関係の話をしていたんだ。来月が修学旅行だからね」
「そ、そうなんですね……」
「城崎さんに何か用があったの?」
「い、いえ……、なんでも……」
先輩は、ただ事実を述べるように口にしていた。そこから、先輩の感情は読み取れない。城崎さんに惚れている、という感じでもなさそう。けれども、やっぱり他の女性と話す、というのは、少し、胸が痛んだ。
俺は先生にもらった応募用紙を記入する。先輩はその横で、お揃いのシャープペンを使ってプロットを記入していた。
「想いの文学賞、出すの?」
「は、はい……。出すつもりです」
「そうなんだね。頑張ってね」
「あ、ありがとうございます……」
申込用紙を書いた後、俺もプロットを作り始めた。想いの文学賞用のプロットを。でも、城崎先輩のことをずっと考えてしまっていた。申込用紙を本田先生に渡そうとしたけれど、本田先生は今日は早く帰ってしまったみたいで、出すことはできなかった。明日出そう、と思った。
その日一日、城崎先輩のことが頭から離れなかった。
―――
「星原。大丈夫か~。星原~」
「あ、ごめん」
昼時、小澤に手を目の前で振られて、俺は気が付いた。弁当箱を持ったままぼーっとしてしまっていたみたいだ。頭の中にあったのは、城崎先輩だった。
「星原、またぼーっとしてるぞ。具合、悪いのか?」
「……あのさ、小澤。もしも超平凡でなんの面白みもない子と、クラスのマドンナの超美人、どっちと付き合いたい?」
「え、付き合うんだったら……? 性格とかにもよるかな。でも、クラスのマドンナの超美人だったら、その、後者に誘惑されるかもしれねえ」
「……。やっぱり、そうなるよね」
「どうしたんだ?」
「……。先輩が、城崎先輩と、距離が近い気がして……」
「なるほどなあ……。城崎先輩が相手、かあ……」
小澤はひどく言い淀んでいる。「うーん」とか「えーと」とかすごく言いにくそうだった。そりゃあ言いにくいと思う。
「まあ、応援してるからな。頑張れ」
「うん……」
しばらくの迷ったような声の後に、そういう、無難な答えが返ってきた。俺が小澤の立場で、同じ質問をされたら、同じように答えてしまうと思う。けれども、なんだか、現実を突きつけられているような感覚があった。
そして、落ち着かないままに俺は午後の授業を受けていた。今日何度目か分からずに、筆箱を開けた時だった。
筆箱の中、形も何もかもが同じ銀色のシャーペンが二本。
「あ……」
昨日の部活、先輩のシャープペンを持ってきてしまったみたいだ。まさか、この時間まで気づかなかったとは。あまりにもぼーっとしてたみたいだ。部活で渡せばいいとは思うけれど、消しゴムだ。授業の行間休み、俺は先輩の教室――2年1組の教室へと向かった。下心は全くなく、さすがに俺が持っているわけにはいかないから。
3階の教室。休み時間ではないから、先輩を囲んで……、というのはなかった。
「失礼します……」
きょろきょろと先輩を探す。すると、俺の方にぱたぱたと近づいてきた。城崎先輩が。
「ああ、もしかして文芸部の子かな! どうしたの?」
「あの、間違って成神先輩のシャープペンを持っていってしまって……」
「あ、レンくんね。今、文芸部の先生に呼ばれてていないから、会うから渡しておくよ!」
城崎先輩は、俺の手にあったシャープペンをひょい、と手に取ってしまった。それは、親切心、というよりも、先輩と喋るチャンスが欲しい、とか悪く言えば牽制、という感じが近かった。まあ、俺は、恋のライバルとして認識すらされていないだろうけれど。
そのまま俺は、その場から離れることしか出来なかった。
二階の廊下を、とぼとぼと、という感じで歩いていた時だった。
「城崎ちゃんってさ、貴公子のこと好きなのかな」
そんな声が聞こえて思わず立ち止まってしまう。盗み聞き、よくないことだ、と分かっていても、つい、立ち止まって、聞き耳をたててしまった。
「狙ってるんじゃない? 貴公子とおんなじ班になりたい、って言ってたからさ~」
「まあ、城崎ちゃんだったらいけんじゃない? 可愛いからね~」
俺の心が、さらに押しつぶされそうだった。俺が隣にいるよりも、あんなに綺麗な先輩と付き合えるんだったら、幸せだと思う。
俺みたいな平凡で感情が薄っぺらくて、面白みのない男よりも絶対いい、と思った。
部活の時間も、やっぱり全然落ち着かなかった。先輩は今日は修学旅行の打ち合わせがあるから、遅く来る。一人の部室、俺は、どこか心ここにあらず、という感じで作業をしていた。
「……、くん、」
「え……?」
「星原くん」
先輩の声が聞こえてくる。先輩はずっと俺のことを呼んでいたみたいだ。先輩は心配そうに俺のことを覗き込んでいる。
「大丈夫? 具合、悪い?」
「い、いえ……」
「さっきは消しゴムありがとう。城崎さんから、わざわざ持ってきてくれた、って訊いたよ」
「すみません、元々は俺が間違ってしまって……。先輩?」
俺の言葉が止まる。先輩の表情が、俺を見つめるような表情になっていたから。
「どうしたの? 何か悩んでる? 嫌なこととか、あった? あんまり、顔色よくないよ?」
「えっと……。
先輩が俺の方にそっと手を伸ばす。そして、そっと髪をかきあげて、俺の額に先輩の手を当てた。先輩と、同じくらいの温度が俺の手に伝わる。
「えっ……」
「……、熱とかは、ないね……」
「今、季節の変わり目とかで、疲れちゃってるかな」
「い、いえ……! だ、大丈夫です……!」
「星原くんが調子が悪いのは、僕も心配だよ」
先輩は心配そうな顔で俺の方を見つめている。
「すみません。大丈夫ですので……」
「そっか。なら、いいんだけど。あんまり、無理しないでね」
「は、はい……」
そして、部活が終わる。プロットが出来上がった。俺は一度先生にプロットを見せに行こうとした時だった。
「あの、文芸部の件ですが……」
「そうだね、文芸部も、今年で終わりですからね……」
俺の耳に間違いなく聞こえてきた。今年で終わり、という言葉。終わり、ってどういうことなんだろう。俺の身体に強烈な焦りが走る。心臓の拍動がひどく乱れていた。