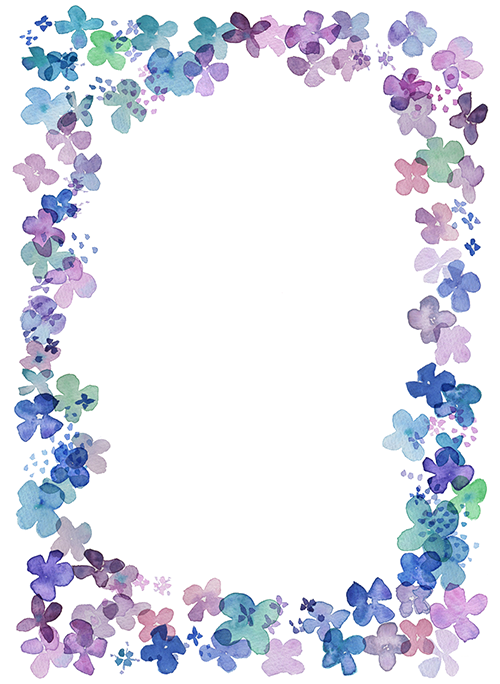先輩を花火大会に誘ってから10日。ついに、花火大会当日を迎えた。
「うーーーーーーーーーん……」
当日の午前中。俺は部屋で呻き声のような声を上げていた。何を着ていけばいいのか分からずに、その日を迎えてしまったから。
「こういう時って何着ればいいんだろう。浴衣……? シャツ……?」
服を胸の前に合わせて、ああでもない、こうでもない、と何度も合わせては取り換えて、を繰り返す。けれども全くしっくりこない。部活で出かけるときは制服だった。だから、ここで初めて私服を先輩に見せることになる。今まで遊ぶとしたらほとんどが小澤達。その時はラフなパーカーとジーンズ、挙げ句の果てにジャージ、とかだったけれども、さすがにその恰好で行くのはあまりにもラフすぎる。ああ、おしゃれのこと、もっと勉強すればよかったな……。なんて思ってしまった。時計を見る。あと5時間後には先輩と会う時間になる。家から待ち合わせの駅まではダッシュして15分くらい。
「春男。どうしたんだ?」
声をかけられて、俺は視線を声の方向に向ける。開け放していたドアの向こうに兄貴――星原夏彦がいた。だぼっとした服を着こなしているおしゃれなイケメンだ。俺とは違って表情も豊か。
「あ、あ、兄貴っ……!? 帰ってたの!? いつからそこに!?」
「さっきから。何回かただいまも言ってたぞ」
「う、嘘!?」
「ほんとほんと。で、服選びに時間かけてどうしたんだ?」
「そ、その……、花火大会、行くから」
「ああ。好きな子と一緒にか?」
「な、なななななんで!? その、一緒に行くって分かったの?」
「……そりゃここまで言ってくれれば分かるだろ。花火大会のポスターめっちゃ貼られてるの見たし、春男がそんな顔してんの初めてみたからそうかなって思って」
「そ、そんな顔って?」
「恋してますよ、みたいな顔」
「こ、恋してますよ、……?」
「そ、いい顔してるよ」
兄貴はなんだか嬉しそうに口角を上げて笑う。恋してますよ、ではないけど、似たようなことを小澤にも言われた気がする。 俺、無表情だ、とか喜怒哀楽が分かりにくいとか散々言われたのに、そんなにわかりやすい顔してたかな。
「部屋、入っていいか? 俺も選ぶの手伝うぞ? 古着屋やってる友達の手伝いとかしてたからな」
「あ、うん。ありがとう」
そして兄貴は服を俺の身体に当てていく。それこそファッションモデル、のように。
「どういう系統がいい? かっこいい、とか……」
「わかんないな、お任せ、してもいい?」
「おっけー。あと、俺の服、ちょっとデカいかもしれないけど貸すよ」
「あ、ありがとう」
そして、兄貴は服を持ってきてくれた。そしてそれも当てていく。兄貴の方がやや背がでかいけれど服のサイズはそこまで変わらない。服の山から合いそうな服を見つけて、そして俺の身体に当てていく。兄貴と俺の姿が鏡に映っていた。兄貴はやっぱり楽しそうだ。
「あ、あのさ、俺に好きな人がいるっていうのは、母さんとか父さんには……」
「もちろん、春男が言うまで内緒にするよ。そういうの茶化すのよくねえもんな」
「ありがとう、お願い」
「もちろん。で、どんな人かは訊いていいか?」
「う、うん……、その、なんだろう……。まず、顔が綺麗で、すっごくモテて……。優しくて、俺のことを気遣ってくれて……。あと、文章が、上手くって……、俺、文章、全然詳しくないんだけど……。その人の文章ってめちゃくちゃ上手くって、俺、こんな文章書いてみたいな、って文章詳しくない俺が思うくらいに……。あと、俺と過ごすのが楽しい、って言ってくれて……」
鏡に映る兄貴はうんうん、と頷いてくれた。兄貴とこうして一緒にいるのは随分と久しぶりだ。仲が悪い、わけじゃなくて、年が6歳、と結構離れてたから、会話する時間がなかったし、学校も被らなかったから。兄弟、というよりはどちらかというと「お盆と正月に会う親戚」みたいな感覚に近い。けれども悪い人ではない。むしろなんだかんだ俺を可愛がってくれる。こんな風に。
「そっかそっか。お前、ほんとにその人のこと好きなんだな。お前がそんな風に何かを熱心に話してるとこも、初めてみたからさ……」
「そうなんだと、思う。小澤にも、言われた」
「そっかそっか」
兄貴は満足そうに頷く。そして、しばらくして、俺の着ていく服が決まった。兄貴の貸してくれた大人っぽい襟付シャツにズボン。普段は絶対にしないような恰好をしている。
「ついでに頭もセッティングするか」
「あ、ありがとう……」
兄貴に連れられて洗面台へと向かう。兄貴はドライヤーとワックスを駆使してふわふわの頭にしてくれた。それこそ髪の毛だけ見ればアイドル、みたいな感じに。
「兄貴、すごいな……」
「そんなおだててもお小遣いは出ないぞ!じゃ、楽しんで来いよ!」
「うん……! ありがとう!」
財布を入れた小さいバッグを持って俺は向かった。学校の最寄り駅。兄貴にコーディネートしてもらった服を着て、俺は最寄り駅に向かった。
「お待たせ。星原くん」
きょろきょろと待ち合わせの中で落ち着かない時間を過ごした。何度も服と視線を往復させてしまう。この間とは全く違う感覚。駅の中には何人ものカップルがいた。駅の中のカップルを見てなんだかそわそわしてしまう
「お、お疲れ様です。先輩、かっこいいですね……、」
先輩、めちゃくちゃかっこいい。帽子に灰色の浴衣。なんというか、文豪をモチーフにした漫画とか、歴史を元にしたゲームに登場するイケメン、という感じ。次元が一つ違っていてもおかしくない、という姿をしていた。
「ありがとう。星原くんもとても素敵だよ」
「あ、ありがとうございます……」
先輩に言われて頬が熱くなる。小さい頃に観た恋愛ドラマで、デートの時に服装を褒められて嬉しそうにしていた画面向こうの登場人物のことを思い出した。当時は「褒められて嬉しい」は分かるけれど、そんなに喜ぶかな、と思った。けれども、今なら分かる。こんな風に言われるのは嬉しい。兄貴に感謝しなきゃな。
「それじゃあ、行こうか」
そして俺達は駅から歩いて花火大会の会場へと向かった。花火大会の会場は駅から5分ほど歩いた河川敷一体。進んでいくに連れて、人がだんだんと多くなっていく。
「わっ……!」
そして、後ろから誰かにどん、と押されてしまった。バランスを崩れて前のめりに転びそうになってしまう。けれども、転びそうになった俺の身体の動きはすぐに止まった。
「大丈夫? 怪我はない?」
先輩がぎゅ、と手首を握ってくれて、そして、俺の腹の方に軽く手を当てて、身体を起こしてくれた。先輩の動きに合わせて、俺も身体を起こす。
「す、すみません、大丈夫です……」
先輩は俺の身体を起こしても、しばらく手首を離すことはなかった。離した。と思ったら、今度は俺の手をぎゅ、と握った。瞬間、俺の身体に強烈な動揺が走る。
「あ、あの……、先輩……!?」
「これから人混みがもっとすごくなりそうだし、はぐれたら大変だからね。手を繋ごうか」
「は、はい……」
先輩の少し大きな手に包まれながら、ばくばくと激しく心臓を鳴らして、俺達は歩いていた。そして、俺達は出店が並んでいるゾーンに近づく。
「何か食べたいものある? 出店、寄ろうか?」
「あ、ありがとう、ございます……。それじゃあ、かき氷、で……」
「大丈夫? かき氷だけで足りる? 結構遅い時間まであるけれど……」
「だ、大丈夫です……」
「もしお腹すいたら、買ってくるから言ってね」
「あ、ありがとうございます」
先輩と一緒、しかもこういう状況だから緊張してしまっているのかもしれない。腹の中に何かが入る気がしなかった。普段だったら、もっとがっつりした、それこそたこ焼きとかからあげとか焼きそばとかをセレクトするはずなのに。
そして、俺達はかき氷を買った。先輩はいちご味。俺はレモン味を買って、花火が見れる場所へと向かった。かき氷を買う一瞬だけは手を離したけれど、その時以外は、「離れるといけない」からって先輩はずっと手を繋いだままだった。
「それじゃあ、この辺りに座ろうか。レジャーシート、ここに敷こうか」
「は、はい……」
そして二人、先輩が用意してくれたレジャーシートの上に座った。花火が始まる。かき氷を食べながら、花火を眺めている。どんどん、パラパラ、と破裂音のような音と共に、きらきらとした光が夜空いっぱいに散っている。隣で先輩がわあ、と声を出している。
「綺麗だね、花火……」
「そうですね……」
俺は花火を見ながらも、先輩の横顔もちらちらと眺めてしまう。先輩は口を開けている。どこか無邪気な子どものようにも見えてしまう。俺の視線は先輩の方に向けられてしまった
「ん、どうしたの?」
先輩の視線が俺の方に向けられる。打ち上げられる花火に照らされる先輩の顔は、いつもよりもずっと綺麗だった。
「あ、い、いえ……」
ドキドキとした、心臓の高鳴りに任せて、お祭りの高揚感に任せて、言ってしまおうか。昔観た恋愛ドラマで、お祭りとか花火大会とかでの告白、があった。今が、告白をするのに、一番いいタイミングなのかもしれない。俺の想いを、伝える時なのかもしれない。俺の唇が、開いてしまった。
「あ、あの……、先輩……!」
俺が、先輩のことを、呼んだ瞬間だった。
どーーーーん! と一際大きい破裂音。その音が、俺の声をかき消してしまう。キラキラとした一際大きい、白色の花火が、空に広がっている。
「ん? 星原くん。どうしたの?」
「い、いえ……。すみません、大丈夫です」
タイミングを逃してしまった。正気に返って、何も言うことが出来なくなってしまった。
あとは、視線を上げるだけ。先輩への想いを抱きながら、花火を見ることしかできなくなってしまった。パンパン、と小さな花火がいくつも夜空に散る。
「二人で来れて、よかったな……」
「え……?」
そんなつぶやきが聞こえてきたような気がした。けれども、すぐに花火の音が鳴ってしまう。気のせいでも、嬉しい。
先輩と二人、花火を楽しんでいた。
「綺麗だったね。花火。特に、あの一番大きい花火が本当に綺麗だった」
「そ、そうですね……」
やがて花火大会が終わって、俺達は駅へと戻ろうとした。人混みを味わいながら、俺達は歩いていく。やっぱり、帰りも、手を繋いで。「はぐれるといけないから」ということではあるけれど。
「今日は、ありがとうございました……」
「こちらこそ、ありがとう。楽しかったよ。……ねえ、星原くん」
「は、はい。なんでしょうか?」
「星原くんは、僕のこと、どう思っているの?」
「えっ……」
突然の質問に、俺は少し戸惑う。
「先輩は、その、素敵で、……。やっぱり、一緒にいて、すごく、楽しいです」
恥ずかしさというか照れから、少し、視線をそらしながら俺は言う。先輩は「そうなんだね。嬉しいよ」と柔らかな声で口にしてくれた。
そして、駅の少し手前で俺達は別れる。駅が結構混んでいたから、俺達は少し離れた、夜の人気のない場所で、俺達は解散することになった。
「先輩、今日はありがとうございました」
「あのさ、星原くん、少しだけ、いい?」
「え……?」
そして、先輩はぎゅ、と俺のことを抱きしめた。俺の心臓がばくばくと激しく跳ねている。夏だからか、先輩の、高い体温が伝わってきた。ほんの一瞬のことではあったけれども、俺にとって強烈な感情を与えていた。
「え、えっと、先輩……、あのっ……」
「……ごめんね。今日が楽しかったから、その、離れるのが、惜しくってね」
先輩が、少し困ったように笑っていた。そこからの記憶がほとんどない。気が付けば家だった。先輩と駅で別れた、というのは覚えているけれども。先輩との花火大会の余韻、そして、抱きしめられた感触が俺の中に残っている。
先輩との花火大会の余韻を残したまま、夏休みが終わりを迎えようとしていた。
「うーーーーーーーーーん……」
当日の午前中。俺は部屋で呻き声のような声を上げていた。何を着ていけばいいのか分からずに、その日を迎えてしまったから。
「こういう時って何着ればいいんだろう。浴衣……? シャツ……?」
服を胸の前に合わせて、ああでもない、こうでもない、と何度も合わせては取り換えて、を繰り返す。けれども全くしっくりこない。部活で出かけるときは制服だった。だから、ここで初めて私服を先輩に見せることになる。今まで遊ぶとしたらほとんどが小澤達。その時はラフなパーカーとジーンズ、挙げ句の果てにジャージ、とかだったけれども、さすがにその恰好で行くのはあまりにもラフすぎる。ああ、おしゃれのこと、もっと勉強すればよかったな……。なんて思ってしまった。時計を見る。あと5時間後には先輩と会う時間になる。家から待ち合わせの駅まではダッシュして15分くらい。
「春男。どうしたんだ?」
声をかけられて、俺は視線を声の方向に向ける。開け放していたドアの向こうに兄貴――星原夏彦がいた。だぼっとした服を着こなしているおしゃれなイケメンだ。俺とは違って表情も豊か。
「あ、あ、兄貴っ……!? 帰ってたの!? いつからそこに!?」
「さっきから。何回かただいまも言ってたぞ」
「う、嘘!?」
「ほんとほんと。で、服選びに時間かけてどうしたんだ?」
「そ、その……、花火大会、行くから」
「ああ。好きな子と一緒にか?」
「な、なななななんで!? その、一緒に行くって分かったの?」
「……そりゃここまで言ってくれれば分かるだろ。花火大会のポスターめっちゃ貼られてるの見たし、春男がそんな顔してんの初めてみたからそうかなって思って」
「そ、そんな顔って?」
「恋してますよ、みたいな顔」
「こ、恋してますよ、……?」
「そ、いい顔してるよ」
兄貴はなんだか嬉しそうに口角を上げて笑う。恋してますよ、ではないけど、似たようなことを小澤にも言われた気がする。 俺、無表情だ、とか喜怒哀楽が分かりにくいとか散々言われたのに、そんなにわかりやすい顔してたかな。
「部屋、入っていいか? 俺も選ぶの手伝うぞ? 古着屋やってる友達の手伝いとかしてたからな」
「あ、うん。ありがとう」
そして兄貴は服を俺の身体に当てていく。それこそファッションモデル、のように。
「どういう系統がいい? かっこいい、とか……」
「わかんないな、お任せ、してもいい?」
「おっけー。あと、俺の服、ちょっとデカいかもしれないけど貸すよ」
「あ、ありがとう」
そして、兄貴は服を持ってきてくれた。そしてそれも当てていく。兄貴の方がやや背がでかいけれど服のサイズはそこまで変わらない。服の山から合いそうな服を見つけて、そして俺の身体に当てていく。兄貴と俺の姿が鏡に映っていた。兄貴はやっぱり楽しそうだ。
「あ、あのさ、俺に好きな人がいるっていうのは、母さんとか父さんには……」
「もちろん、春男が言うまで内緒にするよ。そういうの茶化すのよくねえもんな」
「ありがとう、お願い」
「もちろん。で、どんな人かは訊いていいか?」
「う、うん……、その、なんだろう……。まず、顔が綺麗で、すっごくモテて……。優しくて、俺のことを気遣ってくれて……。あと、文章が、上手くって……、俺、文章、全然詳しくないんだけど……。その人の文章ってめちゃくちゃ上手くって、俺、こんな文章書いてみたいな、って文章詳しくない俺が思うくらいに……。あと、俺と過ごすのが楽しい、って言ってくれて……」
鏡に映る兄貴はうんうん、と頷いてくれた。兄貴とこうして一緒にいるのは随分と久しぶりだ。仲が悪い、わけじゃなくて、年が6歳、と結構離れてたから、会話する時間がなかったし、学校も被らなかったから。兄弟、というよりはどちらかというと「お盆と正月に会う親戚」みたいな感覚に近い。けれども悪い人ではない。むしろなんだかんだ俺を可愛がってくれる。こんな風に。
「そっかそっか。お前、ほんとにその人のこと好きなんだな。お前がそんな風に何かを熱心に話してるとこも、初めてみたからさ……」
「そうなんだと、思う。小澤にも、言われた」
「そっかそっか」
兄貴は満足そうに頷く。そして、しばらくして、俺の着ていく服が決まった。兄貴の貸してくれた大人っぽい襟付シャツにズボン。普段は絶対にしないような恰好をしている。
「ついでに頭もセッティングするか」
「あ、ありがとう……」
兄貴に連れられて洗面台へと向かう。兄貴はドライヤーとワックスを駆使してふわふわの頭にしてくれた。それこそ髪の毛だけ見ればアイドル、みたいな感じに。
「兄貴、すごいな……」
「そんなおだててもお小遣いは出ないぞ!じゃ、楽しんで来いよ!」
「うん……! ありがとう!」
財布を入れた小さいバッグを持って俺は向かった。学校の最寄り駅。兄貴にコーディネートしてもらった服を着て、俺は最寄り駅に向かった。
「お待たせ。星原くん」
きょろきょろと待ち合わせの中で落ち着かない時間を過ごした。何度も服と視線を往復させてしまう。この間とは全く違う感覚。駅の中には何人ものカップルがいた。駅の中のカップルを見てなんだかそわそわしてしまう
「お、お疲れ様です。先輩、かっこいいですね……、」
先輩、めちゃくちゃかっこいい。帽子に灰色の浴衣。なんというか、文豪をモチーフにした漫画とか、歴史を元にしたゲームに登場するイケメン、という感じ。次元が一つ違っていてもおかしくない、という姿をしていた。
「ありがとう。星原くんもとても素敵だよ」
「あ、ありがとうございます……」
先輩に言われて頬が熱くなる。小さい頃に観た恋愛ドラマで、デートの時に服装を褒められて嬉しそうにしていた画面向こうの登場人物のことを思い出した。当時は「褒められて嬉しい」は分かるけれど、そんなに喜ぶかな、と思った。けれども、今なら分かる。こんな風に言われるのは嬉しい。兄貴に感謝しなきゃな。
「それじゃあ、行こうか」
そして俺達は駅から歩いて花火大会の会場へと向かった。花火大会の会場は駅から5分ほど歩いた河川敷一体。進んでいくに連れて、人がだんだんと多くなっていく。
「わっ……!」
そして、後ろから誰かにどん、と押されてしまった。バランスを崩れて前のめりに転びそうになってしまう。けれども、転びそうになった俺の身体の動きはすぐに止まった。
「大丈夫? 怪我はない?」
先輩がぎゅ、と手首を握ってくれて、そして、俺の腹の方に軽く手を当てて、身体を起こしてくれた。先輩の動きに合わせて、俺も身体を起こす。
「す、すみません、大丈夫です……」
先輩は俺の身体を起こしても、しばらく手首を離すことはなかった。離した。と思ったら、今度は俺の手をぎゅ、と握った。瞬間、俺の身体に強烈な動揺が走る。
「あ、あの……、先輩……!?」
「これから人混みがもっとすごくなりそうだし、はぐれたら大変だからね。手を繋ごうか」
「は、はい……」
先輩の少し大きな手に包まれながら、ばくばくと激しく心臓を鳴らして、俺達は歩いていた。そして、俺達は出店が並んでいるゾーンに近づく。
「何か食べたいものある? 出店、寄ろうか?」
「あ、ありがとう、ございます……。それじゃあ、かき氷、で……」
「大丈夫? かき氷だけで足りる? 結構遅い時間まであるけれど……」
「だ、大丈夫です……」
「もしお腹すいたら、買ってくるから言ってね」
「あ、ありがとうございます」
先輩と一緒、しかもこういう状況だから緊張してしまっているのかもしれない。腹の中に何かが入る気がしなかった。普段だったら、もっとがっつりした、それこそたこ焼きとかからあげとか焼きそばとかをセレクトするはずなのに。
そして、俺達はかき氷を買った。先輩はいちご味。俺はレモン味を買って、花火が見れる場所へと向かった。かき氷を買う一瞬だけは手を離したけれど、その時以外は、「離れるといけない」からって先輩はずっと手を繋いだままだった。
「それじゃあ、この辺りに座ろうか。レジャーシート、ここに敷こうか」
「は、はい……」
そして二人、先輩が用意してくれたレジャーシートの上に座った。花火が始まる。かき氷を食べながら、花火を眺めている。どんどん、パラパラ、と破裂音のような音と共に、きらきらとした光が夜空いっぱいに散っている。隣で先輩がわあ、と声を出している。
「綺麗だね、花火……」
「そうですね……」
俺は花火を見ながらも、先輩の横顔もちらちらと眺めてしまう。先輩は口を開けている。どこか無邪気な子どものようにも見えてしまう。俺の視線は先輩の方に向けられてしまった
「ん、どうしたの?」
先輩の視線が俺の方に向けられる。打ち上げられる花火に照らされる先輩の顔は、いつもよりもずっと綺麗だった。
「あ、い、いえ……」
ドキドキとした、心臓の高鳴りに任せて、お祭りの高揚感に任せて、言ってしまおうか。昔観た恋愛ドラマで、お祭りとか花火大会とかでの告白、があった。今が、告白をするのに、一番いいタイミングなのかもしれない。俺の想いを、伝える時なのかもしれない。俺の唇が、開いてしまった。
「あ、あの……、先輩……!」
俺が、先輩のことを、呼んだ瞬間だった。
どーーーーん! と一際大きい破裂音。その音が、俺の声をかき消してしまう。キラキラとした一際大きい、白色の花火が、空に広がっている。
「ん? 星原くん。どうしたの?」
「い、いえ……。すみません、大丈夫です」
タイミングを逃してしまった。正気に返って、何も言うことが出来なくなってしまった。
あとは、視線を上げるだけ。先輩への想いを抱きながら、花火を見ることしかできなくなってしまった。パンパン、と小さな花火がいくつも夜空に散る。
「二人で来れて、よかったな……」
「え……?」
そんなつぶやきが聞こえてきたような気がした。けれども、すぐに花火の音が鳴ってしまう。気のせいでも、嬉しい。
先輩と二人、花火を楽しんでいた。
「綺麗だったね。花火。特に、あの一番大きい花火が本当に綺麗だった」
「そ、そうですね……」
やがて花火大会が終わって、俺達は駅へと戻ろうとした。人混みを味わいながら、俺達は歩いていく。やっぱり、帰りも、手を繋いで。「はぐれるといけないから」ということではあるけれど。
「今日は、ありがとうございました……」
「こちらこそ、ありがとう。楽しかったよ。……ねえ、星原くん」
「は、はい。なんでしょうか?」
「星原くんは、僕のこと、どう思っているの?」
「えっ……」
突然の質問に、俺は少し戸惑う。
「先輩は、その、素敵で、……。やっぱり、一緒にいて、すごく、楽しいです」
恥ずかしさというか照れから、少し、視線をそらしながら俺は言う。先輩は「そうなんだね。嬉しいよ」と柔らかな声で口にしてくれた。
そして、駅の少し手前で俺達は別れる。駅が結構混んでいたから、俺達は少し離れた、夜の人気のない場所で、俺達は解散することになった。
「先輩、今日はありがとうございました」
「あのさ、星原くん、少しだけ、いい?」
「え……?」
そして、先輩はぎゅ、と俺のことを抱きしめた。俺の心臓がばくばくと激しく跳ねている。夏だからか、先輩の、高い体温が伝わってきた。ほんの一瞬のことではあったけれども、俺にとって強烈な感情を与えていた。
「え、えっと、先輩……、あのっ……」
「……ごめんね。今日が楽しかったから、その、離れるのが、惜しくってね」
先輩が、少し困ったように笑っていた。そこからの記憶がほとんどない。気が付けば家だった。先輩と駅で別れた、というのは覚えているけれども。先輩との花火大会の余韻、そして、抱きしめられた感触が俺の中に残っている。
先輩との花火大会の余韻を残したまま、夏休みが終わりを迎えようとしていた。