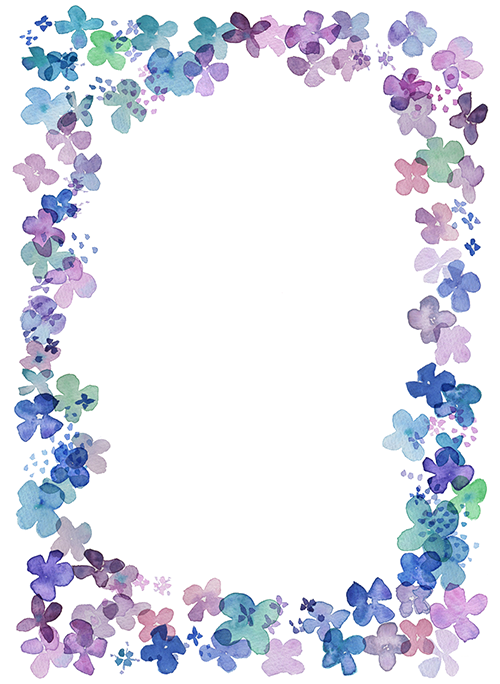そこからしばらく。プロットのOKをもらった頃、夏休みに入った。先生からは「いいね。難しいかもしれないけど頑張ってね」と言われた。
俺は部室の中にいた。夏休みは一日部活をすることが出来る。それは、先輩と一緒に過ごすことが出来るということ。
ちらり、と隣にいる先輩に視線を向ける。夏休みの部室だからか、先輩は、制服のネクタイを少し緩めていて、鎖骨が見えている。授業がある時とは違うラフな格好で、どきりとした。定位置の席に着くと、先輩の使っているシトラスの制汗剤の香りが漂ってくる。
「順調?」
「は、はい。なんとか」
「そっか。もしも詰まったら、すぐに言ってね」
「はい」
あらすじは、高嶺の花のクラスメイトに想いを抱いている、クラスでも目立たない男の子の話。先輩への思いを掛け合わせている。流石に先輩をモデルにはしていないけれども先輩への想いが根底にある。
先輩が、かりかりとペンを滑らせる音が響く。今はお揃いのシャープペンを使って何かを書いている。俺も、その書く音に合わせて、キーボードを叩いていた。
ちらちらと先輩の方に視線を向けてしまう。夏、二人きり、楽しい時間を過ごしていた。
深夜十二時、パソコンの画面と見つめ合いながら、文字を打ち込んでいた。パチパチとキーボードを叩いて、文章作成ソフトの上に、俺の想いをぶつける。その作業がひたすらに楽しい。夏休み。自由な時間。夏休みの宿題をする時間以外は全て創作に当ててしまっている。
文章を書くこと、なんて興味を持てなかったのに、この作業がひどく楽しい。
“あなたのことが、好きなんです……!“
そんなセリフが、画面に表示されている。学校中の憧れのクラスメイトに、勇気を出して告白する、というシーン。
書いているの。画面の中で喋っているのは、。けれども、そこには、俺の、先輩に対しての想いが重ねられているのかもしれない。
「たのしいな」
頭の中にあるのは先輩のこと。思わず、俺の口から笑みがこぼれる。表情筋が硬かった俺だけど、今のは自分でも笑ってる、って分かる。テンションが低くて表情の抑揚が薄い俺だったのに、先輩といて、いろんな感情を知っていっている感じがする。先輩、今度は俺の小説、どんな風に見てくれるかな。また、褒めてくれるかな。
想うのは自由、だから、俺は、先輩のこと、好きでいよう。と思う。
「春男、まだ起きてたの?」
俺の部屋の前を通り掛かった母さんが言う。俺が昼間のシャツ姿、だったから遅くまで起きてる、と思ったんだろう。ちょっと呆れたような声。
「あ、う、うん……。ごめん……。今、寝るから……」
「何してたの? ゲーム? スマホ?」
「そ、その……、部活……、その、部活の、小説、書いてて……」
「ああ、文芸部の。そんなに楽しいの?」
「う、うん……。楽しい……」
「そっか」
母さんは困ったような顔で笑っている。けれども、なんだか嬉しそうだ。
「夜更かしはほどほどにね。健康によくないんだから」
「もう、寝るよ」
「でも、嬉しいわ。春男がそんな風に夢中になってるの、初めて見たから
「あ、う、うん……」
母さんの言葉だけを取ればなんだか説教っぽく聞こえてしまう。けれども、その声の響きは随分嬉しそうで、スキップするようにして、部屋に戻っていった。
夜更かししてあんな嬉しそうにしてる、っていうの初めて見たな……。
先輩に出会って、俺はいろいろと変わったのかもしれない。
――
先輩と一緒に過ごす部活動。夏休みが少しずつ過ぎていった。
8月に入る。経過は順調。昼ごはんを食べ終わった後、先輩が、財布を持ってどこかに行こうとしていた。
「先輩、どちらに?」
「アイスを買いに行こうと思ってるんだ。もしよかったら一緒にいかない?」
「は、はい」
先輩のお誘い。なんだか嬉しい。俺も財布を持って、先輩と一緒に外に向かった。
部室棟を出た瞬間に俺の身体に強烈な暑さが走った。
「やっぱり外は暑いね……」
「そうですね……」
じりじりと暑い夏の空気が俺達を包んでいる。きっと、俺は先輩よりずっと暑さを感じているかもしれない。先輩の隣でこんな風に歩いて、出かけるなんてあんまりないことだから。
コンビニは部室棟から歩いて5分ほど。店内はひんやりとしていた。
「好きなアイスある?」
「俺はおいしいバーが好きですね」
おいしいミニバー。小さめサイズで安くて美味しいロングセラー商品。いちご味とかみかん味みたいなオーソドックスな味から、たこ焼き味、みたいな変わり種まである。大体アイスのケースの一番端っこに毎回あるイメージ。一番好きなアイス。考えていたら食べたくなって、俺はそれに手を伸ばした。一番好きなソーダ味に。
「そっか。僕も久しぶりにそれ食べようかな」
俺と先輩、ソーダ味の方に手を伸ばそうとしていた。先輩も同じ味が好きなのかな。ちょっとだけ嬉しく思う。
「ぁっ……」
俺はつい声を漏らしてしまう。お互いの指先が触れてしまった。ぶわりと指先から熱が走っていくような感覚が走る。
「あ、ごめんね」
「い、いえ……」
先輩は何事もなかったかのようにすっとソーダバーを取る。俺も一歩遅れるようにしてソーダバーを手に取った。そして、会計へと向かう。涼しい店内にいるというのに、身体はなんだか熱かった。
コンビニの外、日陰になっているベンチで二人、同じ味のアイスを食べていた。甘くて爽やかな味とひんやりさりさりとした感触が楽しい。
そして、食べ終わって、立ち上がって学校に戻ろうとした時だった。
「あ……」
つい、声を出していた。コンビニのガラスに花火大会のポスターが貼ってあったから。二週間後。夏休みの終わり際。あるのは知っていたし、話題には出ていたけれど、友達は小澤含めて全員夏休みは部活で忙しいみたいだった。
影ができる。気が付けば先輩もそれを見ていた。先輩は、そのポスターを見たまま、「ねえ、星原くん」と口にした。
「は、はい……」
「花火大会の日、何か予定ある?」
「特、には……ない、ですけど……」
「花火大会、一緒に行かない?」
「えっ…………………!?」
俺の口から声が出て、そしてそのまま思考がストップしてしまった。ナツマツリ、イッショニイカナイ? 花火大会、一緒にいかない?俺の思考が完全にストップしてしまった。
「花火大会、は恋愛小説におけるすごくいい舞台だからね。もしかしたら、何かいいヒントになるかもしれないって思ってね」
「な、なるほど……」
作品作りのため。そういうことなら納得がいった。先輩は俺にそういう想いは抱いていない。それでも、先輩と一緒に花火大会に行ける、ということは楽しみだった。
「星原くんと一緒に行けるんだね。楽しみだよ」
「せ、先輩……。それって、どういう……」
「たくさん思い出作ろうね」
「は、はい……」
先輩はどこかはぐらかすように答えを返した。先輩はどうして俺を誘ってくれたんだろう。それでも、先輩と一緒に花火大会に行ける、という嬉しさがあった。
俺は部室の中にいた。夏休みは一日部活をすることが出来る。それは、先輩と一緒に過ごすことが出来るということ。
ちらり、と隣にいる先輩に視線を向ける。夏休みの部室だからか、先輩は、制服のネクタイを少し緩めていて、鎖骨が見えている。授業がある時とは違うラフな格好で、どきりとした。定位置の席に着くと、先輩の使っているシトラスの制汗剤の香りが漂ってくる。
「順調?」
「は、はい。なんとか」
「そっか。もしも詰まったら、すぐに言ってね」
「はい」
あらすじは、高嶺の花のクラスメイトに想いを抱いている、クラスでも目立たない男の子の話。先輩への思いを掛け合わせている。流石に先輩をモデルにはしていないけれども先輩への想いが根底にある。
先輩が、かりかりとペンを滑らせる音が響く。今はお揃いのシャープペンを使って何かを書いている。俺も、その書く音に合わせて、キーボードを叩いていた。
ちらちらと先輩の方に視線を向けてしまう。夏、二人きり、楽しい時間を過ごしていた。
深夜十二時、パソコンの画面と見つめ合いながら、文字を打ち込んでいた。パチパチとキーボードを叩いて、文章作成ソフトの上に、俺の想いをぶつける。その作業がひたすらに楽しい。夏休み。自由な時間。夏休みの宿題をする時間以外は全て創作に当ててしまっている。
文章を書くこと、なんて興味を持てなかったのに、この作業がひどく楽しい。
“あなたのことが、好きなんです……!“
そんなセリフが、画面に表示されている。学校中の憧れのクラスメイトに、勇気を出して告白する、というシーン。
書いているの。画面の中で喋っているのは、。けれども、そこには、俺の、先輩に対しての想いが重ねられているのかもしれない。
「たのしいな」
頭の中にあるのは先輩のこと。思わず、俺の口から笑みがこぼれる。表情筋が硬かった俺だけど、今のは自分でも笑ってる、って分かる。テンションが低くて表情の抑揚が薄い俺だったのに、先輩といて、いろんな感情を知っていっている感じがする。先輩、今度は俺の小説、どんな風に見てくれるかな。また、褒めてくれるかな。
想うのは自由、だから、俺は、先輩のこと、好きでいよう。と思う。
「春男、まだ起きてたの?」
俺の部屋の前を通り掛かった母さんが言う。俺が昼間のシャツ姿、だったから遅くまで起きてる、と思ったんだろう。ちょっと呆れたような声。
「あ、う、うん……。ごめん……。今、寝るから……」
「何してたの? ゲーム? スマホ?」
「そ、その……、部活……、その、部活の、小説、書いてて……」
「ああ、文芸部の。そんなに楽しいの?」
「う、うん……。楽しい……」
「そっか」
母さんは困ったような顔で笑っている。けれども、なんだか嬉しそうだ。
「夜更かしはほどほどにね。健康によくないんだから」
「もう、寝るよ」
「でも、嬉しいわ。春男がそんな風に夢中になってるの、初めて見たから
「あ、う、うん……」
母さんの言葉だけを取ればなんだか説教っぽく聞こえてしまう。けれども、その声の響きは随分嬉しそうで、スキップするようにして、部屋に戻っていった。
夜更かししてあんな嬉しそうにしてる、っていうの初めて見たな……。
先輩に出会って、俺はいろいろと変わったのかもしれない。
――
先輩と一緒に過ごす部活動。夏休みが少しずつ過ぎていった。
8月に入る。経過は順調。昼ごはんを食べ終わった後、先輩が、財布を持ってどこかに行こうとしていた。
「先輩、どちらに?」
「アイスを買いに行こうと思ってるんだ。もしよかったら一緒にいかない?」
「は、はい」
先輩のお誘い。なんだか嬉しい。俺も財布を持って、先輩と一緒に外に向かった。
部室棟を出た瞬間に俺の身体に強烈な暑さが走った。
「やっぱり外は暑いね……」
「そうですね……」
じりじりと暑い夏の空気が俺達を包んでいる。きっと、俺は先輩よりずっと暑さを感じているかもしれない。先輩の隣でこんな風に歩いて、出かけるなんてあんまりないことだから。
コンビニは部室棟から歩いて5分ほど。店内はひんやりとしていた。
「好きなアイスある?」
「俺はおいしいバーが好きですね」
おいしいミニバー。小さめサイズで安くて美味しいロングセラー商品。いちご味とかみかん味みたいなオーソドックスな味から、たこ焼き味、みたいな変わり種まである。大体アイスのケースの一番端っこに毎回あるイメージ。一番好きなアイス。考えていたら食べたくなって、俺はそれに手を伸ばした。一番好きなソーダ味に。
「そっか。僕も久しぶりにそれ食べようかな」
俺と先輩、ソーダ味の方に手を伸ばそうとしていた。先輩も同じ味が好きなのかな。ちょっとだけ嬉しく思う。
「ぁっ……」
俺はつい声を漏らしてしまう。お互いの指先が触れてしまった。ぶわりと指先から熱が走っていくような感覚が走る。
「あ、ごめんね」
「い、いえ……」
先輩は何事もなかったかのようにすっとソーダバーを取る。俺も一歩遅れるようにしてソーダバーを手に取った。そして、会計へと向かう。涼しい店内にいるというのに、身体はなんだか熱かった。
コンビニの外、日陰になっているベンチで二人、同じ味のアイスを食べていた。甘くて爽やかな味とひんやりさりさりとした感触が楽しい。
そして、食べ終わって、立ち上がって学校に戻ろうとした時だった。
「あ……」
つい、声を出していた。コンビニのガラスに花火大会のポスターが貼ってあったから。二週間後。夏休みの終わり際。あるのは知っていたし、話題には出ていたけれど、友達は小澤含めて全員夏休みは部活で忙しいみたいだった。
影ができる。気が付けば先輩もそれを見ていた。先輩は、そのポスターを見たまま、「ねえ、星原くん」と口にした。
「は、はい……」
「花火大会の日、何か予定ある?」
「特、には……ない、ですけど……」
「花火大会、一緒に行かない?」
「えっ…………………!?」
俺の口から声が出て、そしてそのまま思考がストップしてしまった。ナツマツリ、イッショニイカナイ? 花火大会、一緒にいかない?俺の思考が完全にストップしてしまった。
「花火大会、は恋愛小説におけるすごくいい舞台だからね。もしかしたら、何かいいヒントになるかもしれないって思ってね」
「な、なるほど……」
作品作りのため。そういうことなら納得がいった。先輩は俺にそういう想いは抱いていない。それでも、先輩と一緒に花火大会に行ける、ということは楽しみだった。
「星原くんと一緒に行けるんだね。楽しみだよ」
「せ、先輩……。それって、どういう……」
「たくさん思い出作ろうね」
「は、はい……」
先輩はどこかはぐらかすように答えを返した。先輩はどうして俺を誘ってくれたんだろう。それでも、先輩と一緒に花火大会に行ける、という嬉しさがあった。