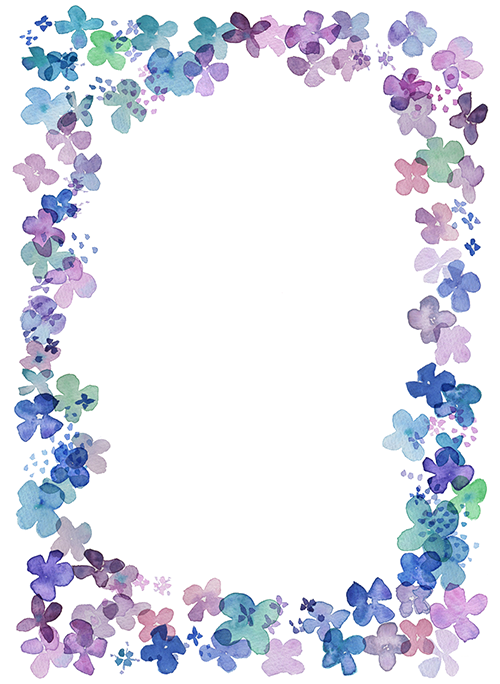今日がテスト前最後の部活。だというのになんだか落ち着かない。今は文化祭に向けて、何を書くか、プロットの前段階のメモを作成している。俺もプロットを書いている。何を、書こうか。使っているのは先輩に昨日買ってもらったシャープペンだ。
「早速シャープペン使ってくれているんだね。ありがとう」
「は、はい……」
先輩の低くて柔らかい声が俺の耳に届いた。それだけで、身体がぶわりと熱くなる。
「あ、あの……、先輩……」
「ん? どうしたの?」
俺は、紙に向けていた視線を、先輩の方に向ける。ばちりと目が合った。やっぱり綺麗な顔をしていて、俺の心臓が跳ねる。こないだまでであれば、なんて名前だったのか分からない感覚に今なら名前が付けられる。間違いなく「好き」の感覚だった。知らない感情が、先輩のおかげで分かってしまう。先輩にもらったシャープペンを持つ指先がひどく熱い。
「せ、先輩は、お付き合いされている方とか、いらっしゃいますか?」
俺はもつれたように口にしてしまう。
「いないよ。どうして?」
「あ、あのっ……! その、恋愛ものを、書きたくって、その参考に、ご意見を、お伺いしたく……! そ、その、失礼がありましたらすみません!」
そんな、誤魔化すような言葉が、俺の口から出て来てしまった。わたわたと、慌てるようにして。今、俺は、とんでもないことを言ってしまったかもしれない。そして、俺が次書く話が自動的にそこで決まってしまった。れ、恋愛もの、書いたこと、ないな……。
「そうなんだね。いいよ。僕が言える範囲であればなんでも聞いて欲しいな」
「そ、それでは、どんな人が、好きですか?」
「うーん……。真面目で何かに真っ直ぐ打ち込む人が好きかな……」
先輩は少し迷った感じで答えてくれる。柔らかな視線。
「そ、その、見た目、とかは……? 顔、とかで好きなタイプ……」
「そうだね……。好きなタイプ……。外見でこういうのが好き、みたどんな姿でも魅力的だと思うよ」
「な、なるほど……」
どんな姿でも魅力的。でも、さすがに、「男だったらどうですか?」と訊くのは、俺には出来なかった。
「そ、その……、あの……、好きな人、いますか?」
俺は、単刀直入にその質問をした。先輩は立ち上がった。そして、しばらく後ろを向く。
「秘密だよ」
「ひ、秘密ですか」
返ってきた答えは、秘密、というもの。秘密、と言われるとさらに気になってしまった。
「星原くんはいるの?」
「は、はい、い、います」
さすがに「先輩です」とは言えないけれど。けれども、俺が答えた時、先輩は後ろを向いたまま、無言の状態だった。
「そうなんだね。実るといいね」
「は、はい。ありがとうございます」
先輩だ、って言ったら、どんな反応するんだろう。驚くのかな。それとも、成就するのかな。でも、流石に、言えない。
先輩は、好きな人いるのか。いないのか。そこからまず気になってしまう。今まで味わったことのない気持ちを抱きながら、テスト期間へと突入してしまった。
――
テスト期間、ずーっと落ち着かなかった。先輩への感情の理由は、恋だったんだ。そう分かって、俺の身体がひどく熱くなっている。先輩は、俺のことをどう思っているんだろう。先輩のことと、名前のついてしまった俺の感情のことについて、考えてしまっていた。
「大丈夫か?」
小澤が俺の方を心配そうに覗き込む。
「えっと……、あんま、大丈夫じゃないかも……?」
「熱でもあるのか? 保健室行くか?」
「だ、大丈夫……。なんだけど、あのさ、ちょっと、着いて来てもらっても、いい?」
「あ、ああ……」
この想いを一人で抱えられるかどうか分からなくて、俺は、小澤に、打ち明けることにした。
「え、えーっと、その、これは、小澤にだけの秘密の話……。絶対に他の人に言わないでね」
「言わねえよ。俺が秘密ばらしたことあるか?」
「ない、ね……」
小澤とは幼稚園の頃からの先輩。楽しい感じの噂好きな部分とか、芸能人とか、人気者の人に惹かれたり、みたいなことはあるけれども、秘密をバラしたりすることはない。だから、俺は小澤のことを信用して、話すことにした。
「えっと、その、あのさ……。俺が男の人を好きって言ったら、どう思う? そ、その、小澤、とは、友達、なんだけど……。その、好きになった、人が、その、男の人で……」
普段とは比べものにならないくらいに言葉がたどたどしくなってしまう。小澤はじっと俺の方を見て、黙って話を聞いていた。驚きも何もない表情。というか、表情が読み取りにくい。どういう感情をしているのか、いつもの俺じゃないけれど分からなくて、ちょっと、焦ってしまった。
「そっか。応援してる」
俺が言い終えた、と分かると、彼は言う。まるで、「高い靴買おうかどうかずっと悩んでるんだ」を答えるかのような「いいと思うよ」だけだった。一切の驚きも何もなくて逆に俺の方がびっくりしてしまった。
「その、びっくりとかしたりは、しないの……?」
「だって、別に、俺の好きな漫画にも男の子が男の子に恋するって描写あるし、全然普通だと思うよ。そんな驚くことじゃ……」
「そ、そうなんだ……」
まさか、そんなにあっさり受け入れられる、とは思わなくて、ちょっと拍子抜けしてしまった。
「……で、好きな人って、もしかして、貴公子?」
「な、なんで分かるの……?」
「そりゃ最近の星原見てたら分かるよ。まあ、それで、その相手を考えた時に、貴公子かな、って思ったらそんなに驚かなかった、って言うのもあると思う」
「そ、そんなに分かりやすかった?」
「分かりやすいよ。今まで星原、全然感情豊かじゃなかったのに、最近は感情を覚えたアンドロイドみたいになってるから」
「そ、そうなんだ」
先輩のことを話していた時、そんなに感情豊かだっただろうか。
「でも貴公子に恋する、って、随分大変だなあ。ライバル多いぞ。超モテるだろ?」
「うん」
最近先輩と二人の時間が多かったけれども先輩は本当にモテる。学校で人が誰かのそばに集まっている、と思ったら先輩だった、ということがあったりするくらいに。
「でも、俺は応援するぜ。相手が誰でも。大事な友達の恋だからな」
「……ありがとう」
それでも、小澤に応援されるのは、嬉しかった。
――
放課後、俺は図書室にいた。テストが近い。だから勉強を集中してやるために。
「…………」
図書館にいるけれど、勉強はほとんど進まなかった。
勉強はそんなに熱心な方じゃない。本当は文芸部の部室に行きたいけれども、テスト期間中は部室棟は特別な用がない限りは入ってはいけないことになっている。もちろん進まない。先輩にもらったシャーペンを眺めて、ノートに数文字書いて終わった。周りを見る。熱心に手を動かしている人。こそこそおしゃべりをしている人。カップルらしい二人組が手を重ねてる姿、そして、本を読んでいる人に俺の視線が向けられた。
本でも読もうかな。
頭の中に今まで普段は絶対にしないような考えが出て来る。テストが近いから、現実逃避のために掃除をする、みたいな感じの思考なのかもしれない。俺は立ち上がり、図書館の中に向かった。
膨大な本の中から一番読みやすそうな本を探してみる。カウンターのそばに「おすすめ」と置かれていた恋愛小説を持って元の席に戻った。タイトルは「喜怒哀楽な恋愛短編集」。高校生の作者さんが文学賞を取ったことがきっかけで出た本だった。
ぱらぱらとめくっていく。短編集のよう。今まであまり読まなかったけれど、先輩の文章を読んだりしたからか、読むことは全く苦にならなかった。いろんな短編がある。それこそ幸せに結ばれる話から、失恋の話まで。
ページをめくり進めていくと「あの人との関係が変わってしまった」というタイトルの短編があった。同じ部活の仲良しの、けれどもすごくモテる先輩に恋する女の子の話。紆余曲折あり、その女の子は先輩に告白することに決める。
「好き、なんです……!」
「……ごめんね」
けれども、その子の告白は成功しなかった。そして、部活の中でも、以前のような関係ではなくなってしまった、という結末。
放心、みたいになってしまった。まだ途中だ、というのに、そのページで閉じてしまった。
「…………」
その結末が、なんだか妙に刺さってしまった。もしかして、これが、俺と先輩のこれから、じゃないか、みたいなことも考えてしまった。先輩への想いは、叶わないのかもしれない、とも思ってしまった。
「早速シャープペン使ってくれているんだね。ありがとう」
「は、はい……」
先輩の低くて柔らかい声が俺の耳に届いた。それだけで、身体がぶわりと熱くなる。
「あ、あの……、先輩……」
「ん? どうしたの?」
俺は、紙に向けていた視線を、先輩の方に向ける。ばちりと目が合った。やっぱり綺麗な顔をしていて、俺の心臓が跳ねる。こないだまでであれば、なんて名前だったのか分からない感覚に今なら名前が付けられる。間違いなく「好き」の感覚だった。知らない感情が、先輩のおかげで分かってしまう。先輩にもらったシャープペンを持つ指先がひどく熱い。
「せ、先輩は、お付き合いされている方とか、いらっしゃいますか?」
俺はもつれたように口にしてしまう。
「いないよ。どうして?」
「あ、あのっ……! その、恋愛ものを、書きたくって、その参考に、ご意見を、お伺いしたく……! そ、その、失礼がありましたらすみません!」
そんな、誤魔化すような言葉が、俺の口から出て来てしまった。わたわたと、慌てるようにして。今、俺は、とんでもないことを言ってしまったかもしれない。そして、俺が次書く話が自動的にそこで決まってしまった。れ、恋愛もの、書いたこと、ないな……。
「そうなんだね。いいよ。僕が言える範囲であればなんでも聞いて欲しいな」
「そ、それでは、どんな人が、好きですか?」
「うーん……。真面目で何かに真っ直ぐ打ち込む人が好きかな……」
先輩は少し迷った感じで答えてくれる。柔らかな視線。
「そ、その、見た目、とかは……? 顔、とかで好きなタイプ……」
「そうだね……。好きなタイプ……。外見でこういうのが好き、みたどんな姿でも魅力的だと思うよ」
「な、なるほど……」
どんな姿でも魅力的。でも、さすがに、「男だったらどうですか?」と訊くのは、俺には出来なかった。
「そ、その……、あの……、好きな人、いますか?」
俺は、単刀直入にその質問をした。先輩は立ち上がった。そして、しばらく後ろを向く。
「秘密だよ」
「ひ、秘密ですか」
返ってきた答えは、秘密、というもの。秘密、と言われるとさらに気になってしまった。
「星原くんはいるの?」
「は、はい、い、います」
さすがに「先輩です」とは言えないけれど。けれども、俺が答えた時、先輩は後ろを向いたまま、無言の状態だった。
「そうなんだね。実るといいね」
「は、はい。ありがとうございます」
先輩だ、って言ったら、どんな反応するんだろう。驚くのかな。それとも、成就するのかな。でも、流石に、言えない。
先輩は、好きな人いるのか。いないのか。そこからまず気になってしまう。今まで味わったことのない気持ちを抱きながら、テスト期間へと突入してしまった。
――
テスト期間、ずーっと落ち着かなかった。先輩への感情の理由は、恋だったんだ。そう分かって、俺の身体がひどく熱くなっている。先輩は、俺のことをどう思っているんだろう。先輩のことと、名前のついてしまった俺の感情のことについて、考えてしまっていた。
「大丈夫か?」
小澤が俺の方を心配そうに覗き込む。
「えっと……、あんま、大丈夫じゃないかも……?」
「熱でもあるのか? 保健室行くか?」
「だ、大丈夫……。なんだけど、あのさ、ちょっと、着いて来てもらっても、いい?」
「あ、ああ……」
この想いを一人で抱えられるかどうか分からなくて、俺は、小澤に、打ち明けることにした。
「え、えーっと、その、これは、小澤にだけの秘密の話……。絶対に他の人に言わないでね」
「言わねえよ。俺が秘密ばらしたことあるか?」
「ない、ね……」
小澤とは幼稚園の頃からの先輩。楽しい感じの噂好きな部分とか、芸能人とか、人気者の人に惹かれたり、みたいなことはあるけれども、秘密をバラしたりすることはない。だから、俺は小澤のことを信用して、話すことにした。
「えっと、その、あのさ……。俺が男の人を好きって言ったら、どう思う? そ、その、小澤、とは、友達、なんだけど……。その、好きになった、人が、その、男の人で……」
普段とは比べものにならないくらいに言葉がたどたどしくなってしまう。小澤はじっと俺の方を見て、黙って話を聞いていた。驚きも何もない表情。というか、表情が読み取りにくい。どういう感情をしているのか、いつもの俺じゃないけれど分からなくて、ちょっと、焦ってしまった。
「そっか。応援してる」
俺が言い終えた、と分かると、彼は言う。まるで、「高い靴買おうかどうかずっと悩んでるんだ」を答えるかのような「いいと思うよ」だけだった。一切の驚きも何もなくて逆に俺の方がびっくりしてしまった。
「その、びっくりとかしたりは、しないの……?」
「だって、別に、俺の好きな漫画にも男の子が男の子に恋するって描写あるし、全然普通だと思うよ。そんな驚くことじゃ……」
「そ、そうなんだ……」
まさか、そんなにあっさり受け入れられる、とは思わなくて、ちょっと拍子抜けしてしまった。
「……で、好きな人って、もしかして、貴公子?」
「な、なんで分かるの……?」
「そりゃ最近の星原見てたら分かるよ。まあ、それで、その相手を考えた時に、貴公子かな、って思ったらそんなに驚かなかった、って言うのもあると思う」
「そ、そんなに分かりやすかった?」
「分かりやすいよ。今まで星原、全然感情豊かじゃなかったのに、最近は感情を覚えたアンドロイドみたいになってるから」
「そ、そうなんだ」
先輩のことを話していた時、そんなに感情豊かだっただろうか。
「でも貴公子に恋する、って、随分大変だなあ。ライバル多いぞ。超モテるだろ?」
「うん」
最近先輩と二人の時間が多かったけれども先輩は本当にモテる。学校で人が誰かのそばに集まっている、と思ったら先輩だった、ということがあったりするくらいに。
「でも、俺は応援するぜ。相手が誰でも。大事な友達の恋だからな」
「……ありがとう」
それでも、小澤に応援されるのは、嬉しかった。
――
放課後、俺は図書室にいた。テストが近い。だから勉強を集中してやるために。
「…………」
図書館にいるけれど、勉強はほとんど進まなかった。
勉強はそんなに熱心な方じゃない。本当は文芸部の部室に行きたいけれども、テスト期間中は部室棟は特別な用がない限りは入ってはいけないことになっている。もちろん進まない。先輩にもらったシャーペンを眺めて、ノートに数文字書いて終わった。周りを見る。熱心に手を動かしている人。こそこそおしゃべりをしている人。カップルらしい二人組が手を重ねてる姿、そして、本を読んでいる人に俺の視線が向けられた。
本でも読もうかな。
頭の中に今まで普段は絶対にしないような考えが出て来る。テストが近いから、現実逃避のために掃除をする、みたいな感じの思考なのかもしれない。俺は立ち上がり、図書館の中に向かった。
膨大な本の中から一番読みやすそうな本を探してみる。カウンターのそばに「おすすめ」と置かれていた恋愛小説を持って元の席に戻った。タイトルは「喜怒哀楽な恋愛短編集」。高校生の作者さんが文学賞を取ったことがきっかけで出た本だった。
ぱらぱらとめくっていく。短編集のよう。今まであまり読まなかったけれど、先輩の文章を読んだりしたからか、読むことは全く苦にならなかった。いろんな短編がある。それこそ幸せに結ばれる話から、失恋の話まで。
ページをめくり進めていくと「あの人との関係が変わってしまった」というタイトルの短編があった。同じ部活の仲良しの、けれどもすごくモテる先輩に恋する女の子の話。紆余曲折あり、その女の子は先輩に告白することに決める。
「好き、なんです……!」
「……ごめんね」
けれども、その子の告白は成功しなかった。そして、部活の中でも、以前のような関係ではなくなってしまった、という結末。
放心、みたいになってしまった。まだ途中だ、というのに、そのページで閉じてしまった。
「…………」
その結末が、なんだか妙に刺さってしまった。もしかして、これが、俺と先輩のこれから、じゃないか、みたいなことも考えてしまった。先輩への想いは、叶わないのかもしれない、とも思ってしまった。