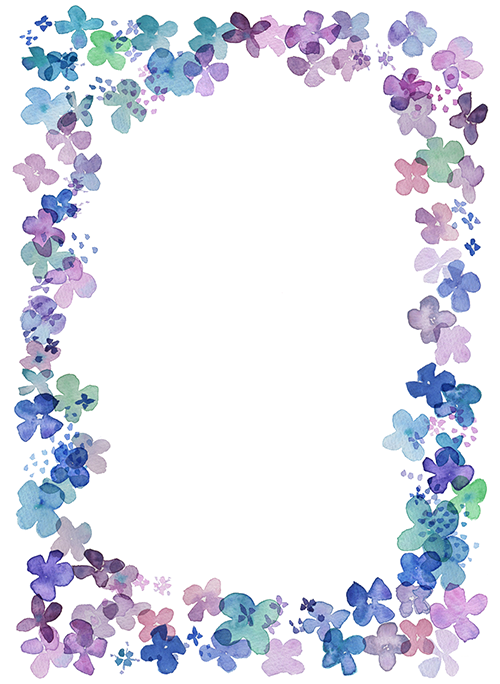「じゃーな。星原! また明日」
「うん、じゃあね」
これから通う、大時高校(おおときこうこう)の入学式を終えた俺、星原春男は、同じクラスの小澤冬人(おざわふゆと)と手を振って別れた。小澤は幼稚園からの幼馴染。身長は178まで伸びて、まだ伸びそうだけれど、八重歯を見せた笑顔はずっと変わらない。中学よりも校則が緩んだからか、ちょっと浮かれたように、髪型をツーブロックにしている。でもよく似合っていた。
小澤と別れた俺は、ぼんやりと帰り道を歩いていた。
「気持ち的には中学時代とあんまり変わらないな」
まるで合成音声みたいな抑揚で呟く。大時高校は徒歩10分で着く家から一番近い高校。だから、通学路も馴染んだ道。クラスメイトも3分の1が顔見知りで、その他のクラスメイトも遠くても「友達の友達の友達」みたいな感じ。今も、胸に入学おめでとうのブローチが付けられている以外はあんまり入学した、という感じがしない。
「制服も中学とおんなじような感じだし、いろいろ兄貴が喋ってたからな」
制服のブレザーの裾を引っ張る。この制服は6つ年上の兄貴のお下がり。しかも、中学時代とほぼ変わらず紺色ブレザーと灰色スラックスと青色ネクタイ。それに、行事に関しても兄貴からなんとなく聞いていたからネタバレ状態。6年も経っているとはいえど、大まかには兄貴の時と変わらなさそう。文化祭が最大のイベント。修学旅行は奈良京都大阪。知ってる。
「高校生活もまあ普通に平坦なんだろうな」
小中、と本当にあっさり平坦、という感じ。生活の中で楽しい事悲しい事はそこそこあったけれども、さっくりと、何も残さずに過ぎていった。
高校、新生活、だから楽しみも多少はあるけれど、そんなに大きくも変わらない。なんとなく予想の付く高校生活のことを頭に浮かべながら、俺は家に帰る道を淡々と歩いている。
――だから“アンドロイド星原“って言われるんだよ。冷め冷めなんだから。
中学時代にいつもつるんでいた友達4人のうち一人に言われた言葉を思い出した。アンドロイド星原、というのは、俺のあだ名。感情もテンションの起伏も低い、という意味で付けられた。
――星原くんって、表情筋ガッチガチだよね
――いい意味でも悪い意味でもなーんか石って感じだよな。星原は
――何しても怒らなさそう。てか怒るの?
――全体的になんとなく冷めてるよね
――まあ、楽しい時もあるんだろうけど、喜怒哀楽がすげーわかりにくいんだよな
そのまま流れてくるように思い出される、俺に対しての評価。文字面だけ取れば悪口にも聞こえなくもないけど、彼等とは昨日もLIMEで駄弁っていたくらいの仲良し。ちなみに一番最後のセリフは小澤が言った。表情があんまり変わらないのと、テンションの起伏が小さいのは事実だから言われるのはしょうがないと思う。
「そんなに顔、変わらない?」
一度立ち止まり、スマートフォンを鏡代わりにして顔を見る。瞳は多少の大きさはあるけれどなんか眠そう、って言われる。ジト目、とでも言うのかな。ただ、全体的に表情筋が硬い。やっぱり、無表情に近いかも。幼稚園~小学校の記念写真は笑っているはずなのに楽しくなさそうって言われた。今日撮影した式の写真も多分そんな感じだと思う。髪型は小さいころから行っている美容院にお任せにしている。あんまりこだわりはない。黒髪のマッシュショート。平凡、って感じの顔。あんまり目つきのよくない漫画のモブキャラって感じ。
「これから新生活が始まるんだ、頑張るぞ」
表情が変わることを期待して呟いてみた。やっぱり、なんか平坦で口が動いている以外何も変わらない。スマートフォンをポケットにしまってまた歩き出す。新生活、っていうよりも「いつもの生活」って感じ。きっとこれから、何かに対して強い熱を抱くことはなさそう。中学の時もそう。だから、なんとなくぼんやりと卒業していくんだろうな、みたいなことを思ってしまった。
「えっ……?」
けれども、思考が途切れて、歩いていた俺の口から間の抜けた声が出る。俺の身体に衝撃が走った。転んでしまった。俺の身体が重力に従って頭から倒れていく。後ろ頭が地面に激突しそうになって、思わず目を閉じてしまう。
「……」
いつまで経っても俺の身体に衝撃は全く襲ってこなかった。俺の身体に伝わっていたのは、誰かに支えられているような感覚。一体、何が起こったんだろう。俺は恐る恐る目を開けた。転びかけた俺の身体が抱きかかえられるようにして誰かに支えられていた。支えてくれている人と目が合う。
「っ…………!?」
俺を支えてくれている人の顔を確認した瞬間、俺の身体に凄まじい衝撃が走る。まるで電流を受けたような時のような衝撃。
俺を助けてくれた人は、びっくりするほどの美形だった。柔らかそうな髪質のふわふわの茶髪、陽の光に透けていてきらきらしている。濃い琥珀色の、まるで色ガラスみたいな透きとおった瞳。すっと通った形のいい鼻。柔らかく孤を描く唇。まるで、ファンタジー漫画の王子様みたいな綺麗な人だった。なんとなく慣れた雰囲気から多分先輩だろうな、と思った。
「大丈夫? 怪我はない?」
「はい、大丈夫、です」
弦楽器のような、穏やかな低い声で訊ねられる。俺は転んだ衝撃の余韻を味わっている。そして、俺の身体が穏やかな動きでゆっくりと起こされ、元の立ち上がる体勢になる。多分180は超えている。美形なだけじゃなくって背が高い。
「よかった」
先輩はふわっと柔らかく笑う。少しだけ膝を曲げて、俺に視線を合わせた。先輩の濃い琥珀色の瞳には、ぽかんと口を開けた俺が映っている。そして、先輩の視線は俺の胸のブローチに向けられる。
「新入生?」
「は、はい……」
「そうなんだね。入学おめでとう。高校生活、楽しんでね」
「あ、ありがとうございます……」
俺はひどく調子の悪いスピーカーのような途切れ途切れの音を出してしまった。こんなこと、あまりない。
俺が礼を言った後、先輩はふわと微笑んで、手を振って去っていく。俺は呆気にとられたように、先輩の背中を見つめていることしか出来なかった。今まで、味わったことのない感覚が俺の身体に走っていた。兄貴も、こんなにイケメンの先輩がいるって話はしてなかった。そりゃあそうだと思う。だって兄貴とこの先輩と学年は被らないから。
そういえば、名前、訊くの忘れてしまった。先輩だと、思うから、また、会える、かな。どんな、人なんだろう。平坦だった俺の頭の中が、あの先輩でいっぱいになっていく。ばくばくと心臓が高鳴って、頬が熱い。
「な、なんだろう……、これ……」
今まであまりだしたことのない、壊れたスピーカーのような声が出てきてしまう。手のひらで顔を覆う。今、俺、どんな顔してるんだろう。今までしたことのない顔をしているかもしれない。そして、今まで知らなかった感情が走っていた。
――
先輩と会った後、頭の中の全部が、あの先輩のことでいっぱいだった。
入学祝いって言われていつもよりも豪華な食事をしている時も、風呂に入っている時も、兄貴に入学おめでとうLIMEの返信をしている時も助けてくれた先輩のことを考えてしまっていた。
ベッドの上、明日から本格的な授業が始まるのになかなか寝付けなかった。ごろごろと意味のない寝返りを繰り返して、ぼんやりと天井を見つめる、を繰り返す。
――大丈夫? 怪我とかない?
――よかった。
――新入生?
――そうなんだね。入学おめでとう。高校生活、楽しんでね。
先輩に言われた、世間話みたいな言葉を、何度も頭の中で巡らせる。先輩の綺麗な顔を、何度も頭の中で再生する。気に入った曲を再生するみたいに。名前も知らないあの先輩の言葉を何度も巡らせている。
転び掛けたところを助けてもらっただけだというのに、どうして、あの先輩のことが、頭から離れないんだろう……。
「まさか、これが、恋?」
つい、呟いてしまった。俺が、男の先輩に、恋を?
「……」
一目ぼれ、運命の出会い、初恋。好き。恋。恋愛。
「恋」の可能性を考えて、そんな、今の俺に関係ありそうな言葉を、言葉を頭の中で巡らせる。でも、そういう言葉で言い表してしまうには、あまりにも経験が足りていないし、味わったことがない。幼稚園とか小学校低学年の時に女の子と手を繋いだくらい。バレンタインデーは義理チョコしかもらったことがない。漫画とかドラマとかで、恋愛の描写には触れたことがある。けれども、そういうの、とは全く結びつかない。そういうのよりも、もっと激しい、生々しさを感じている。
「それに、まだ、俺、先輩のこと、知らないし」
そう。先輩のことを「好き」とか「恋した」とか言い現わすには、まだ先輩のことを何も知らない。先輩がすごい嫌な人だったら? 怖い人だったら? だから、先輩への想いをなんて言い現わすのかは分からない。
それでも……。
「……また、会いたいな」
先輩に、また会いたい、という気持ちだけは、はっきりとしていた。
「うん、じゃあね」
これから通う、大時高校(おおときこうこう)の入学式を終えた俺、星原春男は、同じクラスの小澤冬人(おざわふゆと)と手を振って別れた。小澤は幼稚園からの幼馴染。身長は178まで伸びて、まだ伸びそうだけれど、八重歯を見せた笑顔はずっと変わらない。中学よりも校則が緩んだからか、ちょっと浮かれたように、髪型をツーブロックにしている。でもよく似合っていた。
小澤と別れた俺は、ぼんやりと帰り道を歩いていた。
「気持ち的には中学時代とあんまり変わらないな」
まるで合成音声みたいな抑揚で呟く。大時高校は徒歩10分で着く家から一番近い高校。だから、通学路も馴染んだ道。クラスメイトも3分の1が顔見知りで、その他のクラスメイトも遠くても「友達の友達の友達」みたいな感じ。今も、胸に入学おめでとうのブローチが付けられている以外はあんまり入学した、という感じがしない。
「制服も中学とおんなじような感じだし、いろいろ兄貴が喋ってたからな」
制服のブレザーの裾を引っ張る。この制服は6つ年上の兄貴のお下がり。しかも、中学時代とほぼ変わらず紺色ブレザーと灰色スラックスと青色ネクタイ。それに、行事に関しても兄貴からなんとなく聞いていたからネタバレ状態。6年も経っているとはいえど、大まかには兄貴の時と変わらなさそう。文化祭が最大のイベント。修学旅行は奈良京都大阪。知ってる。
「高校生活もまあ普通に平坦なんだろうな」
小中、と本当にあっさり平坦、という感じ。生活の中で楽しい事悲しい事はそこそこあったけれども、さっくりと、何も残さずに過ぎていった。
高校、新生活、だから楽しみも多少はあるけれど、そんなに大きくも変わらない。なんとなく予想の付く高校生活のことを頭に浮かべながら、俺は家に帰る道を淡々と歩いている。
――だから“アンドロイド星原“って言われるんだよ。冷め冷めなんだから。
中学時代にいつもつるんでいた友達4人のうち一人に言われた言葉を思い出した。アンドロイド星原、というのは、俺のあだ名。感情もテンションの起伏も低い、という意味で付けられた。
――星原くんって、表情筋ガッチガチだよね
――いい意味でも悪い意味でもなーんか石って感じだよな。星原は
――何しても怒らなさそう。てか怒るの?
――全体的になんとなく冷めてるよね
――まあ、楽しい時もあるんだろうけど、喜怒哀楽がすげーわかりにくいんだよな
そのまま流れてくるように思い出される、俺に対しての評価。文字面だけ取れば悪口にも聞こえなくもないけど、彼等とは昨日もLIMEで駄弁っていたくらいの仲良し。ちなみに一番最後のセリフは小澤が言った。表情があんまり変わらないのと、テンションの起伏が小さいのは事実だから言われるのはしょうがないと思う。
「そんなに顔、変わらない?」
一度立ち止まり、スマートフォンを鏡代わりにして顔を見る。瞳は多少の大きさはあるけれどなんか眠そう、って言われる。ジト目、とでも言うのかな。ただ、全体的に表情筋が硬い。やっぱり、無表情に近いかも。幼稚園~小学校の記念写真は笑っているはずなのに楽しくなさそうって言われた。今日撮影した式の写真も多分そんな感じだと思う。髪型は小さいころから行っている美容院にお任せにしている。あんまりこだわりはない。黒髪のマッシュショート。平凡、って感じの顔。あんまり目つきのよくない漫画のモブキャラって感じ。
「これから新生活が始まるんだ、頑張るぞ」
表情が変わることを期待して呟いてみた。やっぱり、なんか平坦で口が動いている以外何も変わらない。スマートフォンをポケットにしまってまた歩き出す。新生活、っていうよりも「いつもの生活」って感じ。きっとこれから、何かに対して強い熱を抱くことはなさそう。中学の時もそう。だから、なんとなくぼんやりと卒業していくんだろうな、みたいなことを思ってしまった。
「えっ……?」
けれども、思考が途切れて、歩いていた俺の口から間の抜けた声が出る。俺の身体に衝撃が走った。転んでしまった。俺の身体が重力に従って頭から倒れていく。後ろ頭が地面に激突しそうになって、思わず目を閉じてしまう。
「……」
いつまで経っても俺の身体に衝撃は全く襲ってこなかった。俺の身体に伝わっていたのは、誰かに支えられているような感覚。一体、何が起こったんだろう。俺は恐る恐る目を開けた。転びかけた俺の身体が抱きかかえられるようにして誰かに支えられていた。支えてくれている人と目が合う。
「っ…………!?」
俺を支えてくれている人の顔を確認した瞬間、俺の身体に凄まじい衝撃が走る。まるで電流を受けたような時のような衝撃。
俺を助けてくれた人は、びっくりするほどの美形だった。柔らかそうな髪質のふわふわの茶髪、陽の光に透けていてきらきらしている。濃い琥珀色の、まるで色ガラスみたいな透きとおった瞳。すっと通った形のいい鼻。柔らかく孤を描く唇。まるで、ファンタジー漫画の王子様みたいな綺麗な人だった。なんとなく慣れた雰囲気から多分先輩だろうな、と思った。
「大丈夫? 怪我はない?」
「はい、大丈夫、です」
弦楽器のような、穏やかな低い声で訊ねられる。俺は転んだ衝撃の余韻を味わっている。そして、俺の身体が穏やかな動きでゆっくりと起こされ、元の立ち上がる体勢になる。多分180は超えている。美形なだけじゃなくって背が高い。
「よかった」
先輩はふわっと柔らかく笑う。少しだけ膝を曲げて、俺に視線を合わせた。先輩の濃い琥珀色の瞳には、ぽかんと口を開けた俺が映っている。そして、先輩の視線は俺の胸のブローチに向けられる。
「新入生?」
「は、はい……」
「そうなんだね。入学おめでとう。高校生活、楽しんでね」
「あ、ありがとうございます……」
俺はひどく調子の悪いスピーカーのような途切れ途切れの音を出してしまった。こんなこと、あまりない。
俺が礼を言った後、先輩はふわと微笑んで、手を振って去っていく。俺は呆気にとられたように、先輩の背中を見つめていることしか出来なかった。今まで、味わったことのない感覚が俺の身体に走っていた。兄貴も、こんなにイケメンの先輩がいるって話はしてなかった。そりゃあそうだと思う。だって兄貴とこの先輩と学年は被らないから。
そういえば、名前、訊くの忘れてしまった。先輩だと、思うから、また、会える、かな。どんな、人なんだろう。平坦だった俺の頭の中が、あの先輩でいっぱいになっていく。ばくばくと心臓が高鳴って、頬が熱い。
「な、なんだろう……、これ……」
今まであまりだしたことのない、壊れたスピーカーのような声が出てきてしまう。手のひらで顔を覆う。今、俺、どんな顔してるんだろう。今までしたことのない顔をしているかもしれない。そして、今まで知らなかった感情が走っていた。
――
先輩と会った後、頭の中の全部が、あの先輩のことでいっぱいだった。
入学祝いって言われていつもよりも豪華な食事をしている時も、風呂に入っている時も、兄貴に入学おめでとうLIMEの返信をしている時も助けてくれた先輩のことを考えてしまっていた。
ベッドの上、明日から本格的な授業が始まるのになかなか寝付けなかった。ごろごろと意味のない寝返りを繰り返して、ぼんやりと天井を見つめる、を繰り返す。
――大丈夫? 怪我とかない?
――よかった。
――新入生?
――そうなんだね。入学おめでとう。高校生活、楽しんでね。
先輩に言われた、世間話みたいな言葉を、何度も頭の中で巡らせる。先輩の綺麗な顔を、何度も頭の中で再生する。気に入った曲を再生するみたいに。名前も知らないあの先輩の言葉を何度も巡らせている。
転び掛けたところを助けてもらっただけだというのに、どうして、あの先輩のことが、頭から離れないんだろう……。
「まさか、これが、恋?」
つい、呟いてしまった。俺が、男の先輩に、恋を?
「……」
一目ぼれ、運命の出会い、初恋。好き。恋。恋愛。
「恋」の可能性を考えて、そんな、今の俺に関係ありそうな言葉を、言葉を頭の中で巡らせる。でも、そういう言葉で言い表してしまうには、あまりにも経験が足りていないし、味わったことがない。幼稚園とか小学校低学年の時に女の子と手を繋いだくらい。バレンタインデーは義理チョコしかもらったことがない。漫画とかドラマとかで、恋愛の描写には触れたことがある。けれども、そういうの、とは全く結びつかない。そういうのよりも、もっと激しい、生々しさを感じている。
「それに、まだ、俺、先輩のこと、知らないし」
そう。先輩のことを「好き」とか「恋した」とか言い現わすには、まだ先輩のことを何も知らない。先輩がすごい嫌な人だったら? 怖い人だったら? だから、先輩への想いをなんて言い現わすのかは分からない。
それでも……。
「……また、会いたいな」
先輩に、また会いたい、という気持ちだけは、はっきりとしていた。