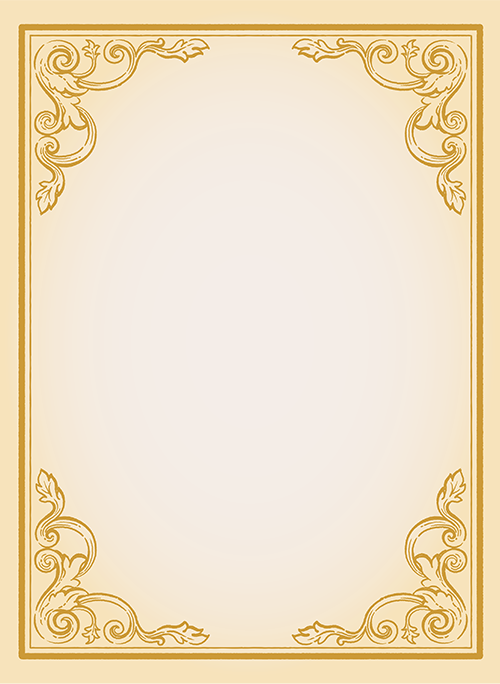「千草様、煌都より文が届いております」
明くる日、そういって志穗さんが文を差し出してくれた。
「文……?」
この字は――姉さまの字だ。
(私が暗殺に失敗したことが気付かれてしまった? それとも、生きていることを咎められる……?)
どちらにせよ良くないことが書かれていることは確かだ。
見て見ぬ振りをするわけにもいかず、私は震える指でそっと封を切る。
その瞬間、ふわりと懐かしい香の香りがたちのぼった。
(――これは)
私の心臓がどくりと跳ねた。
この匂いは、藤の花と甘露を混ぜた香。姉さまがいつも焚いてた香り。
『――千草。私のために、死んで頂戴?』
姉さまの声がすぐ傍で聞こえたようなきがして、ぞくりと身震いした。
次の瞬間――。
「……がはっ」
「千草様っ!?」
喉奥から、熱がこみあげた。
視界がぐにゃりと歪み、背中の呪印が灼けるように疼き出す。
(痛い……なに、これ……っ)
志穗さんがなにか叫んでいるが、全ての音が遠くに聞こえていく。
床に落ちた拍子に文が床に落ちる。それで文に重なっていた護符が目に留まった。
(――姉さま、だ)
姉さまのありったけの清らかな気を込めた護符。それは全身に呪紋が刻まれた私にとっては猛毒だ。
その瞬間、頭の中で声が聞こえた。
《裏切りものには相応しい罰を――》
あの優しく笑う声が、私を殺そうとしている。
(……あぁ)
蹲り、床に爪をたてる。思わず目の奥に熱いものが滲む。
心臓を直接釘で打たれているような感覚が、全身を蝕んでいた。
呪印が――暴走している。姉さまが仕込んでいた、もしもの時の保険だろう。
私が夜神さまを殺せなかったとき、あるいは姉さまを裏切ったときに発動するように仕組まれた呪い。
「千草さまっ!」
「離れて…………っ!」
叫びたいのに痛みで声にならない。
その瞬間、私の体から外へ向かって呪紋がするすると伸びていく。
これは夜神様以外を殺そうとする呪い。夜神様を殺せなくても、この城にいる全員を殺せば、常夜乃国は衰退する。
「……夜神様……っ」
呻くように名を呼んだ。
私を人間として扱ってくれた皆を、ここにいてもいいといってくれた彼を傷付けたくはない。
(嫌だ……こんなの、いや……!)
体から呪紋が漏れ出さないように、歯を食いしばり、爪が畳を裂く。
「夜神様、どうか私を……殺してください……!」
そうしなければ、私は全てを壊すただの呪いとなってしまうのだから。
「千草――!」
扉が音を立てて開いた。風のように飛び込んできた影が、私のすぐ傍へと駆け寄ってくる。
「夜神……さ、ま……」
意識が遠のく中、私はその声を聞き分けた。
仮面をつけた横顔。鋭い眼差しが、痛みに顔を歪める私を真っ直ぐに見つめている。
「呪紋が暴走しているのか!」
夜神様はすぐに掌を私の背へとそえた。
「――っぐ!」
熱く、鋭い光が、その指先から広がる。
痛みと熱に、わたしの体はびくりと震えた。
「はなれて、ください……私の呪紋は暴走して、ここにいる皆を殺してしまうかもしれません……!」
息も絶え絶えにそう叫んだ。
「わたしは……あの人の命令に背きました。だから……これは、罰で……」
「……本当に、そう思ってるのか」
仮面の奥の声は静かだった。
「お前は、殺されかけているんだぞ。それでも、姉を庇うのか」
「――っ」
唇が、震えた。
言い返せなかった。心のどこかで、否と叫んでいる自分がいた。
「――それがお前の望みではないというのでは耐えろ」
なんて静かな言葉だろう。
「お前が我らを殺したくないというのであれば、その力を制御するようになるしかない。そして、呪いを返すんだ」
「呪いを……返す……」
「お前は何者だ。なんのためにここにいる。なにをしたい」
「私は……」
顔をあげると、夜神様と目があった。
私はまだここでほんの僅かしか過ごしていないけれど、一生分の幸せを与えられた。
穏やかな時間を守りたい。もっと、ここにいたい。
「私は……ここに……いたい!」
その瞬間、黒い光がぱんと弾けた。
「……!」
暴れていた呪紋が私の体へと戻っていき、苦しみが引いていく。
息がすこしずつ戻ってくる。
「よく、耐えた」
荒く喉を鳴らすわたしに、夜神は冷たい香草を含ませた布を額に当てた。
そのまま、ゆっくりと抱き上げるようにして床に座らせる。
「なぜ……助けてくれたのですか」
かすれた声が漏れた。
「それがお前の望みだからだ」
夜神様はそっと手を伸ばし、私の頬を撫でた。
「いいか。お前の呪詛は、俺には通じない。だからこうして触れられる」
その指先は優しく、温かい体温を感じた。
「お前が望むならここにいていい。お前は俺の花嫁なのだから――」
その一言に、私の視界が滲む。
「……ありがとうございます」
姉さまの命令でもない、これは私の意志。
ずっと道具として扱われてきた私がはじめて抱いた、意志だった。
明くる日、そういって志穗さんが文を差し出してくれた。
「文……?」
この字は――姉さまの字だ。
(私が暗殺に失敗したことが気付かれてしまった? それとも、生きていることを咎められる……?)
どちらにせよ良くないことが書かれていることは確かだ。
見て見ぬ振りをするわけにもいかず、私は震える指でそっと封を切る。
その瞬間、ふわりと懐かしい香の香りがたちのぼった。
(――これは)
私の心臓がどくりと跳ねた。
この匂いは、藤の花と甘露を混ぜた香。姉さまがいつも焚いてた香り。
『――千草。私のために、死んで頂戴?』
姉さまの声がすぐ傍で聞こえたようなきがして、ぞくりと身震いした。
次の瞬間――。
「……がはっ」
「千草様っ!?」
喉奥から、熱がこみあげた。
視界がぐにゃりと歪み、背中の呪印が灼けるように疼き出す。
(痛い……なに、これ……っ)
志穗さんがなにか叫んでいるが、全ての音が遠くに聞こえていく。
床に落ちた拍子に文が床に落ちる。それで文に重なっていた護符が目に留まった。
(――姉さま、だ)
姉さまのありったけの清らかな気を込めた護符。それは全身に呪紋が刻まれた私にとっては猛毒だ。
その瞬間、頭の中で声が聞こえた。
《裏切りものには相応しい罰を――》
あの優しく笑う声が、私を殺そうとしている。
(……あぁ)
蹲り、床に爪をたてる。思わず目の奥に熱いものが滲む。
心臓を直接釘で打たれているような感覚が、全身を蝕んでいた。
呪印が――暴走している。姉さまが仕込んでいた、もしもの時の保険だろう。
私が夜神さまを殺せなかったとき、あるいは姉さまを裏切ったときに発動するように仕組まれた呪い。
「千草さまっ!」
「離れて…………っ!」
叫びたいのに痛みで声にならない。
その瞬間、私の体から外へ向かって呪紋がするすると伸びていく。
これは夜神様以外を殺そうとする呪い。夜神様を殺せなくても、この城にいる全員を殺せば、常夜乃国は衰退する。
「……夜神様……っ」
呻くように名を呼んだ。
私を人間として扱ってくれた皆を、ここにいてもいいといってくれた彼を傷付けたくはない。
(嫌だ……こんなの、いや……!)
体から呪紋が漏れ出さないように、歯を食いしばり、爪が畳を裂く。
「夜神様、どうか私を……殺してください……!」
そうしなければ、私は全てを壊すただの呪いとなってしまうのだから。
「千草――!」
扉が音を立てて開いた。風のように飛び込んできた影が、私のすぐ傍へと駆け寄ってくる。
「夜神……さ、ま……」
意識が遠のく中、私はその声を聞き分けた。
仮面をつけた横顔。鋭い眼差しが、痛みに顔を歪める私を真っ直ぐに見つめている。
「呪紋が暴走しているのか!」
夜神様はすぐに掌を私の背へとそえた。
「――っぐ!」
熱く、鋭い光が、その指先から広がる。
痛みと熱に、わたしの体はびくりと震えた。
「はなれて、ください……私の呪紋は暴走して、ここにいる皆を殺してしまうかもしれません……!」
息も絶え絶えにそう叫んだ。
「わたしは……あの人の命令に背きました。だから……これは、罰で……」
「……本当に、そう思ってるのか」
仮面の奥の声は静かだった。
「お前は、殺されかけているんだぞ。それでも、姉を庇うのか」
「――っ」
唇が、震えた。
言い返せなかった。心のどこかで、否と叫んでいる自分がいた。
「――それがお前の望みではないというのでは耐えろ」
なんて静かな言葉だろう。
「お前が我らを殺したくないというのであれば、その力を制御するようになるしかない。そして、呪いを返すんだ」
「呪いを……返す……」
「お前は何者だ。なんのためにここにいる。なにをしたい」
「私は……」
顔をあげると、夜神様と目があった。
私はまだここでほんの僅かしか過ごしていないけれど、一生分の幸せを与えられた。
穏やかな時間を守りたい。もっと、ここにいたい。
「私は……ここに……いたい!」
その瞬間、黒い光がぱんと弾けた。
「……!」
暴れていた呪紋が私の体へと戻っていき、苦しみが引いていく。
息がすこしずつ戻ってくる。
「よく、耐えた」
荒く喉を鳴らすわたしに、夜神は冷たい香草を含ませた布を額に当てた。
そのまま、ゆっくりと抱き上げるようにして床に座らせる。
「なぜ……助けてくれたのですか」
かすれた声が漏れた。
「それがお前の望みだからだ」
夜神様はそっと手を伸ばし、私の頬を撫でた。
「いいか。お前の呪詛は、俺には通じない。だからこうして触れられる」
その指先は優しく、温かい体温を感じた。
「お前が望むならここにいていい。お前は俺の花嫁なのだから――」
その一言に、私の視界が滲む。
「……ありがとうございます」
姉さまの命令でもない、これは私の意志。
ずっと道具として扱われてきた私がはじめて抱いた、意志だった。