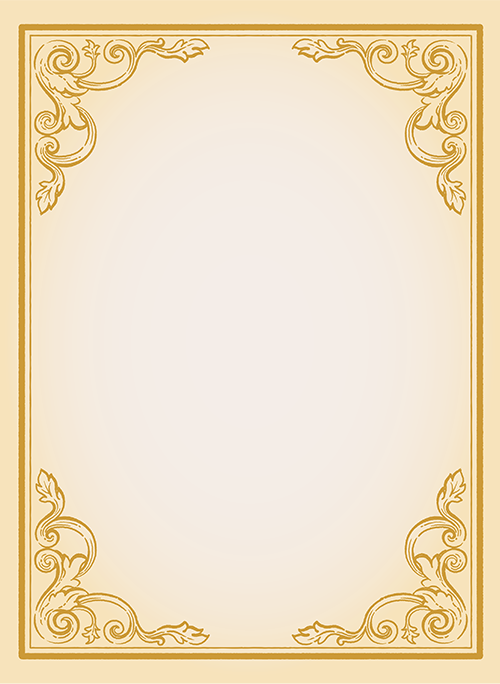――そして次の晩。
私は夜、こっそりと部屋を抜け出し廊下を歩いていた。
寝付きがわるく、夜風に当たろうと思い人知れず部屋を出たのだ。
(勝手に部屋を抜け出したら怒られるかな……)
家では地下室を出ようとした瞬間、酷い折檻を受けたものだ。
なるべく息を殺し、気配を消し、私はそっと中庭へ続く障子を開けた。
「あ……」
庭先に夜神様の姿が見えた。
月明かりの下で、彼は地に膝をつきなにかを眺めている。
(戻らなきゃ――)
「黙っていないでこちらにきたらどうだ」
逃げ出す前に見つかってしまった。
観念してそっと足を進める。
(怒られる……)
部屋から抜け出したことをしられたら……。
故郷でされてきた折檻を思い出し、私は冷や汗を流しながら夜神様の前に出た。
「も、申し訳ありません。私……」
「丁度良かった。お前に見せたいと思っていたんだ」
「え……」
かけられたのは叱責ではなくあまりにも優しい声だった。
おそるおそる顔をあげると、夜神様の視線の先には群れるように咲いた黒い花が咲いていた。
昼間には見えなかったはずの花に私は目を瞬いた。
「……綺麗。こんな花、昨日みた時には」
「これは夜花といってな、夜にしか咲かぬ花なのだ」
驚く私の隣に立ち、夜神様は夜花を見つめる。
「だが、強い毒性があって触れた者に呪いを宿すとされている」
「呪いの花……」
「お前のようだとは思わないか、千草。恐ろしくも、儚く……その美しさは見る者にしかわからない」
「私を……美しいなどと……」
真っ直ぐ見つめられる視線に絶えかね、私はそっと目をそらした。
身体中に呪紋が伸びたこの姿を、恐ろしいといわれども美しいと言われたことははじめてだった。
「お前は、俺が怖いか?」
「……恐ろしい人だと聞いていました」
「そうだろうな。俺は“夜叉”と呼ばれた。人を斬り、呪いを喰い、怨念すら返り血に染めた化け物だ」
その声音に、微かな寂しさが混じっているのを、私は確かに感じた。
「ですが、今は恐ろしくはありません」
私は逸らしていた視線を夜神様に向ける。
「私の目を真っ直ぐ見つめてくださって、この身を醜いと仰らずに普通に接してくださった……私を人のように扱ってくださったのは夜神様がはじめてです」
「俺とお前はどこか似ている」
そっと夜神様は私の頬に手を添えた。
「だから……少しくらい、怖がられずに済む相手がいてもいいと思った」
その言葉が、わたしの胸に深く沈んだ。
(この人も……ずっと、孤独だったんだ)
私ははじめて夜神様の目を見つめ返した。
沈黙が流れる。けれどそれは、心地よい静けさだった。
「私が花ならば、夜神様は月ですね」
私は空を見上げた。
夜空に浮かぶ月は、夜の神の名を拝する彼によく似ていると思ったから。
「私はあの夜、貴方様に救われたのです」
「お前も美しく咲けばいい。ここで、この花のように」
そう言った夜神様の声は、どこまでも優しかった。
“呪いの道具”としてしか扱われなかった私にとって――それははじめての救いだった。
私は夜、こっそりと部屋を抜け出し廊下を歩いていた。
寝付きがわるく、夜風に当たろうと思い人知れず部屋を出たのだ。
(勝手に部屋を抜け出したら怒られるかな……)
家では地下室を出ようとした瞬間、酷い折檻を受けたものだ。
なるべく息を殺し、気配を消し、私はそっと中庭へ続く障子を開けた。
「あ……」
庭先に夜神様の姿が見えた。
月明かりの下で、彼は地に膝をつきなにかを眺めている。
(戻らなきゃ――)
「黙っていないでこちらにきたらどうだ」
逃げ出す前に見つかってしまった。
観念してそっと足を進める。
(怒られる……)
部屋から抜け出したことをしられたら……。
故郷でされてきた折檻を思い出し、私は冷や汗を流しながら夜神様の前に出た。
「も、申し訳ありません。私……」
「丁度良かった。お前に見せたいと思っていたんだ」
「え……」
かけられたのは叱責ではなくあまりにも優しい声だった。
おそるおそる顔をあげると、夜神様の視線の先には群れるように咲いた黒い花が咲いていた。
昼間には見えなかったはずの花に私は目を瞬いた。
「……綺麗。こんな花、昨日みた時には」
「これは夜花といってな、夜にしか咲かぬ花なのだ」
驚く私の隣に立ち、夜神様は夜花を見つめる。
「だが、強い毒性があって触れた者に呪いを宿すとされている」
「呪いの花……」
「お前のようだとは思わないか、千草。恐ろしくも、儚く……その美しさは見る者にしかわからない」
「私を……美しいなどと……」
真っ直ぐ見つめられる視線に絶えかね、私はそっと目をそらした。
身体中に呪紋が伸びたこの姿を、恐ろしいといわれども美しいと言われたことははじめてだった。
「お前は、俺が怖いか?」
「……恐ろしい人だと聞いていました」
「そうだろうな。俺は“夜叉”と呼ばれた。人を斬り、呪いを喰い、怨念すら返り血に染めた化け物だ」
その声音に、微かな寂しさが混じっているのを、私は確かに感じた。
「ですが、今は恐ろしくはありません」
私は逸らしていた視線を夜神様に向ける。
「私の目を真っ直ぐ見つめてくださって、この身を醜いと仰らずに普通に接してくださった……私を人のように扱ってくださったのは夜神様がはじめてです」
「俺とお前はどこか似ている」
そっと夜神様は私の頬に手を添えた。
「だから……少しくらい、怖がられずに済む相手がいてもいいと思った」
その言葉が、わたしの胸に深く沈んだ。
(この人も……ずっと、孤独だったんだ)
私ははじめて夜神様の目を見つめ返した。
沈黙が流れる。けれどそれは、心地よい静けさだった。
「私が花ならば、夜神様は月ですね」
私は空を見上げた。
夜空に浮かぶ月は、夜の神の名を拝する彼によく似ていると思ったから。
「私はあの夜、貴方様に救われたのです」
「お前も美しく咲けばいい。ここで、この花のように」
そう言った夜神様の声は、どこまでも優しかった。
“呪いの道具”としてしか扱われなかった私にとって――それははじめての救いだった。