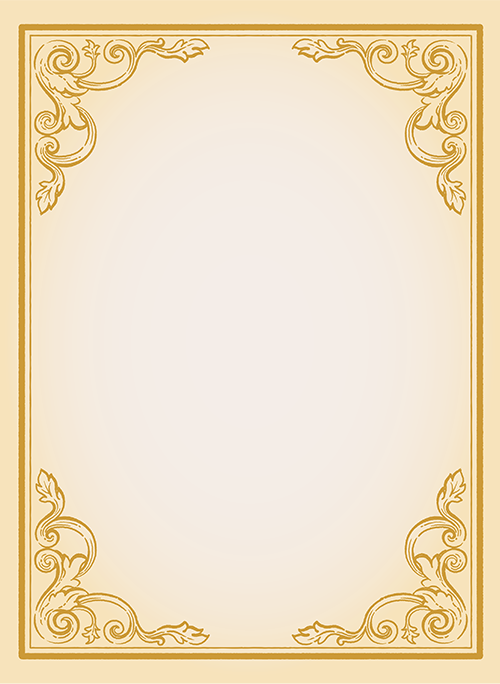翌日、私は小さな離れに移された。
部屋には立派な窓があり、そこからは温かい日が差し込んでいる。
床も壁も真新しく、とても美しい。
卓と寝台しかない簡素な部屋だが、私には十分すぎる部屋だった。
(生きて朝を迎えられるなんて……)
そこには地獄の苦しみも、冷たい視線もなかった。
「朝餉をお持ちしました」
侍女が優しい笑みを浮かべて膳を置いていってくれる。
私の体調を気遣ってか粥を中心とした軽い食事――故郷では有り得ない光景に私は信じられず目を瞬かせた。
まるで人として扱われている。昨晩、あの夜神が私を妻にするといったからなのだろうか。
ぼんやりと目の前の膳それを眺めていると、いつしか夜神様が私の部屋を尋ねてきた。
「朝餉は口にあったか?」
「こんなものを頂いてよろしいのでしょうか?」
食事に手をつけずにいる私を見て、夜神様は匙を手に取るとそれをひとすくい私の口元に運んだ。
「俺を殺すのだろう? 使命を果たす前に死なれては困る」
「え……」
「お前は細すぎる。栄養をつけ、命を濃くしろ。さすればその呪い、俺の体に届くかもしれないぞ?」
ふっと笑いながら、彼は私の唇に匙を軽く当てる。
「自分で食べぬというのであれば、俺が手ずから食べさせてやるが?」
「……じ、自分で食べます」
赤子のような真似をされるなんて恥ずかしい。
私は赤らんだ顔を誤魔化しながら、匙を受け取るとまだ温かいそれをおそるおそる口に運ぶ。
「……おい、しい」
なんて温かくて優しい味だろう。
食べる手が止まらず、二口、三口と食べ進める。
「善い」
それを見て、満足そうに夜神様は私の頭を撫でて去って行くのだった。
(私を殺しにきたわけじゃないのか……)
彼の腰に立派な軍刀が揺れていたが、それが抜かれることは一度もなかった。
結論として、夜神様は私に危害を加えなかった。
自身の命を脅かしにきた私を罰することもなく、ただ時折離れに様子を見にくる。
私の体を暴き呪いの研究をするわけでも、触れれば他者に呪いを移せるという私を利用しようとするわけでもない。
ただ、あまりにも穏やかすぎる時間が流れ、私は戸惑いながら一日、二日と時が流れていった。
「千草様、少し外に出られてはいかがでしょうか?」
「……私などが外に出るなんて」
物いわぬ私を側仕えの侍女――志穗さんは甲斐甲斐しく世話をしてくれた。
「こうして今私が生きていること自体不思議なことなんです。貴女も、私の傍にいるのは恐ろしいでしょう」
「恐ろしくなどありません。夜神様は千草様にも触れさえしなければ、普通に接しても良いと仰っていたので」
志穗さんの笑みは崩れなかった。
(恐ろしくないなんて嘘だ)
故郷では私が身動きひとつするだけで使用人は怯え、悲鳴をあげて逃げていったのだから。
「千草さまはとても可愛らしい顔立ちをされているので、できることなら御髪を整えお化粧をしてさしあげたいのですが……それができないのが心苦しいのですが」
「無理をしなくていいです。怯え、嘲られることには慣れています。たとえ私が夜神様の妻となったからといって、気をつかっていただかなくても――」
私が矢継ぎ早にそう呟くと、志穗さんはやはり変わらず微笑んでいた。
「気遣ってなどおりません。夜神様も同じですから」
「え……?」
「ここにいる誰もが夜神様には触れられません。ですから、千草様への対応は旦那様と同じなのです」
「夜神様に触れられない……?」
戸惑っていると、志穗さんは窓に近づきそっと障子を開けた。
そこから見える中庭は美しく整えられていた。そういえばここにきてからはじめて窓を開けた気がする。
故郷では窓がないのが当たり前だったから。
「……綺麗ですね」
「この離れは夜神様が花嫁様のために建てられた場所です」
「……え?」
手を止め、私は志穗さんをみた。
侍女はしまった口を押さえたが、わたしの驚いた顔に気圧されたのか、小さく続けた。
「どんな方がいらしても怯えないように……気を休めて生活できるように、と壁の厚みや内装など全てを計算されて作ったものです。夜花の咲く庭も、夜神様が自ら植えられたものなんですよ。『故郷を離れ、こんな恐ろしい夜叉の元に嫁ぐのだからせめて美しいものを』と……」
わたしは言葉を失った。
ここにきてから私は誰に蔑まれることもなく、痛い思いもしなかった。
部屋は静かで、朝になると温かい日差しに包まれる、私にはあまりにも温かすぎる場所だったから。
(恐ろしいと謳われていた将がこのようなことを……)
思い出すのは、夜神様の手。
私の腕を掴む力強さ。だけれど、決して痛めつけるようなものではない。
その眼差しは恐ろしくはあったが、いつだって私を気遣ってくれているように見えた。
そしてこの離れの真相を聞き、あの姿を思い出し私の心は不意に締め付けられた。
(あの方は、本当に私をひとりの〝人〟として見ていてくれたんだ――)
指先が震え、気付けば涙がぽろりとこぼれ落ちていた。
ずっと恐ろしくて堪らなかった。殺されると思っていた。
頭の中では『死』は私の運命なのだと納得していたけれど、それでもやはり恐ろしかった。
「ですから、夜神様はとても喜んでおられると思いますよ。自分が触れられる千草様がいらしてくださって」
(……どうして、そんな風に……)
心の奥が、じんわりと熱くなる。
(夜神様……)
部屋には立派な窓があり、そこからは温かい日が差し込んでいる。
床も壁も真新しく、とても美しい。
卓と寝台しかない簡素な部屋だが、私には十分すぎる部屋だった。
(生きて朝を迎えられるなんて……)
そこには地獄の苦しみも、冷たい視線もなかった。
「朝餉をお持ちしました」
侍女が優しい笑みを浮かべて膳を置いていってくれる。
私の体調を気遣ってか粥を中心とした軽い食事――故郷では有り得ない光景に私は信じられず目を瞬かせた。
まるで人として扱われている。昨晩、あの夜神が私を妻にするといったからなのだろうか。
ぼんやりと目の前の膳それを眺めていると、いつしか夜神様が私の部屋を尋ねてきた。
「朝餉は口にあったか?」
「こんなものを頂いてよろしいのでしょうか?」
食事に手をつけずにいる私を見て、夜神様は匙を手に取るとそれをひとすくい私の口元に運んだ。
「俺を殺すのだろう? 使命を果たす前に死なれては困る」
「え……」
「お前は細すぎる。栄養をつけ、命を濃くしろ。さすればその呪い、俺の体に届くかもしれないぞ?」
ふっと笑いながら、彼は私の唇に匙を軽く当てる。
「自分で食べぬというのであれば、俺が手ずから食べさせてやるが?」
「……じ、自分で食べます」
赤子のような真似をされるなんて恥ずかしい。
私は赤らんだ顔を誤魔化しながら、匙を受け取るとまだ温かいそれをおそるおそる口に運ぶ。
「……おい、しい」
なんて温かくて優しい味だろう。
食べる手が止まらず、二口、三口と食べ進める。
「善い」
それを見て、満足そうに夜神様は私の頭を撫でて去って行くのだった。
(私を殺しにきたわけじゃないのか……)
彼の腰に立派な軍刀が揺れていたが、それが抜かれることは一度もなかった。
結論として、夜神様は私に危害を加えなかった。
自身の命を脅かしにきた私を罰することもなく、ただ時折離れに様子を見にくる。
私の体を暴き呪いの研究をするわけでも、触れれば他者に呪いを移せるという私を利用しようとするわけでもない。
ただ、あまりにも穏やかすぎる時間が流れ、私は戸惑いながら一日、二日と時が流れていった。
「千草様、少し外に出られてはいかがでしょうか?」
「……私などが外に出るなんて」
物いわぬ私を側仕えの侍女――志穗さんは甲斐甲斐しく世話をしてくれた。
「こうして今私が生きていること自体不思議なことなんです。貴女も、私の傍にいるのは恐ろしいでしょう」
「恐ろしくなどありません。夜神様は千草様にも触れさえしなければ、普通に接しても良いと仰っていたので」
志穗さんの笑みは崩れなかった。
(恐ろしくないなんて嘘だ)
故郷では私が身動きひとつするだけで使用人は怯え、悲鳴をあげて逃げていったのだから。
「千草さまはとても可愛らしい顔立ちをされているので、できることなら御髪を整えお化粧をしてさしあげたいのですが……それができないのが心苦しいのですが」
「無理をしなくていいです。怯え、嘲られることには慣れています。たとえ私が夜神様の妻となったからといって、気をつかっていただかなくても――」
私が矢継ぎ早にそう呟くと、志穗さんはやはり変わらず微笑んでいた。
「気遣ってなどおりません。夜神様も同じですから」
「え……?」
「ここにいる誰もが夜神様には触れられません。ですから、千草様への対応は旦那様と同じなのです」
「夜神様に触れられない……?」
戸惑っていると、志穗さんは窓に近づきそっと障子を開けた。
そこから見える中庭は美しく整えられていた。そういえばここにきてからはじめて窓を開けた気がする。
故郷では窓がないのが当たり前だったから。
「……綺麗ですね」
「この離れは夜神様が花嫁様のために建てられた場所です」
「……え?」
手を止め、私は志穗さんをみた。
侍女はしまった口を押さえたが、わたしの驚いた顔に気圧されたのか、小さく続けた。
「どんな方がいらしても怯えないように……気を休めて生活できるように、と壁の厚みや内装など全てを計算されて作ったものです。夜花の咲く庭も、夜神様が自ら植えられたものなんですよ。『故郷を離れ、こんな恐ろしい夜叉の元に嫁ぐのだからせめて美しいものを』と……」
わたしは言葉を失った。
ここにきてから私は誰に蔑まれることもなく、痛い思いもしなかった。
部屋は静かで、朝になると温かい日差しに包まれる、私にはあまりにも温かすぎる場所だったから。
(恐ろしいと謳われていた将がこのようなことを……)
思い出すのは、夜神様の手。
私の腕を掴む力強さ。だけれど、決して痛めつけるようなものではない。
その眼差しは恐ろしくはあったが、いつだって私を気遣ってくれているように見えた。
そしてこの離れの真相を聞き、あの姿を思い出し私の心は不意に締め付けられた。
(あの方は、本当に私をひとりの〝人〟として見ていてくれたんだ――)
指先が震え、気付けば涙がぽろりとこぼれ落ちていた。
ずっと恐ろしくて堪らなかった。殺されると思っていた。
頭の中では『死』は私の運命なのだと納得していたけれど、それでもやはり恐ろしかった。
「ですから、夜神様はとても喜んでおられると思いますよ。自分が触れられる千草様がいらしてくださって」
(……どうして、そんな風に……)
心の奥が、じんわりと熱くなる。
(夜神様……)