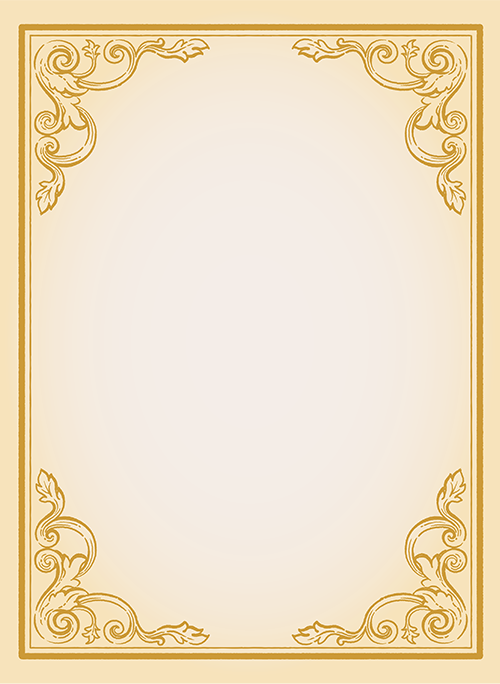目を開けたとき、目の前には天井が広がっていた。
先程までいた部屋とは違う。視線を動かすと、窓が見えそこから日の光が差し込んでいた。
(生きてる……?)
息を吸い込み、体を起こす。
まだ呪紋の痛みが少し残っていたけれど、他に体のどこにも異常はなかった。
それどころか、花嫁衣装から普通の寝間着に着替えさせられている。
(私は失敗してしまった。あの人を殺すどころか、痛みに負けて気を失って……)
その時、ふと視線を感じた。
静かに振り向くと、部屋の隅には黒の軍装を纏った――夜神が立っていた。
「目が覚めたようだな」
すると彼はその場から動かないまま、私の枕元を指さした。
そこには液体で満たされた湯飲みが置かれている。
「飲め。体の毒気を鎮める薬だ。それを飲めば痛みが和らぐだろう」
静かな声だった。
私は俯いたままなにも答えない。やがて痺れを切らした彼が、私の元に歩み寄り湯飲みを差し出す。
「命令だ。飲め。それとも無理矢理口移しをされたいか」
「――っ」
顎を掴まれ、顔をあげられた。
眼前に夜神の顔が広がる。
近くで見るとその恐ろしさと美しさに息を飲み込んでしまう。
「わかり、ました……」
いわれるがままに私は大人しく薬を飲んだ。なんともいえない苦みが口いっぱいに広がる。
「……何故、私を殺さないのですか」
袖口を拭いながら私はぽつりと呟いた。
「お前はどうせ捨て身で俺を殺せと命じられたのだろう。そもそも俺に呪詛は効かないし、死のうとしている人間を殺す趣味もない」
静かな声だった。
「逃がしてやろう。故郷に帰り静かに暮せ」
「……帰る場所などありません」
私の呟きに夜神は小さく瞬いた。
「私は姉に死ねと命じられました。忌み嫌われた双子の片割れ、呪われた私に返る場所などありません」
「姉……? お前、まさか煌都の姫巫女の――」
そして私は畳の上に膝をつき、頭を垂れた。
「お願いです。夜神様、どうか私を殺していただけないでしょうか」
私はずっと終わりを求めていたのかもしれない。
姉さまだって、失敗した私を必要とはしてくれないだろう。
「全ての咎はこの私にあります。国や姉は関係ありません。私に全ての責が――」
「黙れ」
冷たい声だ。
夜神は顎に手を添えられ持ち上げられる。
「――暗い目をしているな。そしてそのような呪いを身に宿すお前が今までどのような生を送ってきたか、大方想像はついた」
そのまま添えられた手は頬へ移動する。
「帰る場所がないなら、ここにいればいい」
「え……」
思わぬ言葉に目を瞬かせた。
「お前はあの姫巫女の妹なのだろう。ならば、俺の妻として申し分ない」
「なにを……いって……」
「お前の呪詛は俺には効かない。だからこうして触れられる……今は、な」
「今は……?」
そしてふっと笑う。
「お前の任務は俺を殺すことだろう? 今は効かずとも、俺の傍にいればいずれ殺せるときがくるかもしれない」
「な――」
「面白い。お前が俺を殺せるか試してみよう」
物珍しい玩具を見つけた子どものように彼は笑った。
姉さま以外にはじめて感じた人の体温は、とても温かく優しいものだった。
「お前、名前は?」
「……神垣千草と、申します」
「千草。お前は今日から俺の妻となれ」
先程までいた部屋とは違う。視線を動かすと、窓が見えそこから日の光が差し込んでいた。
(生きてる……?)
息を吸い込み、体を起こす。
まだ呪紋の痛みが少し残っていたけれど、他に体のどこにも異常はなかった。
それどころか、花嫁衣装から普通の寝間着に着替えさせられている。
(私は失敗してしまった。あの人を殺すどころか、痛みに負けて気を失って……)
その時、ふと視線を感じた。
静かに振り向くと、部屋の隅には黒の軍装を纏った――夜神が立っていた。
「目が覚めたようだな」
すると彼はその場から動かないまま、私の枕元を指さした。
そこには液体で満たされた湯飲みが置かれている。
「飲め。体の毒気を鎮める薬だ。それを飲めば痛みが和らぐだろう」
静かな声だった。
私は俯いたままなにも答えない。やがて痺れを切らした彼が、私の元に歩み寄り湯飲みを差し出す。
「命令だ。飲め。それとも無理矢理口移しをされたいか」
「――っ」
顎を掴まれ、顔をあげられた。
眼前に夜神の顔が広がる。
近くで見るとその恐ろしさと美しさに息を飲み込んでしまう。
「わかり、ました……」
いわれるがままに私は大人しく薬を飲んだ。なんともいえない苦みが口いっぱいに広がる。
「……何故、私を殺さないのですか」
袖口を拭いながら私はぽつりと呟いた。
「お前はどうせ捨て身で俺を殺せと命じられたのだろう。そもそも俺に呪詛は効かないし、死のうとしている人間を殺す趣味もない」
静かな声だった。
「逃がしてやろう。故郷に帰り静かに暮せ」
「……帰る場所などありません」
私の呟きに夜神は小さく瞬いた。
「私は姉に死ねと命じられました。忌み嫌われた双子の片割れ、呪われた私に返る場所などありません」
「姉……? お前、まさか煌都の姫巫女の――」
そして私は畳の上に膝をつき、頭を垂れた。
「お願いです。夜神様、どうか私を殺していただけないでしょうか」
私はずっと終わりを求めていたのかもしれない。
姉さまだって、失敗した私を必要とはしてくれないだろう。
「全ての咎はこの私にあります。国や姉は関係ありません。私に全ての責が――」
「黙れ」
冷たい声だ。
夜神は顎に手を添えられ持ち上げられる。
「――暗い目をしているな。そしてそのような呪いを身に宿すお前が今までどのような生を送ってきたか、大方想像はついた」
そのまま添えられた手は頬へ移動する。
「帰る場所がないなら、ここにいればいい」
「え……」
思わぬ言葉に目を瞬かせた。
「お前はあの姫巫女の妹なのだろう。ならば、俺の妻として申し分ない」
「なにを……いって……」
「お前の呪詛は俺には効かない。だからこうして触れられる……今は、な」
「今は……?」
そしてふっと笑う。
「お前の任務は俺を殺すことだろう? 今は効かずとも、俺の傍にいればいずれ殺せるときがくるかもしれない」
「な――」
「面白い。お前が俺を殺せるか試してみよう」
物珍しい玩具を見つけた子どものように彼は笑った。
姉さま以外にはじめて感じた人の体温は、とても温かく優しいものだった。
「お前、名前は?」
「……神垣千草と、申します」
「千草。お前は今日から俺の妻となれ」