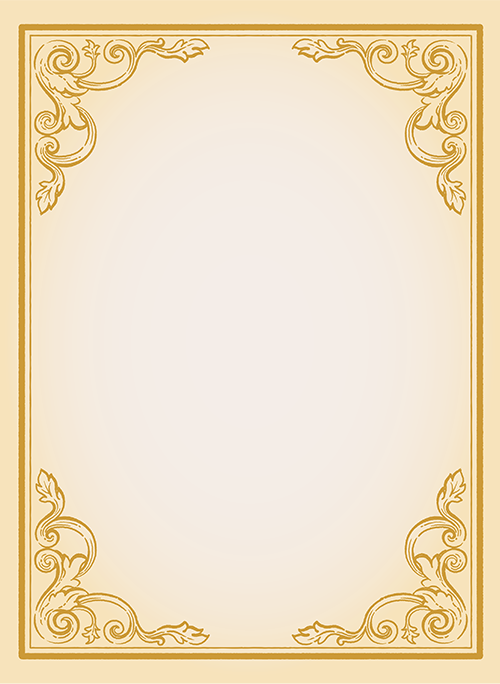「呪いを宿した者がふれれば、たちまち相手に呪を移せる。あなたは夜神に触れるだけでいいの」
姉さまは優しい声で、私に〝人の殺し方〟を教えてくれた。
「でも相手はあの夜叉王。呪いが効かないという噂もある。でも……だからこそ、私はあなたを育てたの」
わたしの袖を捲ると、そこには紫黒の呪紋が刻まれている。
それを姉さまは愛おしそうに眺め見た。
「あなたの身体には穢れが詰まっている。あらゆる呪いの澱を吸って、育ててきたの。まさに〝生きる呪い〟ね」
「生きる呪い……」
「いい? 奇襲は一度しか使えない。しくじれば、死ぬのはあなただけじゃなくなる。だから――絶対に、失敗しないで」
わたしは恐ろしくなって小さく息を呑むと、姉さまはくすりと優しい笑みを浮かべた。
「ふふ……そんな顔しないで? 怖がることはないのだから」
白い指が私の頬にそっと触れ、ゆっくり柔らかく撫でられた。
姉さまには私の呪いは通じない。姉さまだけがわたしに触れて生きていられるこの世で唯一の人。
「千草……なんて無様でなんて愛しい私の妹」
顎をくいっと持ち上げられる。冷徹な瞳で射抜かれる。
「あなたは私の影。私だけのために生きて、私だけのために死ぬ。それが、あなたの幸福よ」
「はい……姉さま」
姉さまの顔が、月明かりの中で少しだけ、ぼやけて見えた。
*
――この男を殺さねば、私に価値はない。
指先の震えを隠すように、着物の袖をぎゅっと握りながら私は目の前の男と対峙した。
無造作に束ねられた長い黒髪。
真っ黒な鎧。だが何よりも印象的なのは、その左の顔を隠す漆黒の仮面。
その片側から覗く赤い瞳は、あまりにも鋭い。
底知れぬ闇を湛えたその光は、獣が獲物を見定めるように、私を射抜いた。
彼は夜神――夜叉王と呼ばれるこの国の長。
「俺を殺すために送られた花嫁か――なんとも面白い、粋な計らいだ」
男はそういって笑った。
(……どうして)
私の心臓は動揺と恐怖で信じられない速度で脈打っていた。
(彼に腕を掴まれた。今だって、触られているままなのに――)
姉様はいった。私に触れるだけで、夜神は死ぬと。
故郷でもそうだった。この身に呪いを宿した私に触れられる者は誰もいなかった――姉様を除いて。
だから頑なにみんな私と距離を取り、絶対に触れようとしなかったのに。
目の前に立つこの男は、私に触れて平気な顔をして立っていた。
「俺が生きているのが不思議だ、という表情だな。よほどその呪い強いと見える」
「――っ!」
夜神は私の袖口をさらに深く捲り上げた。
そこに露わになる紫黒の呪紋。それは私の意志とは関係なく、触れられた相手の命を蝕まんと、淡い光を放つ。
「完全に一体化しているな……まさに〝生きた呪詛〟こんなモノを作り上げるとは煌都の人間は末恐ろしい」
すうっと夜神の指が呪紋を撫でた。
「――っ、ううっ」
その瞬間、身体中に刻まれた呪紋が疼きだす。
全身にぞわりと痛みが走り、視界が歪む。
「……くだらん」
彼が私の手を離した。
私は無様に地面に蹲り、乱れた呼吸を整える。
「そんなもので俺は死なない。どんな呪詛も、毒も……不死身の夜叉王たる俺には効かない」
(夜神様に呪詛がきかないという噂は本当だった……)
呪詛が効かない不死身の夜叉。
それ故、圧倒的強さを誇り、畏怖される。
(私が彼を殺せないなら……私は……もう……)
震えて声が出なかった。
殺されるのだ。呪紋に気付かれたなら、この婚姻の目的に気付かれたなら、生かされる理由なんてない。
「お前……死ぬ覚悟で俺の元に来たな?」
冷たい視線で見下ろされる。
私は痛みに絶え、汗を滲ませながら息も絶え絶えにその男を見上げることしかできなかった。
姉さまは優しい声で、私に〝人の殺し方〟を教えてくれた。
「でも相手はあの夜叉王。呪いが効かないという噂もある。でも……だからこそ、私はあなたを育てたの」
わたしの袖を捲ると、そこには紫黒の呪紋が刻まれている。
それを姉さまは愛おしそうに眺め見た。
「あなたの身体には穢れが詰まっている。あらゆる呪いの澱を吸って、育ててきたの。まさに〝生きる呪い〟ね」
「生きる呪い……」
「いい? 奇襲は一度しか使えない。しくじれば、死ぬのはあなただけじゃなくなる。だから――絶対に、失敗しないで」
わたしは恐ろしくなって小さく息を呑むと、姉さまはくすりと優しい笑みを浮かべた。
「ふふ……そんな顔しないで? 怖がることはないのだから」
白い指が私の頬にそっと触れ、ゆっくり柔らかく撫でられた。
姉さまには私の呪いは通じない。姉さまだけがわたしに触れて生きていられるこの世で唯一の人。
「千草……なんて無様でなんて愛しい私の妹」
顎をくいっと持ち上げられる。冷徹な瞳で射抜かれる。
「あなたは私の影。私だけのために生きて、私だけのために死ぬ。それが、あなたの幸福よ」
「はい……姉さま」
姉さまの顔が、月明かりの中で少しだけ、ぼやけて見えた。
*
――この男を殺さねば、私に価値はない。
指先の震えを隠すように、着物の袖をぎゅっと握りながら私は目の前の男と対峙した。
無造作に束ねられた長い黒髪。
真っ黒な鎧。だが何よりも印象的なのは、その左の顔を隠す漆黒の仮面。
その片側から覗く赤い瞳は、あまりにも鋭い。
底知れぬ闇を湛えたその光は、獣が獲物を見定めるように、私を射抜いた。
彼は夜神――夜叉王と呼ばれるこの国の長。
「俺を殺すために送られた花嫁か――なんとも面白い、粋な計らいだ」
男はそういって笑った。
(……どうして)
私の心臓は動揺と恐怖で信じられない速度で脈打っていた。
(彼に腕を掴まれた。今だって、触られているままなのに――)
姉様はいった。私に触れるだけで、夜神は死ぬと。
故郷でもそうだった。この身に呪いを宿した私に触れられる者は誰もいなかった――姉様を除いて。
だから頑なにみんな私と距離を取り、絶対に触れようとしなかったのに。
目の前に立つこの男は、私に触れて平気な顔をして立っていた。
「俺が生きているのが不思議だ、という表情だな。よほどその呪い強いと見える」
「――っ!」
夜神は私の袖口をさらに深く捲り上げた。
そこに露わになる紫黒の呪紋。それは私の意志とは関係なく、触れられた相手の命を蝕まんと、淡い光を放つ。
「完全に一体化しているな……まさに〝生きた呪詛〟こんなモノを作り上げるとは煌都の人間は末恐ろしい」
すうっと夜神の指が呪紋を撫でた。
「――っ、ううっ」
その瞬間、身体中に刻まれた呪紋が疼きだす。
全身にぞわりと痛みが走り、視界が歪む。
「……くだらん」
彼が私の手を離した。
私は無様に地面に蹲り、乱れた呼吸を整える。
「そんなもので俺は死なない。どんな呪詛も、毒も……不死身の夜叉王たる俺には効かない」
(夜神様に呪詛がきかないという噂は本当だった……)
呪詛が効かない不死身の夜叉。
それ故、圧倒的強さを誇り、畏怖される。
(私が彼を殺せないなら……私は……もう……)
震えて声が出なかった。
殺されるのだ。呪紋に気付かれたなら、この婚姻の目的に気付かれたなら、生かされる理由なんてない。
「お前……死ぬ覚悟で俺の元に来たな?」
冷たい視線で見下ろされる。
私は痛みに絶え、汗を滲ませながら息も絶え絶えにその男を見上げることしかできなかった。