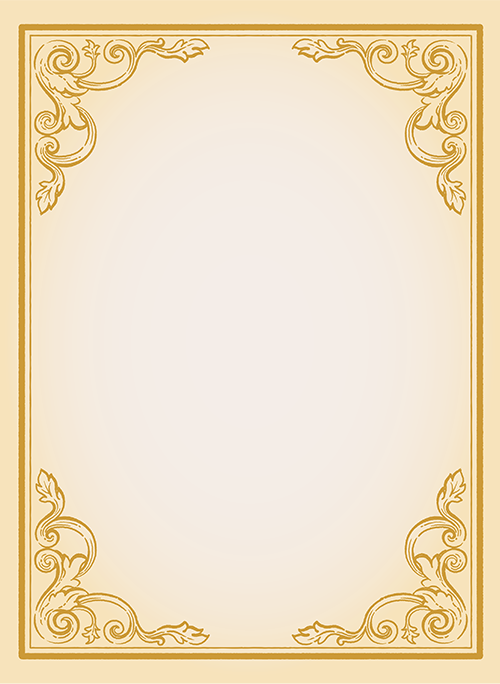あの日から八年という歳月が流れた。
私は姉さまが穢れを身に受けるたびに、それを肩代わりした。
呪紋は広がり続け、やがて私の背を覆い尽くすほどになっていた。
「千草様は本当に気味が悪い」
「触れただけで……いや、目をあわせただけで呪いが移されるかもしれない」
屋敷の者たちは皆私を忌み嫌い、避け続けた。
やがて、私の体は全身包帯で覆われ、誰とも目を合わせぬようにと目隠しも施された。
そして部屋は地上の蔵から、地下の座敷牢へと移された。食事は粗末な物になり、世話をしてくれる者はいない。
外に出られるのは姉さまに呼びだされたときの僅かな時間のみ――。
「千草、今日も宜しく頼むわね」
「……はい」
姉さまが私に手をかざす。
姉さまが祓い、身に宿した呪詛が私の体の中へと入ってくる。
「う、ううううっ――!」
いつものように蹲り激痛に絶える。
これを絶え凌げばやがて痛みが落ち着くはずだった。
「うっ、げほっ……げほっ……」
突然私は咳き込んだ。何かを吐き出すような水音がする。
「――え」
緩んだ目隠しのすき間から真っ赤な血が見えた。
おそるおそる顔をあげると、神鏡に私の姿が映っていた。
痛みにもがいたせいで包帯がはらりと解ける。
私の全身には呪紋が伸びきっていた。
「これ……私……?」
そんな恐ろしい姿を見て、姉さまは「あら」と笑みを零した。
「もう貴女もいっぱいになってしまったのね」
なんてことはなさそうに、平然と私を見つめて姉さまは続ける。
「なんて醜い姿かしら。それではまるで貴女自身が呪いのよう」
「姉さま……私……」
伸ばした手は払い除けられた。
「呪いを受けられない貴女なんて必要ないわ。そうね、貴女を遠い国に嫁がせましょう」
良いことを思いついた、というように姉さまは上機嫌そうに笑う。
「常夜乃国の夜神という将がいるの。彼はどんな攻撃、呪いも通じない夜叉将軍。私たち煌都の敵――」
札越しに私の手に姉様はむき身の小太刀を握らせた。
「貴女を夜神に捧げましょう。そして彼を殺して頂戴?」
それが貴女の最後の仕事よ、そういって姉さまはいつものように微笑みを浮かべるのだった。
そうして私はこの地に来た。
常夜乃国――そこを治めるのは夜神という、夜叉のように恐ろしい将がいる。
表向きは長年冷戦状態を続けてきた、煌都国と常夜乃国との同盟のための政略結婚。
だが、その裏では私という呪いを用い夜神を討ち取るという暗殺計画。
私は黒の無垢袖に身を包み、国へと送られた。
黒い綿帽子に顔は隠れ、誰も私の全身が呪紋で覆われていることなど知る由もない。
「煌都の姫巫女よ、よくぞ常夜乃国へといらっしゃった。歓迎しよう」
口ではそう言われたが、周囲からは冷たい視線が突き刺さる。
恐ろしい野蛮な武者ばかりだ。一歩でも怪しい動きをすれば、私の息の根を奪わんと全員が殺気を放っている。
「――夜神様のご命令です。この部屋から決して出ぬよう」
そして侍女が私をある部屋へと案内した。
そこは窓一つない狭い部屋。周囲には札が張り巡らされている。
(ここでも幽閉されるのはかわりないの、か)
唯一異なることがあるとすれば、目の前の卓には水と簡易的な食事が置かれていたこと。
だけど、食事なんて喉を通らなかった。
(私は、今から人を殺す――)
そして敵将を殺せば私もタダでは済まないだろう。
懐に忍び込ませた小太刀を震える手で握る。静けさだけが密室を包み込んでいた。
そして扉が開いたのは数刻後のことだった。
「お前が、煌都の姫巫女だな」
現れた男の姿に、私は思わず息をのんだ。
黒の軍服。顔の左半分を覆い隠す銀色の仮面。長く伸びた黒髪を無造作に束ねた男――。
片方の眼差しは、底知れぬ闇のように冷たかった。
「はい。煌都より参りました名は――」
頭を下げても、彼は眉一つ動かさなかった。
そして彼はゆっくりと私に歩み寄り、言葉が終わる前に勢いよく腕を引いた。
「きゃっ!?」
「――ほう。これは、面白い」
露わになった腕に伸びる呪紋が紫黒の光を帯びる。
「呪紋の姫――といったところか。お前、この俺を殺すつもりできただろう」
その瞬間、私の計画は全て崩れ落ちた。
私を見下ろす夜神の唇が微かに歪んだ。
それが、笑みだったのかどうか、私にはわからなかった。
私は姉さまが穢れを身に受けるたびに、それを肩代わりした。
呪紋は広がり続け、やがて私の背を覆い尽くすほどになっていた。
「千草様は本当に気味が悪い」
「触れただけで……いや、目をあわせただけで呪いが移されるかもしれない」
屋敷の者たちは皆私を忌み嫌い、避け続けた。
やがて、私の体は全身包帯で覆われ、誰とも目を合わせぬようにと目隠しも施された。
そして部屋は地上の蔵から、地下の座敷牢へと移された。食事は粗末な物になり、世話をしてくれる者はいない。
外に出られるのは姉さまに呼びだされたときの僅かな時間のみ――。
「千草、今日も宜しく頼むわね」
「……はい」
姉さまが私に手をかざす。
姉さまが祓い、身に宿した呪詛が私の体の中へと入ってくる。
「う、ううううっ――!」
いつものように蹲り激痛に絶える。
これを絶え凌げばやがて痛みが落ち着くはずだった。
「うっ、げほっ……げほっ……」
突然私は咳き込んだ。何かを吐き出すような水音がする。
「――え」
緩んだ目隠しのすき間から真っ赤な血が見えた。
おそるおそる顔をあげると、神鏡に私の姿が映っていた。
痛みにもがいたせいで包帯がはらりと解ける。
私の全身には呪紋が伸びきっていた。
「これ……私……?」
そんな恐ろしい姿を見て、姉さまは「あら」と笑みを零した。
「もう貴女もいっぱいになってしまったのね」
なんてことはなさそうに、平然と私を見つめて姉さまは続ける。
「なんて醜い姿かしら。それではまるで貴女自身が呪いのよう」
「姉さま……私……」
伸ばした手は払い除けられた。
「呪いを受けられない貴女なんて必要ないわ。そうね、貴女を遠い国に嫁がせましょう」
良いことを思いついた、というように姉さまは上機嫌そうに笑う。
「常夜乃国の夜神という将がいるの。彼はどんな攻撃、呪いも通じない夜叉将軍。私たち煌都の敵――」
札越しに私の手に姉様はむき身の小太刀を握らせた。
「貴女を夜神に捧げましょう。そして彼を殺して頂戴?」
それが貴女の最後の仕事よ、そういって姉さまはいつものように微笑みを浮かべるのだった。
そうして私はこの地に来た。
常夜乃国――そこを治めるのは夜神という、夜叉のように恐ろしい将がいる。
表向きは長年冷戦状態を続けてきた、煌都国と常夜乃国との同盟のための政略結婚。
だが、その裏では私という呪いを用い夜神を討ち取るという暗殺計画。
私は黒の無垢袖に身を包み、国へと送られた。
黒い綿帽子に顔は隠れ、誰も私の全身が呪紋で覆われていることなど知る由もない。
「煌都の姫巫女よ、よくぞ常夜乃国へといらっしゃった。歓迎しよう」
口ではそう言われたが、周囲からは冷たい視線が突き刺さる。
恐ろしい野蛮な武者ばかりだ。一歩でも怪しい動きをすれば、私の息の根を奪わんと全員が殺気を放っている。
「――夜神様のご命令です。この部屋から決して出ぬよう」
そして侍女が私をある部屋へと案内した。
そこは窓一つない狭い部屋。周囲には札が張り巡らされている。
(ここでも幽閉されるのはかわりないの、か)
唯一異なることがあるとすれば、目の前の卓には水と簡易的な食事が置かれていたこと。
だけど、食事なんて喉を通らなかった。
(私は、今から人を殺す――)
そして敵将を殺せば私もタダでは済まないだろう。
懐に忍び込ませた小太刀を震える手で握る。静けさだけが密室を包み込んでいた。
そして扉が開いたのは数刻後のことだった。
「お前が、煌都の姫巫女だな」
現れた男の姿に、私は思わず息をのんだ。
黒の軍服。顔の左半分を覆い隠す銀色の仮面。長く伸びた黒髪を無造作に束ねた男――。
片方の眼差しは、底知れぬ闇のように冷たかった。
「はい。煌都より参りました名は――」
頭を下げても、彼は眉一つ動かさなかった。
そして彼はゆっくりと私に歩み寄り、言葉が終わる前に勢いよく腕を引いた。
「きゃっ!?」
「――ほう。これは、面白い」
露わになった腕に伸びる呪紋が紫黒の光を帯びる。
「呪紋の姫――といったところか。お前、この俺を殺すつもりできただろう」
その瞬間、私の計画は全て崩れ落ちた。
私を見下ろす夜神の唇が微かに歪んだ。
それが、笑みだったのかどうか、私にはわからなかった。