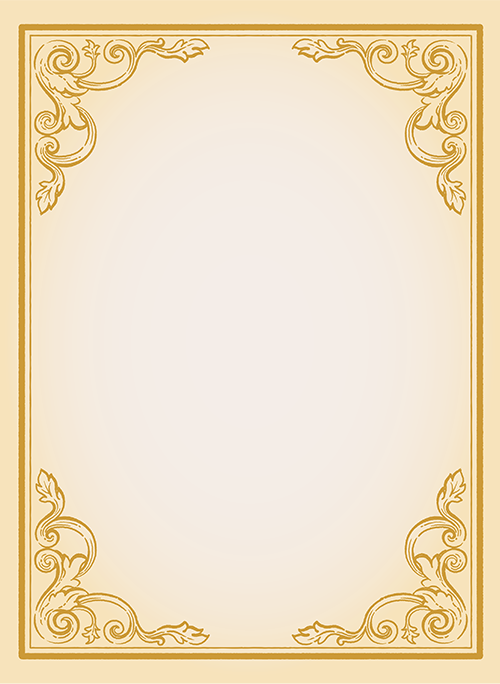同じ月日、同じ時間にこの世に生を受けた私たちを違えたのは、一体なんだったのだろう。
この国には、神の声を聞く巫女がいる。
巫女――神垣紫苑。その名を知らぬ者は、この煌都(こうと)にはいない。
神託を降ろし、呪詛を祓い、帝さえも一目置く美しき姫巫女。
その双子の妹として生まれた私――千草は、生まれた時から「影」だった。
双子は忌み子とされるこの国で、私たちは例外だった。
姉の額には、神に愛された証「神紋」が輝き、対する私は、左頬に黒々とした呪いの痣――「呪紋」を刻んで生まれ落ちた。
「――千草、神前では口を開いてはだめよ。貴女の声は濁っていて、神が嫌うわ」
「はい、姉さま」
姉さまは優しく笑いながらそういった。
だから、私は祈祷の場では沈黙を守った。 祝詞を捧げるのは姉さまだけ。
私は、姉の背後にひざまずく影だ。
同じ衣は着てはならず、食卓でも姉の箸が動くまで手をつけてはならない。
書を学ぶのも、姉が読んだ後でなければ許されなかった。
私は「穢れ」として、神殿の奥に閉じ込められて育った。
それでも、私は幸せだった。
「千草、貴女は本当に良い子ね。私だけの可愛い影……」
姉さまの笑顔のそばにいられるだけで心が満たされたから。
たとえ周囲が私を忌み嫌ったとしても、姉さまだけが私を見てくれていたから。
――あれは私たちが十歳を迎える春のことだった。
「きゃああああああっ!」
呪詛返しに失敗した姉さまの掌に黒い痣が浮かんだのだ。
「これは……強すぎる……」
「そんな華苑はこの国にとって大切な神託の巫女なのに!」
呪いの力が強く、姉さまは何日も高熱に魘され続けた。
私は姉さまに会うことも適わず、ただ幽閉された部屋で姉様の無事を祈り続けた。
「――千草、来なさい」
そんなある日、突然父が私を部屋の外に連れ出した。
「姉さま……!」
姉さまは布団に横たわり、荒い息を繰り返していた。
呪紋は肩口まで広がっている。私は溜まらず姉さまの手を握った。
触れあうことは決して許されなかったはずなのに、その時は誰も私を叱ったりしなかった。
その瞬間――。
「きゃあああっ!」
体に激痛が走った。左の手の平から肩口にかけて熱湯をかけられたような痛みが広がっていく。
「――うっ」
涙ににじむ目で手を見た。
するとそこには姉さまの手にあったはずの呪紋が移っていた。
「やはり、予想通りだ!」
父様の喜ぶ声が聞こえる。
「千草は呪いを引き受けられる……」
そのとき、はじめて父様が私を映した。
「生かしておいて正解だった。お前は華苑を支えるために生まれてきたんだな!」
「…………ここは」
それからすぐに姉さまは目を覚ました。
みんな姉さまの無事を喜んでいた。私も嬉しかった。
でも、焼け付くような呪いの痛みは三日三晩私を苦しめたけれど――私を心配してくれる人は誰もいなかった。
それから私は姉さまの身代わりとして呪いを受けることが役目になった。
呪いを引き受ける度に、体は痛み、血を吐き、痣は増え続けた。
だが姉さまは微笑んで、痛みに蹲る私を見下ろしながら冷たく微笑むのだ。
「よくできたわ、千草。あなたはやっぱり、私の影なのね」
この国には、神の声を聞く巫女がいる。
巫女――神垣紫苑。その名を知らぬ者は、この煌都(こうと)にはいない。
神託を降ろし、呪詛を祓い、帝さえも一目置く美しき姫巫女。
その双子の妹として生まれた私――千草は、生まれた時から「影」だった。
双子は忌み子とされるこの国で、私たちは例外だった。
姉の額には、神に愛された証「神紋」が輝き、対する私は、左頬に黒々とした呪いの痣――「呪紋」を刻んで生まれ落ちた。
「――千草、神前では口を開いてはだめよ。貴女の声は濁っていて、神が嫌うわ」
「はい、姉さま」
姉さまは優しく笑いながらそういった。
だから、私は祈祷の場では沈黙を守った。 祝詞を捧げるのは姉さまだけ。
私は、姉の背後にひざまずく影だ。
同じ衣は着てはならず、食卓でも姉の箸が動くまで手をつけてはならない。
書を学ぶのも、姉が読んだ後でなければ許されなかった。
私は「穢れ」として、神殿の奥に閉じ込められて育った。
それでも、私は幸せだった。
「千草、貴女は本当に良い子ね。私だけの可愛い影……」
姉さまの笑顔のそばにいられるだけで心が満たされたから。
たとえ周囲が私を忌み嫌ったとしても、姉さまだけが私を見てくれていたから。
――あれは私たちが十歳を迎える春のことだった。
「きゃああああああっ!」
呪詛返しに失敗した姉さまの掌に黒い痣が浮かんだのだ。
「これは……強すぎる……」
「そんな華苑はこの国にとって大切な神託の巫女なのに!」
呪いの力が強く、姉さまは何日も高熱に魘され続けた。
私は姉さまに会うことも適わず、ただ幽閉された部屋で姉様の無事を祈り続けた。
「――千草、来なさい」
そんなある日、突然父が私を部屋の外に連れ出した。
「姉さま……!」
姉さまは布団に横たわり、荒い息を繰り返していた。
呪紋は肩口まで広がっている。私は溜まらず姉さまの手を握った。
触れあうことは決して許されなかったはずなのに、その時は誰も私を叱ったりしなかった。
その瞬間――。
「きゃあああっ!」
体に激痛が走った。左の手の平から肩口にかけて熱湯をかけられたような痛みが広がっていく。
「――うっ」
涙ににじむ目で手を見た。
するとそこには姉さまの手にあったはずの呪紋が移っていた。
「やはり、予想通りだ!」
父様の喜ぶ声が聞こえる。
「千草は呪いを引き受けられる……」
そのとき、はじめて父様が私を映した。
「生かしておいて正解だった。お前は華苑を支えるために生まれてきたんだな!」
「…………ここは」
それからすぐに姉さまは目を覚ました。
みんな姉さまの無事を喜んでいた。私も嬉しかった。
でも、焼け付くような呪いの痛みは三日三晩私を苦しめたけれど――私を心配してくれる人は誰もいなかった。
それから私は姉さまの身代わりとして呪いを受けることが役目になった。
呪いを引き受ける度に、体は痛み、血を吐き、痣は増え続けた。
だが姉さまは微笑んで、痛みに蹲る私を見下ろしながら冷たく微笑むのだ。
「よくできたわ、千草。あなたはやっぱり、私の影なのね」