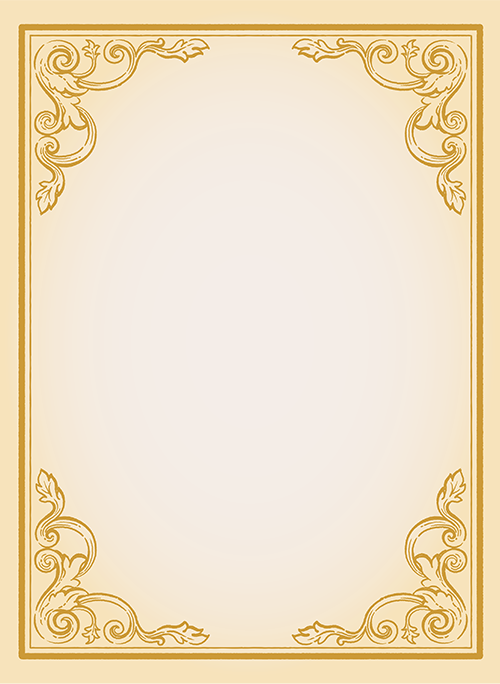「――千草。私のために、死んで頂戴?」
姉さまの声は、いつものように優しく、穏やかで――恐ろしかった。
それでも私は姉さまを見上げて微笑むんだ。
「はい。紫苑姉さまのためなら、喜んで――」
姉さまは光。私はその影だ。
光が清く輝くためには、影が穢れを引き受ける――それが、双子として生まれた私たちの運命だった。
姉さまは呪詛を祓い、都を守る巫女。
私は姉さまの身代わりとして祓った穢れを体に受け、鎮める。
「――ううっ」
呪いを浴びるたびに身体中が焼けるように痛んだ。
血が滲み、身体中に呪いの紋様が浮かび上がる。
「穢らわしい呪いの巫女――」「この女がいなければ紫苑様は完璧な存在だったのに――」
民は私を蔑んだ。
「――ありがとう。私の可愛い千草」
姉さまだけが私を見て微笑んでくれた。
どんなに痛くても、苦しくても、姉さまの役にたてるのが嬉しかったから。
姉さまが微笑んでくれるなら。この命は喜んでくれてやろう。
だから疑問にも思わなかった。
姉さまが私を敵国に嫁がせるといったときも。
「敵国の将・夜神。呪いも術も受け付けぬとされる異端の将よ。私の力では届かない」
姉さまは私の手を握る。
「けれど、貴女なら届くかもしれない。全身に呪紋を刻まれた貴女なら」
「私が……ですか?」
「ええ。これは貴女が表に立って行う最初で最後の大切なお勤め。敵国に嫁ぎ、敵将を殺してらっしゃい」
姉さまはいつもと変わらぬ笑顔で、私に死ねと命じた。
だけど私に断る権利などない。
「はい、姉さま。千草は姉さまのために……生まれてきたのですから」
そうして私は誰にも見送られず、生まれ育った都を離れた。
重々しい空気の中、敵国の使者たちに囲まれ馬車に揺られる。
姉さまのため。これは、私の運命――。
その言葉を、胸の中で何度も繰り返した。
震える手を、真っ黒な無垢袖に包みながら――。
姉さまの声は、いつものように優しく、穏やかで――恐ろしかった。
それでも私は姉さまを見上げて微笑むんだ。
「はい。紫苑姉さまのためなら、喜んで――」
姉さまは光。私はその影だ。
光が清く輝くためには、影が穢れを引き受ける――それが、双子として生まれた私たちの運命だった。
姉さまは呪詛を祓い、都を守る巫女。
私は姉さまの身代わりとして祓った穢れを体に受け、鎮める。
「――ううっ」
呪いを浴びるたびに身体中が焼けるように痛んだ。
血が滲み、身体中に呪いの紋様が浮かび上がる。
「穢らわしい呪いの巫女――」「この女がいなければ紫苑様は完璧な存在だったのに――」
民は私を蔑んだ。
「――ありがとう。私の可愛い千草」
姉さまだけが私を見て微笑んでくれた。
どんなに痛くても、苦しくても、姉さまの役にたてるのが嬉しかったから。
姉さまが微笑んでくれるなら。この命は喜んでくれてやろう。
だから疑問にも思わなかった。
姉さまが私を敵国に嫁がせるといったときも。
「敵国の将・夜神。呪いも術も受け付けぬとされる異端の将よ。私の力では届かない」
姉さまは私の手を握る。
「けれど、貴女なら届くかもしれない。全身に呪紋を刻まれた貴女なら」
「私が……ですか?」
「ええ。これは貴女が表に立って行う最初で最後の大切なお勤め。敵国に嫁ぎ、敵将を殺してらっしゃい」
姉さまはいつもと変わらぬ笑顔で、私に死ねと命じた。
だけど私に断る権利などない。
「はい、姉さま。千草は姉さまのために……生まれてきたのですから」
そうして私は誰にも見送られず、生まれ育った都を離れた。
重々しい空気の中、敵国の使者たちに囲まれ馬車に揺られる。
姉さまのため。これは、私の運命――。
その言葉を、胸の中で何度も繰り返した。
震える手を、真っ黒な無垢袖に包みながら――。