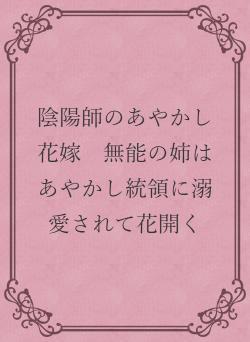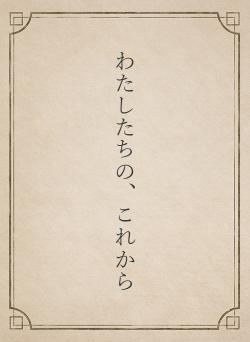日置と別れて家に帰ると、パパがいた。
なんだか偉くてすごい仕事をしているパパは、庭つき犬つき家政婦つきママなしの一軒家にほとんど帰ってこない。
だから、あたしは油断していた。
「響、学校はどうした」
玄関でサンダルを脱いでいると、家の奥からパパが登場した。
薄暗い廊下で、久しぶりに対峙するパパはあまりにも厳しい目をしていた。
「……具合悪いから早退した」
「嘘をつくな」
パパの横を通り過ぎようと思うも、腕をつかまれてしまう。
ぎゅうぎゅうと左腕を圧迫されて、息苦しさを覚える。
暗いところはきらいだ。世界の輪郭がわからなくなる。
「家政婦の今泉さんから報告を受けている。四月からほとんど学校に行ってないと」
「放して」
「いい加減にしなさい。おまえがそんなんだからあいつは出ていったんだ」
パパは家を出ていったママのことをあいつと呼ぶ。家にいたころからあいつと呼んでいた。
あたしはなんでかわからないけど、その呼び方が許せなかった。
「おまえとかあいつって言うな!」
そう叫んでパパを見上げると、一瞬だけパパと目が合った。
どうか世界中のパパとママが血のつながった子どもに向ける目がこんなんじゃありませんように。そんなことを考えた刹那、あたしの頬がカッと熱を持った。
ぶたれたとわかったのは、休むまもなくもう一撃飛んできたからだった。
それからのことは覚えていない。
久しぶりだったから昔のこととごっちゃになって、分厚い辞書で殴られたり、冬の日に庭に締め出されたり、汚い靴で蹴られたり、とにかくいろんなことを思い出した。めちゃくちゃだった。
「おまえはちょっと目を離しているとすぐに『普通』じゃなくなる。どうして普通にふるまえないんだ」
あたしが悪い子だからパパが怒っている。
あたしが変な子だからママはいなくなった。
あたしが電波ちゃんだから友だちができない。
ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。
パパが言う「普通」になりたい。でも、悪い子のあたしは普通になれない。変な子なあたしには普通がわからない。
今泉さんがやってきたことで、パパの手はようやく止まった。
あたしはおろおろする今泉さんを押し倒して、自分の部屋まで駆けた。
――こんなあたし、あたしが一番好きじゃない。
なんだか偉くてすごい仕事をしているパパは、庭つき犬つき家政婦つきママなしの一軒家にほとんど帰ってこない。
だから、あたしは油断していた。
「響、学校はどうした」
玄関でサンダルを脱いでいると、家の奥からパパが登場した。
薄暗い廊下で、久しぶりに対峙するパパはあまりにも厳しい目をしていた。
「……具合悪いから早退した」
「嘘をつくな」
パパの横を通り過ぎようと思うも、腕をつかまれてしまう。
ぎゅうぎゅうと左腕を圧迫されて、息苦しさを覚える。
暗いところはきらいだ。世界の輪郭がわからなくなる。
「家政婦の今泉さんから報告を受けている。四月からほとんど学校に行ってないと」
「放して」
「いい加減にしなさい。おまえがそんなんだからあいつは出ていったんだ」
パパは家を出ていったママのことをあいつと呼ぶ。家にいたころからあいつと呼んでいた。
あたしはなんでかわからないけど、その呼び方が許せなかった。
「おまえとかあいつって言うな!」
そう叫んでパパを見上げると、一瞬だけパパと目が合った。
どうか世界中のパパとママが血のつながった子どもに向ける目がこんなんじゃありませんように。そんなことを考えた刹那、あたしの頬がカッと熱を持った。
ぶたれたとわかったのは、休むまもなくもう一撃飛んできたからだった。
それからのことは覚えていない。
久しぶりだったから昔のこととごっちゃになって、分厚い辞書で殴られたり、冬の日に庭に締め出されたり、汚い靴で蹴られたり、とにかくいろんなことを思い出した。めちゃくちゃだった。
「おまえはちょっと目を離しているとすぐに『普通』じゃなくなる。どうして普通にふるまえないんだ」
あたしが悪い子だからパパが怒っている。
あたしが変な子だからママはいなくなった。
あたしが電波ちゃんだから友だちができない。
ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。
パパが言う「普通」になりたい。でも、悪い子のあたしは普通になれない。変な子なあたしには普通がわからない。
今泉さんがやってきたことで、パパの手はようやく止まった。
あたしはおろおろする今泉さんを押し倒して、自分の部屋まで駆けた。
――こんなあたし、あたしが一番好きじゃない。