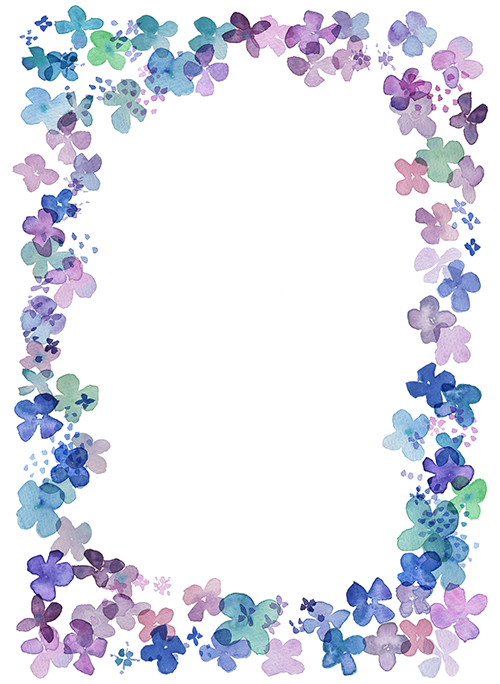創立祭当日の朝、目覚ましのアラームが鳴る前に目が覚めた。
窓からこぼれる朝日が、カーテンの隙間から部屋に差し込んでいる。
時間を確認すると六時三十分だった。いつもなら絶対に起きられない時間だが、今日は違う。
ベッドから起き上がり、伸びをしながら考える。
一ヶ月前の俺だったら、休日の朝からわざわざ学校に行くなんて考えられなかっただろう。
しかし今日は、中等部創立祭の本番。
案内係として八時に集合する約束をしていた。
制服を着て、洗面所で顔を洗う。自分の顔が、少し生き生きとしているように感じた。
「朝から起きてるなんて珍しいね。」
階下に降りると、アカネが朝食の準備をしていた。休日なのに制服を着ている俺を見て、彼女は不思議そうな顔をしている。
「ああ、今日は創立祭だ。」
淡々と答えると、アカネはさらに驚いた表情になった。
「えっ?お兄ちゃんが創立祭に行くの?準備じゃなくて?」
「ああ。」
俺の答えに、アカネはちょっとだけの興味があるようで聞いてきた。
「へぇー、誰と一緒に?」
アカネの目が好奇心で輝いている。
「中等部の後輩だ。」
それ以上は詳しく話したくなかった。一ノ瀬のことをアカネに説明するのは面倒くさそうだったから。
「ふーん、後輩ねぇ。」
アカネは意味ありげな悪い笑みを浮かべたが、それ以上は追及してこなかった。
◇
朝食を素早く済ませ、家を出る。
いつもなら動画を見ながら通学するところだが、今日はスマホに手を伸ばす気にならなかった。
代わりに周囲の景色を眺めながら歩く。
朝の空気は清々しく、道行く人々も休日らしくゆったりとした雰囲気だ。
私立第三学園への道は、この一ヶ月間何度も歩いてきたが、今日は少し違って見える。
学校に近づくと、既に多くの生徒や準備のための車が到着していた。
校門の前には『第三学園中等部創立祭』と書かれた大きな垂れ幕が掲げられている。あれは俺も色塗りを手伝った看板だ。
校内に入ると、準備に忙しい生徒たちの姿が見える。思えば一ヶ月前の俺なら、こんな場所に足を踏み入れることすら考えられなかっただろう。
人が集まる場所、特に活気に満ちたこのような場は、俺にとって最悪の環境だったはずだ。
「先輩!」
声のする方を振り向くと、一ノ瀬が走ってきていた。彼女は中等部の制服に、腕には『実行委員』と書かれた赤い腕章を巻いている。
「おはようございます!来てくれてありがとうございます!」
彼女の笑顔は朝日のように明るかった。
「ああ、約束したからな。」
そう答えると、一ノ瀬はさらに嬉しそうな表情になった。
「先輩のために腕章を用意しておきました!」
彼女は俺に同じ『実行委員』の腕章を手渡してきた。
「これつけるのか?」
「はい!今日は先輩も正式な実行委員ですから!」
少し気恥ずかしい気もしたが、素直に腕章を受け取り、左腕に巻いた。
「似合ってます!」
一ノ瀬が満面の笑みで言う。
「そうか?まあ、どうでもいいけど。」
素っ気なく答えたが、内心では少し照れていた。
「さあ、もうすぐ最終ミーティングが始まります。一緒に行きましょう!」
彼女に導かれるまま、中等部の教室に向かう。他の生徒たちも続々と集まってきていた。
教室に入ると、すでに多くの中等部生がいた。俺が入ってくると、何人かが『綾小路先輩、おはようございます!』と声をかけてきた。
初めは奇妙に思えたこの関係も、この数週間でずいぶん自然なものになってきていた。
一ノ瀬は前に立ち、全体に向けて話し始めた。
「みなさん、おはようございます!いよいよ創立祭本番です。最後に担当と場所の確認をします。」
彼女はリーダーとしての役割をしっかりと果たしている。
指示は明確で、皆も真剣に聞いていた。
「綾小路先輩は私と一緒に休憩所と案内係を担当します。パンフレットの配布と来場者のご案内をお願いします。」
俺に向けられた視線に、少し居心地の悪さを感じる。
しかし、以前のような強い拒絶感はなかった。
ミーティングが終わると、それぞれの持ち場に散っていく。
俺と一ノ瀬は休憩所へと向かった。
「先輩、緊張してますか?」
「別に。」
本当のところ、少し緊張していた。
案内係という役目は、人と話さなければならない。俺の最も苦手とすることだ。
「大丈夫ですよ。先輩は思っているより人と話すのが上手いですから。」
なぜそう言い切れるのか不思議だったが、その彼女の言葉に少し救われた気もした。
休憩所は校庭の一角に設置されていた。
大きなテントの下には机と椅子が並べられ、飲み物や軽食も用意されていた。
入口には案内所を兼ねたカウンターがあり、そこが俺と一ノ瀬の持ち場だ。
「開場は九時からですね。あと三十分ほどです。」
一ノ瀬はパンフレットを整理しながら言った。
「最後の準備をしましょう。先輩、この案内図を見てください。質問されそうな場所はここと、ここと…。」
彼女は丁寧に説明してくれた。校内の配置、各クラスの出し物の場所、トイレや救護室の位置など、細かいところまで教えてくれる。
一ノ瀬の説明は妙に具体的で、まるで何度も創立祭を経験しているかのようだった。
それは俺にとって非常に便利でためになった。
九時になり、校門が開放された。すぐに来場者が入り始める。
主に生徒の家族や近隣の住民たちだろう。
「いらっしゃいませ!第三学園中等部創立祭へようこそ!」
一ノ瀬が元気よく声をかけ、パンフレットを手渡していく。俺も隣で同じように対応するが、彼女ほど自然にはできない。
「こちらがパンフレットです。」
ぎこちない笑顔で渡すが、相手は特に気にしていない様子で、お礼をいって受け取ってくれた。
「先輩、頑張ってますね!」
一ノ瀬が小声で励ましてくれた。
徐々に人の流れが増えてくる。校門からは続々と来場者が入ってきて、休憩所の前はかなりの人で賑わうようになった。
「トイレはどこですか?」
「三年二組の出し物は何ですか?」
「食事できる場所はありますか?」
様々な質問が飛んでくる。
正直、なんて答えればいいのか分からない。
その都度、適切に一ノ瀬がフォローしてくれたおかげで、少しずつ対応できるようになってきた。
「先輩、私が出てくる前に自分で答えられましたね!」
一ノ瀬がそう言うと、確かに俺も少しずつ慣れてきたことを実感した。
「まあな。」
淡々と答えるが、少し慣れてきていたことに気が付いていた。
時間が経つにつれて、俺も次第に案内の仕方が板についてきた。
パンフレットを渡す時の言葉、質問への応対、道案内の仕方。すべてがスムーズになってきた。
「俺、こんなことできるんだな。」
自分でも驚くような言葉が口から漏れた。
「先輩は人と話すのが上手いんですよ。ただ、避けていただけです。」
一ノ瀬のその言葉に、何か心に響くものがあった。確かに俺は人との関わりを避けてきた。
『効率的』という言葉の下に、すべての人間関係を切り捨ててきた。
確かにそれは最短だった。ある意味では。
俺は今起こっていることを見ながら、つい最近までの自分と比較していた。
その時だった。
喧騒の中から聞き覚えのある声が聞こえてきた。
「え?お兄ちゃん?まさか…。」
振り返ると、そこには制服姿のアカネが立っていた。
隣には同じ制服を着た女友達。どうやら創立祭に来ているらしい。
「なんだ、本当にお兄ちゃんじゃない!」
アカネは驚いたような、からかうような表情で俺を見る。そして隣にいる一ノ瀬にも視線を移した。
「えっ?案内係やってるし…。」
アカネの友達が小さく呟いた。
「ねえねえ、まさか本当に創立祭の手伝いしてたの?朝の話、嘘だと思ってたよ。」
アカネは俺から一ノ瀬に視線を移し、にやりと笑った。
「もしかして…この子が『中等部の後輩』?」
アカネの言い方には、明らかな含みがあった。
小さな声ではなかったので、一ノ瀬にも十分聞こえていたはずだ。
「あ、はじめまして。一ノ瀬ナズナです。」
一ノ瀬は丁寧に頭を下げた。
「私はアカネ、このダメ人間の妹。こっちは友達。」
アカネはそう言って、友達を紹介した。
「アカネ、お前こそ何をしてるんだ?」
なるべく平静を装って尋ねる。
「え?中等部の創立祭だよ?私たちが主役じゃん。いるのは当然でしょ?それより、お兄ちゃんが案内係なんて…。誰と目が合っても無視してるお兄ちゃんが?」
アカネはジト目で見てきた。
「アカネのお兄さん、家ではそんなに無口なの?」
アカネの友達が興味深そうに聞いてきた。
「そうなの!朝食も黙々と食べるだけで、私が話しかけても『無駄だ』って一言だけなんだよ。」
アカネの物真似に、友達は笑い始めた。一ノ瀬もつられて微笑む。
「やめろよ、お前ら。」
少し恥ずかしさを感じながら言った。
「そうだ、一ノ瀬ちゃん。お兄ちゃんのこと、どう思う?やっぱり無口?無愛想?」
アカネが一ノ瀬に尋ねる。
「いえ、そんなことないですよ。先輩はとても頼りになって…ただ、少し話すのが苦手なだけで。」
一ノ瀬の優しい擁護に、アカネは一瞬驚いたような顔をした。
「へぇ~。あのね、お兄ちゃんって昔はもっと活発だったんだよ。まあ、昔はね。」
アカネが急に昔の話を始めた。
「ああ、そうなんですね!私、もっと聞きたいです!」
一ノ瀬が興味深そうに聞き返す。
「もういいだろ。」
俺が制止しようとしたが、アカネは止まらなかった。
「いいですか、一ノ瀬さん?この人はね、中学時代に…。」
「おい、もうやめろ!」
尚も話を続けようとするアカネを俺は強制的に黙らせた。
アカネはどこか悪戯っぽい笑みを浮かべた。
「一ノ瀬ちゃん、お兄ちゃんのこと、よろしくね!」
唐突な言葉に、一ノ瀬は少し赤面した。
「はい、もちろんです!」
一ノ瀬の真摯な返事に、アカネと友達は顔を見合わせて笑った。
「じゃあね、お兄ちゃん。」
アカネはそう言って、さっさと友達と共に人ごみの中に消えていった。
俺はため息をついた。
妹にからかわれるのは想定外だった。
そんな想定外のこともあり、午前中の時間はあっという間に過ぎ去っていった。
そして、正午になり、交代要員が来た。
「先輩、お疲れ様です。お昼休憩にしましょう!」
一ノ瀬が俺の腕を引っ張る。
「ああ、そうだな。」
休憩所の役目を引き継ぎ、俺たちは人ごみの中を歩き始めた。
「先輩?お昼は何を食べましょうか?」
「何でもいいぞ。」
「そうですか?では、うちのクラスの出し物、見てみませんか?」
一ノ瀬は俺を校舎の中へと導いた。
廊下は来場者で賑わっていて、各教室では様々な出し物が行われていた。
一ノ瀬のクラスは『和風カフェ』もやっていた。
高等部なのに、通い詰めた一ノ瀬のいる教室は和風の装飾で彩られ、畳風のマットを敷いた小さなスペースがいくつか作られている。
生徒たちが慌ただしく接客していた。
「お久しぶりです、一ノ瀬さん!」
クラスメイトが声をかけてくる。
「こちらが噂の綾小路先輩ですか?」
その子は俺を見て笑顔を向けた。
「はい、いつもお世話になっています。」
一ノ瀬が紹介してくれる。
「よろしく。」
短く挨拶すると、一ノ瀬の友人は少し驚いたような表情をした後、笑顔で応じてくれた。
「どうぞこちらへ。特別席をご用意していますよ。」
その子に導かれて、窓際の小さなスペースに案内された。そこは来場者の目が届きにくい場所で、静かに食事ができそうだった。
「注文は?」
聞かれたので、俺は迷った。
「おすすめは?」
困窮した俺の一手。
それについて、一ノ瀬の友人は嬉しそうに説明してくれた。
「抹茶パフェと和風サンドイッチのセットが人気です!」
「じゃあ、それを。」
俺はおすすめ通りにした。
「じゃあ、私も先輩と同じのを!」
元気よく、一ノ瀬が注文した。
「分かりました。」
一ノ瀬の友人は、注文を終えると、料理を取りに戻っていった。
「先輩、楽しみですね!」
一ノ瀬が嬉しそうに言う。
「そうか?でも、お前、自分のクラスの出し物知ってるだろ?」
「ええ!もちろんです!」
俺は盛大に脱力した。
知っていて、俺に合わせているのか。
なんというか、人に合わせるという、なんとも非効率的な…。
そう思った。
ただ、そもそも一ヶ月前なら、こんな創立祭に来ることすら『非効率』と切り捨てていたはずだ。
俺はもはや戻ることがない改造を受けていた。
目の前の後輩から。
「ん?なんですか、先輩?」
「いや…。」
俺があいまいに答えると、一ノ瀬はにんまりを笑った。
「えへへ。まるで恋人みたいですね。」
そう小さい声で彼女は囁いた。
「ああ、そうかい。」
俺は淡々と返事をした。
「ああっ、もう先輩は素直じゃないですねー。」
目の前の彼女は人の目も気にせず、騒いでいた。
そんなことをしていると、料理が運ばれてきた。
抹茶パフェはきれいな緑色で、和風サンドイッチは具材が彩り豊かだった。
「あっ!先輩、パフェ、来ましたよ!」
「ああ。」
俺と後輩の前に抹茶パフェと和風サンドイッチが置かれた。
「いただきます。」
「…いただきます。」
一口食べると、予想以上においしかった。
「うまいな、これ。」
「本当ですか?よかったです!」
自分が準備をしたわけでもないのに、一ノ瀬は嬉しそうに微笑んだ。
俺はそんな楽しそうに燥いでいる一ノ瀬をじっと見た。
「ん?何ですか?先輩?」
「ああ。いや…。」
俺は適当に答えた。
「ああ、大丈夫です。私は先輩のことには詳しいので。」
「はぁ。」
目の前の後輩は嘘ではないことをいう。
おいおい…、恐ろしい事をサラッと言うな、こいつ。
そんな会話を続けながら、俺と一ノ瀬は食事を終えた。
「頑張ってね!私は先輩と創立祭を回ってきます。」
そして、店を出る前に一ノ瀬がクラスメイトたちに声をかけた。
「いいなぁ!」
一ノ瀬の友人が笑顔で送り出してくれた。
廊下に出ると、さらに人が増えていた。
来場者で賑わう校内を、一ノ瀬と並んで歩く。
「先輩、何か見たいものありますか?」
「特に。お前が行きたいところでいいよ。」
そう答えると、一ノ瀬は嬉しそうな表情になった。
「じゃあ、いろいろ回りましょう!まずは…。こっちです!」
一ノ瀬に引っ張られながら、俺は廊下を進んでいった。
そして、一ノ瀬に最初に連れてこられたのは、いわいる『お化け屋敷』だった。
真っ黒な遮光カーテンで覆われた教室の入口には長い列ができていた。
「先輩、怖いの平気ですか?」
「別に。」
そう答えたが、実は少し苦手だった。
ただ、所詮は中学生が作るものだ。
俺はなんとかなるだろう、と思った。
「じゃあ、先輩は先に入ってください!」
「ああ。」
俺は後輩に言われるがままにお化け屋敷に入っていくことになった。
教室の中に入ると、予想以上に本格的な作りだった。
暗闇な教室。そこには蛍光塗料で描かれた幽霊や妖怪の絵が浮かび上がり、所々に仕掛けが施されている。
パーテイションで区切られた狭い通路は迷路のように曲がりくねり、どこから何が飛び出すか分からない緊張感があった。
突然、何かが背後から俺の肩に触れた。冷たく細い指が首筋を這うような感触。
「うわっ!」
思わず声が出た。
振り返ると、一ノ瀬が立っていた。
彼女は悪戯っぽい笑みを浮かべている。
「ふふふ…先輩、驚いたんですね。」
一ノ瀬がくすくす笑っている。彼女は暗闇の中、音もなく後ろから俺に触れてきたのだ!
「別に、ちょっとびっくりしただけだ。」
取り繕ったが、明らかに動揺していた。
一ノ瀬はさらに楽しむように、俺の周りをふわふわと動き回り、驚かせてきた。
正直、お化け屋敷の仕掛けより、彼女のいたずらの方に驚いてしまった。
「先輩、顔真っ青ですよ。本当に大丈夫ですか?」
彼女は心配するふりをしながらも、その目は明らかに楽しんでいた。
「言ったろ、平気だって。」
俺は咄嗟に彼女の手を掴んだ。
それ以上のいたずらを防ぐためだったが、一ノ瀬は逆に嬉しそうに俺の手に自分の指を絡めてきた。
「じゃあ、一緒に行きましょうよ!」
そう言いながら、彼女は明らかに楽しんでいた。
お化け屋敷を出ると、次は『射的ゲーム』の教室へと連れていかれた。
ここでは小さな的を狙って景品を獲得するゲームをやっていた。
「先輩、やってください!」
「俺が?」
「はい!私、あの景品が欲しいんですよ!」
彼女が指さしたのは、小さなぬいぐるみだった。
「まあ、いいけどさ。」
受付で代金を払い、コルク銃を受け取る。
三発で百円だった。
最初の一発は見事に外れた。
「もう少し左ですね。」
一ノ瀬がアドバイスをくれる。
二発目も外れたが、三発目でようやく的に当たった。
しかし、景品をもらえるほどの得点ではなかった。
「もう一回やるか?」
思わずそう言っている自分がいることに驚いてしまった。
「お願いします!」
その一ノ瀬の期待に満ちた表情に、もはや言葉を取り消すことが出来なかった。
そして、二回目のチャレンジ。
今度は慎重に狙い、一発目から命中した。
「すごい!先輩、上手いですね!」
彼女の称賛に、少し照れくさくなる。
結局、三発全部当て、目当ての景品を獲得することができた。
「ありがとうございます!大切にします!」
一ノ瀬はぬいぐるみを大事そうに抱きしめた。
その後も様々な出し物を見て回った。
写真展、手作り雑貨の販売、ゲームコーナー、よく分からない前衛芸術のようなものを出している模擬店など、どれも生徒たちの創意工夫が感じられるものだった。
そう、こんな気分になるのは久しぶりだった。
半ば後輩の手によって強引に参加させられているという点を差し引いたとしても。
この感覚は久しぶりだったような気がした。
窓からこぼれる朝日が、カーテンの隙間から部屋に差し込んでいる。
時間を確認すると六時三十分だった。いつもなら絶対に起きられない時間だが、今日は違う。
ベッドから起き上がり、伸びをしながら考える。
一ヶ月前の俺だったら、休日の朝からわざわざ学校に行くなんて考えられなかっただろう。
しかし今日は、中等部創立祭の本番。
案内係として八時に集合する約束をしていた。
制服を着て、洗面所で顔を洗う。自分の顔が、少し生き生きとしているように感じた。
「朝から起きてるなんて珍しいね。」
階下に降りると、アカネが朝食の準備をしていた。休日なのに制服を着ている俺を見て、彼女は不思議そうな顔をしている。
「ああ、今日は創立祭だ。」
淡々と答えると、アカネはさらに驚いた表情になった。
「えっ?お兄ちゃんが創立祭に行くの?準備じゃなくて?」
「ああ。」
俺の答えに、アカネはちょっとだけの興味があるようで聞いてきた。
「へぇー、誰と一緒に?」
アカネの目が好奇心で輝いている。
「中等部の後輩だ。」
それ以上は詳しく話したくなかった。一ノ瀬のことをアカネに説明するのは面倒くさそうだったから。
「ふーん、後輩ねぇ。」
アカネは意味ありげな悪い笑みを浮かべたが、それ以上は追及してこなかった。
◇
朝食を素早く済ませ、家を出る。
いつもなら動画を見ながら通学するところだが、今日はスマホに手を伸ばす気にならなかった。
代わりに周囲の景色を眺めながら歩く。
朝の空気は清々しく、道行く人々も休日らしくゆったりとした雰囲気だ。
私立第三学園への道は、この一ヶ月間何度も歩いてきたが、今日は少し違って見える。
学校に近づくと、既に多くの生徒や準備のための車が到着していた。
校門の前には『第三学園中等部創立祭』と書かれた大きな垂れ幕が掲げられている。あれは俺も色塗りを手伝った看板だ。
校内に入ると、準備に忙しい生徒たちの姿が見える。思えば一ヶ月前の俺なら、こんな場所に足を踏み入れることすら考えられなかっただろう。
人が集まる場所、特に活気に満ちたこのような場は、俺にとって最悪の環境だったはずだ。
「先輩!」
声のする方を振り向くと、一ノ瀬が走ってきていた。彼女は中等部の制服に、腕には『実行委員』と書かれた赤い腕章を巻いている。
「おはようございます!来てくれてありがとうございます!」
彼女の笑顔は朝日のように明るかった。
「ああ、約束したからな。」
そう答えると、一ノ瀬はさらに嬉しそうな表情になった。
「先輩のために腕章を用意しておきました!」
彼女は俺に同じ『実行委員』の腕章を手渡してきた。
「これつけるのか?」
「はい!今日は先輩も正式な実行委員ですから!」
少し気恥ずかしい気もしたが、素直に腕章を受け取り、左腕に巻いた。
「似合ってます!」
一ノ瀬が満面の笑みで言う。
「そうか?まあ、どうでもいいけど。」
素っ気なく答えたが、内心では少し照れていた。
「さあ、もうすぐ最終ミーティングが始まります。一緒に行きましょう!」
彼女に導かれるまま、中等部の教室に向かう。他の生徒たちも続々と集まってきていた。
教室に入ると、すでに多くの中等部生がいた。俺が入ってくると、何人かが『綾小路先輩、おはようございます!』と声をかけてきた。
初めは奇妙に思えたこの関係も、この数週間でずいぶん自然なものになってきていた。
一ノ瀬は前に立ち、全体に向けて話し始めた。
「みなさん、おはようございます!いよいよ創立祭本番です。最後に担当と場所の確認をします。」
彼女はリーダーとしての役割をしっかりと果たしている。
指示は明確で、皆も真剣に聞いていた。
「綾小路先輩は私と一緒に休憩所と案内係を担当します。パンフレットの配布と来場者のご案内をお願いします。」
俺に向けられた視線に、少し居心地の悪さを感じる。
しかし、以前のような強い拒絶感はなかった。
ミーティングが終わると、それぞれの持ち場に散っていく。
俺と一ノ瀬は休憩所へと向かった。
「先輩、緊張してますか?」
「別に。」
本当のところ、少し緊張していた。
案内係という役目は、人と話さなければならない。俺の最も苦手とすることだ。
「大丈夫ですよ。先輩は思っているより人と話すのが上手いですから。」
なぜそう言い切れるのか不思議だったが、その彼女の言葉に少し救われた気もした。
休憩所は校庭の一角に設置されていた。
大きなテントの下には机と椅子が並べられ、飲み物や軽食も用意されていた。
入口には案内所を兼ねたカウンターがあり、そこが俺と一ノ瀬の持ち場だ。
「開場は九時からですね。あと三十分ほどです。」
一ノ瀬はパンフレットを整理しながら言った。
「最後の準備をしましょう。先輩、この案内図を見てください。質問されそうな場所はここと、ここと…。」
彼女は丁寧に説明してくれた。校内の配置、各クラスの出し物の場所、トイレや救護室の位置など、細かいところまで教えてくれる。
一ノ瀬の説明は妙に具体的で、まるで何度も創立祭を経験しているかのようだった。
それは俺にとって非常に便利でためになった。
九時になり、校門が開放された。すぐに来場者が入り始める。
主に生徒の家族や近隣の住民たちだろう。
「いらっしゃいませ!第三学園中等部創立祭へようこそ!」
一ノ瀬が元気よく声をかけ、パンフレットを手渡していく。俺も隣で同じように対応するが、彼女ほど自然にはできない。
「こちらがパンフレットです。」
ぎこちない笑顔で渡すが、相手は特に気にしていない様子で、お礼をいって受け取ってくれた。
「先輩、頑張ってますね!」
一ノ瀬が小声で励ましてくれた。
徐々に人の流れが増えてくる。校門からは続々と来場者が入ってきて、休憩所の前はかなりの人で賑わうようになった。
「トイレはどこですか?」
「三年二組の出し物は何ですか?」
「食事できる場所はありますか?」
様々な質問が飛んでくる。
正直、なんて答えればいいのか分からない。
その都度、適切に一ノ瀬がフォローしてくれたおかげで、少しずつ対応できるようになってきた。
「先輩、私が出てくる前に自分で答えられましたね!」
一ノ瀬がそう言うと、確かに俺も少しずつ慣れてきたことを実感した。
「まあな。」
淡々と答えるが、少し慣れてきていたことに気が付いていた。
時間が経つにつれて、俺も次第に案内の仕方が板についてきた。
パンフレットを渡す時の言葉、質問への応対、道案内の仕方。すべてがスムーズになってきた。
「俺、こんなことできるんだな。」
自分でも驚くような言葉が口から漏れた。
「先輩は人と話すのが上手いんですよ。ただ、避けていただけです。」
一ノ瀬のその言葉に、何か心に響くものがあった。確かに俺は人との関わりを避けてきた。
『効率的』という言葉の下に、すべての人間関係を切り捨ててきた。
確かにそれは最短だった。ある意味では。
俺は今起こっていることを見ながら、つい最近までの自分と比較していた。
その時だった。
喧騒の中から聞き覚えのある声が聞こえてきた。
「え?お兄ちゃん?まさか…。」
振り返ると、そこには制服姿のアカネが立っていた。
隣には同じ制服を着た女友達。どうやら創立祭に来ているらしい。
「なんだ、本当にお兄ちゃんじゃない!」
アカネは驚いたような、からかうような表情で俺を見る。そして隣にいる一ノ瀬にも視線を移した。
「えっ?案内係やってるし…。」
アカネの友達が小さく呟いた。
「ねえねえ、まさか本当に創立祭の手伝いしてたの?朝の話、嘘だと思ってたよ。」
アカネは俺から一ノ瀬に視線を移し、にやりと笑った。
「もしかして…この子が『中等部の後輩』?」
アカネの言い方には、明らかな含みがあった。
小さな声ではなかったので、一ノ瀬にも十分聞こえていたはずだ。
「あ、はじめまして。一ノ瀬ナズナです。」
一ノ瀬は丁寧に頭を下げた。
「私はアカネ、このダメ人間の妹。こっちは友達。」
アカネはそう言って、友達を紹介した。
「アカネ、お前こそ何をしてるんだ?」
なるべく平静を装って尋ねる。
「え?中等部の創立祭だよ?私たちが主役じゃん。いるのは当然でしょ?それより、お兄ちゃんが案内係なんて…。誰と目が合っても無視してるお兄ちゃんが?」
アカネはジト目で見てきた。
「アカネのお兄さん、家ではそんなに無口なの?」
アカネの友達が興味深そうに聞いてきた。
「そうなの!朝食も黙々と食べるだけで、私が話しかけても『無駄だ』って一言だけなんだよ。」
アカネの物真似に、友達は笑い始めた。一ノ瀬もつられて微笑む。
「やめろよ、お前ら。」
少し恥ずかしさを感じながら言った。
「そうだ、一ノ瀬ちゃん。お兄ちゃんのこと、どう思う?やっぱり無口?無愛想?」
アカネが一ノ瀬に尋ねる。
「いえ、そんなことないですよ。先輩はとても頼りになって…ただ、少し話すのが苦手なだけで。」
一ノ瀬の優しい擁護に、アカネは一瞬驚いたような顔をした。
「へぇ~。あのね、お兄ちゃんって昔はもっと活発だったんだよ。まあ、昔はね。」
アカネが急に昔の話を始めた。
「ああ、そうなんですね!私、もっと聞きたいです!」
一ノ瀬が興味深そうに聞き返す。
「もういいだろ。」
俺が制止しようとしたが、アカネは止まらなかった。
「いいですか、一ノ瀬さん?この人はね、中学時代に…。」
「おい、もうやめろ!」
尚も話を続けようとするアカネを俺は強制的に黙らせた。
アカネはどこか悪戯っぽい笑みを浮かべた。
「一ノ瀬ちゃん、お兄ちゃんのこと、よろしくね!」
唐突な言葉に、一ノ瀬は少し赤面した。
「はい、もちろんです!」
一ノ瀬の真摯な返事に、アカネと友達は顔を見合わせて笑った。
「じゃあね、お兄ちゃん。」
アカネはそう言って、さっさと友達と共に人ごみの中に消えていった。
俺はため息をついた。
妹にからかわれるのは想定外だった。
そんな想定外のこともあり、午前中の時間はあっという間に過ぎ去っていった。
そして、正午になり、交代要員が来た。
「先輩、お疲れ様です。お昼休憩にしましょう!」
一ノ瀬が俺の腕を引っ張る。
「ああ、そうだな。」
休憩所の役目を引き継ぎ、俺たちは人ごみの中を歩き始めた。
「先輩?お昼は何を食べましょうか?」
「何でもいいぞ。」
「そうですか?では、うちのクラスの出し物、見てみませんか?」
一ノ瀬は俺を校舎の中へと導いた。
廊下は来場者で賑わっていて、各教室では様々な出し物が行われていた。
一ノ瀬のクラスは『和風カフェ』もやっていた。
高等部なのに、通い詰めた一ノ瀬のいる教室は和風の装飾で彩られ、畳風のマットを敷いた小さなスペースがいくつか作られている。
生徒たちが慌ただしく接客していた。
「お久しぶりです、一ノ瀬さん!」
クラスメイトが声をかけてくる。
「こちらが噂の綾小路先輩ですか?」
その子は俺を見て笑顔を向けた。
「はい、いつもお世話になっています。」
一ノ瀬が紹介してくれる。
「よろしく。」
短く挨拶すると、一ノ瀬の友人は少し驚いたような表情をした後、笑顔で応じてくれた。
「どうぞこちらへ。特別席をご用意していますよ。」
その子に導かれて、窓際の小さなスペースに案内された。そこは来場者の目が届きにくい場所で、静かに食事ができそうだった。
「注文は?」
聞かれたので、俺は迷った。
「おすすめは?」
困窮した俺の一手。
それについて、一ノ瀬の友人は嬉しそうに説明してくれた。
「抹茶パフェと和風サンドイッチのセットが人気です!」
「じゃあ、それを。」
俺はおすすめ通りにした。
「じゃあ、私も先輩と同じのを!」
元気よく、一ノ瀬が注文した。
「分かりました。」
一ノ瀬の友人は、注文を終えると、料理を取りに戻っていった。
「先輩、楽しみですね!」
一ノ瀬が嬉しそうに言う。
「そうか?でも、お前、自分のクラスの出し物知ってるだろ?」
「ええ!もちろんです!」
俺は盛大に脱力した。
知っていて、俺に合わせているのか。
なんというか、人に合わせるという、なんとも非効率的な…。
そう思った。
ただ、そもそも一ヶ月前なら、こんな創立祭に来ることすら『非効率』と切り捨てていたはずだ。
俺はもはや戻ることがない改造を受けていた。
目の前の後輩から。
「ん?なんですか、先輩?」
「いや…。」
俺があいまいに答えると、一ノ瀬はにんまりを笑った。
「えへへ。まるで恋人みたいですね。」
そう小さい声で彼女は囁いた。
「ああ、そうかい。」
俺は淡々と返事をした。
「ああっ、もう先輩は素直じゃないですねー。」
目の前の彼女は人の目も気にせず、騒いでいた。
そんなことをしていると、料理が運ばれてきた。
抹茶パフェはきれいな緑色で、和風サンドイッチは具材が彩り豊かだった。
「あっ!先輩、パフェ、来ましたよ!」
「ああ。」
俺と後輩の前に抹茶パフェと和風サンドイッチが置かれた。
「いただきます。」
「…いただきます。」
一口食べると、予想以上においしかった。
「うまいな、これ。」
「本当ですか?よかったです!」
自分が準備をしたわけでもないのに、一ノ瀬は嬉しそうに微笑んだ。
俺はそんな楽しそうに燥いでいる一ノ瀬をじっと見た。
「ん?何ですか?先輩?」
「ああ。いや…。」
俺は適当に答えた。
「ああ、大丈夫です。私は先輩のことには詳しいので。」
「はぁ。」
目の前の後輩は嘘ではないことをいう。
おいおい…、恐ろしい事をサラッと言うな、こいつ。
そんな会話を続けながら、俺と一ノ瀬は食事を終えた。
「頑張ってね!私は先輩と創立祭を回ってきます。」
そして、店を出る前に一ノ瀬がクラスメイトたちに声をかけた。
「いいなぁ!」
一ノ瀬の友人が笑顔で送り出してくれた。
廊下に出ると、さらに人が増えていた。
来場者で賑わう校内を、一ノ瀬と並んで歩く。
「先輩、何か見たいものありますか?」
「特に。お前が行きたいところでいいよ。」
そう答えると、一ノ瀬は嬉しそうな表情になった。
「じゃあ、いろいろ回りましょう!まずは…。こっちです!」
一ノ瀬に引っ張られながら、俺は廊下を進んでいった。
そして、一ノ瀬に最初に連れてこられたのは、いわいる『お化け屋敷』だった。
真っ黒な遮光カーテンで覆われた教室の入口には長い列ができていた。
「先輩、怖いの平気ですか?」
「別に。」
そう答えたが、実は少し苦手だった。
ただ、所詮は中学生が作るものだ。
俺はなんとかなるだろう、と思った。
「じゃあ、先輩は先に入ってください!」
「ああ。」
俺は後輩に言われるがままにお化け屋敷に入っていくことになった。
教室の中に入ると、予想以上に本格的な作りだった。
暗闇な教室。そこには蛍光塗料で描かれた幽霊や妖怪の絵が浮かび上がり、所々に仕掛けが施されている。
パーテイションで区切られた狭い通路は迷路のように曲がりくねり、どこから何が飛び出すか分からない緊張感があった。
突然、何かが背後から俺の肩に触れた。冷たく細い指が首筋を這うような感触。
「うわっ!」
思わず声が出た。
振り返ると、一ノ瀬が立っていた。
彼女は悪戯っぽい笑みを浮かべている。
「ふふふ…先輩、驚いたんですね。」
一ノ瀬がくすくす笑っている。彼女は暗闇の中、音もなく後ろから俺に触れてきたのだ!
「別に、ちょっとびっくりしただけだ。」
取り繕ったが、明らかに動揺していた。
一ノ瀬はさらに楽しむように、俺の周りをふわふわと動き回り、驚かせてきた。
正直、お化け屋敷の仕掛けより、彼女のいたずらの方に驚いてしまった。
「先輩、顔真っ青ですよ。本当に大丈夫ですか?」
彼女は心配するふりをしながらも、その目は明らかに楽しんでいた。
「言ったろ、平気だって。」
俺は咄嗟に彼女の手を掴んだ。
それ以上のいたずらを防ぐためだったが、一ノ瀬は逆に嬉しそうに俺の手に自分の指を絡めてきた。
「じゃあ、一緒に行きましょうよ!」
そう言いながら、彼女は明らかに楽しんでいた。
お化け屋敷を出ると、次は『射的ゲーム』の教室へと連れていかれた。
ここでは小さな的を狙って景品を獲得するゲームをやっていた。
「先輩、やってください!」
「俺が?」
「はい!私、あの景品が欲しいんですよ!」
彼女が指さしたのは、小さなぬいぐるみだった。
「まあ、いいけどさ。」
受付で代金を払い、コルク銃を受け取る。
三発で百円だった。
最初の一発は見事に外れた。
「もう少し左ですね。」
一ノ瀬がアドバイスをくれる。
二発目も外れたが、三発目でようやく的に当たった。
しかし、景品をもらえるほどの得点ではなかった。
「もう一回やるか?」
思わずそう言っている自分がいることに驚いてしまった。
「お願いします!」
その一ノ瀬の期待に満ちた表情に、もはや言葉を取り消すことが出来なかった。
そして、二回目のチャレンジ。
今度は慎重に狙い、一発目から命中した。
「すごい!先輩、上手いですね!」
彼女の称賛に、少し照れくさくなる。
結局、三発全部当て、目当ての景品を獲得することができた。
「ありがとうございます!大切にします!」
一ノ瀬はぬいぐるみを大事そうに抱きしめた。
その後も様々な出し物を見て回った。
写真展、手作り雑貨の販売、ゲームコーナー、よく分からない前衛芸術のようなものを出している模擬店など、どれも生徒たちの創意工夫が感じられるものだった。
そう、こんな気分になるのは久しぶりだった。
半ば後輩の手によって強引に参加させられているという点を差し引いたとしても。
この感覚は久しぶりだったような気がした。