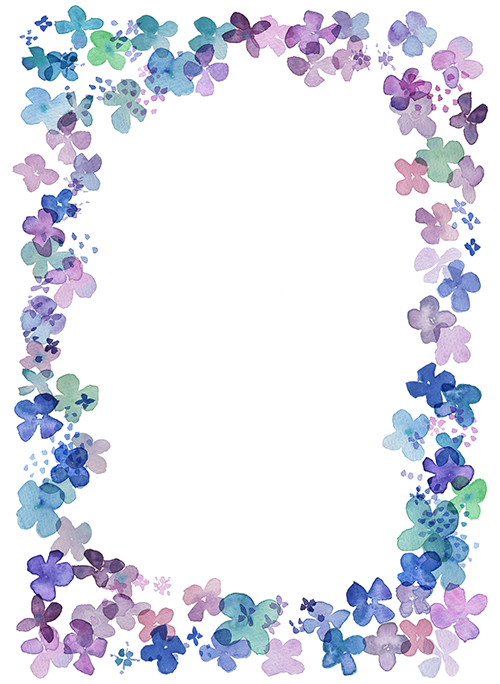創立祭まであと二日となった金曜日の放課後、俺は習慣のように中等部の教室へと向かっていた。
最終確認の日だったからか、教室は例になく活気に溢れていた。
「先輩!」
一ノ瀬が駆け寄ってきた。彼女の手には大きなクリップボードが握られていた。
「待たせたな。」
そう答えると、一ノ瀬は嬉しそうに微笑んだ。
「今日は全体の最終確認です。休憩所も屋台も全て揃えて、動線をチェックします。」
「分かった。」
最終確認のために、俺と一ノ瀬は校内の各所を回ることになった。
各クラスの出し物や屋台、展示などをチェックしていく。
校内を歩きながら、一ノ瀬は学校の色々な場所について詳しく説明してくれた。
「この中庭の桜の木、春には綺麗なんですよ。クラス写真もここで撮るんです。」
「あの噴水は、創立者の寄贈品なんだそうです。五十年以上前からあるんですよ。」
彼女の説明は、まるで長年この学校にいるかのように詳細だった。
「一ノ瀬、詳しいな?」
素直な疑問を口にすると、彼女は少し考えるような素振りを見せた。
「まあ、中学三年生ですから。」
「ああ、そうか。」
納得のいく説明ではあったが、何か引っかかる部分があった。
まあ、それは今に始まったことではない。
しかし、すべてのことは何か一つの出来事から始まっている、と俺には感じられた。
そう、人は矛盾した嘘をつくと違和感だらけに感じる。
しかし、一ノ瀬の話には、そういったものがないように思えた。
…俺が騙されている?
そうなのかもしれない。
そう、俺は騙されているのだ。
騙されて『効率的』な生活から離れて…。
これで思考を止めた俺は、隣にいた一ノ瀬を見た。
彼女は俺を見てきた。
「ん?何ですか?先輩?」
そんな一ノ瀬の様子に俺は苦笑いを浮かべた。
◇
校内の巡回を終え、空き教室で二人きりになった時、一ノ瀬が突然言った。
「先輩は本当は何が好きなんですか?」
「何が好きって?」
「趣味とか、興味のあることとか。」
考えてみると、『動画を見る』こと以外に何も思いつかなかった。かつては読書が好きだったが、それも遠い過去のことのように感じられた。
「特にない。」
答えながらも、何か寂しさを感じた。
「中学時代は、SF小説が好きだったって言ってましたよね?」
「ああ。」
俺は反射的に答えた。
「もし、先輩が過去に戻れるとしたら、何をしますか?」
唐突な質問だった。
「さぁな。」
「もしですよ?」
彼女はどこか遠くを見つめながら話し始めた。
「私が戻れたとしたら、絶対、悔いのないようにしたいです。」
「たとえば?」
「それは…。」
後輩は目をつぶった。
「それは秘密です。」
「なんだ、それ。」
またいつものように彼女は俺の質問に答えなかった。
彼女は何かをしんみりと感じている。
なんだろう、俺はそれに合わせていた。
しばらく、沈黙が周囲を支配した。
「先輩。」
そんな後、一ノ瀬は突然明るい声で言った。
「先輩は将来の夢とかあるんですか?雨の日に資料室で見てた動画みたいに、色々なものに興味があるんですよね?」
唐突な質問に、考え込んだ。将来の夢。
かつては考えたこともあったが、その意味も無意味さも俺は知っていた。
「特にない。大学に行って、普通に就職するんじゃないか。」
「まあ、そうですね。それは普通の人生ですね。」
「そうだろ?」
「そうですね、先輩らしいですね。」
しみじみと彼女はポツリとそれだけ漏らした。
◇
創立祭前日の朝、目覚ましのアラームが鳴る前に目を覚ました。
窓から差し込む朝日に照らされた部屋を見回し、今日が特別な日だということを思い出す。
いつもなら五回のスヌーズを使い果たしてようやく起きる俺だが、今日は違った。体が勝手に動き、準備を始めていた。
朝食の席で、アカネが不思議そうに俺を見つめていた。
「お兄ちゃん、今日も学校?創立祭の準備?」
「ああ。」
「なんか変わったよね。前だったら土曜なんて絶対に引きこもってたのに。」
アカネの言葉に、俺も自分の変化を実感していた。
確かに以前の俺なら、休日に学校なんて考えられなかっただろう。
「人は変わるんだよ。」
自分でも意外な発言に、アカネは驚いたようだった。
「何?お兄ちゃん、誰かに騙されているの?」
それはどこか皮肉や揶揄を含めた口調だった。
「馬鹿言うな。行ってくる。」
俺は相手にせずにそれだけいって、家から出た。
家の玄関を出た、俺は考えた。
本当に自分は変わったのだろうか?と。
一月前の俺であれば、今の状況は考えられないほど『非効率的』だ。
土曜の朝から学校に行き、創立祭の準備をし、人と関わる。無駄な時間の使い方の極みだ。
だが今の俺は、それを苦痛と感じていない。
この変化は一体何なのか。そして、それを引き起こしたのは一ノ瀬ナズナという後輩だった。
謎の後輩。
彼女はどうして、俺にことを知っている?
どうして、俺に近づいている?
どうして、俺と一緒にいるんだ?
明日の花火の後、全ての謎が解けるという。
真相は驚くべきことかもしれない。
悲しいことかもしれない。
しかし、その時はもう少しで来るのだ。
俺はそれ以上考えることを半ば放棄しながら、学校へ向かっていった。
◇
校門を潜ると、すでに多くの生徒が集まっていた。
土曜日にもかかわらず、創立祭の準備のために集まった生徒たちだ。
中等部の教室に向かうと、一ノ瀬を含めたクラスメイトたちが準備に取り掛かっていた。
「先輩、おはようございます!来てくれてありがとうございます!」
一ノ瀬が満面の笑みで迎えてくれた。
その笑顔に、昔なら不快感を覚えたかもしれないが、今は少し心が温かくなるのを感じた。
「ああ、おはよう。」
簡潔だが、冷たくない答え方。それが今の俺にとって自然な対応になっていた。
「今日は休憩所の最終確認と、案内表示の設置をお願いできますか?」
一ノ瀬の指示に従って、俺は作業を始めた。
休憩所のテントが正しく設置されているか確認し、折れていたり緩んでいたりする部分を修正する。
案内表示の設置も順調に進んでいった。校内の各所に、来場者が迷わないよう矢印や案内図を貼り付けていく。他の生徒と協力しながら作業することも、不思議と自然に感じられた。
昼食の時間になると、一ノ瀬が俺を呼んだ。
「先輩、お昼ご飯一緒にどうですか?」
いつもと同じように屋上へと向かう。今日も一ノ瀬は俺のために弁当を作ってきてくれたようだ。
「いつも作ってくれて、悪いな。」
弁当箱を受け取りながら言うと、一ノ瀬は嬉しそうに首を振った。
「いえいえ、先輩に食べてもらうの、楽しいんです。」
そう言われて、何かムズムズするような恥ずかしさを感じた。
弁当を広げると、俺の好物が詰められていた。オムライス、唐揚げ、卵焼き…全て手の込んだものばかりだ。
「うまいな、これ。」
素直に褒めると、一ノ瀬の顔が明るくなった。
「ありがとうございます!先輩に気に入ってもらえて嬉しいです。」
快晴の空の下、屋上での昼食は、穏やかに過ぎていった。
以前なら考えられなかった状況だ。
「先輩、明日も朝八時集合なんですが、大丈夫ですか?」
「ああ、問題ない。」
「そして…夜の花火も、約束通り一緒に見てくれますか?」
一ノ瀬の目に期待と不安が混じっているのを見て、俺は自然に頷いた。
「約束したことは守るさ。」
その言葉に、彼女の表情が明るく輝いた。
「ありがとうございます!先輩と一緒に見る花火、楽しみにしています。」
午後の作業も順調に進み、夕方近くには準備がほぼ完了した。
「皆さん、お疲れ様でした!」
一ノ瀬がみんなの前で挨拶をする。彼女のリーダーシップに、クラスメイトたちも自然と従っている様子が印象的だった。
「明日は朝八時集合です。全員、忘れ物のないようにしてください。それでは解散します!」
生徒たちが帰り支度を始める中、一ノ瀬が俺のところにやってきた。
「先輩、今日も手伝ってくれてありがとうございます。本当に助かりました。」
「いや、別に。」
素っ気なく答えようとしたが、なぜかその言葉が出てこなかった。
代わりに、自然と口から出たのは別の言葉だった。
「楽しかったよ。」
自分でも驚くような言葉だったが、それは嘘ではなかった。
確かに今日の作業は、思っていたよりも充実していた。
一ノ瀬の顔に驚きと喜びが広がった。
「本当ですか?先輩が楽しんでくれて、私も嬉しいです!」
帰り道、一ノ瀬と一緒に歩いた。
「明日は創立祭ですね。先輩との特別な一日になるといいなぁ。」
何気ない言葉のようで、何か深い意味を感じさせた。
それは彼女が持っている、どこか不思議な雰囲気から連想させられる、『何か』だった。
そういえば、明日、一ノ瀬は全ての謎を明かすという。
彼女がなぜ俺のことをあれほど知っているのか。なぜ俺に接近したのか。
その答えが明らかになるのだ。
それを知ったとき、俺はどうするのだろう?
その答えはまだ分からない。
ただ確かなのは、一ノ瀬ナズナとの出会いが、俺の内側に何かの変化をもたらしているということだけだった。
最終確認の日だったからか、教室は例になく活気に溢れていた。
「先輩!」
一ノ瀬が駆け寄ってきた。彼女の手には大きなクリップボードが握られていた。
「待たせたな。」
そう答えると、一ノ瀬は嬉しそうに微笑んだ。
「今日は全体の最終確認です。休憩所も屋台も全て揃えて、動線をチェックします。」
「分かった。」
最終確認のために、俺と一ノ瀬は校内の各所を回ることになった。
各クラスの出し物や屋台、展示などをチェックしていく。
校内を歩きながら、一ノ瀬は学校の色々な場所について詳しく説明してくれた。
「この中庭の桜の木、春には綺麗なんですよ。クラス写真もここで撮るんです。」
「あの噴水は、創立者の寄贈品なんだそうです。五十年以上前からあるんですよ。」
彼女の説明は、まるで長年この学校にいるかのように詳細だった。
「一ノ瀬、詳しいな?」
素直な疑問を口にすると、彼女は少し考えるような素振りを見せた。
「まあ、中学三年生ですから。」
「ああ、そうか。」
納得のいく説明ではあったが、何か引っかかる部分があった。
まあ、それは今に始まったことではない。
しかし、すべてのことは何か一つの出来事から始まっている、と俺には感じられた。
そう、人は矛盾した嘘をつくと違和感だらけに感じる。
しかし、一ノ瀬の話には、そういったものがないように思えた。
…俺が騙されている?
そうなのかもしれない。
そう、俺は騙されているのだ。
騙されて『効率的』な生活から離れて…。
これで思考を止めた俺は、隣にいた一ノ瀬を見た。
彼女は俺を見てきた。
「ん?何ですか?先輩?」
そんな一ノ瀬の様子に俺は苦笑いを浮かべた。
◇
校内の巡回を終え、空き教室で二人きりになった時、一ノ瀬が突然言った。
「先輩は本当は何が好きなんですか?」
「何が好きって?」
「趣味とか、興味のあることとか。」
考えてみると、『動画を見る』こと以外に何も思いつかなかった。かつては読書が好きだったが、それも遠い過去のことのように感じられた。
「特にない。」
答えながらも、何か寂しさを感じた。
「中学時代は、SF小説が好きだったって言ってましたよね?」
「ああ。」
俺は反射的に答えた。
「もし、先輩が過去に戻れるとしたら、何をしますか?」
唐突な質問だった。
「さぁな。」
「もしですよ?」
彼女はどこか遠くを見つめながら話し始めた。
「私が戻れたとしたら、絶対、悔いのないようにしたいです。」
「たとえば?」
「それは…。」
後輩は目をつぶった。
「それは秘密です。」
「なんだ、それ。」
またいつものように彼女は俺の質問に答えなかった。
彼女は何かをしんみりと感じている。
なんだろう、俺はそれに合わせていた。
しばらく、沈黙が周囲を支配した。
「先輩。」
そんな後、一ノ瀬は突然明るい声で言った。
「先輩は将来の夢とかあるんですか?雨の日に資料室で見てた動画みたいに、色々なものに興味があるんですよね?」
唐突な質問に、考え込んだ。将来の夢。
かつては考えたこともあったが、その意味も無意味さも俺は知っていた。
「特にない。大学に行って、普通に就職するんじゃないか。」
「まあ、そうですね。それは普通の人生ですね。」
「そうだろ?」
「そうですね、先輩らしいですね。」
しみじみと彼女はポツリとそれだけ漏らした。
◇
創立祭前日の朝、目覚ましのアラームが鳴る前に目を覚ました。
窓から差し込む朝日に照らされた部屋を見回し、今日が特別な日だということを思い出す。
いつもなら五回のスヌーズを使い果たしてようやく起きる俺だが、今日は違った。体が勝手に動き、準備を始めていた。
朝食の席で、アカネが不思議そうに俺を見つめていた。
「お兄ちゃん、今日も学校?創立祭の準備?」
「ああ。」
「なんか変わったよね。前だったら土曜なんて絶対に引きこもってたのに。」
アカネの言葉に、俺も自分の変化を実感していた。
確かに以前の俺なら、休日に学校なんて考えられなかっただろう。
「人は変わるんだよ。」
自分でも意外な発言に、アカネは驚いたようだった。
「何?お兄ちゃん、誰かに騙されているの?」
それはどこか皮肉や揶揄を含めた口調だった。
「馬鹿言うな。行ってくる。」
俺は相手にせずにそれだけいって、家から出た。
家の玄関を出た、俺は考えた。
本当に自分は変わったのだろうか?と。
一月前の俺であれば、今の状況は考えられないほど『非効率的』だ。
土曜の朝から学校に行き、創立祭の準備をし、人と関わる。無駄な時間の使い方の極みだ。
だが今の俺は、それを苦痛と感じていない。
この変化は一体何なのか。そして、それを引き起こしたのは一ノ瀬ナズナという後輩だった。
謎の後輩。
彼女はどうして、俺にことを知っている?
どうして、俺に近づいている?
どうして、俺と一緒にいるんだ?
明日の花火の後、全ての謎が解けるという。
真相は驚くべきことかもしれない。
悲しいことかもしれない。
しかし、その時はもう少しで来るのだ。
俺はそれ以上考えることを半ば放棄しながら、学校へ向かっていった。
◇
校門を潜ると、すでに多くの生徒が集まっていた。
土曜日にもかかわらず、創立祭の準備のために集まった生徒たちだ。
中等部の教室に向かうと、一ノ瀬を含めたクラスメイトたちが準備に取り掛かっていた。
「先輩、おはようございます!来てくれてありがとうございます!」
一ノ瀬が満面の笑みで迎えてくれた。
その笑顔に、昔なら不快感を覚えたかもしれないが、今は少し心が温かくなるのを感じた。
「ああ、おはよう。」
簡潔だが、冷たくない答え方。それが今の俺にとって自然な対応になっていた。
「今日は休憩所の最終確認と、案内表示の設置をお願いできますか?」
一ノ瀬の指示に従って、俺は作業を始めた。
休憩所のテントが正しく設置されているか確認し、折れていたり緩んでいたりする部分を修正する。
案内表示の設置も順調に進んでいった。校内の各所に、来場者が迷わないよう矢印や案内図を貼り付けていく。他の生徒と協力しながら作業することも、不思議と自然に感じられた。
昼食の時間になると、一ノ瀬が俺を呼んだ。
「先輩、お昼ご飯一緒にどうですか?」
いつもと同じように屋上へと向かう。今日も一ノ瀬は俺のために弁当を作ってきてくれたようだ。
「いつも作ってくれて、悪いな。」
弁当箱を受け取りながら言うと、一ノ瀬は嬉しそうに首を振った。
「いえいえ、先輩に食べてもらうの、楽しいんです。」
そう言われて、何かムズムズするような恥ずかしさを感じた。
弁当を広げると、俺の好物が詰められていた。オムライス、唐揚げ、卵焼き…全て手の込んだものばかりだ。
「うまいな、これ。」
素直に褒めると、一ノ瀬の顔が明るくなった。
「ありがとうございます!先輩に気に入ってもらえて嬉しいです。」
快晴の空の下、屋上での昼食は、穏やかに過ぎていった。
以前なら考えられなかった状況だ。
「先輩、明日も朝八時集合なんですが、大丈夫ですか?」
「ああ、問題ない。」
「そして…夜の花火も、約束通り一緒に見てくれますか?」
一ノ瀬の目に期待と不安が混じっているのを見て、俺は自然に頷いた。
「約束したことは守るさ。」
その言葉に、彼女の表情が明るく輝いた。
「ありがとうございます!先輩と一緒に見る花火、楽しみにしています。」
午後の作業も順調に進み、夕方近くには準備がほぼ完了した。
「皆さん、お疲れ様でした!」
一ノ瀬がみんなの前で挨拶をする。彼女のリーダーシップに、クラスメイトたちも自然と従っている様子が印象的だった。
「明日は朝八時集合です。全員、忘れ物のないようにしてください。それでは解散します!」
生徒たちが帰り支度を始める中、一ノ瀬が俺のところにやってきた。
「先輩、今日も手伝ってくれてありがとうございます。本当に助かりました。」
「いや、別に。」
素っ気なく答えようとしたが、なぜかその言葉が出てこなかった。
代わりに、自然と口から出たのは別の言葉だった。
「楽しかったよ。」
自分でも驚くような言葉だったが、それは嘘ではなかった。
確かに今日の作業は、思っていたよりも充実していた。
一ノ瀬の顔に驚きと喜びが広がった。
「本当ですか?先輩が楽しんでくれて、私も嬉しいです!」
帰り道、一ノ瀬と一緒に歩いた。
「明日は創立祭ですね。先輩との特別な一日になるといいなぁ。」
何気ない言葉のようで、何か深い意味を感じさせた。
それは彼女が持っている、どこか不思議な雰囲気から連想させられる、『何か』だった。
そういえば、明日、一ノ瀬は全ての謎を明かすという。
彼女がなぜ俺のことをあれほど知っているのか。なぜ俺に接近したのか。
その答えが明らかになるのだ。
それを知ったとき、俺はどうするのだろう?
その答えはまだ分からない。
ただ確かなのは、一ノ瀬ナズナとの出会いが、俺の内側に何かの変化をもたらしているということだけだった。