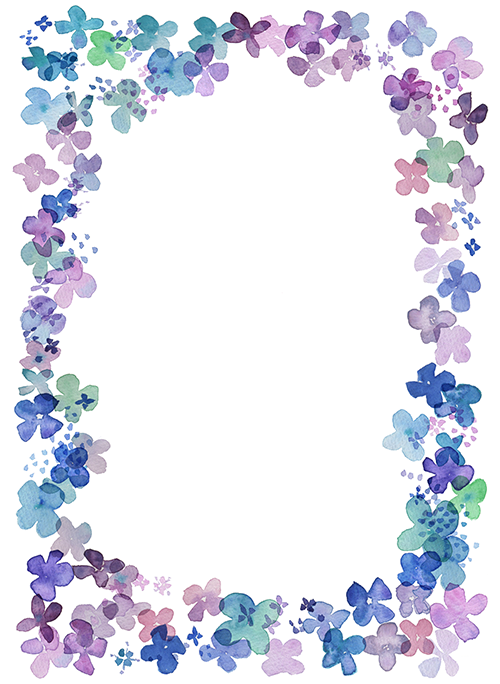気が付けば、創立祭まであと三日となっていた。
もう一週間以上、俺は放課後に中等部の教室に通い、準備を手伝っていた。
最初は脅迫によって仕方なく来ていた場所が、いつの間にか日課となっていることに、自分でもどこか驚きがあった。
教室に入ると、生徒たちが俺に気づき、いくつかの顔が明るくなった。
もはや違和感なく迎え入れられる。『綾小路先輩』と声をかけてくる生徒たちもいる。
部外者ではなく、準備の一員として認識されていたのだ。
今、自分の所属しているクラスの生徒よりも、この年下の知らないメンバーと話している。
その奇妙な状態に俺は苦笑するほかになかった。
「先輩、こんにちは!」
一ノ瀬が笑顔で近づいてきた。
「ああ。今日は何をする?」
「今日はパンフレットの仕分けと、屋台の最終確認です!」
テキパキとした感じで彼女はそう言った。一ノ瀬は準備のリーダーとして、指示を出したり全体の進行を見たりしている。
俺以外の生徒と話すときには、どこか真面目で物静かな印象のある彼女。
俺に対しての強引さとは正反対な真面目で丁寧な雰囲気で、一ノ瀬は要所要所、的確な指示を出していた。
彼女はリーダーとしての役割を立派に果たしていた。
俺もパンフレットの仕分け作業に加わり、黙々と作業を進めた。
途中、班の男子生徒が話しかけてきた。
「綾小路先輩、高等部の創立祭はどんな感じなんですか?」
不意の質問に少し戸惑ったが、考えてみれば高等部の創立祭はまだ先のことで、俺自身経験していない。
「まだ経験してないから分からないよ。」
素直に答えると、男子生徒は少し驚いた表情を見せた。
「そうなんですか。てっきり先輩は高等部の行事にも積極的に参加してるものだと思ってました。」
その言葉に、思わず笑みがこぼれそうになった。
俺が『積極的』?とんでもない誤解だ。
まあ、現状をみれば、そんな誤解を生むのは仕方がないことかもしれない。
しかしそもそも一月前の俺であれば、こんな『非効率的』な行事には絶対に関わらなかっただろう。
いつの間にか俺は、生徒たちの間で『積極的に参加する先輩』というイメージが形成されつつあるようだった。
なんとも皮肉な話だった。
作業の合間、一ノ瀬が近づいてきた。
「先輩、調子はどうですか?」
「普通だ。」
正直に俺は答える。
そう、普通だった。
俺はいつも、普通のはずだった。
「あはは。」
後輩は笑い出した。
「何がおかしい?」
「いえ、なんだか…懐かしい感じがして。」
彼女はポツリとそういった。
今の俺の回答から『懐かしい』とはこれいかに?
いやはや、こいつの感性はいったいどうなっているんだろう?
心優しい俺は、ほんのちょっとだけ、この不思議な後輩について心配をした。
…ただ、大したことじゃない。
俺は作業に戻った。
彼女もすぐに他の生徒たちの輪に加わり、装飾の準備を手伝いはじめていた。
そんな雰囲気の中で、俺も延々と作業をしていた。
すると、時間が過ぎるのは早い。
気づけば、今日の準備作業も終わりの時間となっていた。
「皆さん、今日も一日お疲れ様でした!明日は最終確認になりますので、八時に集合でお願いします。」
一ノ瀬がリーダーとして全員に声をかける。
彼女の指示に、クラスメイトたちは素直に従っていた。
生徒たちが次々と教室を後にする中、俺も鞄を手に取った。
「先輩、お疲れ様です。一緒に帰りましょう?」
一ノ瀬が俺の隣に立っていた。もはやこれは毎日の光景だ。
「ああ。」
簡素な返事だが、彼女はそれだけで満足そうに微笑む。
◇
校門を出て、夕暮れの道を歩き始める。
周囲は徐々に暗くなりつつあり、街灯が一つ二つと灯り始めていた。
そんな中でも、隣にいる彼女はあれこれと話を振ってくる。
それが何かいつものことのようになっている。
自然でいて、不快ではない。
俺はもはやそれに飲み込まれている。
そんな想像をしながら歩いている、と住宅街に入った。
「先輩、変わりましたね。」
突然、一ノ瀬が言った。
「どういう意味だ?」
「最初は全然話してくれなかったのに、今は自分から話すこともあるし、みんなともちゃんと接してる。」
彼女は満足そうに微笑んだ。
「それが何か?」
俺は問題があるのか、と聞いた。
「嬉しいです。優しい先輩がいる気がして。」
彼女の真摯な言葉に、何か心の奥が震えるような感覚を覚えた。
「俺はいつも優しいだろ?」
「そう…。ですね。」
彼女はそう言って俺に微笑んだ。
そこで俺は思った。
この後輩と初めて出会ったときのこと。
初めから俺は目の前の彼女を強烈に拒絶した。
それはつい最近のことだったけれど。
それが嘘のように、今の時間が過ぎていた。
俺は黙っていた。
じっと、その様子を後輩は見ていた。
彼女は確かに何かを知っているような様子で俺を見ていた。
「俺は…。その。」
俺は何かを言おうとして、言葉に詰まった。」
「ああ。先輩。分かりますよ。先輩が本当は優しくて、人と関わることを恐れているだけだってこと。」
後輩は青空を見ながら、誰かを見ているかのように呟いた。
その言葉が胸に刺さった。
優しい?俺が?冗談じゃない。
俺はただ『効率的』に生きようとしているだけだ。人との関わりを避けているのも、無駄な時間を省くためなのだ。
…分からない。俺は何も…。
俺は沈黙を続けていた。
ふと、一ノ瀬はこちらを見た。
「明日は創立祭前日です。全員で最終確認をするので、絶対に来てくださいね。」
彼女は話題を変えた。
「ああ、分かった。」
素直に返事をする自分に、少し前の自分であれば驚いただろう。しかし今は、それが自然なことのように感じられた。
この変化が良いことなのか悪いことなのか、まだ判断できない。
ただ、一つだけ確かなのは、俺の心の中で何かが動き始めているということだった。
◇
創立祭前日の一日前、放課後はいつも通り創立祭の準備に取り組んでいた。
明日と明後日のスケジュールの最終確認と、それぞれの役割の再確認だ。
「先輩は案内係と休憩所の担当ですからね。こちらが案内用のパンフレットで、これを来場者に配りながら、必要に応じて校内を案内していただきます。」
一ノ瀬が俺に説明していた。
「俺が案内係?人と話すのは得意じゃないんだが?」
正直なところを伝えると、彼女は笑った。
「大丈夫です。先輩は思っているより話すのが上手ですよ。それに私もずっと近くにいますから。」
彼女の言葉に、なぜか安心感を覚えた。
最終確認を終え、出発しようとした時、一ノ瀬が俺を呼び止めた。
「先輩、明日は朝早くから来てもらえますか?開場前の準備があるので、八時に集合なんです。」
「土曜の朝八時か…わかった。行くよ。」
一月前の俺だったら、土曜の朝に学校に来るなんて考えられなかっただろう。それも効率的とは程遠い『創立祭の準備』のためだなんて。
だが今は、それを苦痛と思わなくなっていた。
「先輩、明日はもうひとつお願いがあります。」
一ノ瀬は少し恥ずかしそうに言った。
「なんだ?」
「創立祭の締めくくりに花火があるんです。先輩と一緒に見たいなって…。」
その言葉に、心臓が一拍早くなった気がした。
「花火?」
「はい。夜七時からなんですけど…その時間になったら、あの丘で一緒に見ませんか?」
彼女の表情には期待と不安が入り混じっていた。まるで大切な約束をするかのような真剣さ。
「ああ、分かった。」
すんなりと受け入れられた自分に、俺自身、少し驚いてしまうほどだった。
「やった!約束ですよ。絶対に来てくださいね。」
一ノ瀬の表情が明るく輝いた。
「先輩、そのとき…あの日のことを全部説明します。私がなぜ先輩のことをそこまで知っているのか、なぜ先輩と関わりたかったのか…全部。」
その言葉に、俺は真剣に頷いた。
長い間抱いていた疑問がついに解消される。
彼女の謎がすべて明かされる。
俺は考えた。
一ノ瀬ナズナという少女のことを。
彼女とは俺にとって何者なのか?
そして、彼女との出会いが俺の人生にどのような影響を与えたのか。
それは、今の状況が物語っていたのかもしれない。
もう一週間以上、俺は放課後に中等部の教室に通い、準備を手伝っていた。
最初は脅迫によって仕方なく来ていた場所が、いつの間にか日課となっていることに、自分でもどこか驚きがあった。
教室に入ると、生徒たちが俺に気づき、いくつかの顔が明るくなった。
もはや違和感なく迎え入れられる。『綾小路先輩』と声をかけてくる生徒たちもいる。
部外者ではなく、準備の一員として認識されていたのだ。
今、自分の所属しているクラスの生徒よりも、この年下の知らないメンバーと話している。
その奇妙な状態に俺は苦笑するほかになかった。
「先輩、こんにちは!」
一ノ瀬が笑顔で近づいてきた。
「ああ。今日は何をする?」
「今日はパンフレットの仕分けと、屋台の最終確認です!」
テキパキとした感じで彼女はそう言った。一ノ瀬は準備のリーダーとして、指示を出したり全体の進行を見たりしている。
俺以外の生徒と話すときには、どこか真面目で物静かな印象のある彼女。
俺に対しての強引さとは正反対な真面目で丁寧な雰囲気で、一ノ瀬は要所要所、的確な指示を出していた。
彼女はリーダーとしての役割を立派に果たしていた。
俺もパンフレットの仕分け作業に加わり、黙々と作業を進めた。
途中、班の男子生徒が話しかけてきた。
「綾小路先輩、高等部の創立祭はどんな感じなんですか?」
不意の質問に少し戸惑ったが、考えてみれば高等部の創立祭はまだ先のことで、俺自身経験していない。
「まだ経験してないから分からないよ。」
素直に答えると、男子生徒は少し驚いた表情を見せた。
「そうなんですか。てっきり先輩は高等部の行事にも積極的に参加してるものだと思ってました。」
その言葉に、思わず笑みがこぼれそうになった。
俺が『積極的』?とんでもない誤解だ。
まあ、現状をみれば、そんな誤解を生むのは仕方がないことかもしれない。
しかしそもそも一月前の俺であれば、こんな『非効率的』な行事には絶対に関わらなかっただろう。
いつの間にか俺は、生徒たちの間で『積極的に参加する先輩』というイメージが形成されつつあるようだった。
なんとも皮肉な話だった。
作業の合間、一ノ瀬が近づいてきた。
「先輩、調子はどうですか?」
「普通だ。」
正直に俺は答える。
そう、普通だった。
俺はいつも、普通のはずだった。
「あはは。」
後輩は笑い出した。
「何がおかしい?」
「いえ、なんだか…懐かしい感じがして。」
彼女はポツリとそういった。
今の俺の回答から『懐かしい』とはこれいかに?
いやはや、こいつの感性はいったいどうなっているんだろう?
心優しい俺は、ほんのちょっとだけ、この不思議な後輩について心配をした。
…ただ、大したことじゃない。
俺は作業に戻った。
彼女もすぐに他の生徒たちの輪に加わり、装飾の準備を手伝いはじめていた。
そんな雰囲気の中で、俺も延々と作業をしていた。
すると、時間が過ぎるのは早い。
気づけば、今日の準備作業も終わりの時間となっていた。
「皆さん、今日も一日お疲れ様でした!明日は最終確認になりますので、八時に集合でお願いします。」
一ノ瀬がリーダーとして全員に声をかける。
彼女の指示に、クラスメイトたちは素直に従っていた。
生徒たちが次々と教室を後にする中、俺も鞄を手に取った。
「先輩、お疲れ様です。一緒に帰りましょう?」
一ノ瀬が俺の隣に立っていた。もはやこれは毎日の光景だ。
「ああ。」
簡素な返事だが、彼女はそれだけで満足そうに微笑む。
◇
校門を出て、夕暮れの道を歩き始める。
周囲は徐々に暗くなりつつあり、街灯が一つ二つと灯り始めていた。
そんな中でも、隣にいる彼女はあれこれと話を振ってくる。
それが何かいつものことのようになっている。
自然でいて、不快ではない。
俺はもはやそれに飲み込まれている。
そんな想像をしながら歩いている、と住宅街に入った。
「先輩、変わりましたね。」
突然、一ノ瀬が言った。
「どういう意味だ?」
「最初は全然話してくれなかったのに、今は自分から話すこともあるし、みんなともちゃんと接してる。」
彼女は満足そうに微笑んだ。
「それが何か?」
俺は問題があるのか、と聞いた。
「嬉しいです。優しい先輩がいる気がして。」
彼女の真摯な言葉に、何か心の奥が震えるような感覚を覚えた。
「俺はいつも優しいだろ?」
「そう…。ですね。」
彼女はそう言って俺に微笑んだ。
そこで俺は思った。
この後輩と初めて出会ったときのこと。
初めから俺は目の前の彼女を強烈に拒絶した。
それはつい最近のことだったけれど。
それが嘘のように、今の時間が過ぎていた。
俺は黙っていた。
じっと、その様子を後輩は見ていた。
彼女は確かに何かを知っているような様子で俺を見ていた。
「俺は…。その。」
俺は何かを言おうとして、言葉に詰まった。」
「ああ。先輩。分かりますよ。先輩が本当は優しくて、人と関わることを恐れているだけだってこと。」
後輩は青空を見ながら、誰かを見ているかのように呟いた。
その言葉が胸に刺さった。
優しい?俺が?冗談じゃない。
俺はただ『効率的』に生きようとしているだけだ。人との関わりを避けているのも、無駄な時間を省くためなのだ。
…分からない。俺は何も…。
俺は沈黙を続けていた。
ふと、一ノ瀬はこちらを見た。
「明日は創立祭前日です。全員で最終確認をするので、絶対に来てくださいね。」
彼女は話題を変えた。
「ああ、分かった。」
素直に返事をする自分に、少し前の自分であれば驚いただろう。しかし今は、それが自然なことのように感じられた。
この変化が良いことなのか悪いことなのか、まだ判断できない。
ただ、一つだけ確かなのは、俺の心の中で何かが動き始めているということだった。
◇
創立祭前日の一日前、放課後はいつも通り創立祭の準備に取り組んでいた。
明日と明後日のスケジュールの最終確認と、それぞれの役割の再確認だ。
「先輩は案内係と休憩所の担当ですからね。こちらが案内用のパンフレットで、これを来場者に配りながら、必要に応じて校内を案内していただきます。」
一ノ瀬が俺に説明していた。
「俺が案内係?人と話すのは得意じゃないんだが?」
正直なところを伝えると、彼女は笑った。
「大丈夫です。先輩は思っているより話すのが上手ですよ。それに私もずっと近くにいますから。」
彼女の言葉に、なぜか安心感を覚えた。
最終確認を終え、出発しようとした時、一ノ瀬が俺を呼び止めた。
「先輩、明日は朝早くから来てもらえますか?開場前の準備があるので、八時に集合なんです。」
「土曜の朝八時か…わかった。行くよ。」
一月前の俺だったら、土曜の朝に学校に来るなんて考えられなかっただろう。それも効率的とは程遠い『創立祭の準備』のためだなんて。
だが今は、それを苦痛と思わなくなっていた。
「先輩、明日はもうひとつお願いがあります。」
一ノ瀬は少し恥ずかしそうに言った。
「なんだ?」
「創立祭の締めくくりに花火があるんです。先輩と一緒に見たいなって…。」
その言葉に、心臓が一拍早くなった気がした。
「花火?」
「はい。夜七時からなんですけど…その時間になったら、あの丘で一緒に見ませんか?」
彼女の表情には期待と不安が入り混じっていた。まるで大切な約束をするかのような真剣さ。
「ああ、分かった。」
すんなりと受け入れられた自分に、俺自身、少し驚いてしまうほどだった。
「やった!約束ですよ。絶対に来てくださいね。」
一ノ瀬の表情が明るく輝いた。
「先輩、そのとき…あの日のことを全部説明します。私がなぜ先輩のことをそこまで知っているのか、なぜ先輩と関わりたかったのか…全部。」
その言葉に、俺は真剣に頷いた。
長い間抱いていた疑問がついに解消される。
彼女の謎がすべて明かされる。
俺は考えた。
一ノ瀬ナズナという少女のことを。
彼女とは俺にとって何者なのか?
そして、彼女との出会いが俺の人生にどのような影響を与えたのか。
それは、今の状況が物語っていたのかもしれない。