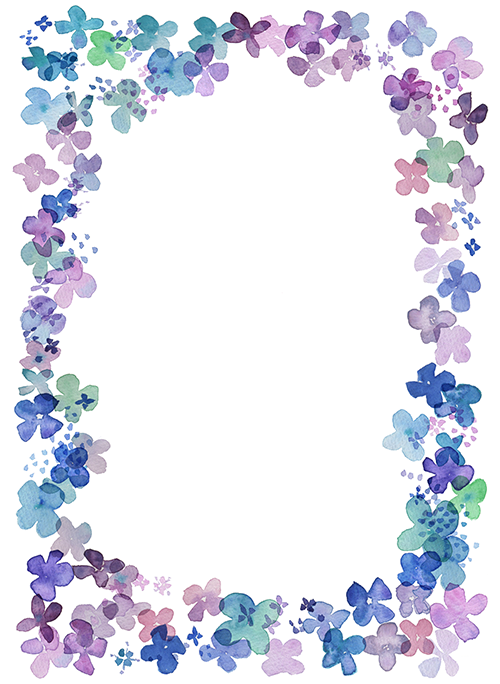放課後のチャイムが鳴り響き、教室から生徒たちが次々と出ていく。
部活に向かう者、友人と遊びに行く者、それぞれの目的地へと足早に向かっていく。
かつての俺なら、この時間は自宅へと直行していた。だが今日は違う。
中等部の第二教室棟へ向かわなければならない。
一ノ瀬との約束、いや、半ば脅迫めいた形で引き受けた創立祭の手伝いがあるからだ。
鞄を持ち、重い足取りで廊下を歩いていた。
昨日のことを思い返す。屋上で頬を膨らませた一ノ瀬の姿。
『私が先輩と一緒にいたいからです。』
その素直な言葉。
そして最後には例の脅しも出てきたけれど、なぜか俺はそれほど恐怖を感じなかった。
むしろ、一ノ瀬と会話する中で、自分の中に何か変化が起きていることに気づいてしまった。
『仮に今、それをバラされたからといっても、この後輩がいるし。』
昨日心の中でそう思った自分に、正直なところ驚いていた。
いつの間にか、一ノ瀬の存在が俺の日常に溶け込み始めていた。
否定したいところだったが、それは否定できないことだった。
しかし、しかし。
それは…。
俺には、これがいいことなのか、悪いことなのか。
そもそも、今の俺はなぜ、中等部へ向かっているのだろう?
高等部の校舎を出て、中庭を横切る。中等部の校舎は高等部とは別棟になっており、これまで足を踏み入れたことはなかった。そこは未知の領域。まるで異世界に足を踏み入れるような感覚だった。
第二教室棟の入り口に立つと、小さな不安が胸をよぎる。本当にこんなところに来ていいのだろうか。
生徒たちの視線が気になる。ここで立ち止まって、約束を破るという選択肢もある。
だが、その先に待っているのは過去の暴露。あの屈辱を再び味わうことになる。
ただ、正直なところ、脅しだけで来たわけではないような気もしていた。
一ノ瀬という少女への好奇心。
彼女がなぜ俺のことをあれほど知っているのか。なぜ俺に執着するのか。
その謎を解きたいという気持ちも正直、あった。
深呼吸をして、中に入る。廊下には中等部の生徒たちの姿があり、見知らぬ高等部生が現れたことに好奇の目を向けてくる。
居心地の悪さを感じながら、案内板を探す。こういう人の視線を感じる場面が、一番苦手だった。
自分の存在感を消すことで生きてきた俺にとって、注目されることは拷問に等しい。
「先輩!」
声がして振り返ると、一ノ瀬が廊下の向こうから手を振っていた。
見覚えのある笑顔に、妙な安堵感を覚える。
彼女の存在が、この見知らぬ環境での唯一の頼りになっていた。
「こっちです!」
彼女に導かれるまま、俺は教室に向かう。その廊下を歩く間も、周囲の視線が気になって仕方がなかった。
教室に入ると、すでに数人の中等部生がいて、何かの作業をしていた。
「みんな、これが綾小路先輩。高等部一年生で、今日から創立祭の準備を手伝ってくださいます。」
一ノ瀬が俺を紹介する。クラスメイトたちは一瞬作業の手を止め、俺に視線を向けた。
「よろしくお願いします。」
全員が揃って頭を下げる。俺は思わず戸惑いながらも、小さく頭を下げ返した。
「私たちのグループは休憩所の設営担当なんです。」
一ノ瀬が説明する。
「椅子やテーブル、テントなどを運んだり設置したりする作業を手伝ってもらえますか?」
俺は無言で頷いた。こういう肉体労働なら、最低限の会話で済む。それがせめてもの救いだった。
作業が始まると、中等部の男子生徒たちと共に、倉庫から椅子やテーブルを運びだす作業に従事した。
黙々と物を運ぶ作業は、意外なことに集中できた。誰とも会話する必要がなく、ただ指示された通りに動けばいいだけだった。
時折、一ノ瀬の姿が視界に入る。彼女はクラスメイトたちと話す時、俺といるときとは全く違う表情をしていた。
どこか淡々とした様子で、まじめで物静かな印象を受けた。
俺に対して見せる活発で強引な態度とは別人のようだった。
一時間ほど作業をした後、休憩時間となった。他の生徒たちがグループになって談笑する中、俺は一人隅に立っていた。
「先輩、お疲れ様です。」
一ノ瀬が近づいてきた。
「作業はどうですか?大変じゃないですか?」
「別に。」
短く答える俺に、一ノ瀬は微笑んだ。
「先輩、なんでクラスメイトと話すときと、俺と話すときで態度が違うんだ?」
思わず質問してしまった。
一ノ瀬は少し驚いた表情を見せた後、小さく笑った。
「気のせいですよ。」
その答えに、何か釈然としないものを感じた。
◇
休憩が終わり、再び作業に戻る。
夕方までかかって、休憩所の基本的な設営は完了した。
付き合わされた俺の苦労もあってか、テントの骨組みが組み立てられ、椅子とテーブルが配置されたのだ。
時間が経過しており、ここで今日は解散となった。
他の生徒たちが帰り支度をする中、一ノ瀬が俺に近づいて生きた。
「先輩、それじゃあ、今日も一緒に帰りましょう!」
「ああ。」
いつものように俺は彼女と一緒に自宅に帰ることになった。
クラスメイトたちに挨拶をして、一ノ瀬と一緒に中等部の校舎を出た。
夕暮れの校庭は部活動をする生徒たちの声が響いている。
「今日は大変でしたね。先輩、疲れませんでした?」
一ノ瀬が心配そうに俺の顔を覗き込んできた。
「別に。単純作業だからな。」
「でも、重いものをたくさん運んでましたよね。先輩、結構力持ちなんですね!」
何気ない褒め言葉。
誉め言葉になれていない俺は、少し照れくさい気持ちになった。
「そうか?普通だと思うが。」
「いえいえ、あんな重いテーブルを一人で運べるなんてすごいです!」
校門を出て、いつもの帰り道を歩き始める。雲一つない青空が、少しずつ夕焼け色に染まり始めていた。
「あのさ。」
ふと思いついて尋ねた。
「創立祭って、何をするんだ?」
一ノ瀬は少し驚いたような顔をした。
「先輩、創立祭に行ったことないんですか?」
「いや、高校に入学したばかりだからな。まだ経験してない。」
「そっか!じゃあ説明しますね。」
彼女は嬉しそうに話し始めた。
「各クラスが出し物をするんです。カフェとか、ゲームコーナーとか、お化け屋敷とか。それから校庭では屋台が出て、最後には花火もあるんですよ!」
彼女の話し方には、どこか懐かしむような調子があった。
まるで過去の記憶を語るかのように。
まあ、昨年までの創立祭で何かあったのかもしれない、と俺は推理した。
「ふーん。」
正直、あまり興味が湧かなかった。情報が耳から入ってすぐに耳から出ていった。
ただ、彼女に連れまわれることを前提に聞くに限る。
「先輩、来てくれますよね?当日も手伝ってもらいたいんです。」
「ああ。約束したからな。」
俺は諦めたようにそういった。
「やった!絶対楽しいですよ!」
一ノ瀬が嬉しそうに拍手した。
住宅街に入った。この道を一ノ瀬と歩くのは、もう何度目だろう。最初は脅迫めいた形で始まったこの帰り道も、今では不思議と自然な流れになっていた。
「先輩、明日のお弁当も作ってきますね。何か食べたいものありますか?」
「特にない。お前の好きなようにしてくれ。」
毎日手作り弁当を持ってきてくれる彼女に、少し申し訳ない気持ちもあった。
「じゃあ、明日はオムライスにしようかな。先輩、卵料理好きですよね?」
俺の好みを完璧に把握している彼女に、もはや驚きはなかった。
「ああ。」
単調な返事をする俺に、一ノ瀬は構わず話し続けた。
彼女は休憩所の装飾をどうするか、花を飾りたいとか、看板のデザインはどうするかとか、次から次へと創立祭の話題を展開していく。
公園の前を通りかかったとき、一ノ瀬が立ち止まった。昨日も立ち寄った小さな公園だ。
「ちょっと寄っていきませんか?」
「また?毎日立ち寄る必要はないだろう。」
「そんなことないですよ。少し休憩しましょう。」
断る気力もなく、公園に入る。
ブランコに座る一ノ瀬を見て、俺も隣に腰掛けた。
「先輩は子供の頃、よく公園で遊びましたか?」
「別に。普通の子供と同じだろう。」
「どんな遊びが好きだったんですか?」
彼女の質問には、いつも俺の過去へ迫るような意図を感じる。それでも、こんな無害な話題なら答えても構わないだろう。
「かくれんぼとかかな。あとは缶蹴り。」
「へぇ!私も好きでした!」
一ノ瀬はブランコをゆっくり漕ぎながら、嬉しそうに話した。
「特に鬼になるのが楽しかったです。みんなを探し出すのって、ドキドキしませんでした?」
「そうかな。俺は隠れる方が好きだったな。」
思わず素直な感想を口にしていた。存在感を消す技術は、子供の頃から磨かれていたのかもしれない。
夕陽が徐々に沈みかけ、辺りが暗くなり始めていた。
「そろそろ帰ろうか。」
俺が立ち上がると、一ノ瀬も素直に従った。
「はい。明日も楽しみですね!」
俺はそれに答えない。
しかし、一ノ瀬はそんな俺の腕を取って、先に進み始めた。
公園を出て、再び歩き始める。
いつもの十字路に近づくと、そこが別れ道だということを俺も一ノ瀬も…、お互いに分かっていた。
「先輩、送ってもらってありがとうございます。」
一ノ瀬が十字路で立ち止まった。
「送ったわけじゃない。強引に付き合わされているだけだ。」
「はいはい、そうですね。でも、嬉しいです。明日も学校で会いましょうね。」
「ああ。」
彼女は手を振って、角を曲がっていった。
俺はその後ろ姿を見送った後、自分の道を歩き始めた。
帰り道、スマホを取り出し、いつもの動画を再生しはじめた。
しかし、なぜか以前ほど集中できなかった。画面の向こう側の世界よりも、今日実際に体験した『異なる世界』の方が、妙にリアルに感じられた。
それは『効率的』ではなかった。
確実に『無駄な時間』だった。
しかし、それを日常として受け止めている俺がそこにはいた。
◇
創立祭の準備が続く数日間、俺は放課後になると必ず中等部の教室へと足を運んだ。
初日こそぎこちなかったが、毎日顔を合わせるうちに、徐々に中等部の生徒たちとも簡単な挨拶を交わすようになっていた。
特に休憩所の設営チームのメンバーたちは、最初の緊張感がほぐれ、俺に対しても自然に接するようになっていた。俺自身も、最低限の受け答えはするようになっていた。
一ノ瀬はそんな俺の変化を、嬉しそうに見守っていた。
相変わらず、クラスメイトたちの前では物静かな態度を取りながらも、俺と二人きりになると活発な本来の姿を見せる。
最初は脅迫めいた態度だった彼女も、今では冗談めいた調子で『告白マニア』の話を持ち出すようになっていた。
「先輩、今日も手伝ってくれないと、あの話を広めちゃいますよ?」
そう言いながら笑う一ノ瀬に、俺はもはや恐怖は感じなくなっていた。
むしろ、それは俺たちの間での暗黙の了解のような形になりつつあった。
◇
今日も放課後、俺は中等部の教室へと向かった。いよいよ、創立祭に近づいてきて、準備も佳境に入っていた。
教室に入ると、一ノ瀬が手を振った。
「先輩、今日は装飾の仕上げをします。この看板の色塗りを手伝ってもらえますか?」
彼女に導かれるまま、俺は大きな看板の前に座る。『第三学園中等部創立祭』と書かれた文字の輪郭が描かれており、それに色を塗る作業だった。
黙々と筆を動かす俺の隣で、一ノ瀬も同じように作業に没頭していた。他のメンバーたちは教室の別の場所で、他の装飾品を作っている。
穏やかな沈黙が流れた。ただ、それは不思議と居心地が悪くはなかった。
「先輩は何か趣味ありますか?スマホの動画以外で。」
突然、一ノ瀬が質問してきた。
「特にない。」
短く答える。
「本当ですか?中学時代は読書が好きだったんじゃないですか?」
その言葉に、俺は思わず筆を止めた。確かに中学時代は、図書室で過ごすことが多かった。特にSF小説を好んで読んでいた。だが、それは誰にも話していないはずだ。
ということは、創作ノートの存在からの連想か?
「例のノートからの連想か?」
「ふふっ、どうでしょうね?」
意味ありげに一ノ瀬は笑った。
「悪趣味だな。」
俺は諦めたように答えるほかになかった。
「当たりですか?やっぱり。」
一ノ瀬は嬉しそうに笑った。
「俺のことをどこまで知ってるんだ?」
本気で恐ろしくなってきた。
「先輩が思っている以上に、私は先輩のことを知ってますよ。」
一ノ瀬は意味深な笑みを浮かべた。
「じゃあ言ってみろ。俺の好きな作家は?」
「アーサー・C・クラークですね。『幼年期の終わり』が特に好きで、何度も読み返したことがある。」
正確すぎる答え。それは確かにその通りだった。
「お前、一体何者だ…。」
俺は思わず、声に出してしまった。
「ただの中等部三年生です。」
そう言って、一ノ瀬は再び作業に戻った。
正直、恐ろしかった。
仮に彼女が俺の『創作ノート』の中身を知っていた、としよう。
でも、そこから好きな作家や作品まで連想できるものだろうか?
…いや、俺の好きだった小説と書いていた内容はまったく違った。
とすれば、彼女の答えはどこから出てきたのか?
まさか、エスパーで俺の心を読んでいるのか?
それとも、タイムマシンを使って過去を見に行ったのか?
もはや、俺にはそういった解釈しかできなかった。
ただ、こういった謎めいた事象の真相について、彼女に聞いても『秘密です。』とはぐらかされる。
それももはや、一つの様式美と化していた。
作業が終わり、夕方になると、一ノ瀬は俺を呼んだ。
「先輩、ちょっと付いてきてください。」
彼女に導かれるまま、俺は中等部の校舎内を歩いた。昇降口を過ぎ、中庭を横切り、体育館の裏手へと続く小道に入る。
「どこに連れて行く気だ?」
「特別な場所です。先輩にだけ見せたいんです。」
そう言って、一ノ瀬は足早に進んでいく。俺は半ば呆れながらも、その後を追った。
体育館の裏手を過ぎ、小さな坂を上ると、突然視界が開けた。そこには小高い丘があり、学校全体と、その先に広がる街並みが一望できた。
「ここ、すごいでしょう?」
一ノ瀬が誇らしげに言った。夕日に照らされた街並みは、確かに美しかった。思わず息を呑むほどの景色だった。
「学校裏のこんな場所があったなんて…」
思わず呟いた。
「ほとんどの人は知らないんです。私の秘密の場所なんです。」
一ノ瀬は嬉しそうに言った。そして草の上に腰を下ろし、俺も隣に座るように促した。
夕日が徐々に山の向こうに沈んでいく。オレンジ色の光が街全体を包み込み、窓ガラスに反射して輝いている。
「なぜこんな場所を俺に見せる?」
疑問が口から漏れた。
「先輩にだけ、見せたかったんです。」
一ノ瀬はまっすぐに俺の目を見て言った。
「なぜ俺に?他にもっと親しい友達がいるだろう。」
「先輩との関係は特別なんです。」
その言葉に、妙な鼓動を感じた。
「一ノ瀬、本当のことを話してくれ。なぜ俺のことをそこまで知っている?なぜ俺につきまとう?」
真剣に尋ねる。
一ノ瀬は少し考えるように空を見上げた後、穏やかな声で答えた。
「先輩だって、私に本当のことを言ってないですよね?だから私も言えません。」
一ノ瀬の言葉が心に刺さる。
言い返そうとするが、言葉が見つからない。
彼女の真摯な眼差しに、何かを感じていた。
「時間が遅くなりました。帰りましょう。」
一ノ瀬が立ち上がり、俺も無言で従った。
帰り道、俺と一ノ瀬は並んで歩いた。いつもならイヤホンを耳に差して動画を見ていた時間だが、今日はスマホに手を伸ばす気にもならなかった。
別れる時、一ノ瀬が言った。
「明日も来てくださいね。」
「ああ。」
俺は短く返事をした。
部活に向かう者、友人と遊びに行く者、それぞれの目的地へと足早に向かっていく。
かつての俺なら、この時間は自宅へと直行していた。だが今日は違う。
中等部の第二教室棟へ向かわなければならない。
一ノ瀬との約束、いや、半ば脅迫めいた形で引き受けた創立祭の手伝いがあるからだ。
鞄を持ち、重い足取りで廊下を歩いていた。
昨日のことを思い返す。屋上で頬を膨らませた一ノ瀬の姿。
『私が先輩と一緒にいたいからです。』
その素直な言葉。
そして最後には例の脅しも出てきたけれど、なぜか俺はそれほど恐怖を感じなかった。
むしろ、一ノ瀬と会話する中で、自分の中に何か変化が起きていることに気づいてしまった。
『仮に今、それをバラされたからといっても、この後輩がいるし。』
昨日心の中でそう思った自分に、正直なところ驚いていた。
いつの間にか、一ノ瀬の存在が俺の日常に溶け込み始めていた。
否定したいところだったが、それは否定できないことだった。
しかし、しかし。
それは…。
俺には、これがいいことなのか、悪いことなのか。
そもそも、今の俺はなぜ、中等部へ向かっているのだろう?
高等部の校舎を出て、中庭を横切る。中等部の校舎は高等部とは別棟になっており、これまで足を踏み入れたことはなかった。そこは未知の領域。まるで異世界に足を踏み入れるような感覚だった。
第二教室棟の入り口に立つと、小さな不安が胸をよぎる。本当にこんなところに来ていいのだろうか。
生徒たちの視線が気になる。ここで立ち止まって、約束を破るという選択肢もある。
だが、その先に待っているのは過去の暴露。あの屈辱を再び味わうことになる。
ただ、正直なところ、脅しだけで来たわけではないような気もしていた。
一ノ瀬という少女への好奇心。
彼女がなぜ俺のことをあれほど知っているのか。なぜ俺に執着するのか。
その謎を解きたいという気持ちも正直、あった。
深呼吸をして、中に入る。廊下には中等部の生徒たちの姿があり、見知らぬ高等部生が現れたことに好奇の目を向けてくる。
居心地の悪さを感じながら、案内板を探す。こういう人の視線を感じる場面が、一番苦手だった。
自分の存在感を消すことで生きてきた俺にとって、注目されることは拷問に等しい。
「先輩!」
声がして振り返ると、一ノ瀬が廊下の向こうから手を振っていた。
見覚えのある笑顔に、妙な安堵感を覚える。
彼女の存在が、この見知らぬ環境での唯一の頼りになっていた。
「こっちです!」
彼女に導かれるまま、俺は教室に向かう。その廊下を歩く間も、周囲の視線が気になって仕方がなかった。
教室に入ると、すでに数人の中等部生がいて、何かの作業をしていた。
「みんな、これが綾小路先輩。高等部一年生で、今日から創立祭の準備を手伝ってくださいます。」
一ノ瀬が俺を紹介する。クラスメイトたちは一瞬作業の手を止め、俺に視線を向けた。
「よろしくお願いします。」
全員が揃って頭を下げる。俺は思わず戸惑いながらも、小さく頭を下げ返した。
「私たちのグループは休憩所の設営担当なんです。」
一ノ瀬が説明する。
「椅子やテーブル、テントなどを運んだり設置したりする作業を手伝ってもらえますか?」
俺は無言で頷いた。こういう肉体労働なら、最低限の会話で済む。それがせめてもの救いだった。
作業が始まると、中等部の男子生徒たちと共に、倉庫から椅子やテーブルを運びだす作業に従事した。
黙々と物を運ぶ作業は、意外なことに集中できた。誰とも会話する必要がなく、ただ指示された通りに動けばいいだけだった。
時折、一ノ瀬の姿が視界に入る。彼女はクラスメイトたちと話す時、俺といるときとは全く違う表情をしていた。
どこか淡々とした様子で、まじめで物静かな印象を受けた。
俺に対して見せる活発で強引な態度とは別人のようだった。
一時間ほど作業をした後、休憩時間となった。他の生徒たちがグループになって談笑する中、俺は一人隅に立っていた。
「先輩、お疲れ様です。」
一ノ瀬が近づいてきた。
「作業はどうですか?大変じゃないですか?」
「別に。」
短く答える俺に、一ノ瀬は微笑んだ。
「先輩、なんでクラスメイトと話すときと、俺と話すときで態度が違うんだ?」
思わず質問してしまった。
一ノ瀬は少し驚いた表情を見せた後、小さく笑った。
「気のせいですよ。」
その答えに、何か釈然としないものを感じた。
◇
休憩が終わり、再び作業に戻る。
夕方までかかって、休憩所の基本的な設営は完了した。
付き合わされた俺の苦労もあってか、テントの骨組みが組み立てられ、椅子とテーブルが配置されたのだ。
時間が経過しており、ここで今日は解散となった。
他の生徒たちが帰り支度をする中、一ノ瀬が俺に近づいて生きた。
「先輩、それじゃあ、今日も一緒に帰りましょう!」
「ああ。」
いつものように俺は彼女と一緒に自宅に帰ることになった。
クラスメイトたちに挨拶をして、一ノ瀬と一緒に中等部の校舎を出た。
夕暮れの校庭は部活動をする生徒たちの声が響いている。
「今日は大変でしたね。先輩、疲れませんでした?」
一ノ瀬が心配そうに俺の顔を覗き込んできた。
「別に。単純作業だからな。」
「でも、重いものをたくさん運んでましたよね。先輩、結構力持ちなんですね!」
何気ない褒め言葉。
誉め言葉になれていない俺は、少し照れくさい気持ちになった。
「そうか?普通だと思うが。」
「いえいえ、あんな重いテーブルを一人で運べるなんてすごいです!」
校門を出て、いつもの帰り道を歩き始める。雲一つない青空が、少しずつ夕焼け色に染まり始めていた。
「あのさ。」
ふと思いついて尋ねた。
「創立祭って、何をするんだ?」
一ノ瀬は少し驚いたような顔をした。
「先輩、創立祭に行ったことないんですか?」
「いや、高校に入学したばかりだからな。まだ経験してない。」
「そっか!じゃあ説明しますね。」
彼女は嬉しそうに話し始めた。
「各クラスが出し物をするんです。カフェとか、ゲームコーナーとか、お化け屋敷とか。それから校庭では屋台が出て、最後には花火もあるんですよ!」
彼女の話し方には、どこか懐かしむような調子があった。
まるで過去の記憶を語るかのように。
まあ、昨年までの創立祭で何かあったのかもしれない、と俺は推理した。
「ふーん。」
正直、あまり興味が湧かなかった。情報が耳から入ってすぐに耳から出ていった。
ただ、彼女に連れまわれることを前提に聞くに限る。
「先輩、来てくれますよね?当日も手伝ってもらいたいんです。」
「ああ。約束したからな。」
俺は諦めたようにそういった。
「やった!絶対楽しいですよ!」
一ノ瀬が嬉しそうに拍手した。
住宅街に入った。この道を一ノ瀬と歩くのは、もう何度目だろう。最初は脅迫めいた形で始まったこの帰り道も、今では不思議と自然な流れになっていた。
「先輩、明日のお弁当も作ってきますね。何か食べたいものありますか?」
「特にない。お前の好きなようにしてくれ。」
毎日手作り弁当を持ってきてくれる彼女に、少し申し訳ない気持ちもあった。
「じゃあ、明日はオムライスにしようかな。先輩、卵料理好きですよね?」
俺の好みを完璧に把握している彼女に、もはや驚きはなかった。
「ああ。」
単調な返事をする俺に、一ノ瀬は構わず話し続けた。
彼女は休憩所の装飾をどうするか、花を飾りたいとか、看板のデザインはどうするかとか、次から次へと創立祭の話題を展開していく。
公園の前を通りかかったとき、一ノ瀬が立ち止まった。昨日も立ち寄った小さな公園だ。
「ちょっと寄っていきませんか?」
「また?毎日立ち寄る必要はないだろう。」
「そんなことないですよ。少し休憩しましょう。」
断る気力もなく、公園に入る。
ブランコに座る一ノ瀬を見て、俺も隣に腰掛けた。
「先輩は子供の頃、よく公園で遊びましたか?」
「別に。普通の子供と同じだろう。」
「どんな遊びが好きだったんですか?」
彼女の質問には、いつも俺の過去へ迫るような意図を感じる。それでも、こんな無害な話題なら答えても構わないだろう。
「かくれんぼとかかな。あとは缶蹴り。」
「へぇ!私も好きでした!」
一ノ瀬はブランコをゆっくり漕ぎながら、嬉しそうに話した。
「特に鬼になるのが楽しかったです。みんなを探し出すのって、ドキドキしませんでした?」
「そうかな。俺は隠れる方が好きだったな。」
思わず素直な感想を口にしていた。存在感を消す技術は、子供の頃から磨かれていたのかもしれない。
夕陽が徐々に沈みかけ、辺りが暗くなり始めていた。
「そろそろ帰ろうか。」
俺が立ち上がると、一ノ瀬も素直に従った。
「はい。明日も楽しみですね!」
俺はそれに答えない。
しかし、一ノ瀬はそんな俺の腕を取って、先に進み始めた。
公園を出て、再び歩き始める。
いつもの十字路に近づくと、そこが別れ道だということを俺も一ノ瀬も…、お互いに分かっていた。
「先輩、送ってもらってありがとうございます。」
一ノ瀬が十字路で立ち止まった。
「送ったわけじゃない。強引に付き合わされているだけだ。」
「はいはい、そうですね。でも、嬉しいです。明日も学校で会いましょうね。」
「ああ。」
彼女は手を振って、角を曲がっていった。
俺はその後ろ姿を見送った後、自分の道を歩き始めた。
帰り道、スマホを取り出し、いつもの動画を再生しはじめた。
しかし、なぜか以前ほど集中できなかった。画面の向こう側の世界よりも、今日実際に体験した『異なる世界』の方が、妙にリアルに感じられた。
それは『効率的』ではなかった。
確実に『無駄な時間』だった。
しかし、それを日常として受け止めている俺がそこにはいた。
◇
創立祭の準備が続く数日間、俺は放課後になると必ず中等部の教室へと足を運んだ。
初日こそぎこちなかったが、毎日顔を合わせるうちに、徐々に中等部の生徒たちとも簡単な挨拶を交わすようになっていた。
特に休憩所の設営チームのメンバーたちは、最初の緊張感がほぐれ、俺に対しても自然に接するようになっていた。俺自身も、最低限の受け答えはするようになっていた。
一ノ瀬はそんな俺の変化を、嬉しそうに見守っていた。
相変わらず、クラスメイトたちの前では物静かな態度を取りながらも、俺と二人きりになると活発な本来の姿を見せる。
最初は脅迫めいた態度だった彼女も、今では冗談めいた調子で『告白マニア』の話を持ち出すようになっていた。
「先輩、今日も手伝ってくれないと、あの話を広めちゃいますよ?」
そう言いながら笑う一ノ瀬に、俺はもはや恐怖は感じなくなっていた。
むしろ、それは俺たちの間での暗黙の了解のような形になりつつあった。
◇
今日も放課後、俺は中等部の教室へと向かった。いよいよ、創立祭に近づいてきて、準備も佳境に入っていた。
教室に入ると、一ノ瀬が手を振った。
「先輩、今日は装飾の仕上げをします。この看板の色塗りを手伝ってもらえますか?」
彼女に導かれるまま、俺は大きな看板の前に座る。『第三学園中等部創立祭』と書かれた文字の輪郭が描かれており、それに色を塗る作業だった。
黙々と筆を動かす俺の隣で、一ノ瀬も同じように作業に没頭していた。他のメンバーたちは教室の別の場所で、他の装飾品を作っている。
穏やかな沈黙が流れた。ただ、それは不思議と居心地が悪くはなかった。
「先輩は何か趣味ありますか?スマホの動画以外で。」
突然、一ノ瀬が質問してきた。
「特にない。」
短く答える。
「本当ですか?中学時代は読書が好きだったんじゃないですか?」
その言葉に、俺は思わず筆を止めた。確かに中学時代は、図書室で過ごすことが多かった。特にSF小説を好んで読んでいた。だが、それは誰にも話していないはずだ。
ということは、創作ノートの存在からの連想か?
「例のノートからの連想か?」
「ふふっ、どうでしょうね?」
意味ありげに一ノ瀬は笑った。
「悪趣味だな。」
俺は諦めたように答えるほかになかった。
「当たりですか?やっぱり。」
一ノ瀬は嬉しそうに笑った。
「俺のことをどこまで知ってるんだ?」
本気で恐ろしくなってきた。
「先輩が思っている以上に、私は先輩のことを知ってますよ。」
一ノ瀬は意味深な笑みを浮かべた。
「じゃあ言ってみろ。俺の好きな作家は?」
「アーサー・C・クラークですね。『幼年期の終わり』が特に好きで、何度も読み返したことがある。」
正確すぎる答え。それは確かにその通りだった。
「お前、一体何者だ…。」
俺は思わず、声に出してしまった。
「ただの中等部三年生です。」
そう言って、一ノ瀬は再び作業に戻った。
正直、恐ろしかった。
仮に彼女が俺の『創作ノート』の中身を知っていた、としよう。
でも、そこから好きな作家や作品まで連想できるものだろうか?
…いや、俺の好きだった小説と書いていた内容はまったく違った。
とすれば、彼女の答えはどこから出てきたのか?
まさか、エスパーで俺の心を読んでいるのか?
それとも、タイムマシンを使って過去を見に行ったのか?
もはや、俺にはそういった解釈しかできなかった。
ただ、こういった謎めいた事象の真相について、彼女に聞いても『秘密です。』とはぐらかされる。
それももはや、一つの様式美と化していた。
作業が終わり、夕方になると、一ノ瀬は俺を呼んだ。
「先輩、ちょっと付いてきてください。」
彼女に導かれるまま、俺は中等部の校舎内を歩いた。昇降口を過ぎ、中庭を横切り、体育館の裏手へと続く小道に入る。
「どこに連れて行く気だ?」
「特別な場所です。先輩にだけ見せたいんです。」
そう言って、一ノ瀬は足早に進んでいく。俺は半ば呆れながらも、その後を追った。
体育館の裏手を過ぎ、小さな坂を上ると、突然視界が開けた。そこには小高い丘があり、学校全体と、その先に広がる街並みが一望できた。
「ここ、すごいでしょう?」
一ノ瀬が誇らしげに言った。夕日に照らされた街並みは、確かに美しかった。思わず息を呑むほどの景色だった。
「学校裏のこんな場所があったなんて…」
思わず呟いた。
「ほとんどの人は知らないんです。私の秘密の場所なんです。」
一ノ瀬は嬉しそうに言った。そして草の上に腰を下ろし、俺も隣に座るように促した。
夕日が徐々に山の向こうに沈んでいく。オレンジ色の光が街全体を包み込み、窓ガラスに反射して輝いている。
「なぜこんな場所を俺に見せる?」
疑問が口から漏れた。
「先輩にだけ、見せたかったんです。」
一ノ瀬はまっすぐに俺の目を見て言った。
「なぜ俺に?他にもっと親しい友達がいるだろう。」
「先輩との関係は特別なんです。」
その言葉に、妙な鼓動を感じた。
「一ノ瀬、本当のことを話してくれ。なぜ俺のことをそこまで知っている?なぜ俺につきまとう?」
真剣に尋ねる。
一ノ瀬は少し考えるように空を見上げた後、穏やかな声で答えた。
「先輩だって、私に本当のことを言ってないですよね?だから私も言えません。」
一ノ瀬の言葉が心に刺さる。
言い返そうとするが、言葉が見つからない。
彼女の真摯な眼差しに、何かを感じていた。
「時間が遅くなりました。帰りましょう。」
一ノ瀬が立ち上がり、俺も無言で従った。
帰り道、俺と一ノ瀬は並んで歩いた。いつもならイヤホンを耳に差して動画を見ていた時間だが、今日はスマホに手を伸ばす気にもならなかった。
別れる時、一ノ瀬が言った。
「明日も来てくださいね。」
「ああ。」
俺は短く返事をした。