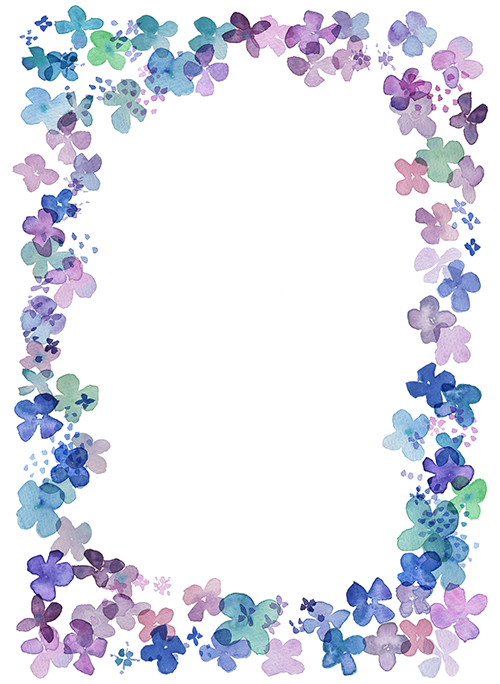あの屋上での約束から一週間が経っていた。
もはや俺の日常は、一ノ瀬と過ごすものとなっていた。
お昼を一緒に食べて、放課後には一緒に帰る。
最初は脅迫めいた形で始まったその関係も、今では奇妙な日常と化していた。
今日も昼のチャイムが鳴ると、俺は半ば諦めたような気持ちで席を立った。教室を出ると、いつものように彼女が廊下で待っていた。
「先輩、こんにちは!今日もお弁当作ってきましたよ。」
一ノ瀬は満面の笑みを浮かべながら、俺の腕に手を伸ばしてきた。
最初の頃は拒否していたその接触も、今では抵抗するエネルギーすら湧かなくなっていた。
「ああ、わかった。行こう。」
屋上への階段を上りながら、俺は考えていた。
あれほど『効率的』な生活にこだわっていた自分が、こうして毎日一ノ瀬と昼食を共にするなんて。
無駄以外の何物でもないはずなのに、なぜか完全に拒絶できない自分がいた。
窓の外を見ると、今日は晴れている。
曇りの日は心配になるが、幸いにも雨の日はまだ一度しかなかった。あの日は屋上に行けず、一ノ瀬に半ば強制的に資料室に連れて行かれた。
結局、俺のお気に入りの隠れ家も彼女に侵食されてしまったのだ。
でも、あの日の資料室での時間は、屋上よりも良かったかもしれない。
彼女はいつもより静かに、本を読みながら隣に座っていた。俺も久しぶりに飽きるまで動画を見られた。
「先輩、今日はウインナーのお花作ってみました!見てくださいね。」
一ノ瀬は途切れることなく話し続けていた。そんな彼女を横目で見ながら、俺は自分の変化を感じていた。以前なら完全にスマホの画面だけを見つめていたはずの時間に、人の顔を見ているのだから。
それも女子生徒の。
それはほんの少し前の自分が聞くと、それはまったくもって信じられないことだっただろう。
まあ、大方美人局というか、騙されているというか。
そういった解釈を過去の俺だったらしているに違いなかった。
いや、もしかしたら、と俺の心は揺れた。
じっと、隣にいる一ノ瀬の横顔見る。
彼女は嬉しそうに微笑んできた。
屈託のない笑顔に嫌悪や嘘はなさそうだ。
だとしたら、この謎めいた彼女の真意とは?
しかし、それは今の俺には分からなかった。
屋上のドアを開けると、いつものように二人だけの空間が広がった。
一ノ瀬はすぐに、お弁当の準備を始める。
これももはや確立された流れだった。
「前回の雨の日、資料室で先輩が動画を見ていたの、気になってました。あんなに集中して見るなんて、何を見てたんですか?」
彼女の唐突な質問に、少し戸惑った。
「別に…。」
「そうですか。まあ、先輩らしい答えですね。」
彼女はどこかあきれ顔だった。
まあ、理解されなくてもいい、と俺は思った。
「今日もいい天気ですね。でも、天気予報だと来週はまた雨が降るみたいですよ。その時はまた資料室で一緒に過ごしましょうね。」
彼女は空を見上げながら言った。俺も無意識に同じ方向を見る。
確かに青空が広がっていた。
こんな何気ない光景へ再び目を向けるようになったのも、彼女と過ごすようになってスマホの時間を取り上げられるようになってからだった。
それがいいことなのか悪いことなのか、俺にはわからなかった。
お弁当の蓋を開けると、彼女の言った通り、ウインナーが花の形に切られていた。
他にも卵焼き、唐揚げ、野菜の炒め物など、色とりどりのおかずが並んでいる。
「いただきます。」
「…いただきます。」
一ノ瀬と俺は食事を開始する。
もはや、これがかなり前から続いているかに思えるような、不思議な感じだった。
「美味しい。」
食べ始めて、思わず言葉が漏れた。
一ノ瀬の作る弁当は毎日違うメニューで、いつも俺の好みに合わせてある。それがどうして可能なのか、未だに謎だった。
「よかった!先輩に喜んでもらえると嬉しいです。雨の日は、お弁当が冷めないよう保温容器を用意しないといけませんね。」
彼女の屈託のない笑顔を見ると、最初に抱いていた恐怖感が薄れていくのを感じる。
それでも、彼女の謎めいた正体については、疑問が消えることはなかった。
「ねえ先輩、もうすぐ中等部の創立祭なんですよ。」
突然、彼女が話題を変えた。
「創立祭?」
「はい。毎年この時期にあるんです。中等部と高等部は別々に開催するんですよ。創立祭の日が雨だと大変なんですけど、でも室内企画もたくさんあるから楽しめますよ。」
俺はなんとなく頷いた。
入学して間もない俺にとって、学校の行事はまだ把握しきれていない。
「楽しいですよ。屋台や出し物があって、きっといい思い出になります。」
一ノ瀬の話し方には、どこか懐かしむような調子があった。
まるで過去の記憶を語るかのようだった。
…お前そんな年齢じゃないだろ、と俺は一人、心の中で突っ込んだ。
「先輩、見に来てくれますか?」
唐突な誘いに、俺は箸を止めた。
「なぜ俺が?」
「だって…」
彼女は少し俯いて考え込むような素振りを見せた。
「先輩と一緒に創立祭を楽しみたいんです。前回の雨の日、資料室で先輩と静かに過ごした時間も素敵でしたけど、楽しいことも一緒に経験したいんです。」
その言葉に込められた感情の強さに、何か奇妙な違和感を覚えた。
まるで彼女にとって、それが単なる学校行事以上の意味を持っているかのようだ。
「わからないな。考えておく。」
曖昧な返事をすると、彼女はニコニコと不思議な笑みを浮かべた。
また、何か悪だくみをしているのかもしれない。
「先輩。そういえば、何か夢はありますか?」
また唐突な質問だ。
一ノ瀬との会話はいつもこうだった。
「特にない。効率的に生きるだけだ。」
それは半分は本心だった。
だが、かつて抱いていた小さな夢のことが頭をよぎった。
創作ノートに書きためた物語のこと。ライトノベル作家になりたいと思っていた頃のこと。
「本当ですか?」
一ノ瀬の目がまっすぐ俺を見つめる。
いや、実は彼女は知っているのかもしれない。
なにしろ、創作ノートのことを知っているのだ。
だとすれば、嘘をつく必要もないのかもしれない。
「…昔は、ちょっとだけ考えていたことならある。」
俺は嘘でもなく、本当でもないことを話した。
「昔の夢ですか?」
「そうかもしれない。ただ、それは別に大したことじゃない。中学のとき少しだけだ。気の迷いのようなものさ。」
言いながら、当時の自分を思い出した。
…ああ、確かにそんな時期があった。
ただ、今になっても、そんな記憶を思い出せる自分に驚きだった。
一ノ瀬の顔が明るくなった。
「やっぱり!先輩は繊細な感性を持っていると思ってましたよ!」
なぜそこまで確信めいた態度を取れるのか。
直観、推察。
そんなものを超えた何か…。
彼女の言動は、いつも俺の理解を超えていた。
「いつか、先輩の書いた物語を読んでみたいです。その先輩が良かったら、それ…。見せてくれませんか?」
「ああ、いつかな。」
「約束ですよ?」
「ああ、いつかな。」
俺は言葉を繰り返す。正直、誰にも見せる気はなかった。
そんな俺の様子を察したのか、彼女は何か遠い目で見ていた。
俺はそんな彼女を見る。
「ああ、そろそろチャイムが鳴りますね。教室に戻りましょうか。」
一ノ瀬がお弁当箱を片付け始めた。
「ああ。」
短い返事をしながらも、俺も内心では同じようなことを感じていた。
この屋上での時間が、いつの間にか心地よくなっていたのだ。
階段を下りながら、一ノ瀬が言った。
「あ、そうだ。先輩、この後、私のクラスは創立祭の話し合いがあるんです。少し長引くかもしれないけど、放課後一緒に帰りましょう?」
もう日課となっていたため、特に断る理由もなかった。
「ああ、いいよ。」
教室の前で別れるとき、彼女は嬉しそうに手を振った。
「じゃあ、放課後に先輩の教室の前で待ってますね!」
◇
授業が終わり、放課後のチャイムが鳴った。
教室には生徒たちがまだ残っていた。
部活動の準備をする者、友達と下校の約束をする者。
彼らと違い、俺はただ鞄をまとめるだけだった。
教室を出ると、案の定、一ノ瀬が廊下で待っていた。
もう誰にも見られてもおかしくないと思えるほど、この光景は日常となっていた。
「先輩、お疲れ様です!」
彼女は明るく声をかけてきた。
「ああ。話し合いはどうだった?」
思いがけない質問を自分がしたことに、少し驚いた。以前なら絶対にしなかった会話だ。
「うーん。まあ、いろいろ決まりましたよ。それでね、実は先輩にお願いがあるんです!」
彼女の表情から、何か重要なことを言い出しそうな予感がした。
校門を出て、いつもの帰り道を歩き始める。一ノ瀬はそわそわしているようだった。
「私のクラスは休憩所担当で、椅子やテーブル、テントなどを運んだり設置したりする作業があるんです。それで、人手が足りなくて…。」
まあ、ある意味で予想通りだった。
創立祭の手伝いを頼まれるんだな。
しかし、そんな面倒なことになるとは…。
正直、創立祭当日にいっしょに回ってほしい、くらいで終わるかと踏んでいたのだが。
「断る。そんな非効率的なことをする暇はない。」
きっぱりと断る。
「でも先輩、この私が苦しんでいるんです。手伝おう、とかそういう気にはならないんですか?」
「そうかな?では、なぜ俺が手伝わなければならないんだ?」
俺は淡々と答えた。
「いつも先輩は私の作ったお弁当、食べてますよね?」
「…。」
ああ、そう来たか。
「いや、勝手に作ってきているだけだろう?」
「そうですか!もぉー。」
一ノ瀬はそう言って、頬っぺたをリスのように膨らませた。
「そうだろ。だから、俺は手伝わない。」
俺は自らの意思を伝えた。
彼女の様子が変わった。
じっとこちらを見ている。
プルプルと何かの感情を抑えているかのような雰囲気だった。
「違うんもん!」
「なにが?」
一ノ瀬がいきなり足を踏み鳴らし始めた。
まるで駄々をこねる子供だった。
「ダメです!ダメです!先輩は私と一緒にクラスの出し物の手伝いをするんです!」
目の前の一ノ瀬は幼児退行していた。
さすがにこの反応は初めてだったので、ちょっと驚いた。
ふむ、どうするか?
「どうして?同じクラスのやつもいるだろう?俺みたいな上級生が手伝うと何かおかしいだろ?」
俺は冷静な言葉で落ち着かせようとした。
内容は、さりげなく作業への距離が入っているのが、俺らしい効率的なものだったが。
「ダメです!絶対に一緒に手伝いをするんですよ!」
「だから…どうして?」
俺がそういうと。
一ノ瀬が足踏みを止め、俺をじっと見てきた。
「私が先輩と一緒にいたいからです。」
素直な言葉に、一瞬言葉が出なかった。
「そんな理由で俺の時間を奪うのはなぁ…。」
「はぁ、先輩…。」
一ノ瀬は呆れたように言葉を続けた。
「もし手伝ってくれないなら、『告白マニア』であることを…」
一ノ瀬の次の一手。
うーん、まあ妥当な…。
俺の知性が心の中でそう小さく呟いた。
またあの脅し。最初の頃は恐れていたが、今となっては少し慣れてきた気がする。
仮に今、それをバラされたからといっても、何か目の前の後輩がいるし。
…?
…?…?
…?…?…?…?
えっ?
俺は一人、自分の心から浮かんできた、その自分の思考に驚いてしまった。
「どうしたんですか、先輩?」
「ああ、いや、その…。」
そう答えるしかできない。
俺は自分の思考がまとまらなくなった。
「大丈夫ですか?そんなに噂が広まるのが、嫌でしたか?」
心配した様子で一ノ瀬が腕を掴んできた。
いや、違うんだ。
違う、そういう意味じゃない。
「えっと。だな。違うんだ。」
俺は辛うじて言葉を繋げた。そして、一ノ瀬を見た。
「何がですか?」
じっと、彼女は俺を見ていた。
「いや、そうだな。えっと。…分かった。手伝う。」
俺は話が混乱するので、そう答えると、一ノ瀬の顔が明るくなった。
「本当ですか?ありがとうございます!先輩と一緒に準備できるなんて、嬉しいです!」
彼女の喜びようは、とってもわかりやすい。
そこまで喜ぶことなのだろうか。
「いつから始まるんだ?」
「明日の放課後からです。中等部の第二教室棟に来てください。」
俺は無言で頷いた。
ため息をつきそうになるのを必死で抑える。
これで確実に『効率的な放課後』は消滅した。
「先輩、本当にありがとうございます。きっと楽しいですよ。」
彼女の無邪気な笑顔を見ていると、何か言い返す気力も失せる。
「ああ、まあ。約束は守る。」
いつもの十字路に着き、別れの時間となった。
「じゃあ、明日も屋上でお昼を食べて、放課後は創立祭の準備をして、一緒に帰りましょうね!」
一ノ瀬は一日の予定を全て決めてしまったかのように言った。
「…わかった。」
俺はそう答えるしかなかった。
「約束ですよ!」
彼女は手を振って別の道へと曲がっていった。
一人になった道を歩きながら、俺は考えていた。
なぜ自分はここまで彼女の言いなりになっているのだろう。
確かに最初は脅迫めいたものがあったが、今となっては、もはやそれだけではない気がする。
それにあの時の自分自身の思考。
『仮に今、それをバラされたからといっても、この後輩がいるし。』
なんだこれは?
俺の中で何かが変わり始めている。
まさか、この一ノ瀬という後輩の存在が俺にとって…。
いや、その考えは早急すぎる。まだ何も分からない。
ただ、最初に抱いていた恐怖感や拒絶感が、いつの間にか薄れていることは確かだった。
あれほど効率を追求していた俺が、非効率的な創立祭の準備を手伝うことに同意するなんて。
もはや自分でも理解できない行動だ。
それでも、彼女の嬉しそうな顔を思い出すと、不思議と悪い気はしない。
その感覚が、ますます俺を混乱させた。
結局、明日から俺の放課後は彼女のために費やされることになる。
効率性とは程遠い時間の使い方だが、どこか期待している自分がいることに気づいて、俺は軽く頭を振った。
これはきっと、俺の『効率的』な生活が一ノ瀬ナズナという少女によって、少しずつ崩されていっている証拠だろう。
もう後戻りはできないのかもしれない。
そして不思議なことに、それを完全に拒絶できない自分がいた。
家に着きながら、俺はそんなことを考えていた。
これから先、一体どうなるのだろう。
俺の『効率的』な学園生活は、もう二度と戻ってこないのかもしれない。
しかし、一方で別の観点から意味不明なことを思う自分がいることに、俺は静かに驚いていた。
もはや俺の日常は、一ノ瀬と過ごすものとなっていた。
お昼を一緒に食べて、放課後には一緒に帰る。
最初は脅迫めいた形で始まったその関係も、今では奇妙な日常と化していた。
今日も昼のチャイムが鳴ると、俺は半ば諦めたような気持ちで席を立った。教室を出ると、いつものように彼女が廊下で待っていた。
「先輩、こんにちは!今日もお弁当作ってきましたよ。」
一ノ瀬は満面の笑みを浮かべながら、俺の腕に手を伸ばしてきた。
最初の頃は拒否していたその接触も、今では抵抗するエネルギーすら湧かなくなっていた。
「ああ、わかった。行こう。」
屋上への階段を上りながら、俺は考えていた。
あれほど『効率的』な生活にこだわっていた自分が、こうして毎日一ノ瀬と昼食を共にするなんて。
無駄以外の何物でもないはずなのに、なぜか完全に拒絶できない自分がいた。
窓の外を見ると、今日は晴れている。
曇りの日は心配になるが、幸いにも雨の日はまだ一度しかなかった。あの日は屋上に行けず、一ノ瀬に半ば強制的に資料室に連れて行かれた。
結局、俺のお気に入りの隠れ家も彼女に侵食されてしまったのだ。
でも、あの日の資料室での時間は、屋上よりも良かったかもしれない。
彼女はいつもより静かに、本を読みながら隣に座っていた。俺も久しぶりに飽きるまで動画を見られた。
「先輩、今日はウインナーのお花作ってみました!見てくださいね。」
一ノ瀬は途切れることなく話し続けていた。そんな彼女を横目で見ながら、俺は自分の変化を感じていた。以前なら完全にスマホの画面だけを見つめていたはずの時間に、人の顔を見ているのだから。
それも女子生徒の。
それはほんの少し前の自分が聞くと、それはまったくもって信じられないことだっただろう。
まあ、大方美人局というか、騙されているというか。
そういった解釈を過去の俺だったらしているに違いなかった。
いや、もしかしたら、と俺の心は揺れた。
じっと、隣にいる一ノ瀬の横顔見る。
彼女は嬉しそうに微笑んできた。
屈託のない笑顔に嫌悪や嘘はなさそうだ。
だとしたら、この謎めいた彼女の真意とは?
しかし、それは今の俺には分からなかった。
屋上のドアを開けると、いつものように二人だけの空間が広がった。
一ノ瀬はすぐに、お弁当の準備を始める。
これももはや確立された流れだった。
「前回の雨の日、資料室で先輩が動画を見ていたの、気になってました。あんなに集中して見るなんて、何を見てたんですか?」
彼女の唐突な質問に、少し戸惑った。
「別に…。」
「そうですか。まあ、先輩らしい答えですね。」
彼女はどこかあきれ顔だった。
まあ、理解されなくてもいい、と俺は思った。
「今日もいい天気ですね。でも、天気予報だと来週はまた雨が降るみたいですよ。その時はまた資料室で一緒に過ごしましょうね。」
彼女は空を見上げながら言った。俺も無意識に同じ方向を見る。
確かに青空が広がっていた。
こんな何気ない光景へ再び目を向けるようになったのも、彼女と過ごすようになってスマホの時間を取り上げられるようになってからだった。
それがいいことなのか悪いことなのか、俺にはわからなかった。
お弁当の蓋を開けると、彼女の言った通り、ウインナーが花の形に切られていた。
他にも卵焼き、唐揚げ、野菜の炒め物など、色とりどりのおかずが並んでいる。
「いただきます。」
「…いただきます。」
一ノ瀬と俺は食事を開始する。
もはや、これがかなり前から続いているかに思えるような、不思議な感じだった。
「美味しい。」
食べ始めて、思わず言葉が漏れた。
一ノ瀬の作る弁当は毎日違うメニューで、いつも俺の好みに合わせてある。それがどうして可能なのか、未だに謎だった。
「よかった!先輩に喜んでもらえると嬉しいです。雨の日は、お弁当が冷めないよう保温容器を用意しないといけませんね。」
彼女の屈託のない笑顔を見ると、最初に抱いていた恐怖感が薄れていくのを感じる。
それでも、彼女の謎めいた正体については、疑問が消えることはなかった。
「ねえ先輩、もうすぐ中等部の創立祭なんですよ。」
突然、彼女が話題を変えた。
「創立祭?」
「はい。毎年この時期にあるんです。中等部と高等部は別々に開催するんですよ。創立祭の日が雨だと大変なんですけど、でも室内企画もたくさんあるから楽しめますよ。」
俺はなんとなく頷いた。
入学して間もない俺にとって、学校の行事はまだ把握しきれていない。
「楽しいですよ。屋台や出し物があって、きっといい思い出になります。」
一ノ瀬の話し方には、どこか懐かしむような調子があった。
まるで過去の記憶を語るかのようだった。
…お前そんな年齢じゃないだろ、と俺は一人、心の中で突っ込んだ。
「先輩、見に来てくれますか?」
唐突な誘いに、俺は箸を止めた。
「なぜ俺が?」
「だって…」
彼女は少し俯いて考え込むような素振りを見せた。
「先輩と一緒に創立祭を楽しみたいんです。前回の雨の日、資料室で先輩と静かに過ごした時間も素敵でしたけど、楽しいことも一緒に経験したいんです。」
その言葉に込められた感情の強さに、何か奇妙な違和感を覚えた。
まるで彼女にとって、それが単なる学校行事以上の意味を持っているかのようだ。
「わからないな。考えておく。」
曖昧な返事をすると、彼女はニコニコと不思議な笑みを浮かべた。
また、何か悪だくみをしているのかもしれない。
「先輩。そういえば、何か夢はありますか?」
また唐突な質問だ。
一ノ瀬との会話はいつもこうだった。
「特にない。効率的に生きるだけだ。」
それは半分は本心だった。
だが、かつて抱いていた小さな夢のことが頭をよぎった。
創作ノートに書きためた物語のこと。ライトノベル作家になりたいと思っていた頃のこと。
「本当ですか?」
一ノ瀬の目がまっすぐ俺を見つめる。
いや、実は彼女は知っているのかもしれない。
なにしろ、創作ノートのことを知っているのだ。
だとすれば、嘘をつく必要もないのかもしれない。
「…昔は、ちょっとだけ考えていたことならある。」
俺は嘘でもなく、本当でもないことを話した。
「昔の夢ですか?」
「そうかもしれない。ただ、それは別に大したことじゃない。中学のとき少しだけだ。気の迷いのようなものさ。」
言いながら、当時の自分を思い出した。
…ああ、確かにそんな時期があった。
ただ、今になっても、そんな記憶を思い出せる自分に驚きだった。
一ノ瀬の顔が明るくなった。
「やっぱり!先輩は繊細な感性を持っていると思ってましたよ!」
なぜそこまで確信めいた態度を取れるのか。
直観、推察。
そんなものを超えた何か…。
彼女の言動は、いつも俺の理解を超えていた。
「いつか、先輩の書いた物語を読んでみたいです。その先輩が良かったら、それ…。見せてくれませんか?」
「ああ、いつかな。」
「約束ですよ?」
「ああ、いつかな。」
俺は言葉を繰り返す。正直、誰にも見せる気はなかった。
そんな俺の様子を察したのか、彼女は何か遠い目で見ていた。
俺はそんな彼女を見る。
「ああ、そろそろチャイムが鳴りますね。教室に戻りましょうか。」
一ノ瀬がお弁当箱を片付け始めた。
「ああ。」
短い返事をしながらも、俺も内心では同じようなことを感じていた。
この屋上での時間が、いつの間にか心地よくなっていたのだ。
階段を下りながら、一ノ瀬が言った。
「あ、そうだ。先輩、この後、私のクラスは創立祭の話し合いがあるんです。少し長引くかもしれないけど、放課後一緒に帰りましょう?」
もう日課となっていたため、特に断る理由もなかった。
「ああ、いいよ。」
教室の前で別れるとき、彼女は嬉しそうに手を振った。
「じゃあ、放課後に先輩の教室の前で待ってますね!」
◇
授業が終わり、放課後のチャイムが鳴った。
教室には生徒たちがまだ残っていた。
部活動の準備をする者、友達と下校の約束をする者。
彼らと違い、俺はただ鞄をまとめるだけだった。
教室を出ると、案の定、一ノ瀬が廊下で待っていた。
もう誰にも見られてもおかしくないと思えるほど、この光景は日常となっていた。
「先輩、お疲れ様です!」
彼女は明るく声をかけてきた。
「ああ。話し合いはどうだった?」
思いがけない質問を自分がしたことに、少し驚いた。以前なら絶対にしなかった会話だ。
「うーん。まあ、いろいろ決まりましたよ。それでね、実は先輩にお願いがあるんです!」
彼女の表情から、何か重要なことを言い出しそうな予感がした。
校門を出て、いつもの帰り道を歩き始める。一ノ瀬はそわそわしているようだった。
「私のクラスは休憩所担当で、椅子やテーブル、テントなどを運んだり設置したりする作業があるんです。それで、人手が足りなくて…。」
まあ、ある意味で予想通りだった。
創立祭の手伝いを頼まれるんだな。
しかし、そんな面倒なことになるとは…。
正直、創立祭当日にいっしょに回ってほしい、くらいで終わるかと踏んでいたのだが。
「断る。そんな非効率的なことをする暇はない。」
きっぱりと断る。
「でも先輩、この私が苦しんでいるんです。手伝おう、とかそういう気にはならないんですか?」
「そうかな?では、なぜ俺が手伝わなければならないんだ?」
俺は淡々と答えた。
「いつも先輩は私の作ったお弁当、食べてますよね?」
「…。」
ああ、そう来たか。
「いや、勝手に作ってきているだけだろう?」
「そうですか!もぉー。」
一ノ瀬はそう言って、頬っぺたをリスのように膨らませた。
「そうだろ。だから、俺は手伝わない。」
俺は自らの意思を伝えた。
彼女の様子が変わった。
じっとこちらを見ている。
プルプルと何かの感情を抑えているかのような雰囲気だった。
「違うんもん!」
「なにが?」
一ノ瀬がいきなり足を踏み鳴らし始めた。
まるで駄々をこねる子供だった。
「ダメです!ダメです!先輩は私と一緒にクラスの出し物の手伝いをするんです!」
目の前の一ノ瀬は幼児退行していた。
さすがにこの反応は初めてだったので、ちょっと驚いた。
ふむ、どうするか?
「どうして?同じクラスのやつもいるだろう?俺みたいな上級生が手伝うと何かおかしいだろ?」
俺は冷静な言葉で落ち着かせようとした。
内容は、さりげなく作業への距離が入っているのが、俺らしい効率的なものだったが。
「ダメです!絶対に一緒に手伝いをするんですよ!」
「だから…どうして?」
俺がそういうと。
一ノ瀬が足踏みを止め、俺をじっと見てきた。
「私が先輩と一緒にいたいからです。」
素直な言葉に、一瞬言葉が出なかった。
「そんな理由で俺の時間を奪うのはなぁ…。」
「はぁ、先輩…。」
一ノ瀬は呆れたように言葉を続けた。
「もし手伝ってくれないなら、『告白マニア』であることを…」
一ノ瀬の次の一手。
うーん、まあ妥当な…。
俺の知性が心の中でそう小さく呟いた。
またあの脅し。最初の頃は恐れていたが、今となっては少し慣れてきた気がする。
仮に今、それをバラされたからといっても、何か目の前の後輩がいるし。
…?
…?…?
…?…?…?…?
えっ?
俺は一人、自分の心から浮かんできた、その自分の思考に驚いてしまった。
「どうしたんですか、先輩?」
「ああ、いや、その…。」
そう答えるしかできない。
俺は自分の思考がまとまらなくなった。
「大丈夫ですか?そんなに噂が広まるのが、嫌でしたか?」
心配した様子で一ノ瀬が腕を掴んできた。
いや、違うんだ。
違う、そういう意味じゃない。
「えっと。だな。違うんだ。」
俺は辛うじて言葉を繋げた。そして、一ノ瀬を見た。
「何がですか?」
じっと、彼女は俺を見ていた。
「いや、そうだな。えっと。…分かった。手伝う。」
俺は話が混乱するので、そう答えると、一ノ瀬の顔が明るくなった。
「本当ですか?ありがとうございます!先輩と一緒に準備できるなんて、嬉しいです!」
彼女の喜びようは、とってもわかりやすい。
そこまで喜ぶことなのだろうか。
「いつから始まるんだ?」
「明日の放課後からです。中等部の第二教室棟に来てください。」
俺は無言で頷いた。
ため息をつきそうになるのを必死で抑える。
これで確実に『効率的な放課後』は消滅した。
「先輩、本当にありがとうございます。きっと楽しいですよ。」
彼女の無邪気な笑顔を見ていると、何か言い返す気力も失せる。
「ああ、まあ。約束は守る。」
いつもの十字路に着き、別れの時間となった。
「じゃあ、明日も屋上でお昼を食べて、放課後は創立祭の準備をして、一緒に帰りましょうね!」
一ノ瀬は一日の予定を全て決めてしまったかのように言った。
「…わかった。」
俺はそう答えるしかなかった。
「約束ですよ!」
彼女は手を振って別の道へと曲がっていった。
一人になった道を歩きながら、俺は考えていた。
なぜ自分はここまで彼女の言いなりになっているのだろう。
確かに最初は脅迫めいたものがあったが、今となっては、もはやそれだけではない気がする。
それにあの時の自分自身の思考。
『仮に今、それをバラされたからといっても、この後輩がいるし。』
なんだこれは?
俺の中で何かが変わり始めている。
まさか、この一ノ瀬という後輩の存在が俺にとって…。
いや、その考えは早急すぎる。まだ何も分からない。
ただ、最初に抱いていた恐怖感や拒絶感が、いつの間にか薄れていることは確かだった。
あれほど効率を追求していた俺が、非効率的な創立祭の準備を手伝うことに同意するなんて。
もはや自分でも理解できない行動だ。
それでも、彼女の嬉しそうな顔を思い出すと、不思議と悪い気はしない。
その感覚が、ますます俺を混乱させた。
結局、明日から俺の放課後は彼女のために費やされることになる。
効率性とは程遠い時間の使い方だが、どこか期待している自分がいることに気づいて、俺は軽く頭を振った。
これはきっと、俺の『効率的』な生活が一ノ瀬ナズナという少女によって、少しずつ崩されていっている証拠だろう。
もう後戻りはできないのかもしれない。
そして不思議なことに、それを完全に拒絶できない自分がいた。
家に着きながら、俺はそんなことを考えていた。
これから先、一体どうなるのだろう。
俺の『効率的』な学園生活は、もう二度と戻ってこないのかもしれない。
しかし、一方で別の観点から意味不明なことを思う自分がいることに、俺は静かに驚いていた。