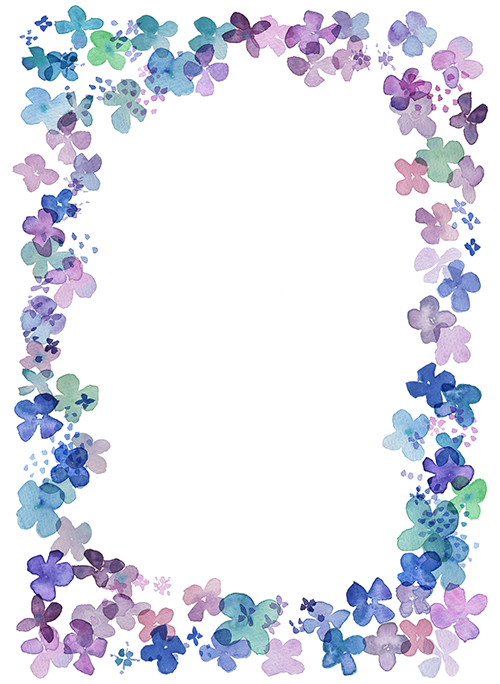翌日の朝、俺は重い頭でベッドから起き上がった。
普段なら五回目のスヌーズでようやく目を覚ますのに、今日は最初のアラームで目が覚めてしまった。
昨日の一ノ瀬との約束が、頭から離れなかったからだ。
朝の準備をしながら、今日という日を回避できないかと考え続けた。
ああ、今日雨が降れば、屋上で食べることはできないだろうに。
そんな思考に憑りつかれた。
しかし、天気に関していえば快晴。
だとすれば、俺が学校を休むという選択肢もある。
ただ、これらは結局のところ、単なる先延ばしに過ぎない。
いずれ顔を合わせれば、同じことだ。
食卓では、アカネが俺の様子を不思議そうに見ていた。
「お兄ちゃん、動画、見ないんだ?」
「ああ…。」
いつも通りの返事をしたつもりだったが、何かがおかしかったのだろう。
アカネは、俺をちょっとだけ見つめた後に、再び食事に戻った。
それから無言で朝食を食べ終えた。
今日はいつものように動画を見る気分になれなかった。
何かに追い詰められているような感覚。まるで処刑台に向かう死刑囚のような心境だった。
学校に向かう途中、一ノ瀬ナズナという後輩のことを考えていた。
あいつはいったい何者なのか。
なぜ俺のことをあそこまで知っているのか。そして、なぜ俺に執着するのか。
学校に着いてからも、その不安は消えなかった。
教室に入り、いつもの席に着く。誰も俺に目を向けない。
いつもならそれが心地よいのに、今日は違った。むしろ、この透明な存在が今日を境に崩れ去るのではないかという恐れがあった。
授業中も上の空だった。ただ時間が過ぎるのを待っているだけ。指名されても、なんとか答えはしたものの、内容は覚えていない。
そして、昼休み。
チャイムが鳴った瞬間、俺は憂鬱な気持ちに支配された。
いつもなら、さっと教室を抜け出して資料室へ向かうところだが、今日は違う。
約束の場所、屋上へと向かわなければならない。
ゆっくりと席を立ち、廊下に出る。
階段に向かおうとしたとき、背後から声がした。
「先輩!」
一ノ瀬だった。
いつの間にここまで来ていたのか。彼女は満面の笑みを浮かべていた。
「約束、覚えてましたか?」
「…ああ。」
忘れるわけがない。忘れたくても忘れられない約束だ。
「じゃあ、行きましょう!」
そう言って、彼女は俺の腕に手を回した。昨日と同じ状況だ。
俺は抵抗せず、ただ黙って彼女に連れていかれるままになった。
廊下では何人かの生徒が俺たちを見て驚いていたが、後輩は全く気にしない様子だった。
むしろ、俺を連れていることを誇示しているかのようだ。
屋上へと続く階段を上る。足が鉛のように重い。
彼女は俺の腕を引っ張りながら、何やら楽しげに話していた。
「今日ね、お弁当作ってきたんですよ。先輩の好きそうなものばかり入れました。」
なぜ俺の好みを知っているのか、と問うのもむなしい気がした。もう驚かないよう自分に言い聞かせる。
屋上のドアを開けると、外は晴れていた。
風が心地良く吹き、少なくとも天気だけは最高だった。
後輩は屋上の隅に敷物を広げ、そこに座るよう促した。
「さあ、ここに座ってください。」
俺は黙って座る。彼女は俺の隣に座り、バッグから取り出した二段のお弁当箱を開けた。
「じゃーん!どうですか?」
中には唐揚げ、卵焼き、ウインナー、ブロッコリーの炒め物など、色とりどりのおかずが並んでいた。
確かに俺の好きなものばかりだ。
…その正確さに、また彼女への異様な恐怖を感じてしまった。
「いただきます。」
一ノ瀬が先に手を合わせ、俺も小さく『いただきます』と呟いた。
一口食べると、予想以上においしかった。
唐揚げはカリッと揚がり、中はジューシー。卵焼きは甘さ控えめで、俺好みの味付けだった。
「おいしい…。」
思わず声が漏れた。
「本当ですか?よかった!」
後輩は本当に嬉しそうに微笑んだ。この笑顔が作り物だとしたら、相当の演技力だ。
沈黙の中、俺たちは食事を続けた。俺はなるべく早く食べ終わって、この場を去りたかった。
一方、後輩はゆっくりと食べながら、時折俺の顔を見ていた。
やがて、彼女が話し始めた。
「先輩、少しだけ話していいですか?」
「…何を?」
「先輩がどうして効率を重視するようになったのか、聞かせてくださいよ!」
俺はため息をついた。
もはや、彼女はこの答えを知っているのではないか?
俺はそんなことを思った。
「別に大した理由はない。無駄を省くほうが合理的だから、それだけだ。」
「本当ですか?」
後輩の目がまっすぐ俺を見つめる。
「…そうだ。」
「でも?本当は?」
その言葉に、思わず箸を止めた。
なぜ彼女はこうも俺の心の奥を読み取ることができるのか。
「ただ、もう一度傷つくのが怖いだけなんじゃないですか?」
返す言葉が見つからなかった。
ただ黙って弁当を食べ続けるしかない。
「先輩の創作ノート、私、読みたいです。」
俺は読ませたくなかった。
誰にも…。
「………。」
「私は先輩の書いたものを読みたいんです。きっと素敵な物語なんでしょうね。」
そういう一ノ瀬には、馬鹿にしたような様子はない。
本気で俺の書いたモノが読みたそうだった。
その様子に俺は苦笑いした。
「大したものじゃない。ただの中二病全開の駄文だ。」
「いいえ、そんなことないと思います。先輩はきっと、繊細で、深い洞察力を持っているはずです。」
なぜそう断言できるのか。俺のことを知り尽くしているかのような口ぶり。どこまでも不可解な少女だ。
「なあ、正直に答えてくれ。」
決意を固めて、俺は質問した。
「お前、なぜ俺のことをそこまで知っている?ストーカーか?それとも…。」
後輩は少し考え込むような素振りを見せた後、ゆっくりと答えた。
「ただの直感です。」
「直感で創作ノートの存在までわかるか?」
「それは…いつか説明します。今はまだその時じゃないんです。」
もどかしい返答だったが、今日はこれ以上追求しても無駄だと感じた。
弁当を食べ終えると、後輩は丁寧に箱を片付け始めた。
「ありがとうございました。おいしかったですか?」
「ああ、うまかった。」
素直に認めると、彼女の顔が喜びで輝いた。
「本当ですか?嬉しいです!」
こんな風に喜ばれると、悪い気はしない。むしろ、少し心が軽くなったような気がした。
「これで約束は果たしたな。」
俺はそう言って立ち上がった。これで終わりのはずだ。彼女との接触はこれきりだと思っていた。
「あ、まだです。」
後輩が俺の袖を引っ張った。
「何?お前との約束は昼食を共にすることだっただろう。」
「はい、でも、明日も一緒に食べてほしいんです。」
俺は唖然とした。
「何を言ってる?一度だけの約束だったはずだ。」
「そうでしたっけ?私はそんな約束していませんよ。」
彼女の顔には悪戯っぽい笑みが浮かんでいた。
「嘘だ!昨日、お前は…。」
「昨日は『明日、屋上で一緒にお昼を食べましょう』と言っただけですよ。一度だけとは言ってません。」
確かに、彼女はそう明言していなかった。俺が勝手に『一度だけ』と思い込んでいたのだ。
「冗談だろ…。」
「冗談じゃありません。明日も来てください。もし来なかったら…。」
言外に『秘密を暴露する』という脅しが込められている。
そう、俺は騙されたのだ。
それに気が付いたとき、絶望的な気分になった。
「どこまで俺を追い詰めるつもりだ?」
「追い詰めるなんて、そんなつもりはありません。ただ、先輩と一緒にいたいだけですよ?」
その言葉に、複雑な感情が湧き上がった。
恐怖と怒りの中に、少しだけ、諦めのようなものを感じた。
ただ、一つ言えるのは、誰かが本気で自分を求めてくれている。
それは考えてみると、俺の人生で初めての経験なような気がした。
ただ、問題は、その相手がストーカーだ、という点にあるのだけれど。
「わかった…明日も来る。」
諦めたように俺がそういうと、彼女は嬉しそうに手を叩いた。
「約束ですよ!明日も美味しいお弁当作ってきます!」
チャイムが鳴り、昼休みの終わりを告げる。
俺たちは屋上を後にした。階段を下りながら、後輩が言った。
「先輩、今日は楽しかったです。ありがとうございました。」
「そうか。」
俺はそれだけ言った。
正直、もうあまり関わりたくはない。
しかし、俺にとって残念なことがあった。
それは、もはや彼女と関わらないことは不可能だろう、と理解できるだけの知性が俺にあることだった。
明日からは、後輩との学生生活が始まるのだ。
…間違いなく。
重い気もしたし、効率的ではないというのは分かり切っていた。
ただ、もうそれすらもどうでもいい気がしてきた。
◇
すべての授業が終わり、俺は何も考えずに教室を出た。
他の生徒たちはグループになって下校の準備をしている。あいつらが帰った後にゆっくり出るつもりだった。
廊下に一歩踏み出した瞬間、突然袖を引っ張られた。
「先輩。一緒に帰りますよ!」
見覚えのある声だった。
振り向くと、一ノ瀬ナズナという不可解な中等部の後輩が立っていた。細身の体に合わない力強さで俺の腕を掴んできた。
「おい!馬鹿やめろ。危ない。」
驚きと混乱で、それ以上言葉がでなかった。
彼女との約束はお昼だけ、なはず。
なぜ彼女は高等部の教室前にいるのか。
「先輩を待っていたんです。一緒に帰りましょう!」
あまりにも自然な態度に、言葉が見つからない。
この後輩との屋上での約束は明日のことだ。
今日はもう関わりたくなかった。
俺は必至で言い訳を考えた。
「断る。今日は用事がある。」
即席の理由を言い放った。
実際には何の予定もないが、とにかくこの不気味な後輩から離れたかった。
「えー、また嘘ついてます?」
彼女は俺の目をじっと見て言った。
まるで心を見透かされているようで不快だった。
「嘘じゃない。本当に用事がある。」
「じゃあ、何の用事ですか?」
追求されて言葉に詰まった。
「…それはお前に関係ない。」
「関係あります!先輩の帰りを邪魔する用事なんて、邪魔する価値がありますよ!」
後輩は屈託のない笑顔で言った。その表情からは脅迫をした人間の面影はまったく感じられない。
だが、彼女がどこまで俺の秘密を知っているかを考えると、背筋が寒くなる。
「とにかく離せ。人に見られたら変に思われる。」
廊下には他の生徒たちがまだいた。高等部の男子が中等部の女子に腕を掴まれている姿なんて、確実に噂になる。
それも悪質な噂だ。
…ああ、それはとても嫌だった。
「大丈夫ですよ。先輩って学校では透明人間みたいなものでしょ?」
その言葉に、皮肉な真実を感じた。
確かに俺は存在感を消すことに長けている。
でも、それでも今の状況はリスクが高すぎる。
「いいから離せ。」
腕を振り払おうとしたが、彼女の握力は想像以上に強かった。
「離しません。一緒に帰りましょう。先輩のお家はどこですか?」
「そんなこと、誰が教えるか!」
突然のことに動揺して声が大きくなった。
いくつかの視線が俺たちに向けられる。
これ以上抵抗すると余計に目立ってしまう。
結局、俺は観念して後輩の要求に従うことにした。
「…わかった。少しだけなら一緒に歩いてやる。でも学校の外までだ。」
「やった!ありがとうございます、先輩!」
喜びを露わにする後輩の反応は、完全に俺の脅しを忘れているようだった。
ただの明るい後輩のようだ。
だが、俺は忘れない。
あの屋上での脅し。
『先輩の秘密が今の学校中に広まったらどうなるでしょうね』と言った彼女の言葉を。
校舎を出て中庭を通り、校門へと向かった。
一ノ瀬は終始俺の腕を離さず、まるで恋人同士のように歩いている。
「おい、もう離せ。これ以上くっついていると誤解される。」
「誤解?どんな誤解ですか?」
彼女は無邪気な表情で聞いてきた。本当に分からないのか、それとも分かっていて聞いているのか。
「そんなこと…説明するまでもないだろ。」
思わず顔が熱くなるのを感じた。恥ずかしさと苛立ちが混ざった感情だ。
「ふーん。」
一ノ瀬はニヤリと笑った。何かを企んでいる表情に見えた。
校門を出ると、彼女はようやく俺の腕を離した。少し肩の力が抜ける。
「どっちに帰るんですか?」
「お前こそどっちだ?」
警戒心を解かないまま尋ねると、彼女は北の方角を指さした。
「あっちです。住宅街の方。」
俺も同じ方向だった。これは偶然なのか、それとも…。
「…俺もそっちだ。」
「本当ですか?じゃあやっぱり一緒に帰れますね!」
彼女は小さく拍手をして喜んだ。あまりにも都合の良い一致に疑念が湧いた。
「お前、本当にそっちに住んでるのか?」
「もちろんです!嘘なんてつきませんよ。」
確信に満ちた彼女の言葉に、それ以上追求する気力がなかった。
並んで歩き始めると、彼女は話し続けた。
「先輩は毎日一人で帰ってるんですか?」
「ああ。それが効率的だからな。」
「友達とは帰らないんですか?」
「友達なんていない。それに、人と一緒に帰るのは時間の無駄だ。」
そう言い切ったが、今まさに後輩と一緒に帰っている矛盾に気づかないはずがなかった。
「時間の無駄?本当にそう思ってるんですか?」
彼女の問いかけには何か深い意味がありそうだった。
「当然だ。無駄話をして時間を潰すより、一人で早く帰って自分の時間を確保する方が効率的だろう。」
「先輩はその『効率的』って言葉が好きですね。」
彼女は少し首を傾げながら言った。
「効率を追求することで、無駄な時間を省ける。それだけのことだ。」
「でも今、私と一緒に帰っていますよね?これは効率的じゃないですか?」
鋭い指摘に言葉に詰まった。
「…特別な状況だ。お前が無理やり付いてきただけで、俺が望んだわけじゃない。」
「そうですか?でも、抵抗してないじゃないですか。」
一ノ瀬の目はまっすぐに俺を見ていた。
まるで心の奥底まで見透かされているようで居心地が悪い。
「…抵抗したって無駄だと思っただけだ。」
弱々しい言い訳だった。
住宅街に入った。この辺りは静かで、通学する学生の姿もまばらになってきた。
「先輩って本当はどんな人なんですか?」
突然の質問に戸惑った。
「どういう意味だ?」
「みんなの前では無口で存在感を消しているけど、本当の先輩はそんな人じゃないと思うんです。」
彼女の洞察力はあまりにも鋭すぎる。まるで長年俺を観察してきたかのようだ。
「勝手な想像をするな。俺はいつも俺だ。」
「本当ですか?でも、昔は違ったんですよね?」
気が付くと、彼女はまた俺の過去に触れようとしていた。
「…話題を変えろ。」
警戒心を強めながら答えた。彼女が俺の中学時代の出来事をどこまで知っているのか。それを考えるだけで恐ろしかった。
「わかりました。じゃあ…先輩は放課後何をして過ごすんですか?」
彼女は軽やかに話題を変えた。
「特に何も。家に帰って休む。スマホで動画を見る。それだけだ。」
「ずっと動画ですか?」
「ああ。だいたいな。」
「でも、そんなに面白いですか?」
彼女の素朴な疑問に、ふと考え込んでしまった。
面白いかどうか、そんなことを考えたこともなかった。ただ、短時間で多くの情報を得られる効率的な方法だと思い込んでいただけだ。
「…別に面白いかどうかは関係ない。効率的かどうかが重要なんだ。」
「効率的…。でも何のための効率なんですか?」
彼女の指摘は鋭い。
「もちろん、人生に勝つためだ。」
俺は堂々と答える。
「はぁ…。」
一ノ瀬はため息をついた。そして、口を開いた。
「今の先輩は、客観的にみて、どこも勝っていないとおもいますけど。」
失礼な言い方だった。
なぜ、よく知らない中等部の後輩にそんなことを言われてないといけないんだ?
「お前には関係ない。」
冷たく切り返した。
「そうですね。でも、私は先輩と話せて楽しいです。」
一ノ瀬はそう言って笑顔を見せた。
こいつ…。
何も動じていない。
俺は絶望した。
何も俺のいうことをこいつは効かない。
それどこから、俺自身へのダメージが大きい。
疲れた。
それから、一ノ瀬に話しかけられながら、俺は住宅街の中を歩き続けていた。
「あっ!先輩、いい公園ですね。先輩、行ってみましょうよ!」
一ノ瀬が指さした先には、小さな公園があった。
滑り台、ブランコ、砂場…シンプルな公園だ。
彼女は俺の返事を待たずに、俺の腕をとって公園に向かって走り出した。
俺はため息をつきながらも、強制的に公園へと引きずられていった。
その小さな公園に着いた。
「先輩!ブランコ!」
「俺はブランコじゃない。」
俺が定番の返しをしても、彼女は無視した。
そして、一ノ瀬はブランコへと近づいていく。
俺はまるで彼女の付属品のように引っ張られていく。
「先輩、先輩!ここに座りましょうよ!」
隣のブランコを指さしていた。
「バカバカしい。もう子供じゃないんだぞ。」
「大人だってブランコくらいしますよ!人生に勝つためには、たまにはこうした非効率的なことも大切です。」
そう言って、俺の袖をさらに強く引っ張った。
もはや、抵抗する気もうせてしまう。
渋々ながらも、彼女になされるがまま、俺は隣のブランコに腰掛けた。
「ほら、やっぱり楽しいですよね!」
彼女は嬉しそうに笑った。
…はぁ。
俺は心の中でため息をついた。
ブランコをゆっくりと漕ぎ始める。
子供の頃以来だろうか。
見ると、隣でブランコを漕いでいる一ノ瀬は、それなりの勢いでブランコを楽しんでいる。
「気持ちいいですね!」
一ノ瀬は素直に楽しさを表現した。
「…そうか。」
それは楽しそうにしている一ノ瀬の隣で、楽しそうな彼女を見ていた。
奇妙な時間だった。
彼女は、俺と適当な話をしながらも、そのまましばらくブランコを漕いだ後、漕ぐのをやめた一ノ瀬がふと言った。
「先輩は昔から一人で過ごすのが好きだったんですか?」
「…ああ、そうだ。昔から一人だ。」
俺は適当に答えた。
「嘘ですね。先輩にも友達がいて、楽しく過ごしていた時期があるんですよね。」
彼女はまるで俺の過去を知っているかのように言った。
「なぜそう断言できる?」
「だって、先輩は優しそうな目をしているから。人と関わることを避けているけど、本当は違うんだと思っています。」
その言葉に、一面の彼女の観察力は恐ろしいほど鋭い。
それとも、俺の心を読む特別な能力でもあるのだろうか。
俺は無言で返した。
その言葉に返す言葉は自分自身よく分からなかった。
そして、思った。
彼女が俺の秘密をなぜ知っているのか。
山下への告白のこと、創作ノートのこと。これまで俺との接点がまったくなかった中等部生がそんなことを知るはずがない。
だが、今はそれを追求する気力がなかった。
今、その話題を出せば、墓穴を掘っています。
また彼女の脅しが始まるのだろう。
「帰ろう。もう遅い。」
ブランコから立ち上がった。
夕暮れが近づいていることに気づいたからだ。
「はーい。先輩」
一ノ瀬は、素直にブランコから降りた。
公園を出て、再び住宅街の道を歩き始めた。
「先輩のお家はどの辺りですか?」
「教えるつもりはない。」
ナチュラルに俺の住所を知ろうとする彼女に恐怖を感じた。
「そうですか。残念です。」
彼女は少し肩を落としたが、すぐに明るい表情に戻った。
「私はあの角を曲がったところです。そろそろ別れましょうか。」
住宅街の十字路を指さした。
「ああ、そうだな。」
どこか安堵感を覚えた。やっと一人になれる。
元の孤独で『効率的な時間』に戻れる。
俺はどこかほっとしていた。
「明日の屋上、約束ですからね?」
別れ際、一ノ瀬は念を押した。
「ああ、約束は守る。」
そう答えると、彼女は満面の笑みを浮かべた。
「ありがとうございます!明日のお弁当、先輩の好物を入れておきますね。」
一ノ瀬は手を振って、十字路を右に曲がっていった。
俺はさっさと別の方向へと進みだす。
一人になった道を、俺はゆっくりと歩き始めた。
頭の中は一ノ瀬ナズナという謎の後輩のことでいっぱいだった。
彼女の正体、彼女が俺の過去をどうして知っているのか、なぜ俺に接近するのか。
明日も屋上で一ノ瀬と会う。
それはもはや避けられない事実だ。
俺は帰宅をしながら、自分や自分の心境、これからのことを考え続けていた。
それは面倒なことではあったが、久しぶりな感覚がした。
普段なら五回目のスヌーズでようやく目を覚ますのに、今日は最初のアラームで目が覚めてしまった。
昨日の一ノ瀬との約束が、頭から離れなかったからだ。
朝の準備をしながら、今日という日を回避できないかと考え続けた。
ああ、今日雨が降れば、屋上で食べることはできないだろうに。
そんな思考に憑りつかれた。
しかし、天気に関していえば快晴。
だとすれば、俺が学校を休むという選択肢もある。
ただ、これらは結局のところ、単なる先延ばしに過ぎない。
いずれ顔を合わせれば、同じことだ。
食卓では、アカネが俺の様子を不思議そうに見ていた。
「お兄ちゃん、動画、見ないんだ?」
「ああ…。」
いつも通りの返事をしたつもりだったが、何かがおかしかったのだろう。
アカネは、俺をちょっとだけ見つめた後に、再び食事に戻った。
それから無言で朝食を食べ終えた。
今日はいつものように動画を見る気分になれなかった。
何かに追い詰められているような感覚。まるで処刑台に向かう死刑囚のような心境だった。
学校に向かう途中、一ノ瀬ナズナという後輩のことを考えていた。
あいつはいったい何者なのか。
なぜ俺のことをあそこまで知っているのか。そして、なぜ俺に執着するのか。
学校に着いてからも、その不安は消えなかった。
教室に入り、いつもの席に着く。誰も俺に目を向けない。
いつもならそれが心地よいのに、今日は違った。むしろ、この透明な存在が今日を境に崩れ去るのではないかという恐れがあった。
授業中も上の空だった。ただ時間が過ぎるのを待っているだけ。指名されても、なんとか答えはしたものの、内容は覚えていない。
そして、昼休み。
チャイムが鳴った瞬間、俺は憂鬱な気持ちに支配された。
いつもなら、さっと教室を抜け出して資料室へ向かうところだが、今日は違う。
約束の場所、屋上へと向かわなければならない。
ゆっくりと席を立ち、廊下に出る。
階段に向かおうとしたとき、背後から声がした。
「先輩!」
一ノ瀬だった。
いつの間にここまで来ていたのか。彼女は満面の笑みを浮かべていた。
「約束、覚えてましたか?」
「…ああ。」
忘れるわけがない。忘れたくても忘れられない約束だ。
「じゃあ、行きましょう!」
そう言って、彼女は俺の腕に手を回した。昨日と同じ状況だ。
俺は抵抗せず、ただ黙って彼女に連れていかれるままになった。
廊下では何人かの生徒が俺たちを見て驚いていたが、後輩は全く気にしない様子だった。
むしろ、俺を連れていることを誇示しているかのようだ。
屋上へと続く階段を上る。足が鉛のように重い。
彼女は俺の腕を引っ張りながら、何やら楽しげに話していた。
「今日ね、お弁当作ってきたんですよ。先輩の好きそうなものばかり入れました。」
なぜ俺の好みを知っているのか、と問うのもむなしい気がした。もう驚かないよう自分に言い聞かせる。
屋上のドアを開けると、外は晴れていた。
風が心地良く吹き、少なくとも天気だけは最高だった。
後輩は屋上の隅に敷物を広げ、そこに座るよう促した。
「さあ、ここに座ってください。」
俺は黙って座る。彼女は俺の隣に座り、バッグから取り出した二段のお弁当箱を開けた。
「じゃーん!どうですか?」
中には唐揚げ、卵焼き、ウインナー、ブロッコリーの炒め物など、色とりどりのおかずが並んでいた。
確かに俺の好きなものばかりだ。
…その正確さに、また彼女への異様な恐怖を感じてしまった。
「いただきます。」
一ノ瀬が先に手を合わせ、俺も小さく『いただきます』と呟いた。
一口食べると、予想以上においしかった。
唐揚げはカリッと揚がり、中はジューシー。卵焼きは甘さ控えめで、俺好みの味付けだった。
「おいしい…。」
思わず声が漏れた。
「本当ですか?よかった!」
後輩は本当に嬉しそうに微笑んだ。この笑顔が作り物だとしたら、相当の演技力だ。
沈黙の中、俺たちは食事を続けた。俺はなるべく早く食べ終わって、この場を去りたかった。
一方、後輩はゆっくりと食べながら、時折俺の顔を見ていた。
やがて、彼女が話し始めた。
「先輩、少しだけ話していいですか?」
「…何を?」
「先輩がどうして効率を重視するようになったのか、聞かせてくださいよ!」
俺はため息をついた。
もはや、彼女はこの答えを知っているのではないか?
俺はそんなことを思った。
「別に大した理由はない。無駄を省くほうが合理的だから、それだけだ。」
「本当ですか?」
後輩の目がまっすぐ俺を見つめる。
「…そうだ。」
「でも?本当は?」
その言葉に、思わず箸を止めた。
なぜ彼女はこうも俺の心の奥を読み取ることができるのか。
「ただ、もう一度傷つくのが怖いだけなんじゃないですか?」
返す言葉が見つからなかった。
ただ黙って弁当を食べ続けるしかない。
「先輩の創作ノート、私、読みたいです。」
俺は読ませたくなかった。
誰にも…。
「………。」
「私は先輩の書いたものを読みたいんです。きっと素敵な物語なんでしょうね。」
そういう一ノ瀬には、馬鹿にしたような様子はない。
本気で俺の書いたモノが読みたそうだった。
その様子に俺は苦笑いした。
「大したものじゃない。ただの中二病全開の駄文だ。」
「いいえ、そんなことないと思います。先輩はきっと、繊細で、深い洞察力を持っているはずです。」
なぜそう断言できるのか。俺のことを知り尽くしているかのような口ぶり。どこまでも不可解な少女だ。
「なあ、正直に答えてくれ。」
決意を固めて、俺は質問した。
「お前、なぜ俺のことをそこまで知っている?ストーカーか?それとも…。」
後輩は少し考え込むような素振りを見せた後、ゆっくりと答えた。
「ただの直感です。」
「直感で創作ノートの存在までわかるか?」
「それは…いつか説明します。今はまだその時じゃないんです。」
もどかしい返答だったが、今日はこれ以上追求しても無駄だと感じた。
弁当を食べ終えると、後輩は丁寧に箱を片付け始めた。
「ありがとうございました。おいしかったですか?」
「ああ、うまかった。」
素直に認めると、彼女の顔が喜びで輝いた。
「本当ですか?嬉しいです!」
こんな風に喜ばれると、悪い気はしない。むしろ、少し心が軽くなったような気がした。
「これで約束は果たしたな。」
俺はそう言って立ち上がった。これで終わりのはずだ。彼女との接触はこれきりだと思っていた。
「あ、まだです。」
後輩が俺の袖を引っ張った。
「何?お前との約束は昼食を共にすることだっただろう。」
「はい、でも、明日も一緒に食べてほしいんです。」
俺は唖然とした。
「何を言ってる?一度だけの約束だったはずだ。」
「そうでしたっけ?私はそんな約束していませんよ。」
彼女の顔には悪戯っぽい笑みが浮かんでいた。
「嘘だ!昨日、お前は…。」
「昨日は『明日、屋上で一緒にお昼を食べましょう』と言っただけですよ。一度だけとは言ってません。」
確かに、彼女はそう明言していなかった。俺が勝手に『一度だけ』と思い込んでいたのだ。
「冗談だろ…。」
「冗談じゃありません。明日も来てください。もし来なかったら…。」
言外に『秘密を暴露する』という脅しが込められている。
そう、俺は騙されたのだ。
それに気が付いたとき、絶望的な気分になった。
「どこまで俺を追い詰めるつもりだ?」
「追い詰めるなんて、そんなつもりはありません。ただ、先輩と一緒にいたいだけですよ?」
その言葉に、複雑な感情が湧き上がった。
恐怖と怒りの中に、少しだけ、諦めのようなものを感じた。
ただ、一つ言えるのは、誰かが本気で自分を求めてくれている。
それは考えてみると、俺の人生で初めての経験なような気がした。
ただ、問題は、その相手がストーカーだ、という点にあるのだけれど。
「わかった…明日も来る。」
諦めたように俺がそういうと、彼女は嬉しそうに手を叩いた。
「約束ですよ!明日も美味しいお弁当作ってきます!」
チャイムが鳴り、昼休みの終わりを告げる。
俺たちは屋上を後にした。階段を下りながら、後輩が言った。
「先輩、今日は楽しかったです。ありがとうございました。」
「そうか。」
俺はそれだけ言った。
正直、もうあまり関わりたくはない。
しかし、俺にとって残念なことがあった。
それは、もはや彼女と関わらないことは不可能だろう、と理解できるだけの知性が俺にあることだった。
明日からは、後輩との学生生活が始まるのだ。
…間違いなく。
重い気もしたし、効率的ではないというのは分かり切っていた。
ただ、もうそれすらもどうでもいい気がしてきた。
◇
すべての授業が終わり、俺は何も考えずに教室を出た。
他の生徒たちはグループになって下校の準備をしている。あいつらが帰った後にゆっくり出るつもりだった。
廊下に一歩踏み出した瞬間、突然袖を引っ張られた。
「先輩。一緒に帰りますよ!」
見覚えのある声だった。
振り向くと、一ノ瀬ナズナという不可解な中等部の後輩が立っていた。細身の体に合わない力強さで俺の腕を掴んできた。
「おい!馬鹿やめろ。危ない。」
驚きと混乱で、それ以上言葉がでなかった。
彼女との約束はお昼だけ、なはず。
なぜ彼女は高等部の教室前にいるのか。
「先輩を待っていたんです。一緒に帰りましょう!」
あまりにも自然な態度に、言葉が見つからない。
この後輩との屋上での約束は明日のことだ。
今日はもう関わりたくなかった。
俺は必至で言い訳を考えた。
「断る。今日は用事がある。」
即席の理由を言い放った。
実際には何の予定もないが、とにかくこの不気味な後輩から離れたかった。
「えー、また嘘ついてます?」
彼女は俺の目をじっと見て言った。
まるで心を見透かされているようで不快だった。
「嘘じゃない。本当に用事がある。」
「じゃあ、何の用事ですか?」
追求されて言葉に詰まった。
「…それはお前に関係ない。」
「関係あります!先輩の帰りを邪魔する用事なんて、邪魔する価値がありますよ!」
後輩は屈託のない笑顔で言った。その表情からは脅迫をした人間の面影はまったく感じられない。
だが、彼女がどこまで俺の秘密を知っているかを考えると、背筋が寒くなる。
「とにかく離せ。人に見られたら変に思われる。」
廊下には他の生徒たちがまだいた。高等部の男子が中等部の女子に腕を掴まれている姿なんて、確実に噂になる。
それも悪質な噂だ。
…ああ、それはとても嫌だった。
「大丈夫ですよ。先輩って学校では透明人間みたいなものでしょ?」
その言葉に、皮肉な真実を感じた。
確かに俺は存在感を消すことに長けている。
でも、それでも今の状況はリスクが高すぎる。
「いいから離せ。」
腕を振り払おうとしたが、彼女の握力は想像以上に強かった。
「離しません。一緒に帰りましょう。先輩のお家はどこですか?」
「そんなこと、誰が教えるか!」
突然のことに動揺して声が大きくなった。
いくつかの視線が俺たちに向けられる。
これ以上抵抗すると余計に目立ってしまう。
結局、俺は観念して後輩の要求に従うことにした。
「…わかった。少しだけなら一緒に歩いてやる。でも学校の外までだ。」
「やった!ありがとうございます、先輩!」
喜びを露わにする後輩の反応は、完全に俺の脅しを忘れているようだった。
ただの明るい後輩のようだ。
だが、俺は忘れない。
あの屋上での脅し。
『先輩の秘密が今の学校中に広まったらどうなるでしょうね』と言った彼女の言葉を。
校舎を出て中庭を通り、校門へと向かった。
一ノ瀬は終始俺の腕を離さず、まるで恋人同士のように歩いている。
「おい、もう離せ。これ以上くっついていると誤解される。」
「誤解?どんな誤解ですか?」
彼女は無邪気な表情で聞いてきた。本当に分からないのか、それとも分かっていて聞いているのか。
「そんなこと…説明するまでもないだろ。」
思わず顔が熱くなるのを感じた。恥ずかしさと苛立ちが混ざった感情だ。
「ふーん。」
一ノ瀬はニヤリと笑った。何かを企んでいる表情に見えた。
校門を出ると、彼女はようやく俺の腕を離した。少し肩の力が抜ける。
「どっちに帰るんですか?」
「お前こそどっちだ?」
警戒心を解かないまま尋ねると、彼女は北の方角を指さした。
「あっちです。住宅街の方。」
俺も同じ方向だった。これは偶然なのか、それとも…。
「…俺もそっちだ。」
「本当ですか?じゃあやっぱり一緒に帰れますね!」
彼女は小さく拍手をして喜んだ。あまりにも都合の良い一致に疑念が湧いた。
「お前、本当にそっちに住んでるのか?」
「もちろんです!嘘なんてつきませんよ。」
確信に満ちた彼女の言葉に、それ以上追求する気力がなかった。
並んで歩き始めると、彼女は話し続けた。
「先輩は毎日一人で帰ってるんですか?」
「ああ。それが効率的だからな。」
「友達とは帰らないんですか?」
「友達なんていない。それに、人と一緒に帰るのは時間の無駄だ。」
そう言い切ったが、今まさに後輩と一緒に帰っている矛盾に気づかないはずがなかった。
「時間の無駄?本当にそう思ってるんですか?」
彼女の問いかけには何か深い意味がありそうだった。
「当然だ。無駄話をして時間を潰すより、一人で早く帰って自分の時間を確保する方が効率的だろう。」
「先輩はその『効率的』って言葉が好きですね。」
彼女は少し首を傾げながら言った。
「効率を追求することで、無駄な時間を省ける。それだけのことだ。」
「でも今、私と一緒に帰っていますよね?これは効率的じゃないですか?」
鋭い指摘に言葉に詰まった。
「…特別な状況だ。お前が無理やり付いてきただけで、俺が望んだわけじゃない。」
「そうですか?でも、抵抗してないじゃないですか。」
一ノ瀬の目はまっすぐに俺を見ていた。
まるで心の奥底まで見透かされているようで居心地が悪い。
「…抵抗したって無駄だと思っただけだ。」
弱々しい言い訳だった。
住宅街に入った。この辺りは静かで、通学する学生の姿もまばらになってきた。
「先輩って本当はどんな人なんですか?」
突然の質問に戸惑った。
「どういう意味だ?」
「みんなの前では無口で存在感を消しているけど、本当の先輩はそんな人じゃないと思うんです。」
彼女の洞察力はあまりにも鋭すぎる。まるで長年俺を観察してきたかのようだ。
「勝手な想像をするな。俺はいつも俺だ。」
「本当ですか?でも、昔は違ったんですよね?」
気が付くと、彼女はまた俺の過去に触れようとしていた。
「…話題を変えろ。」
警戒心を強めながら答えた。彼女が俺の中学時代の出来事をどこまで知っているのか。それを考えるだけで恐ろしかった。
「わかりました。じゃあ…先輩は放課後何をして過ごすんですか?」
彼女は軽やかに話題を変えた。
「特に何も。家に帰って休む。スマホで動画を見る。それだけだ。」
「ずっと動画ですか?」
「ああ。だいたいな。」
「でも、そんなに面白いですか?」
彼女の素朴な疑問に、ふと考え込んでしまった。
面白いかどうか、そんなことを考えたこともなかった。ただ、短時間で多くの情報を得られる効率的な方法だと思い込んでいただけだ。
「…別に面白いかどうかは関係ない。効率的かどうかが重要なんだ。」
「効率的…。でも何のための効率なんですか?」
彼女の指摘は鋭い。
「もちろん、人生に勝つためだ。」
俺は堂々と答える。
「はぁ…。」
一ノ瀬はため息をついた。そして、口を開いた。
「今の先輩は、客観的にみて、どこも勝っていないとおもいますけど。」
失礼な言い方だった。
なぜ、よく知らない中等部の後輩にそんなことを言われてないといけないんだ?
「お前には関係ない。」
冷たく切り返した。
「そうですね。でも、私は先輩と話せて楽しいです。」
一ノ瀬はそう言って笑顔を見せた。
こいつ…。
何も動じていない。
俺は絶望した。
何も俺のいうことをこいつは効かない。
それどこから、俺自身へのダメージが大きい。
疲れた。
それから、一ノ瀬に話しかけられながら、俺は住宅街の中を歩き続けていた。
「あっ!先輩、いい公園ですね。先輩、行ってみましょうよ!」
一ノ瀬が指さした先には、小さな公園があった。
滑り台、ブランコ、砂場…シンプルな公園だ。
彼女は俺の返事を待たずに、俺の腕をとって公園に向かって走り出した。
俺はため息をつきながらも、強制的に公園へと引きずられていった。
その小さな公園に着いた。
「先輩!ブランコ!」
「俺はブランコじゃない。」
俺が定番の返しをしても、彼女は無視した。
そして、一ノ瀬はブランコへと近づいていく。
俺はまるで彼女の付属品のように引っ張られていく。
「先輩、先輩!ここに座りましょうよ!」
隣のブランコを指さしていた。
「バカバカしい。もう子供じゃないんだぞ。」
「大人だってブランコくらいしますよ!人生に勝つためには、たまにはこうした非効率的なことも大切です。」
そう言って、俺の袖をさらに強く引っ張った。
もはや、抵抗する気もうせてしまう。
渋々ながらも、彼女になされるがまま、俺は隣のブランコに腰掛けた。
「ほら、やっぱり楽しいですよね!」
彼女は嬉しそうに笑った。
…はぁ。
俺は心の中でため息をついた。
ブランコをゆっくりと漕ぎ始める。
子供の頃以来だろうか。
見ると、隣でブランコを漕いでいる一ノ瀬は、それなりの勢いでブランコを楽しんでいる。
「気持ちいいですね!」
一ノ瀬は素直に楽しさを表現した。
「…そうか。」
それは楽しそうにしている一ノ瀬の隣で、楽しそうな彼女を見ていた。
奇妙な時間だった。
彼女は、俺と適当な話をしながらも、そのまましばらくブランコを漕いだ後、漕ぐのをやめた一ノ瀬がふと言った。
「先輩は昔から一人で過ごすのが好きだったんですか?」
「…ああ、そうだ。昔から一人だ。」
俺は適当に答えた。
「嘘ですね。先輩にも友達がいて、楽しく過ごしていた時期があるんですよね。」
彼女はまるで俺の過去を知っているかのように言った。
「なぜそう断言できる?」
「だって、先輩は優しそうな目をしているから。人と関わることを避けているけど、本当は違うんだと思っています。」
その言葉に、一面の彼女の観察力は恐ろしいほど鋭い。
それとも、俺の心を読む特別な能力でもあるのだろうか。
俺は無言で返した。
その言葉に返す言葉は自分自身よく分からなかった。
そして、思った。
彼女が俺の秘密をなぜ知っているのか。
山下への告白のこと、創作ノートのこと。これまで俺との接点がまったくなかった中等部生がそんなことを知るはずがない。
だが、今はそれを追求する気力がなかった。
今、その話題を出せば、墓穴を掘っています。
また彼女の脅しが始まるのだろう。
「帰ろう。もう遅い。」
ブランコから立ち上がった。
夕暮れが近づいていることに気づいたからだ。
「はーい。先輩」
一ノ瀬は、素直にブランコから降りた。
公園を出て、再び住宅街の道を歩き始めた。
「先輩のお家はどの辺りですか?」
「教えるつもりはない。」
ナチュラルに俺の住所を知ろうとする彼女に恐怖を感じた。
「そうですか。残念です。」
彼女は少し肩を落としたが、すぐに明るい表情に戻った。
「私はあの角を曲がったところです。そろそろ別れましょうか。」
住宅街の十字路を指さした。
「ああ、そうだな。」
どこか安堵感を覚えた。やっと一人になれる。
元の孤独で『効率的な時間』に戻れる。
俺はどこかほっとしていた。
「明日の屋上、約束ですからね?」
別れ際、一ノ瀬は念を押した。
「ああ、約束は守る。」
そう答えると、彼女は満面の笑みを浮かべた。
「ありがとうございます!明日のお弁当、先輩の好物を入れておきますね。」
一ノ瀬は手を振って、十字路を右に曲がっていった。
俺はさっさと別の方向へと進みだす。
一人になった道を、俺はゆっくりと歩き始めた。
頭の中は一ノ瀬ナズナという謎の後輩のことでいっぱいだった。
彼女の正体、彼女が俺の過去をどうして知っているのか、なぜ俺に接近するのか。
明日も屋上で一ノ瀬と会う。
それはもはや避けられない事実だ。
俺は帰宅をしながら、自分や自分の心境、これからのことを考え続けていた。
それは面倒なことではあったが、久しぶりな感覚がした。