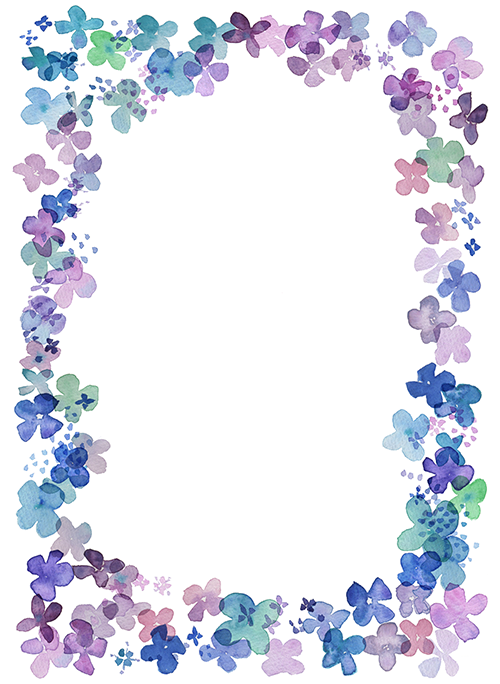翌日、俺は決意していた。
資料室には二度と足を踏み入れない。
あの不気味な中等部の後輩少女と再び接触するリスクは避けたい。
これ以上、彼女と向かい合っていると、やばいことになる。
もはや効率的な学園生活は崩壊する。
それは間違いない。
我ながら、ナイスな判断だと思った。
昼休みが始まると同時に、クラスメイトたちが教室から溢れ出す。
俺はいつものように一人で学食へと移動した。
そこで脳内作戦会議を行う。
いや、もう内容は決定している。
それの最終確認だ。
よし、今日は…。
『資料室が使えないなら、屋上へ行こう。』
かくして、全会一致でその案が可決された。
学食で食事を終えた俺は、移動を始めた。
周囲の生徒に見つかないように自然で溶け込むかのような移動。
俺は、人気のない階段を上りだした。
完全だ。
周囲の環境に溶け込んで、目立たないはずだった。
日頃の効率性を突き詰めた生活から生まれたステルス性。
それをいかんなく発揮していた。
…はずだった。
「先輩、どこに行くんですか?」
背後から声がした。
恐る恐る、俺が振り返ると、そこには昨日の女子生徒が立っていた。
髪はジャギーの入ったショートカット。昨日と同じ中等部の制服を着ている。紛れもない彼女だった。
「なぜここにいる?」
声に思わず苛立ちが混じる。
「先輩のことだから、昨日のことがあって資料室にはいかないだろうな、って思いましたので。」
彼女は微笑みながら言った。
俺と何年も知り合いであるかのような自然さだった。
なんだこいつ。
…怖い。
俺は本格的に目の前の彼女が空恐ろしく感じた。
「俺を探すな。関わるな。」
俺はそう言って背を向けた。
しかし、そいつはしつこく後をついてきた。
「先輩、屋上に行くんですね。一緒に行きましょう。」
そう言って、彼女は俺の腕をつかんだ。
もう逃げられない。
いや、そもそも…。
なぜ、彼女は、俺がこれから屋上へいこうとしていることを知ってるんだよ、と思ったが、言い返す気力もなかった。
まるで囚人が繋がれて歩かされているかごとく、俺は彼女に腕を掴まれて連れまわれていた。
階段を黙々と上っていく。
足音がやけに大きく聞こえた。
幸い、周囲には生徒がいない。
だから、高等部の俺がこんな中等部の女子生徒に腕を掴まされて、移動している情けない姿は見られていない。
「おい。」
「なんですか?」
彼女は俺の腕を大切そうに抱きしめながら、答えた。
「今の状態を誰かに見られたら、嫌だろう?手を放せ。」
「どうしてですか?別にいいじゃないですか?見られても?」
彼女はそれだけ言って、何も変わらない。
だめだ、こいつ。
俺は諦めて、後輩と一緒に階段を進んだ。
屋上のドアまでたどり着き、ドアノブに手をかけた。
開くことを祈りながら回す。
カチャリ。
ドアは開いた。
扉を開け、外に出る。
「開いてました。良かった。」
彼女は嬉しそうに言った。
まるでデートでもしているかのような口ぶりだ。
「お前、一体何なんだ?なぜ俺につきまとう?」
我慢の限界だった。周りに人がいないことを確認して、声を荒げた。
「だから言ったじゃないですか。先輩に興味があるんです。」
一ノ瀬は全く動じない様子で答えた。
「冗談じゃない!俺はお前なんか知らないし、関わりたくもない!もう二度と姿を見せるな!」
怒りのまま叫んだ。こんなに感情的になるなんて、自分でも珍しいことだった。
一ノ瀬の表情が初めて変わった。
笑顔が消え、速やかに静かな眼差しに変わった。
「先輩、本当に私を追い払いたいですか?そうしたら、また一人になりますよ。中学の時みたいに。」
その言葉に、俺の体が硬直した。
「中学…?」
「山下ユカリさんに告白して振られた後、クラス中に広まって『告白マニア』って呼ばれていましたよね。」
血の気が引いた。誰にも話していないはずの過去。
この学校では絶対に知られていないはずの事実。
「どうして…それを…。」
言葉が詰まる。俺の背中に冷や汗が伝い落ちていくのを感じた。
「友達だと思っていた人たちにも無視されるようになって、ひどく孤立した毎日を送った。だから、同じ中学から進級してくる人がいない高校へ進学して、誰とも関わらない生活を選んだ。『効率的』という言葉で自分を守っている。」
一ノ瀬は淡々と続けた。
その言葉の一つ一つが、俺の心を刺し貫いていく。
これは恐怖以上の何かだった。まるで自分の内面をガラス張りにされたような、そんな感覚。
「黙れ。」
俺はそういうほかになかった。
けれど、思いのほかダメージが来ていた。
「でも本当は、もう一度あの痛みを味わうのが怖いだけ。」
「黙れ!」
今度は怒鳴った。
「うるさい!お前に何が分かるんだよ!」
反射的に叫んでしまった。
恐怖と屈辱感でいっぱいだ。
ただ、彼女は何も答えなかった。
その俺の叫びに答える代わりに彼女は屋上の柵に近づき、校庭を見下ろした。
「さあ、先輩にはまだ早いですかね?」
その口調はまるでお母さんが出来の悪い息子を諭すようなものだった。
その余裕のある態度が余計に苛立った。
苛立つ。
ただ、後輩のその態度を見ていると、俺がバカみたいだ。
「何が目的だ。」
俺は一言だけ聞いた。
「明日の昼休み、ここで一緒にお昼を食べましょう。私がお弁当を作ってきます。」
彼女は振り返り、再び笑顔を見せた。
「断る。」
俺は咄嗟に言った。
「そうですか。」
彼女は少し残念そうに俯いた。
だが、すぐに顔を上げると、静かな声で言った。
「でも、先輩の秘密が今の学校中に広まったらどうなるでしょうね。」
その言葉は、明らかな脅しだった。
「おい!やめろ!」
「明日からは、また先輩の『告白マニア』の話を聞きたがる人がたくさんいることになるでしょうね。」
彼女の発言に、俺は心臓が止まりそうになった。
新しい学校でも、あの屈辱的な過去が知れ渡る。
また、笑いものになる恐怖がフラッシュバックした。
「お前…お前…。」
言葉にならない怒りと恐怖が入り混じる。何度も深呼吸して、なんとか平静を装おうとした。
「脅迫か?」
低い声で言うと、彼女は首を傾げた。
「脅迫なんて、そんな大げさな。私は先輩と一緒にお昼を食べたいだけですよ。お願いです。」
そう言いながらも、微笑んでいる彼女の目は笑っていない。
俺はこの場から逃げ出したい衝動に駆られた。
だが、それは無意味だった。
明日、屋上に来なければ、俺の秘密が学校中に広まる。それは何としても避けたかった。
俺がせっかく作り上げた『効率的』な学園生活。
誰にも関わらず、誰にも干渉されない平穏な日々。それが全て崩れ去る。
「…一度だけだ。」
「分かりました!では、先輩。明日の昼休み、ここで私と一緒にお昼を食べしょう?」
一ノ瀬は嬉しそうに微笑んだ。
「約束してくださいね。必ず来ると。」
丁寧な言葉とは裏腹に、それは命令だった。
「…わかった。」
屈辱感で胸が張り裂けそうになりながらも、俺は頷いた。
「約束する。俺は明日、ここで一緒に昼食を取る。」
その言葉に、パアぁと後輩の顔が明るくなった。
「やった!約束ですよ。絶対に破らないでくださいね。」
そこまで言って、じっと彼女は俺を見てきた。
「ああ、約束だ。」
いや、嘘を言ってもしょうがないだろう。
「本当に?」
「ああ、本当だ。」
「本当の本当に?」
「ああ。」
そんなやり取りをしていると、昼休みの終わりを告げる予鈴のチャイムが鳴った。
「あっ、先輩。今日はこれで終わりですね。」
そう言って、ようやく後輩は、俺の体から細い腕を離した。
そして、彼女は屋上のドアに向かった。
そこでふと立ち止まり、振り返る。
「ちなみに、明日来なかったら、私は先輩のことをみんなに話します。山下さんの件も、それからあの創作ノートのことも。」
心臓が止まりそうになった。
創作ノート?
それさえも知っているのか?
中学時代、俺が密かに短編小説やエッセイを書きためていたノート。
それを知る人間は、この世に一人もいないはずだった。
「なぜ…それを…。」
言葉にならなかった。恐怖と混乱で頭が真っ白になる。
「明日、お話ししましょう。楽しみですね!」
そう言い残し、一ノ瀬は屋上を後にした。
扉が閉まり、俺一人が残された屋上。
突然の静寂に、自分の心臓の音がやけに大きく聞こえた。
足元から力が抜け、その場に崩れ落ちる。
なんだ、あいつは?
なぜ俺のことをそこまで知っている?
俺は、山下への告白の失敗を、ただ単に彼女に言っただけ。彼女を通じてクラスメイトに広まり、『告白マニア』と呼ばれるようになったただそれだけ。
それなのになぜあいつが知っている?
創作ノートのことまで?
あんなもの、誰にも見せたことがない。
俺は母親の目にも触れないように、小学校の頃に使っていたカバンの奥底にしまってあるはずだ。
それなのに。
何かがおかしい。完全におかしい。
頭をかかえて、俺は天を仰いだ。
なにが何だか、わからなくなってきた。
俺の身に何が起きているのか。
一ノ瀬ナズナとは一体何者なのか。
なぜ俺のことをそこまで知っているのか。
ストーカーなのか?
いや、それにしては情報が詳細すぎる。
同じ中学出身者?
でも見た覚えがない。
親類の誰かから聞いた?
アカネあたりが何か話したのか?
どの仮説も納得できるものではなかった。
そして何より恐ろしかったのは、後輩が俺の内面まで見抜いているという感覚だった。
「痛みを味わうのが怖い」―そんな弱さを、俺自身認めたくなかった。
しかし、ほぼ初対面の一ノ瀬ナズナという少女は、俺の心理を直接刺してきた。
正直、彼女の言葉があっているのか、今の俺にはよくわからない。
しかし、一ノ瀬ナズナという少女の出現によって、俺の築き上げた防壁が崩れ始めようとしていることは事実だった。
俺はゆっくりと立ち上がり、屋上を後にした。
階段を下りながら、明日のことを考えていた。
彼女と昼食を共にする。たった一度のことだ。
それを我慢すれば、俺の秘密は守られる。俺はまた平穏で安全で『効率的』な日常に戻れる。
そう自分に言い聞かせながらも、どこか心の奥で、それが嘘だと気づいていた。
もはや、二度とその日常は帰ってこない、そうどこかで分かっていた。
教室に戻ると、授業はすでに始まっていた。
扉を開け、遅刻の謝罪をして席に着く。
クラスメイトたちの視線が一瞬俺に集まるが、すぐに別の方向に向けられた。
俺という存在は、この教室ではただのオブジェクトのようなものだから。
でも、明日からそれも変わるかもしれない。彼女が俺の秘密を広めたら…。
いや、そんなことはない。俺は約束を守る。明日、屋上で彼女と昼食を共にする。たった一度だけ。それだけだ。
授業に集中しようとしたが、頭の中は一ノ瀬のことでいっぱいだった。
数学の公式も、英語の単語も、全く入ってこない。
脳内では一ノ瀬の言葉が繰り返し響いていた。
「明日の昼休み、ここで一緒にお昼を食べましょう。」
「先輩の秘密が今の学校中に広まったらどうなるでしょうね。」
「創作ノートのことも。」
どれもこれも、俺の心に深い不安を植え付ける言葉ばかりだ。
最後の授業が終わり、放課後になった。
資料室には二度と足を踏み入れない。
あの不気味な中等部の後輩少女と再び接触するリスクは避けたい。
これ以上、彼女と向かい合っていると、やばいことになる。
もはや効率的な学園生活は崩壊する。
それは間違いない。
我ながら、ナイスな判断だと思った。
昼休みが始まると同時に、クラスメイトたちが教室から溢れ出す。
俺はいつものように一人で学食へと移動した。
そこで脳内作戦会議を行う。
いや、もう内容は決定している。
それの最終確認だ。
よし、今日は…。
『資料室が使えないなら、屋上へ行こう。』
かくして、全会一致でその案が可決された。
学食で食事を終えた俺は、移動を始めた。
周囲の生徒に見つかないように自然で溶け込むかのような移動。
俺は、人気のない階段を上りだした。
完全だ。
周囲の環境に溶け込んで、目立たないはずだった。
日頃の効率性を突き詰めた生活から生まれたステルス性。
それをいかんなく発揮していた。
…はずだった。
「先輩、どこに行くんですか?」
背後から声がした。
恐る恐る、俺が振り返ると、そこには昨日の女子生徒が立っていた。
髪はジャギーの入ったショートカット。昨日と同じ中等部の制服を着ている。紛れもない彼女だった。
「なぜここにいる?」
声に思わず苛立ちが混じる。
「先輩のことだから、昨日のことがあって資料室にはいかないだろうな、って思いましたので。」
彼女は微笑みながら言った。
俺と何年も知り合いであるかのような自然さだった。
なんだこいつ。
…怖い。
俺は本格的に目の前の彼女が空恐ろしく感じた。
「俺を探すな。関わるな。」
俺はそう言って背を向けた。
しかし、そいつはしつこく後をついてきた。
「先輩、屋上に行くんですね。一緒に行きましょう。」
そう言って、彼女は俺の腕をつかんだ。
もう逃げられない。
いや、そもそも…。
なぜ、彼女は、俺がこれから屋上へいこうとしていることを知ってるんだよ、と思ったが、言い返す気力もなかった。
まるで囚人が繋がれて歩かされているかごとく、俺は彼女に腕を掴まれて連れまわれていた。
階段を黙々と上っていく。
足音がやけに大きく聞こえた。
幸い、周囲には生徒がいない。
だから、高等部の俺がこんな中等部の女子生徒に腕を掴まされて、移動している情けない姿は見られていない。
「おい。」
「なんですか?」
彼女は俺の腕を大切そうに抱きしめながら、答えた。
「今の状態を誰かに見られたら、嫌だろう?手を放せ。」
「どうしてですか?別にいいじゃないですか?見られても?」
彼女はそれだけ言って、何も変わらない。
だめだ、こいつ。
俺は諦めて、後輩と一緒に階段を進んだ。
屋上のドアまでたどり着き、ドアノブに手をかけた。
開くことを祈りながら回す。
カチャリ。
ドアは開いた。
扉を開け、外に出る。
「開いてました。良かった。」
彼女は嬉しそうに言った。
まるでデートでもしているかのような口ぶりだ。
「お前、一体何なんだ?なぜ俺につきまとう?」
我慢の限界だった。周りに人がいないことを確認して、声を荒げた。
「だから言ったじゃないですか。先輩に興味があるんです。」
一ノ瀬は全く動じない様子で答えた。
「冗談じゃない!俺はお前なんか知らないし、関わりたくもない!もう二度と姿を見せるな!」
怒りのまま叫んだ。こんなに感情的になるなんて、自分でも珍しいことだった。
一ノ瀬の表情が初めて変わった。
笑顔が消え、速やかに静かな眼差しに変わった。
「先輩、本当に私を追い払いたいですか?そうしたら、また一人になりますよ。中学の時みたいに。」
その言葉に、俺の体が硬直した。
「中学…?」
「山下ユカリさんに告白して振られた後、クラス中に広まって『告白マニア』って呼ばれていましたよね。」
血の気が引いた。誰にも話していないはずの過去。
この学校では絶対に知られていないはずの事実。
「どうして…それを…。」
言葉が詰まる。俺の背中に冷や汗が伝い落ちていくのを感じた。
「友達だと思っていた人たちにも無視されるようになって、ひどく孤立した毎日を送った。だから、同じ中学から進級してくる人がいない高校へ進学して、誰とも関わらない生活を選んだ。『効率的』という言葉で自分を守っている。」
一ノ瀬は淡々と続けた。
その言葉の一つ一つが、俺の心を刺し貫いていく。
これは恐怖以上の何かだった。まるで自分の内面をガラス張りにされたような、そんな感覚。
「黙れ。」
俺はそういうほかになかった。
けれど、思いのほかダメージが来ていた。
「でも本当は、もう一度あの痛みを味わうのが怖いだけ。」
「黙れ!」
今度は怒鳴った。
「うるさい!お前に何が分かるんだよ!」
反射的に叫んでしまった。
恐怖と屈辱感でいっぱいだ。
ただ、彼女は何も答えなかった。
その俺の叫びに答える代わりに彼女は屋上の柵に近づき、校庭を見下ろした。
「さあ、先輩にはまだ早いですかね?」
その口調はまるでお母さんが出来の悪い息子を諭すようなものだった。
その余裕のある態度が余計に苛立った。
苛立つ。
ただ、後輩のその態度を見ていると、俺がバカみたいだ。
「何が目的だ。」
俺は一言だけ聞いた。
「明日の昼休み、ここで一緒にお昼を食べましょう。私がお弁当を作ってきます。」
彼女は振り返り、再び笑顔を見せた。
「断る。」
俺は咄嗟に言った。
「そうですか。」
彼女は少し残念そうに俯いた。
だが、すぐに顔を上げると、静かな声で言った。
「でも、先輩の秘密が今の学校中に広まったらどうなるでしょうね。」
その言葉は、明らかな脅しだった。
「おい!やめろ!」
「明日からは、また先輩の『告白マニア』の話を聞きたがる人がたくさんいることになるでしょうね。」
彼女の発言に、俺は心臓が止まりそうになった。
新しい学校でも、あの屈辱的な過去が知れ渡る。
また、笑いものになる恐怖がフラッシュバックした。
「お前…お前…。」
言葉にならない怒りと恐怖が入り混じる。何度も深呼吸して、なんとか平静を装おうとした。
「脅迫か?」
低い声で言うと、彼女は首を傾げた。
「脅迫なんて、そんな大げさな。私は先輩と一緒にお昼を食べたいだけですよ。お願いです。」
そう言いながらも、微笑んでいる彼女の目は笑っていない。
俺はこの場から逃げ出したい衝動に駆られた。
だが、それは無意味だった。
明日、屋上に来なければ、俺の秘密が学校中に広まる。それは何としても避けたかった。
俺がせっかく作り上げた『効率的』な学園生活。
誰にも関わらず、誰にも干渉されない平穏な日々。それが全て崩れ去る。
「…一度だけだ。」
「分かりました!では、先輩。明日の昼休み、ここで私と一緒にお昼を食べしょう?」
一ノ瀬は嬉しそうに微笑んだ。
「約束してくださいね。必ず来ると。」
丁寧な言葉とは裏腹に、それは命令だった。
「…わかった。」
屈辱感で胸が張り裂けそうになりながらも、俺は頷いた。
「約束する。俺は明日、ここで一緒に昼食を取る。」
その言葉に、パアぁと後輩の顔が明るくなった。
「やった!約束ですよ。絶対に破らないでくださいね。」
そこまで言って、じっと彼女は俺を見てきた。
「ああ、約束だ。」
いや、嘘を言ってもしょうがないだろう。
「本当に?」
「ああ、本当だ。」
「本当の本当に?」
「ああ。」
そんなやり取りをしていると、昼休みの終わりを告げる予鈴のチャイムが鳴った。
「あっ、先輩。今日はこれで終わりですね。」
そう言って、ようやく後輩は、俺の体から細い腕を離した。
そして、彼女は屋上のドアに向かった。
そこでふと立ち止まり、振り返る。
「ちなみに、明日来なかったら、私は先輩のことをみんなに話します。山下さんの件も、それからあの創作ノートのことも。」
心臓が止まりそうになった。
創作ノート?
それさえも知っているのか?
中学時代、俺が密かに短編小説やエッセイを書きためていたノート。
それを知る人間は、この世に一人もいないはずだった。
「なぜ…それを…。」
言葉にならなかった。恐怖と混乱で頭が真っ白になる。
「明日、お話ししましょう。楽しみですね!」
そう言い残し、一ノ瀬は屋上を後にした。
扉が閉まり、俺一人が残された屋上。
突然の静寂に、自分の心臓の音がやけに大きく聞こえた。
足元から力が抜け、その場に崩れ落ちる。
なんだ、あいつは?
なぜ俺のことをそこまで知っている?
俺は、山下への告白の失敗を、ただ単に彼女に言っただけ。彼女を通じてクラスメイトに広まり、『告白マニア』と呼ばれるようになったただそれだけ。
それなのになぜあいつが知っている?
創作ノートのことまで?
あんなもの、誰にも見せたことがない。
俺は母親の目にも触れないように、小学校の頃に使っていたカバンの奥底にしまってあるはずだ。
それなのに。
何かがおかしい。完全におかしい。
頭をかかえて、俺は天を仰いだ。
なにが何だか、わからなくなってきた。
俺の身に何が起きているのか。
一ノ瀬ナズナとは一体何者なのか。
なぜ俺のことをそこまで知っているのか。
ストーカーなのか?
いや、それにしては情報が詳細すぎる。
同じ中学出身者?
でも見た覚えがない。
親類の誰かから聞いた?
アカネあたりが何か話したのか?
どの仮説も納得できるものではなかった。
そして何より恐ろしかったのは、後輩が俺の内面まで見抜いているという感覚だった。
「痛みを味わうのが怖い」―そんな弱さを、俺自身認めたくなかった。
しかし、ほぼ初対面の一ノ瀬ナズナという少女は、俺の心理を直接刺してきた。
正直、彼女の言葉があっているのか、今の俺にはよくわからない。
しかし、一ノ瀬ナズナという少女の出現によって、俺の築き上げた防壁が崩れ始めようとしていることは事実だった。
俺はゆっくりと立ち上がり、屋上を後にした。
階段を下りながら、明日のことを考えていた。
彼女と昼食を共にする。たった一度のことだ。
それを我慢すれば、俺の秘密は守られる。俺はまた平穏で安全で『効率的』な日常に戻れる。
そう自分に言い聞かせながらも、どこか心の奥で、それが嘘だと気づいていた。
もはや、二度とその日常は帰ってこない、そうどこかで分かっていた。
教室に戻ると、授業はすでに始まっていた。
扉を開け、遅刻の謝罪をして席に着く。
クラスメイトたちの視線が一瞬俺に集まるが、すぐに別の方向に向けられた。
俺という存在は、この教室ではただのオブジェクトのようなものだから。
でも、明日からそれも変わるかもしれない。彼女が俺の秘密を広めたら…。
いや、そんなことはない。俺は約束を守る。明日、屋上で彼女と昼食を共にする。たった一度だけ。それだけだ。
授業に集中しようとしたが、頭の中は一ノ瀬のことでいっぱいだった。
数学の公式も、英語の単語も、全く入ってこない。
脳内では一ノ瀬の言葉が繰り返し響いていた。
「明日の昼休み、ここで一緒にお昼を食べましょう。」
「先輩の秘密が今の学校中に広まったらどうなるでしょうね。」
「創作ノートのことも。」
どれもこれも、俺の心に深い不安を植え付ける言葉ばかりだ。
最後の授業が終わり、放課後になった。