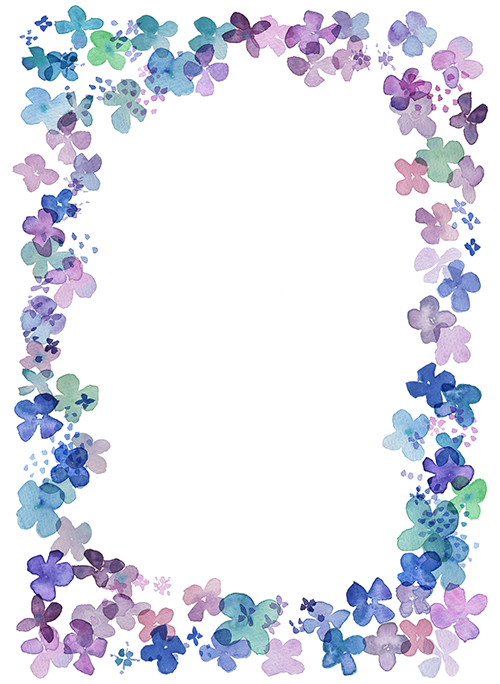今日も今日とて、俺は可及的速やかに授業が終わることを望んでいた。
俺の祈りが通じたのか、いつの間にか授業は終わり、いつものような昼休みが始まった。
生徒たちが教室から溢れ出し、中庭や学食へと向かっていく。
俺はひっそりと目立たないように学食へと向かった。
淡々と食事を終わらせて、俺は約束の地へと向かう。
その人の流れに背を向けるように、俺は階段へと足を向けた。
階段を一歩ずつ上りながら、周囲を確認する。
そして、誰もいないことを確認する。
そう、この昼休みにここの階段には人が少ない。
あとは資料室まで一直線だった。
四階に到着。
廊下は人気がなく、俺一人分の足音だけが虚しく響いた。
誰もが一階の学食や中庭に集まる時間帯だった。
だからこそ、ここは最高の隠れ家となる。
第四資料室の前に立ち、深呼吸する。ドアノブに手をかけ、回す。
ガチャリ。
「あ、先輩。こんにちは。」
予想外の声に、俺は一瞬で凍りついた。
資料室の窓際に、見知らぬ女子生徒が立っていた。
中等部の制服を着ていた。
細身の体格に、ショートカット。ジャギーの入った黒髪。
顔は整っており、小さな鼻や大きな目が特徴的でかわいいと感じられる風貌だった。
肌は透き通るような白さ、唇は薄めながらも自然な血色で、彼女の活発そうな雰囲気を生み出していた。
大きな瞳で俺を見つめている。
俺は無言で扉を閉め、踵を返した。
こんな場所に人がいるなんて、想定外だった。
今日はもう別の場所を探すしかない。
「ちょちょちょ、ちょっと、待ってください!」
背後から声がした。
次の瞬間、扉が再び開き、細い手が俺の制服の袖をつかんだ。
「離せ!それに誰だよ、お前!」
冷たく言い放ったが、女子生徒は手を放さない。
細いのに、異様に力が強い。
そのまま、引っ張られて資料室へと引きずり込まれてしまった。
…もしかして、俺、非力か?
「一ノ瀬ナズナです。中等部三年生です。先輩、逃げなくていいじゃないですかぁ!」
彼女は必死な様子で俺を引き留める。
「いいから、離せ!暑苦しい!」
「ちょっと、ちょっとだけ、お話しましょう?先輩?」
なぜか必死だ。しかしそれが余計にイライラさせた。
「嫌だ、俺はお前と話すことなど無い!」
「そんなことないでしょ?ね、先輩?」
そう言って、抵抗する俺をこいつは完全にシャットアウト。
もう疲れてきた。
いや、俺…。
目の前の女の子よりも力がないのか。
まあ、いいや。
疲れたのだから、俺は抵抗を辞めた。
それに、俺にはこいつに関して気がかりなところがあった。
「どうして俺のことを知ってる?」
そう、どうしてこいつは俺のことを先輩だと知っているんだ?
「先輩のことは色々知ってますよ。綾小路キョウ先輩、高等部一年生。『効率』を重視する生活を送っていて、スマホの動画を見るのが日課ですよね?」
一ノ瀬は俺の目をまっすぐ見つめながら言った。その視線には妙な既視感があった。
まるで昔からの知り合いのように俺を見つめていた。
もちろん、俺はこんなやつ、知らない。
「お前は誰だ?」
「一ノ瀬ナズナです。さっき言いましたよ?」
おどけた様子で彼女は俺にそう言った。
うるせぇ、と内心思った。
「お前、もしかして…。」
「なんですか?」
そうって彼女は、可愛らしく首をかしげている。
もちろん、俺の腕を離さずに…。
「俺をストーキングしてるのか?」
「違いますよ。たまたま、先輩がここにいることを知っていただけです。」
一ノ瀬は軽快に言った。
その態度はあまりにも自然で、かえって不自然に感じる。
「たまたま、今、会ったんだろ?」
「ああ、そうともいいますね!」
ニコニコと彼女は言った。
「なぜここにいる?」
なんだか、ばからしくなってきた俺は苛立ちを抑えきれなくなってきた。
「ちょっと静かな場所が欲しくて。中等部は昼休みうるさいんです。」
「他を探せ。ここは俺の場所だ。」
冷たく言い放つ。
「先輩のものじゃないですよね?学校の施設ですから。」
一ノ瀬は笑顔を崩さない。
まるで俺の反応を楽しんでいるかのようだ。
「……じゃあな。俺は出ていく、それでいいだろ。」
これ以上の会話は時間の無駄だ。
「いいえ、先輩。ここで一緒に動画でも見ましょうよ!」
「いやだ。」
俺は即答した。
怒りが込み上げてくる。
俺の生活は誰にも干渉されないように設計されている。
それが最も効率的だからだ。
赤の他人にとにかく言われる筋合いはない。
「まぁまぁ、そんなに怒らない。ねぇ、先輩。椅子に座ってください。」
後輩はそう言って、俺をさらに引っ張った。
「おいおい。」
俺は急に引っ張られたので、バランスを崩しそうになる。
彼女は俺の意思を完全に無視して、俺を半ば無理やりパイプ椅子に座らせた。
「監禁しているのか?」
「まぁ、似たようなもんですかね?」
彼女はそんなことを言いながら、俺の隣にパイプ椅子において、そこに座った。
「うーん。疲れた!」
「お前が俺を無理やり引っ張るからだろ!」
俺は突っ込みを入れた。
俺の突っ込みは、完全に無視された。
「先輩、いつも見てる動画って、短いやつばかりですよね。なぜですか?」
「効率的だからだ。」
無視するつもりだったが、思わず口から言葉が漏れる。
「へえ、効率的。でも、それって本当に効率的なんですか?次から次へと新しい刺激を求めるだけじゃ、何も残らないと思いますけど。」
一ノ瀬の言葉が心に刺さる。何も残らない?それが目的なのに。
「残す必要はない。その瞬間を楽しめればいい。」
「でも、それって逃避じゃないですか?」
思わず顔を上げると、一ノ瀬の真剣な眼差しと目が合った。
「何から逃げてるんですか、先輩?」
「……黙れ。お前に何がわかる。」
スマホの画面を見つめ直す。動画を再生しようとするが、彼女からの視線が邪魔で集中できない。
ああ、なんなんだ、こいつ。
俺は心の中で愚痴った。
「先輩の好きな動画配信者、あの海外の人ですよね。毎週水曜に投稿してるやつ。」
その言葉に、再び顔を上げる。なぜそんなことまで知っている?
「…どうして知ってる?」
「当ててみただけです。」
一ノ瀬は微笑んだが、その目は笑っていなかった。
俺はもはや、この目の前にいるストーカーをどう解釈していいものか、悩んでしまった。
じっと、黙る。
「わかりました。今日はこれで。」
一ノ瀬は立ち上がった。
「では、明日も来ますね。先輩と話すのは、楽しいですね!」
「俺は楽しくない。」
俺はきっぱりと感想を言った。
「また、会いましょう!」
彼女は、そういいながら一ノ瀬は資料室を出て行った。
無視された。
…それはまあ、いいや。
彼女が去った後、俺は深いため息をついた。
なんだあいつは?
俺についてなぜそこまで知っている?
考えれば考えるほど不気味だった。
スマホを見るが、いつもの楽しみが台無しになった気分だ。
結局、その日の昼休みは何も手につかなかった。
俺の祈りが通じたのか、いつの間にか授業は終わり、いつものような昼休みが始まった。
生徒たちが教室から溢れ出し、中庭や学食へと向かっていく。
俺はひっそりと目立たないように学食へと向かった。
淡々と食事を終わらせて、俺は約束の地へと向かう。
その人の流れに背を向けるように、俺は階段へと足を向けた。
階段を一歩ずつ上りながら、周囲を確認する。
そして、誰もいないことを確認する。
そう、この昼休みにここの階段には人が少ない。
あとは資料室まで一直線だった。
四階に到着。
廊下は人気がなく、俺一人分の足音だけが虚しく響いた。
誰もが一階の学食や中庭に集まる時間帯だった。
だからこそ、ここは最高の隠れ家となる。
第四資料室の前に立ち、深呼吸する。ドアノブに手をかけ、回す。
ガチャリ。
「あ、先輩。こんにちは。」
予想外の声に、俺は一瞬で凍りついた。
資料室の窓際に、見知らぬ女子生徒が立っていた。
中等部の制服を着ていた。
細身の体格に、ショートカット。ジャギーの入った黒髪。
顔は整っており、小さな鼻や大きな目が特徴的でかわいいと感じられる風貌だった。
肌は透き通るような白さ、唇は薄めながらも自然な血色で、彼女の活発そうな雰囲気を生み出していた。
大きな瞳で俺を見つめている。
俺は無言で扉を閉め、踵を返した。
こんな場所に人がいるなんて、想定外だった。
今日はもう別の場所を探すしかない。
「ちょちょちょ、ちょっと、待ってください!」
背後から声がした。
次の瞬間、扉が再び開き、細い手が俺の制服の袖をつかんだ。
「離せ!それに誰だよ、お前!」
冷たく言い放ったが、女子生徒は手を放さない。
細いのに、異様に力が強い。
そのまま、引っ張られて資料室へと引きずり込まれてしまった。
…もしかして、俺、非力か?
「一ノ瀬ナズナです。中等部三年生です。先輩、逃げなくていいじゃないですかぁ!」
彼女は必死な様子で俺を引き留める。
「いいから、離せ!暑苦しい!」
「ちょっと、ちょっとだけ、お話しましょう?先輩?」
なぜか必死だ。しかしそれが余計にイライラさせた。
「嫌だ、俺はお前と話すことなど無い!」
「そんなことないでしょ?ね、先輩?」
そう言って、抵抗する俺をこいつは完全にシャットアウト。
もう疲れてきた。
いや、俺…。
目の前の女の子よりも力がないのか。
まあ、いいや。
疲れたのだから、俺は抵抗を辞めた。
それに、俺にはこいつに関して気がかりなところがあった。
「どうして俺のことを知ってる?」
そう、どうしてこいつは俺のことを先輩だと知っているんだ?
「先輩のことは色々知ってますよ。綾小路キョウ先輩、高等部一年生。『効率』を重視する生活を送っていて、スマホの動画を見るのが日課ですよね?」
一ノ瀬は俺の目をまっすぐ見つめながら言った。その視線には妙な既視感があった。
まるで昔からの知り合いのように俺を見つめていた。
もちろん、俺はこんなやつ、知らない。
「お前は誰だ?」
「一ノ瀬ナズナです。さっき言いましたよ?」
おどけた様子で彼女は俺にそう言った。
うるせぇ、と内心思った。
「お前、もしかして…。」
「なんですか?」
そうって彼女は、可愛らしく首をかしげている。
もちろん、俺の腕を離さずに…。
「俺をストーキングしてるのか?」
「違いますよ。たまたま、先輩がここにいることを知っていただけです。」
一ノ瀬は軽快に言った。
その態度はあまりにも自然で、かえって不自然に感じる。
「たまたま、今、会ったんだろ?」
「ああ、そうともいいますね!」
ニコニコと彼女は言った。
「なぜここにいる?」
なんだか、ばからしくなってきた俺は苛立ちを抑えきれなくなってきた。
「ちょっと静かな場所が欲しくて。中等部は昼休みうるさいんです。」
「他を探せ。ここは俺の場所だ。」
冷たく言い放つ。
「先輩のものじゃないですよね?学校の施設ですから。」
一ノ瀬は笑顔を崩さない。
まるで俺の反応を楽しんでいるかのようだ。
「……じゃあな。俺は出ていく、それでいいだろ。」
これ以上の会話は時間の無駄だ。
「いいえ、先輩。ここで一緒に動画でも見ましょうよ!」
「いやだ。」
俺は即答した。
怒りが込み上げてくる。
俺の生活は誰にも干渉されないように設計されている。
それが最も効率的だからだ。
赤の他人にとにかく言われる筋合いはない。
「まぁまぁ、そんなに怒らない。ねぇ、先輩。椅子に座ってください。」
後輩はそう言って、俺をさらに引っ張った。
「おいおい。」
俺は急に引っ張られたので、バランスを崩しそうになる。
彼女は俺の意思を完全に無視して、俺を半ば無理やりパイプ椅子に座らせた。
「監禁しているのか?」
「まぁ、似たようなもんですかね?」
彼女はそんなことを言いながら、俺の隣にパイプ椅子において、そこに座った。
「うーん。疲れた!」
「お前が俺を無理やり引っ張るからだろ!」
俺は突っ込みを入れた。
俺の突っ込みは、完全に無視された。
「先輩、いつも見てる動画って、短いやつばかりですよね。なぜですか?」
「効率的だからだ。」
無視するつもりだったが、思わず口から言葉が漏れる。
「へえ、効率的。でも、それって本当に効率的なんですか?次から次へと新しい刺激を求めるだけじゃ、何も残らないと思いますけど。」
一ノ瀬の言葉が心に刺さる。何も残らない?それが目的なのに。
「残す必要はない。その瞬間を楽しめればいい。」
「でも、それって逃避じゃないですか?」
思わず顔を上げると、一ノ瀬の真剣な眼差しと目が合った。
「何から逃げてるんですか、先輩?」
「……黙れ。お前に何がわかる。」
スマホの画面を見つめ直す。動画を再生しようとするが、彼女からの視線が邪魔で集中できない。
ああ、なんなんだ、こいつ。
俺は心の中で愚痴った。
「先輩の好きな動画配信者、あの海外の人ですよね。毎週水曜に投稿してるやつ。」
その言葉に、再び顔を上げる。なぜそんなことまで知っている?
「…どうして知ってる?」
「当ててみただけです。」
一ノ瀬は微笑んだが、その目は笑っていなかった。
俺はもはや、この目の前にいるストーカーをどう解釈していいものか、悩んでしまった。
じっと、黙る。
「わかりました。今日はこれで。」
一ノ瀬は立ち上がった。
「では、明日も来ますね。先輩と話すのは、楽しいですね!」
「俺は楽しくない。」
俺はきっぱりと感想を言った。
「また、会いましょう!」
彼女は、そういいながら一ノ瀬は資料室を出て行った。
無視された。
…それはまあ、いいや。
彼女が去った後、俺は深いため息をついた。
なんだあいつは?
俺についてなぜそこまで知っている?
考えれば考えるほど不気味だった。
スマホを見るが、いつもの楽しみが台無しになった気分だ。
結局、その日の昼休みは何も手につかなかった。