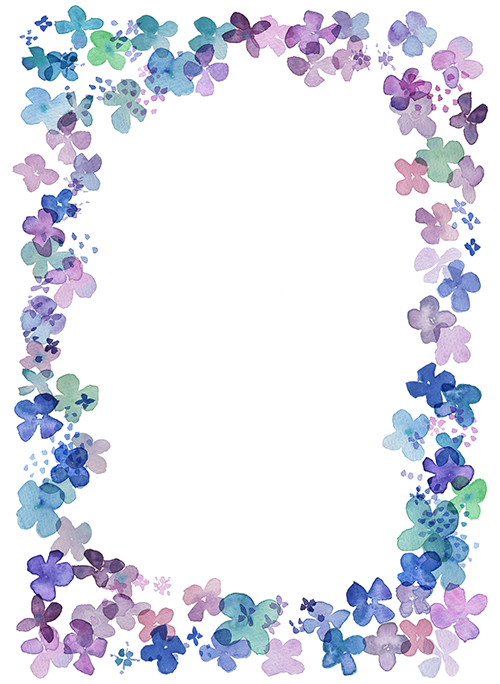丘の上から見える夜空には、花火大会の途中休憩のような静けさが広がっていた。
先ほどまでの連続した打ち上げ花火の煙がかすかに星明かりに照らされ、幾筋もの白い線を描いていた。
メインの花火は一段落したものの、フィナーレを飾る最後の一発がまだ残されているのだろう。そんな期待に満ちた静寂の中、一ノ瀬の言葉が落ちた。
「私には未来の記憶があります。」
その言葉に、一瞬何を言っているのか理解できなかった。
「何…?」
「信じられないと思います。でも、これが真実なんです。今の私の意識は、一年後の未来から戻ってきています。」
冗談を言っているのかと思ったが、彼女の目は真剣そのものだった。
満月と無数の星々の光に照らされた彼女の瞳には、嘘をついている様子は微塵も見えない。
俺は静かに彼女を見続けた。声が出なかった。
夜の風が通り過ぎていく。
遠くからは創立祭の最後の喧騒が、かすかに聞こえていた。
一ノ瀬は手を膝の上で組み、静かに話し始めた。
「一年後の未来で、私は高等部に進級して高校一年生になっていました。その時の先輩は高校二年生。私たちは高等部の創立祭で知り合い、徐々に親しくなっていきました。」
彼女の話によれば、未来では俺と彼女は高等部の創立祭がきっかけで知り合い、次第に特別な関係になっていったという。
その創立祭は、今日の中等部創立祭とはまた違うもの。それに未来の物語だ。
「その未来で、先輩は私に全てを話してくれました。中学時代のトラウマのこと、山下さんのこと、創作ノートのこと、そして『効率的』という言葉で自分を守っていたことも。」
それが、彼女が俺の過去をそれほど詳しく知っている理由だという。彼女は星空を見上げながら話を続けた。
「なぜ一年前に戻ったんだ?」
俺の声は、自分でも驚くほど冷静だった。頭の中は混乱していたのに。
「それが…私にもよく分からないんです。ある日突然、一年前の自分の体に戻されていたんです。なぜそうなったのか、どうしてこんなことが起きたのか、私には心当たりすらありません。」
一ノ瀬の話は荒唐無稽だった。
一年前に意識が戻る。タイムリープ。まるでSF小説の世界の出来事だ。
こんなことが現実に起こるはずがない。
しかし――そう考えながらも、不思議と納得している自分がいた。
ふと頭上を見上げると、無数の星々が夜空を彩っていた。月の光が差し込み、まるで別世界にいるような感覚を与えてくれた。
「それで、俺に近づいたのか?」
「はい。先輩に、もっと早く会いたかったんです。」
一ノ瀬は俺の方を向き、月明かりに照らされた彼女の顔は美しかった。
「本当に信じられないような話だが…お前の言うことを聞いていると、どこか納得してしまう自分がいる。」
この一ヶ月の出来事が、急に筋の通った物語として頭の中で整理されていく感覚。
あの不可解な言動、俺の過去への言及、何もかもが今、意味を持ち始めていた。
そうでなければ、説明のつかないことの数々。
彼女が俺の過去を詳細に知っていること、彼女の言動の不可解さ――そして何より、彼女の真剣な態度には、嘘はないように感じられた。
一ノ瀬は希望を込めた目で俺を見つめた。
彼女の睫毛が夜風でわずかに動いていた。
「先輩…信じてくれますか?」
「ああ、信じる。お前のことを信じる。」
その言葉に、一ノ瀬の目から涙が溢れ出した。月光に反射した透明な雫が頬を伝い落ちていた。
「ありがとうございます…本当に…。」
彼女が泣きながら言った時、遠くの空に最後の小さな花火が上がった。
赤と青の光が瞬き、夜空に一瞬の華を咲かせる。その閃光だけが丘の上の俺たちを照らし、隣にいる彼女の涙をきらめかせた。
そうだ、彼女はどれほど寂しかっただろう。
未来の記憶を持ちながら、誰にも打ち明けられず一人で抱えていた。両親や友人、そして俺がそばにいたとしても、彼女の特殊な事情を理解できる人間は誰もいなかった。
それは、きっと言葉にできないほどの孤独だったに違いない。
その思いが胸に刺さった。こんな風に他人のことを深く考えるなんて、一ヶ月前の俺には想像もできなかった。
「先輩と初めて会った日を覚えていますか?資料室で…。」
一ノ瀬は涙を拭いながら言った。彼女の声は少し震えていたが、それでも穏やかだった。
「ああ、俺はお前を見て逃げ出したんだよな。」
あの日のことを思い出す。資料室のドアを開けた瞬間、見知らぬ女子生徒がいて、無言で逃げ出した自分。今思えば、なんと滑稽な光景だったことか。
「はい。でも未来では、先輩から私に話しかけてくれたんです。高等部の創立祭で準備をしていた私に…。」
その話し方は、どこか遠い大切な思い出を語るかのようだった。
「俺から?それは意外だな。」
自分から誰かに話しかけるなんて、あまり考えられないことだった。
「そうなんです。だから、今度は私から先輩に近づこうと思ったんです。でも、最初は受け入れてもらえなくて…山下さんの話で脅すしかなくて…本当にごめんなさい。」
「今となっては、もういいさ。むしろ、お前のおかげで変われたのかもしれない。」
これは心の奥にしまっておく言葉だったはずなのに。
自分でも驚くほど素直な言葉が出てきた。
「本当ですか?」
「ああ。俺は人と関わるのが怖かっただけなんだ。」
草の葉が夜風にそよぎ、かすかな音を奏でていた。
頭上では星々が煌々と輝き、遠くからは創立祭の余韻が届いていた。
俺は言葉を続けた。
「でも、お前と過ごした時間は…『非効率的』なはずなのに、不思議と充実してた。ありがとう、一ノ瀬。」
その言葉に、一ノ瀬は満面の笑みを浮かべた。
「はい、先輩…。良かった。私、先輩のために、未来から帰ってきたんだって、って。そう思います。」
彼女はそっと俺の方を向いた。数週間前まで知らなかった人なのに、これほど近しく感じる不思議さ。
「先輩、これから先の未来は決まっていません。でも私は信じています。先輩と私は、また特別な関係になれると思います。」
彼女はそう言って目を閉じた。その表情には、穏やかさがあった。
そのすべてを語り終えた安堵。
秘密を打ち明けた後の静けさ。
俺はそんな彼女の姿をじっと見つめていた。
この一ヶ月で、どれほどの変化があっただろう。
最初は面倒でしかなかった彼女との付き合いが、いつの間にか俺の中心になっていた。
そう、ありがとう一ノ瀬。お前のおかげで、俺は変われた。
次の瞬間、一ノ瀬は目を開けた。
しかし、その表情は突然変わった。先ほどまでの穏やかさが消え、戸惑いに満ちた表情になった。彼女は周囲を見回し始めた。
「ここ…どこ…?なんで私…?」
その様子に、俺は不思議に思った。あまりにも急な変化に、一瞬何が起きたのか理解できなかった。
「一ノ瀬?どうした?」
彼女は俺を見て、明らかに驚いた表情を浮かべた。それは見知らぬ人を見る目だった。
「あなたは?そもそも、なぜここに…私はなぜ…?」
その瞬間、俺は理解した。
これが本来の一ノ瀬ナズナなのだ。未来からタイムリープしてきた意識が元に戻り、おそらく、本来の彼女の意識に戻ったのだ。
空気がピンと張り詰めた。何かが完全に変わってしまった感覚。
目の前にいるのは、同じ一ノ瀬なのに、全く別の人物だった。
戸惑い、混乱している彼女に、俺は優しく微笑みかけた。
「大丈夫だよ、一ノ瀬さん。何も心配することはないんだよ。」
目の前の状況が全く理解できないという表情。それも当然だろう。
彼女にとっては、突然見知らぬ場所で見知らぬ高校生と二人きりになっているのだから。
そんな彼女を前に、俺は勇気を出して言った。
「実は、君とはここ数週間、一緒に創立祭の準備をしていたんだ。今日は創立祭で、二人で花火を見に来たんだ。」
単純化して説明すると、彼女はますます困惑した表情になった。
「でも…私、あなたとはほとんど話したことがなくて…どうして…あなたとだけで…。」
そうか、本来の一ノ瀬にとって、俺はほとんど接点のない上級生なんだ。
すべてがリセットされたように感じる。けれど、俺の中の変化は、しっかりと残っている。
俺は深呼吸をして、彼女の目をまっすぐ見つめた。
乱暴に真実を告げるわけにもいかない。彼女を安心させることが先決だった。
「詳しいことは後で説明する。ただ、今は信じてほしい。」
驚きと戸惑いに満ちた目で俺を見つめる一ノ瀬。
彼女はまだ状況を理解していないようだが、俺の言葉に少し安心したような表情を見せた。
「わ、私は…。」
言葉を探す彼女に、俺は優しく微笑みかけた。
「どうして…あなたは、私といっしょに?」
「それは長い話なんだ。今はただ、ここから一緒に帰ろう。大丈夫、説明するから。」
俺は立ち上がり、彼女に手を差し伸べた。
少しためらった後、彼女はその手を取った。その手は冷たかったが、確かな温もりがあった。
一ノ瀬とともに丘を下りながら、俺は考えた。
そう、この出会いは偶然ではない。
未来から来た一ノ瀬の思いは、確かに俺を完全に変えてしまった。
今目の前にいる本来の一ノ瀬は、あの活発な彼女とは違う。
そんな彼女の様子が、一歩一歩と丘を下りる姿から伝わってくる。
だが、それでいい。
今度は俺が彼女に話しかけてくれたように、俺が彼女に話しかけるときなのかもしれない。
あの未来の彼女のように、自分から一歩踏み出す勇気を持つ時なのだろう。
夜空には月と煌びやかな星々が見えた。
創立祭の余韻が漂う校庭を遠くに見ながら、俺は一ノ瀬に今日一日のことを、少しずつ説明し始めた。
彼女は戸惑いながらも、小さく頷きながら聞いていた。
未来からの一ノ瀬が俺に教えてくれたことは、俺の中に残っていた。
効率だけではない、人生。
これからの日々は、きっと『効率的』ではないだろう。
もっと複雑で、時に面倒で、予測できないことだらけだろう。でも、それでいい。
星空の下、俺は一ノ瀬に説明をしながら歩き続けた。
そして、俺は思った。
そう、これは新しい出会い。そしてこれから俺は彼女と仲良くなるのかもしれない、と。
やがて俺は、この後輩に自分の書いた物語を見せる未来すら来るのかもしない。
それがいつになるのかは分からないけれども。
しかし、その未来は確実にやってくるような気がしていた。
先ほどまでの連続した打ち上げ花火の煙がかすかに星明かりに照らされ、幾筋もの白い線を描いていた。
メインの花火は一段落したものの、フィナーレを飾る最後の一発がまだ残されているのだろう。そんな期待に満ちた静寂の中、一ノ瀬の言葉が落ちた。
「私には未来の記憶があります。」
その言葉に、一瞬何を言っているのか理解できなかった。
「何…?」
「信じられないと思います。でも、これが真実なんです。今の私の意識は、一年後の未来から戻ってきています。」
冗談を言っているのかと思ったが、彼女の目は真剣そのものだった。
満月と無数の星々の光に照らされた彼女の瞳には、嘘をついている様子は微塵も見えない。
俺は静かに彼女を見続けた。声が出なかった。
夜の風が通り過ぎていく。
遠くからは創立祭の最後の喧騒が、かすかに聞こえていた。
一ノ瀬は手を膝の上で組み、静かに話し始めた。
「一年後の未来で、私は高等部に進級して高校一年生になっていました。その時の先輩は高校二年生。私たちは高等部の創立祭で知り合い、徐々に親しくなっていきました。」
彼女の話によれば、未来では俺と彼女は高等部の創立祭がきっかけで知り合い、次第に特別な関係になっていったという。
その創立祭は、今日の中等部創立祭とはまた違うもの。それに未来の物語だ。
「その未来で、先輩は私に全てを話してくれました。中学時代のトラウマのこと、山下さんのこと、創作ノートのこと、そして『効率的』という言葉で自分を守っていたことも。」
それが、彼女が俺の過去をそれほど詳しく知っている理由だという。彼女は星空を見上げながら話を続けた。
「なぜ一年前に戻ったんだ?」
俺の声は、自分でも驚くほど冷静だった。頭の中は混乱していたのに。
「それが…私にもよく分からないんです。ある日突然、一年前の自分の体に戻されていたんです。なぜそうなったのか、どうしてこんなことが起きたのか、私には心当たりすらありません。」
一ノ瀬の話は荒唐無稽だった。
一年前に意識が戻る。タイムリープ。まるでSF小説の世界の出来事だ。
こんなことが現実に起こるはずがない。
しかし――そう考えながらも、不思議と納得している自分がいた。
ふと頭上を見上げると、無数の星々が夜空を彩っていた。月の光が差し込み、まるで別世界にいるような感覚を与えてくれた。
「それで、俺に近づいたのか?」
「はい。先輩に、もっと早く会いたかったんです。」
一ノ瀬は俺の方を向き、月明かりに照らされた彼女の顔は美しかった。
「本当に信じられないような話だが…お前の言うことを聞いていると、どこか納得してしまう自分がいる。」
この一ヶ月の出来事が、急に筋の通った物語として頭の中で整理されていく感覚。
あの不可解な言動、俺の過去への言及、何もかもが今、意味を持ち始めていた。
そうでなければ、説明のつかないことの数々。
彼女が俺の過去を詳細に知っていること、彼女の言動の不可解さ――そして何より、彼女の真剣な態度には、嘘はないように感じられた。
一ノ瀬は希望を込めた目で俺を見つめた。
彼女の睫毛が夜風でわずかに動いていた。
「先輩…信じてくれますか?」
「ああ、信じる。お前のことを信じる。」
その言葉に、一ノ瀬の目から涙が溢れ出した。月光に反射した透明な雫が頬を伝い落ちていた。
「ありがとうございます…本当に…。」
彼女が泣きながら言った時、遠くの空に最後の小さな花火が上がった。
赤と青の光が瞬き、夜空に一瞬の華を咲かせる。その閃光だけが丘の上の俺たちを照らし、隣にいる彼女の涙をきらめかせた。
そうだ、彼女はどれほど寂しかっただろう。
未来の記憶を持ちながら、誰にも打ち明けられず一人で抱えていた。両親や友人、そして俺がそばにいたとしても、彼女の特殊な事情を理解できる人間は誰もいなかった。
それは、きっと言葉にできないほどの孤独だったに違いない。
その思いが胸に刺さった。こんな風に他人のことを深く考えるなんて、一ヶ月前の俺には想像もできなかった。
「先輩と初めて会った日を覚えていますか?資料室で…。」
一ノ瀬は涙を拭いながら言った。彼女の声は少し震えていたが、それでも穏やかだった。
「ああ、俺はお前を見て逃げ出したんだよな。」
あの日のことを思い出す。資料室のドアを開けた瞬間、見知らぬ女子生徒がいて、無言で逃げ出した自分。今思えば、なんと滑稽な光景だったことか。
「はい。でも未来では、先輩から私に話しかけてくれたんです。高等部の創立祭で準備をしていた私に…。」
その話し方は、どこか遠い大切な思い出を語るかのようだった。
「俺から?それは意外だな。」
自分から誰かに話しかけるなんて、あまり考えられないことだった。
「そうなんです。だから、今度は私から先輩に近づこうと思ったんです。でも、最初は受け入れてもらえなくて…山下さんの話で脅すしかなくて…本当にごめんなさい。」
「今となっては、もういいさ。むしろ、お前のおかげで変われたのかもしれない。」
これは心の奥にしまっておく言葉だったはずなのに。
自分でも驚くほど素直な言葉が出てきた。
「本当ですか?」
「ああ。俺は人と関わるのが怖かっただけなんだ。」
草の葉が夜風にそよぎ、かすかな音を奏でていた。
頭上では星々が煌々と輝き、遠くからは創立祭の余韻が届いていた。
俺は言葉を続けた。
「でも、お前と過ごした時間は…『非効率的』なはずなのに、不思議と充実してた。ありがとう、一ノ瀬。」
その言葉に、一ノ瀬は満面の笑みを浮かべた。
「はい、先輩…。良かった。私、先輩のために、未来から帰ってきたんだって、って。そう思います。」
彼女はそっと俺の方を向いた。数週間前まで知らなかった人なのに、これほど近しく感じる不思議さ。
「先輩、これから先の未来は決まっていません。でも私は信じています。先輩と私は、また特別な関係になれると思います。」
彼女はそう言って目を閉じた。その表情には、穏やかさがあった。
そのすべてを語り終えた安堵。
秘密を打ち明けた後の静けさ。
俺はそんな彼女の姿をじっと見つめていた。
この一ヶ月で、どれほどの変化があっただろう。
最初は面倒でしかなかった彼女との付き合いが、いつの間にか俺の中心になっていた。
そう、ありがとう一ノ瀬。お前のおかげで、俺は変われた。
次の瞬間、一ノ瀬は目を開けた。
しかし、その表情は突然変わった。先ほどまでの穏やかさが消え、戸惑いに満ちた表情になった。彼女は周囲を見回し始めた。
「ここ…どこ…?なんで私…?」
その様子に、俺は不思議に思った。あまりにも急な変化に、一瞬何が起きたのか理解できなかった。
「一ノ瀬?どうした?」
彼女は俺を見て、明らかに驚いた表情を浮かべた。それは見知らぬ人を見る目だった。
「あなたは?そもそも、なぜここに…私はなぜ…?」
その瞬間、俺は理解した。
これが本来の一ノ瀬ナズナなのだ。未来からタイムリープしてきた意識が元に戻り、おそらく、本来の彼女の意識に戻ったのだ。
空気がピンと張り詰めた。何かが完全に変わってしまった感覚。
目の前にいるのは、同じ一ノ瀬なのに、全く別の人物だった。
戸惑い、混乱している彼女に、俺は優しく微笑みかけた。
「大丈夫だよ、一ノ瀬さん。何も心配することはないんだよ。」
目の前の状況が全く理解できないという表情。それも当然だろう。
彼女にとっては、突然見知らぬ場所で見知らぬ高校生と二人きりになっているのだから。
そんな彼女を前に、俺は勇気を出して言った。
「実は、君とはここ数週間、一緒に創立祭の準備をしていたんだ。今日は創立祭で、二人で花火を見に来たんだ。」
単純化して説明すると、彼女はますます困惑した表情になった。
「でも…私、あなたとはほとんど話したことがなくて…どうして…あなたとだけで…。」
そうか、本来の一ノ瀬にとって、俺はほとんど接点のない上級生なんだ。
すべてがリセットされたように感じる。けれど、俺の中の変化は、しっかりと残っている。
俺は深呼吸をして、彼女の目をまっすぐ見つめた。
乱暴に真実を告げるわけにもいかない。彼女を安心させることが先決だった。
「詳しいことは後で説明する。ただ、今は信じてほしい。」
驚きと戸惑いに満ちた目で俺を見つめる一ノ瀬。
彼女はまだ状況を理解していないようだが、俺の言葉に少し安心したような表情を見せた。
「わ、私は…。」
言葉を探す彼女に、俺は優しく微笑みかけた。
「どうして…あなたは、私といっしょに?」
「それは長い話なんだ。今はただ、ここから一緒に帰ろう。大丈夫、説明するから。」
俺は立ち上がり、彼女に手を差し伸べた。
少しためらった後、彼女はその手を取った。その手は冷たかったが、確かな温もりがあった。
一ノ瀬とともに丘を下りながら、俺は考えた。
そう、この出会いは偶然ではない。
未来から来た一ノ瀬の思いは、確かに俺を完全に変えてしまった。
今目の前にいる本来の一ノ瀬は、あの活発な彼女とは違う。
そんな彼女の様子が、一歩一歩と丘を下りる姿から伝わってくる。
だが、それでいい。
今度は俺が彼女に話しかけてくれたように、俺が彼女に話しかけるときなのかもしれない。
あの未来の彼女のように、自分から一歩踏み出す勇気を持つ時なのだろう。
夜空には月と煌びやかな星々が見えた。
創立祭の余韻が漂う校庭を遠くに見ながら、俺は一ノ瀬に今日一日のことを、少しずつ説明し始めた。
彼女は戸惑いながらも、小さく頷きながら聞いていた。
未来からの一ノ瀬が俺に教えてくれたことは、俺の中に残っていた。
効率だけではない、人生。
これからの日々は、きっと『効率的』ではないだろう。
もっと複雑で、時に面倒で、予測できないことだらけだろう。でも、それでいい。
星空の下、俺は一ノ瀬に説明をしながら歩き続けた。
そして、俺は思った。
そう、これは新しい出会い。そしてこれから俺は彼女と仲良くなるのかもしれない、と。
やがて俺は、この後輩に自分の書いた物語を見せる未来すら来るのかもしない。
それがいつになるのかは分からないけれども。
しかし、その未来は確実にやってくるような気がしていた。