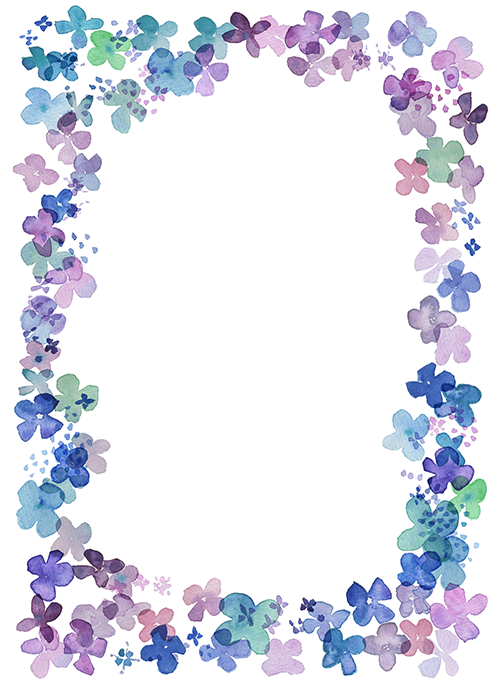「先輩、ちょっと休憩しませんか?」
一ノ瀬が提案した。確かに、もう二時間近く歩き回っていた。
「そうだな。」
人の少ない階段の踊り場に腰掛ける。
窓からは校庭の賑わいが見えた。
「楽しいですか?」
一ノ瀬が突然聞いてきた。
「ああ、思ったより。」
正直に答えると、彼女は嬉しそうな表情になった。
「よかった…本当によかったです!」
彼女は『俺が楽しい』といったことをまるで自分が感じたことのように喜んでいた。
「じゃあ、先輩、次はどこに行きたいですか?」
後輩の言葉に対して、俺は一瞬の思考を働かせた。
「特にないけど、人の少ないところがいいな。」
人ごみの中を長時間歩き回ると、やはり疲れるのだ。
「そうですね…あ、そういえば。」
彼女は何かを思いついたような表情をした。
「あの場所に行ってみませんか?」
「あの場所?」
「初めて会った場所です。」
その言葉で、彼女が何を言っているのか理解した。
「資料室か。」
何か含みのある笑顔を浮かべる、一ノ瀬。
「おい、違うのか?」
思わずそんな言葉が口から出た。
「いいえ、資料室です。そこへ行ってみましょう。」
「ああ。」
一ノ瀬の提案に素直に従い、高等部棟の最上階へと向かった。
階段を上りながら、俺は当時の思い出を振り返っていた。
以前は毎日のように通っていた資料室だが、一ノ瀬と過ごすようになってからは、雨の日以外に、ほとんど足を踏み入れていなかった。
四階に到着し、第四資料室の前に立つ。
扉は相変わらずの様子で、そこには『第四資料室』と書かれたプレートがかかっていた。
「そういえば、俺はお前を見て逃げ出したんだよな。」
俺は自然にそのセリフを口に出していた。
「先輩、中に入りましょうよ!」
一ノ瀬の提案に、少しためらいながらも頷いた。
ドアノブを回すと、カギはかかっていなかった。
ドアが開いた。
中に入ると、なにも変わっていなかった。
埃を被った本棚、パイプ椅子、机。窓のカーテンは開けられていて、昼の光が部屋を照らしていた。
ここは、俺が毎日のように通っていた場所。
一ノ瀬はじっと、その部屋を見ていた。
俺も視線を合わせて、資料室を見た。
そして、パイプ椅子に座ると、以前と同じように埃が舞い上がった。
「ここで先輩はいつも何をしていたんですか?」
一ノ瀬が聞いてきた。彼女は知っているはずなのに、なぜまた聞くのだろう。
「動画を見ていた。」
俺はこれまでに何度も言った言葉を口に出した。
彼女は俺を見ていた。
「…先輩は変わりましたよね。」
一ノ瀬はそう言って、小さく笑った。
「おい、どういう意味だ?」
「最初は全然話してくれなかったのに、今は自分から話すこともあるし、人とも普通に接している。」
彼女の言葉に、確かに自分の変化を実感した。今日の案内係もそうだ。一ヶ月前の俺なら、絶対にできなかったことだ。
「それが何か?」
「嬉しいです。本当の先輩に会えた気がして。」
彼女の真摯な言葉に、何か心の奥が震えるような感覚を覚えた。
「俺はいつも本当の俺だぞ?」
「そう…ですね。」
彼女は微笑みながら、俺を見ていた。
その表情は、うまく言うことができない。
もしそれを言葉で表現できるとすれば…、彼女は俺を通して、どこか遠くを見ているみたいだった。
そう、遠くを。
しばらく沈黙を楽しんだ後、一ノ瀬が言った。
「もう一ヶ所、行きたい場所があります。」
「どこだ?」
「屋上です。」
資料室を後にし、さらに階段を上がって屋上へと向かった。
屋上のドア。
そこもカギはかかっていなかった。
この学校のセキュリティの低さが気になったが、俺には都合がよい。
そう思いこんだ。
ああ、そうだ。
ここもある意味、思い出の場所だった。
一ノ瀬に脅されて、渋々昼食を共にし始めた場所。
今では当たり前のように一緒に弁当を食べる場所になっていた。
「ここからの景色、好きなんです。」
一ノ瀬が柵に寄りかかり、校庭を見下ろした。
創立祭で賑わう校庭は、上から見ると小さな祭りのように見えた。
「俺も悪くないと思うようになった。」
素直な感想を言うと、一ノ瀬の顔が明るくなった。
「本当ですか?嬉しいです!」
風が彼女の髪を揺らす。短いジャギーヘアが踊るようだった。
「先輩、この学校に入学してよかったですか?」
突然の質問に、考え込んでしまった。
「さあな。」
正直なところ、答えが分からなかった。
最初は誰とも関わらない『効率的』な生活を送るためにこの学校を選んだ。しかし今は、一ノ瀬という後輩と毎日を過ごしている。
「でも、先輩がここにいなかったら、私と会うことはなかったかもしれません。」
一ノ瀬のその言葉に、何か特別な重みを感じた。
「そうだな。」
屋上から見える景色を眺めながら、ふと俺は考えた。
一ヶ月前の自分には想像もできなかった今の状況。
人との関わりを避けていた自分が、今はこうして創立祭を楽しんでいる。
一ノ瀬ナズナという少女との出会いが、これまでの俺の在り方を破壊してしまったように感じた。
「そろそろ休憩所に戻らないといけないかな?」
「あ、本当ですね。すみません、つい時間を忘れてしまいました。」
一ノ瀬はすぐに態勢を立て直した。
「行きましょう!午後の交代時間ですね。」
彼女は円満の笑みを浮かべた。
元気いっぱいの彼女。
俺はその眩しすぎる彼女の影響を受けすぎていると感じた。
◇
休憩所に戻ると、先ほどの交代要員から再び仕事を引き継いだ。
午後も来場者は途切れることなく、パンフレット配りや案内で忙しかった。
しかし、午前中と違って、俺は自然に対応できるようになっていた。
笑顔での挨拶、的確な案内、質問への丁寧な回答。
さすがの俺も慣れつつあった。
「先輩、すごく上手になりましたね!」
一ノ瀬がそう褒めてくれると、少し照れくさい気分になった。
「そうか?まあ、慣れただけだ。」
「いえ、先輩の本来の優しさが出てるんですよ。」
その言葉に、何と返していいか分からなかった。
俺が優しい?
そんな風に言われたことは今までなかった。
「俺が?優しい?」
「そうですよ!」
彼女は自信満々にそう答えた。
「そうかね?まあ、確かに俺ほど優しい人は世の中にいないな。」
俺は皮肉を込めながら、自虐を行った。
「はぁ、まあ…。先輩らしいというか。」
彼女は苦笑いしていた。
◇
こうして午後の時間も過ぎていき、夕方になると、校内放送が流れた。
「皆様、本日は第三学園中等部創立祭にお越しいただき、ありがとうございます。間もなく午後六時となります。創立祭の締めくくりとして、これより校庭にて花火を打ち上げます。どうぞお楽しみください。」
一ノ瀬は俺を見て、目を輝かせた。
「先輩、花火があるんですよ!」
「ああ、そういえば、そうだったな。」
そうだ。
それは、俺が今日ここにいる理由の一つだった。
周囲を見ると、休憩所の来場者もだいぶ減ってきていた。
多くの人が花火の場所取りに向かっているようだ。
「そろそろ片付けを始めましょうか。花火までにはまだ少し時間がありますが、準備しておかないと。」
一ノ瀬の提案に頷き、俺たちは休憩所の片付けを始めた。
使われていない椅子を畳み、ゴミを集め、パンフレットを整理する。
他の実行委員たちも手伝いに来て、作業は順調に進んだ。
片付けが終わると、一ノ瀬がにっこりと笑った。
「先輩、ずっと手伝ってくれてありがとうございます。本当に助かりました。」
「別に。約束しただけだ。」
そうは答えたものの、以前ほど素っ気なさを込めることができなかった。
実際、今日一日は予想以上に充実していたし、案外楽しかった。
「でも、私は先輩が来てくれて嬉しかったです!」
一ノ瀬の言葉に、どう返していいか分からなかった。
周りを見ると、生徒たちが続々と校庭に集まり始めていた。
花火の準備が始まっているようだ。
「さぁて、先輩、花火を一緒に行きますよ!」
「ああ、行こう。」
俺は答えた。
そう、これからこの謎に満ちた後輩と一緒に花火を見る。
そして目の前の先輩の告白を聞くことになる。
そう、彼女の秘密について。
それが何なのか、今の俺には予想もつかない。
しかし、きっと事実は大したことではないのだろう。
そう思った。
◇
俺たちは実行委員の腕章を返却し、丘へと向かった。
学校の裏手に回り、小さな坂を上っていく。
木々の間を抜けると、見晴らしの良い場所に出た。
ここからは学校全体が見渡せる。
校庭には人々が集まり、花火の打ち上げ準備が進んでいる様子も見える。空はすでに夕暮れ色に染まり始めていた。
「ここからの景色、綺麗ですね。」
一ノ瀬が感嘆の声を上げた。確かに、ここからの眺めは素晴らしかった。
「ああ。」
俺も同意する。
そして、俺と一ノ瀬は隣り合う位置で丘の上に腰を下ろし、花火の始まりを待った。
風が心地よく吹き、一日の疲れを癒してくれる。
この静かな場所で、今日一日を振り返る。一ヶ月前の俺には想像もできなかった一日だった。
「先輩、今日は楽しかったですか?」
一ノ瀬が再び質問してきた。
「ああ、意外と。」
素直に答えると、彼女は満面の笑みを浮かべた。
「本当に?よかった!私も先輩と一緒に過ごせて楽しかったです。」
その言葉に何か心温まるものを感じた。
それは、かなり久しぶりな感覚だった。
俺は迷った。その気持ちを口に出すべきなのか。
じっと、後輩を見る。
彼女の女子生徒らしい容姿が見えた。
「なんですか?先輩?」
「いいや、なんでもない。」
俺は言いよどんだ。
「あはは。」
彼女は笑った。
でも、それ以上、彼女は何も聞いてこなかった。
だから、俺も黙って花火を待つことにした。
◇
しばらくして、校庭から最初の打ち上げ花火の音が聞こえた。
「始まりました!」
一ノ瀬が嬉しそうに声を上げた。
夜空に最初の花火が大きく開き、辺りを明るく照らす。鮮やかな色が広がり、続いて二発、三発と打ち上げられていく。
丘の上からの眺めは格別だった。
学校の上空に広がる花火が、打ち上げられて花が咲く。
「綺麗…。」
一ノ瀬のつぶやきが聞こえた。彼女の横顔が花火の光に照らされ、神秘的に見えた。
「ああ、すごくいい場所だな。」
率直な感想を伝えると、彼女は嬉しそうに微笑んだ。
「実は…ここは私の大切な場所なんです。誰にも教えたことがなかった。」
その言葉に、何か特別なものを感じた。彼女にとって秘密の場所を、俺に共有してくれたのだ。
「なぜ俺に?」
花火の合間に尋ねる。
「先輩は特別だからです。」
彼女の瞳が真剣に俺を見つめていた。
次々と打ち上げられる花火を眺めながら、俺たちは静かに座っていた。普段なら退屈に感じるような時間でも、今は心地よい沈黙だった。
「先輩、私の隣にいるとき、どんな気持ちになりますか?」
突然の質問に、少し戸惑った。
「どんな気持ちって…普通だ。」
「そうですか?」
俺の適当な回答に彼女は一瞬考えるような仕草をした。
「…ええっとですね、先輩。きっと、最初は私に脅されて仕方なく付き合ってたと思いますけど、それは今も同じですか?」
「…最初はそうだった。お前に脅されて、嫌々付き合っていた。だが今は…違う。」
「違う?」
「お前と一緒にいても、嫌じゃない。むしろ…」
言葉を選びながら続ける。
「楽しいと思うこともある。」
その言葉に、一ノ瀬の顔に喜びが広がった。
「本当ですか?嬉しいです…。」
花火の明かりに照らされた彼女の顔に、涙が光っているのが見えた。
「なぜ泣く?」
「嬉しいからです。先輩がそう言ってくれるのを、ずっと待っていたから。」
その言葉の意味を考える間もなく、大きな花火が打ち上がり、俺たちの会話を一瞬中断させた。
しばらく花火を眺めた後、一ノ瀬が再び口を開いた。
「先輩は中学時代、本当に辛かったんですよね。山下さんに振られて、クラスの笑いものになって…」
突然過去の話題に戻られて、胸が締め付けられる感覚がした。しかし、以前のような激しい拒絶反応は起きなかった。
「ああ、最悪だった。」
素直に認める俺に、一ノ瀬は優しい目を向けた。
「でも先輩、一つだけ知っておいてほしいことがあります。あの出来事は、先輩が悪いわけじゃないんです。それを笑う人たちこそが間違っていたんです。」
「…そうかもな。」
静かに答える。
「先輩が高校で誰とも関わらないように生きてきたのも、あの痛みをもう一度味わいたくなかったからですよね。」
「ああ。」
俺はようやく、その言葉を口にした。
夜空に打ち上げられる、花火が終わりに近づいていた。
一ノ瀬が提案した。確かに、もう二時間近く歩き回っていた。
「そうだな。」
人の少ない階段の踊り場に腰掛ける。
窓からは校庭の賑わいが見えた。
「楽しいですか?」
一ノ瀬が突然聞いてきた。
「ああ、思ったより。」
正直に答えると、彼女は嬉しそうな表情になった。
「よかった…本当によかったです!」
彼女は『俺が楽しい』といったことをまるで自分が感じたことのように喜んでいた。
「じゃあ、先輩、次はどこに行きたいですか?」
後輩の言葉に対して、俺は一瞬の思考を働かせた。
「特にないけど、人の少ないところがいいな。」
人ごみの中を長時間歩き回ると、やはり疲れるのだ。
「そうですね…あ、そういえば。」
彼女は何かを思いついたような表情をした。
「あの場所に行ってみませんか?」
「あの場所?」
「初めて会った場所です。」
その言葉で、彼女が何を言っているのか理解した。
「資料室か。」
何か含みのある笑顔を浮かべる、一ノ瀬。
「おい、違うのか?」
思わずそんな言葉が口から出た。
「いいえ、資料室です。そこへ行ってみましょう。」
「ああ。」
一ノ瀬の提案に素直に従い、高等部棟の最上階へと向かった。
階段を上りながら、俺は当時の思い出を振り返っていた。
以前は毎日のように通っていた資料室だが、一ノ瀬と過ごすようになってからは、雨の日以外に、ほとんど足を踏み入れていなかった。
四階に到着し、第四資料室の前に立つ。
扉は相変わらずの様子で、そこには『第四資料室』と書かれたプレートがかかっていた。
「そういえば、俺はお前を見て逃げ出したんだよな。」
俺は自然にそのセリフを口に出していた。
「先輩、中に入りましょうよ!」
一ノ瀬の提案に、少しためらいながらも頷いた。
ドアノブを回すと、カギはかかっていなかった。
ドアが開いた。
中に入ると、なにも変わっていなかった。
埃を被った本棚、パイプ椅子、机。窓のカーテンは開けられていて、昼の光が部屋を照らしていた。
ここは、俺が毎日のように通っていた場所。
一ノ瀬はじっと、その部屋を見ていた。
俺も視線を合わせて、資料室を見た。
そして、パイプ椅子に座ると、以前と同じように埃が舞い上がった。
「ここで先輩はいつも何をしていたんですか?」
一ノ瀬が聞いてきた。彼女は知っているはずなのに、なぜまた聞くのだろう。
「動画を見ていた。」
俺はこれまでに何度も言った言葉を口に出した。
彼女は俺を見ていた。
「…先輩は変わりましたよね。」
一ノ瀬はそう言って、小さく笑った。
「おい、どういう意味だ?」
「最初は全然話してくれなかったのに、今は自分から話すこともあるし、人とも普通に接している。」
彼女の言葉に、確かに自分の変化を実感した。今日の案内係もそうだ。一ヶ月前の俺なら、絶対にできなかったことだ。
「それが何か?」
「嬉しいです。本当の先輩に会えた気がして。」
彼女の真摯な言葉に、何か心の奥が震えるような感覚を覚えた。
「俺はいつも本当の俺だぞ?」
「そう…ですね。」
彼女は微笑みながら、俺を見ていた。
その表情は、うまく言うことができない。
もしそれを言葉で表現できるとすれば…、彼女は俺を通して、どこか遠くを見ているみたいだった。
そう、遠くを。
しばらく沈黙を楽しんだ後、一ノ瀬が言った。
「もう一ヶ所、行きたい場所があります。」
「どこだ?」
「屋上です。」
資料室を後にし、さらに階段を上がって屋上へと向かった。
屋上のドア。
そこもカギはかかっていなかった。
この学校のセキュリティの低さが気になったが、俺には都合がよい。
そう思いこんだ。
ああ、そうだ。
ここもある意味、思い出の場所だった。
一ノ瀬に脅されて、渋々昼食を共にし始めた場所。
今では当たり前のように一緒に弁当を食べる場所になっていた。
「ここからの景色、好きなんです。」
一ノ瀬が柵に寄りかかり、校庭を見下ろした。
創立祭で賑わう校庭は、上から見ると小さな祭りのように見えた。
「俺も悪くないと思うようになった。」
素直な感想を言うと、一ノ瀬の顔が明るくなった。
「本当ですか?嬉しいです!」
風が彼女の髪を揺らす。短いジャギーヘアが踊るようだった。
「先輩、この学校に入学してよかったですか?」
突然の質問に、考え込んでしまった。
「さあな。」
正直なところ、答えが分からなかった。
最初は誰とも関わらない『効率的』な生活を送るためにこの学校を選んだ。しかし今は、一ノ瀬という後輩と毎日を過ごしている。
「でも、先輩がここにいなかったら、私と会うことはなかったかもしれません。」
一ノ瀬のその言葉に、何か特別な重みを感じた。
「そうだな。」
屋上から見える景色を眺めながら、ふと俺は考えた。
一ヶ月前の自分には想像もできなかった今の状況。
人との関わりを避けていた自分が、今はこうして創立祭を楽しんでいる。
一ノ瀬ナズナという少女との出会いが、これまでの俺の在り方を破壊してしまったように感じた。
「そろそろ休憩所に戻らないといけないかな?」
「あ、本当ですね。すみません、つい時間を忘れてしまいました。」
一ノ瀬はすぐに態勢を立て直した。
「行きましょう!午後の交代時間ですね。」
彼女は円満の笑みを浮かべた。
元気いっぱいの彼女。
俺はその眩しすぎる彼女の影響を受けすぎていると感じた。
◇
休憩所に戻ると、先ほどの交代要員から再び仕事を引き継いだ。
午後も来場者は途切れることなく、パンフレット配りや案内で忙しかった。
しかし、午前中と違って、俺は自然に対応できるようになっていた。
笑顔での挨拶、的確な案内、質問への丁寧な回答。
さすがの俺も慣れつつあった。
「先輩、すごく上手になりましたね!」
一ノ瀬がそう褒めてくれると、少し照れくさい気分になった。
「そうか?まあ、慣れただけだ。」
「いえ、先輩の本来の優しさが出てるんですよ。」
その言葉に、何と返していいか分からなかった。
俺が優しい?
そんな風に言われたことは今までなかった。
「俺が?優しい?」
「そうですよ!」
彼女は自信満々にそう答えた。
「そうかね?まあ、確かに俺ほど優しい人は世の中にいないな。」
俺は皮肉を込めながら、自虐を行った。
「はぁ、まあ…。先輩らしいというか。」
彼女は苦笑いしていた。
◇
こうして午後の時間も過ぎていき、夕方になると、校内放送が流れた。
「皆様、本日は第三学園中等部創立祭にお越しいただき、ありがとうございます。間もなく午後六時となります。創立祭の締めくくりとして、これより校庭にて花火を打ち上げます。どうぞお楽しみください。」
一ノ瀬は俺を見て、目を輝かせた。
「先輩、花火があるんですよ!」
「ああ、そういえば、そうだったな。」
そうだ。
それは、俺が今日ここにいる理由の一つだった。
周囲を見ると、休憩所の来場者もだいぶ減ってきていた。
多くの人が花火の場所取りに向かっているようだ。
「そろそろ片付けを始めましょうか。花火までにはまだ少し時間がありますが、準備しておかないと。」
一ノ瀬の提案に頷き、俺たちは休憩所の片付けを始めた。
使われていない椅子を畳み、ゴミを集め、パンフレットを整理する。
他の実行委員たちも手伝いに来て、作業は順調に進んだ。
片付けが終わると、一ノ瀬がにっこりと笑った。
「先輩、ずっと手伝ってくれてありがとうございます。本当に助かりました。」
「別に。約束しただけだ。」
そうは答えたものの、以前ほど素っ気なさを込めることができなかった。
実際、今日一日は予想以上に充実していたし、案外楽しかった。
「でも、私は先輩が来てくれて嬉しかったです!」
一ノ瀬の言葉に、どう返していいか分からなかった。
周りを見ると、生徒たちが続々と校庭に集まり始めていた。
花火の準備が始まっているようだ。
「さぁて、先輩、花火を一緒に行きますよ!」
「ああ、行こう。」
俺は答えた。
そう、これからこの謎に満ちた後輩と一緒に花火を見る。
そして目の前の先輩の告白を聞くことになる。
そう、彼女の秘密について。
それが何なのか、今の俺には予想もつかない。
しかし、きっと事実は大したことではないのだろう。
そう思った。
◇
俺たちは実行委員の腕章を返却し、丘へと向かった。
学校の裏手に回り、小さな坂を上っていく。
木々の間を抜けると、見晴らしの良い場所に出た。
ここからは学校全体が見渡せる。
校庭には人々が集まり、花火の打ち上げ準備が進んでいる様子も見える。空はすでに夕暮れ色に染まり始めていた。
「ここからの景色、綺麗ですね。」
一ノ瀬が感嘆の声を上げた。確かに、ここからの眺めは素晴らしかった。
「ああ。」
俺も同意する。
そして、俺と一ノ瀬は隣り合う位置で丘の上に腰を下ろし、花火の始まりを待った。
風が心地よく吹き、一日の疲れを癒してくれる。
この静かな場所で、今日一日を振り返る。一ヶ月前の俺には想像もできなかった一日だった。
「先輩、今日は楽しかったですか?」
一ノ瀬が再び質問してきた。
「ああ、意外と。」
素直に答えると、彼女は満面の笑みを浮かべた。
「本当に?よかった!私も先輩と一緒に過ごせて楽しかったです。」
その言葉に何か心温まるものを感じた。
それは、かなり久しぶりな感覚だった。
俺は迷った。その気持ちを口に出すべきなのか。
じっと、後輩を見る。
彼女の女子生徒らしい容姿が見えた。
「なんですか?先輩?」
「いいや、なんでもない。」
俺は言いよどんだ。
「あはは。」
彼女は笑った。
でも、それ以上、彼女は何も聞いてこなかった。
だから、俺も黙って花火を待つことにした。
◇
しばらくして、校庭から最初の打ち上げ花火の音が聞こえた。
「始まりました!」
一ノ瀬が嬉しそうに声を上げた。
夜空に最初の花火が大きく開き、辺りを明るく照らす。鮮やかな色が広がり、続いて二発、三発と打ち上げられていく。
丘の上からの眺めは格別だった。
学校の上空に広がる花火が、打ち上げられて花が咲く。
「綺麗…。」
一ノ瀬のつぶやきが聞こえた。彼女の横顔が花火の光に照らされ、神秘的に見えた。
「ああ、すごくいい場所だな。」
率直な感想を伝えると、彼女は嬉しそうに微笑んだ。
「実は…ここは私の大切な場所なんです。誰にも教えたことがなかった。」
その言葉に、何か特別なものを感じた。彼女にとって秘密の場所を、俺に共有してくれたのだ。
「なぜ俺に?」
花火の合間に尋ねる。
「先輩は特別だからです。」
彼女の瞳が真剣に俺を見つめていた。
次々と打ち上げられる花火を眺めながら、俺たちは静かに座っていた。普段なら退屈に感じるような時間でも、今は心地よい沈黙だった。
「先輩、私の隣にいるとき、どんな気持ちになりますか?」
突然の質問に、少し戸惑った。
「どんな気持ちって…普通だ。」
「そうですか?」
俺の適当な回答に彼女は一瞬考えるような仕草をした。
「…ええっとですね、先輩。きっと、最初は私に脅されて仕方なく付き合ってたと思いますけど、それは今も同じですか?」
「…最初はそうだった。お前に脅されて、嫌々付き合っていた。だが今は…違う。」
「違う?」
「お前と一緒にいても、嫌じゃない。むしろ…」
言葉を選びながら続ける。
「楽しいと思うこともある。」
その言葉に、一ノ瀬の顔に喜びが広がった。
「本当ですか?嬉しいです…。」
花火の明かりに照らされた彼女の顔に、涙が光っているのが見えた。
「なぜ泣く?」
「嬉しいからです。先輩がそう言ってくれるのを、ずっと待っていたから。」
その言葉の意味を考える間もなく、大きな花火が打ち上がり、俺たちの会話を一瞬中断させた。
しばらく花火を眺めた後、一ノ瀬が再び口を開いた。
「先輩は中学時代、本当に辛かったんですよね。山下さんに振られて、クラスの笑いものになって…」
突然過去の話題に戻られて、胸が締め付けられる感覚がした。しかし、以前のような激しい拒絶反応は起きなかった。
「ああ、最悪だった。」
素直に認める俺に、一ノ瀬は優しい目を向けた。
「でも先輩、一つだけ知っておいてほしいことがあります。あの出来事は、先輩が悪いわけじゃないんです。それを笑う人たちこそが間違っていたんです。」
「…そうかもな。」
静かに答える。
「先輩が高校で誰とも関わらないように生きてきたのも、あの痛みをもう一度味わいたくなかったからですよね。」
「ああ。」
俺はようやく、その言葉を口にした。
夜空に打ち上げられる、花火が終わりに近づいていた。