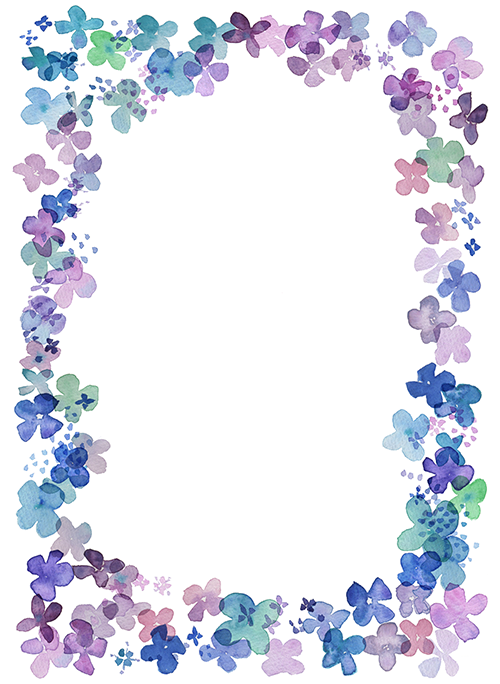目覚ましのアラームがけたたましく鳴り響き、俺は重い瞼を無理やり開けた。
五回目のスヌーズだ。
体が言うことを効かない。
いや、それ以上に…俺の精神が悲鳴を上げていた。
『なぜ俺は学校なんかに行かなければならないんだ!』
それは毎朝毎朝、同じ疑問だった。
しかし、その答えは決まっている。
中卒無職になるわけにはいかない、からだ。
だがしかし…。
この朝の瞬間だけは、いつもいつも絶対に学校に行きたくない精神との戦い。
もちろん俺は断じて不登校などではない。
それに社会契約や一度した約束は守る主義だ。
だからこそ、苦しむ。起きなければならぬ。
しかし、朝の俺はとにかく眠いのだ。
つまりは起きたくないんだけれど。
アラームが鳴り響いている。
これ以上は遅刻必至。
鳴り止まないアラームを消し、天井を見つめることにした。
俺はゆっくりと重力に逆らうかのように、ベッドから体を引きはがすように起き上がった。
自分の部屋の中では、俺の制服がハンガーにかけられているのが見えた。
ハンガーから視線を窓の外に移す。
そこに曇り空が見えた。
それはまるで俺の心境を表しているかのようだった。
いつもと同じような灰色の一日が始まろうとしていた。
◇
私立第三学園高等部に入学したのは今年だった。
つまり、俺は高校一年生。
思わず、ピカピカの一年生なんて言葉が思い浮かんだ。
まあ、ある意味でその通りかもしれない。
というのも、高校受験の段階で、俺は決めていた。
同じ中学の連中が行かないような学校を選ぶのだ、と。
その理由は単純だった。
新しい環境で、誰にも知られることなく、静かに高校生活を送るためだ。
そしてその願い通り、俺は中学時代の人間関係を断ち切り、『ピカピカの一年生』になった。
その代償がこれだ。
私立第三学園――その名前だけは進学校を掲げている割に、実際の大学合格実績は周辺の学校に比べて見劣りする。
近隣には本物の進学校や、スポーツで有名な私立があり、将来を真剣に考える連中や青春を謳歌したい連中は、誰もがそちらに流れていった。
かといって、偏差値が低いというわけもなく、成績が悪い連中は別の学校へと流れていく。
この中途半端な立ち位置の高校へ、俺の中学からここに流れてきたのは俺以外にいるのだろうか?
俺は寡聞にして知らないが、いないことを願っている。
まあ、それはいいのだ。
それよりも…。
ああ…。
もし、家から最短距離の学校にしていれば、と思う。
この第三学園は決して通えないほど遠くはないが、最寄りの高校よりは遠い。
そこにしていれば、より長い睡眠時間が確保できただろう。
しかし、背に腹は代えられない事情というものが、俺にはあったのだ。
◇
俺が起きて真っ先に洗面所での身支度をした。
必要最低限かつ効率的な作業。
顔を洗い、歯を磨き、制服に着替える。
髪は手櫛で整える。
俺にはおしゃれなんぞ関係ないし、無駄な時間は使わない主義だ。
鏡に映る自分の顔。
特徴のない、どこにでもいそうな高校生だ。
でもそれも気にならない。
だって、俺のことなんて誰も見ていないのだから。
「おはよう、お兄ちゃん。」
食卓に向かうと、妹のアカネが既に席についていた。
アカネは同じ学校の中等部三年生。
俺とは対照的に社交的で明るい性格をしている。
アカネはショートカットの髪に、きちんと手入れされた前髪。澄んだ瞳と整った顔立ち。
手首には編み込みのブレスレット。
細部まで気を配った身なりは、友人関係の豊かさを物語っていた。
「ああ。」
返事は最低限の言葉だけ。
余計な会話は効率が悪い。
「今日もそっけないね。クラスでは友達できた?」
アカネの問いかけは、毎朝のルーティンのようなものだった。
俺の答えが分かっていても、兄妹関係として最低限の会話として続けているのだろう。
「必要ない。無駄だ。」
「はいはい。」
そういって、アカネは呆れた表情を浮かべた。
きっと俺の苦労の末に生まれたこの崇高な理念を理解できないのだろう。
俺の『効率』という考え方を。
まあ、幸い俺は寛大だ。
アカネを無視して、朝食を開始した。
目の前の食卓には、母が出勤前に用意していったトーストと目玉焼き、少しの野菜サラダが並んでいる。
母は早朝から夕方まで働いているため、朝はすでに家を出ていることが多い。
朝食を用意するのが精一杯なのだ。
朝食も無言で済ませ、イヤホンを耳に差し込む。
動画配信サイトを開き、適当な動画を流しながら食べる。
指を上にスライドさせ、次から次へと短い動画が流れていく。
猫が飼い主の顔を踏みつける動画。
外国人がラーメンを食べて驚く動画。30秒で笑いを取る動画。
思わず小さく笑ってしまう。これは間違いなく効率的だ。
最小限の時間で最大限の娯楽を得られる。
長い映画を見たり、本を読んだりするより、はるかに効率的だ。
「お兄ちゃん、食事中にスマホ辞めなよ。」
アカネの声は、イヤホンごしに小さく聞こえた。
無視する。
目の前のトーストに口をつけながら、次の動画へとスクロールする。
人間の会話よりも、これらの方がよほど効率よく情報を得られる。
アカネは諦めたようで、自分のスマホを取り出して友達とメッセージをやりとりし始めた。
指先を器用に動かし、時折笑みを浮かべる。
おいおい、今さっき君は『俺にスマホを使うな』って言ったばかりじゃないか。
と、内心突っ込みを入れた。
しかし、俺は寛大な性格なので、それを口にはしなかった。
大方、友人とどうでもいい話をしているのだろう。
死ぬほど無駄な時間の使い方だと思った。
食事を終え、歯を磨き、カバンを持って玄関へ向かう。
アカネも後に続いてくる。兄妹で同じ学校だが、俺たちは一緒に登校することは絶対にない。
アカネには友達がいるし、俺は一人が効率的だからだ。
母が残した弁当箱をカバンに入れ、家を出た。
灰色の曇り空の下、俺は直射日光を避けることが出来ることに感謝しながら通学路を進んだ。
だがしかし、ここで一つはっきりさせることがある。
それは通学中、周囲の景色を眺めるのは時間の無駄ということだ。
その間にも情報を得ることができる。
現代文明の利器。スマホ。
俺は歩きながら、手にしたスマホの画面上に指を滑らせる。
すると、スマホ画面上で次々と短い動画が切り替わっていく。
これがこの世で最も効率的な情報収集だ。
画面には食レポをする外国人。日本のラーメンを評価している。
猫が鉄琴を弾く映像や、海外の有名俳優のインタビュー、何かの料理の作り方まで、十数本の動画を消費できる。
横断歩道で信号待ちをしている間も、通学路を歩いている間、俺はスマホから目を離すことはない。
周囲の人々の姿はただのぼんやりとした別のなにかの存在にすぎない。
彼らの存在は、スマホの小さな画面の向こう側の世界よりもずっと遠い。
画面には、世界中から集められた断片的な情報が次々と流れていく。
一本の動画を最後まで見ることなく、次々と新しい刺激を求めていく。
そうすることで、脳内の空虚さを埋めることができる。考える必要がなくなるのだ。
それこそがきっと効率的な生き方。
俺はそう信じて、歩き続けた。
◇
私立第三学園は、中等部と高等部が同じ敷地内にある一貫校だった。
ごく普通の鉄筋コンクリート造りの校舎が並び、中等部棟と高等部棟は別々の建物となっている。
その間には渡り廊下や体育館などが配置されている。
特別な特徴があるわけでもなく、どこにでもあるような学校だ。
生徒たちからは単に『第三』と呼ばれている。
俺にとっては、毎日時間を無駄に過ごすだけの場所以上の意味はなかったけれど。
校門をくぐると、学生たちが談笑しながら、靴箱のある玄関へと向かっているのが見えた。
ああ、面倒くさそう。
人生で最も面倒なのは、人間関係だ。
それを100%カットしている俺はかなり身軽で、効率的だった。
生徒たちの流れに紛れて、できるだけ存在感を消すように歩く。
彼らの会話は俺には届かない。
イヤホンから流れる動画の音声が、現実世界からの侵入を遮断してくれる。それが心地よかった。
高等部の靴箱に到着し、上履きに履き替える。廊下は生徒たちで溢れかえっている。
スマホゲームを一緒にやっている男子生徒たち、おしゃべりに花を咲かせる女子生徒たち。
彼らは俺の存在に気づくことなく、自分たちの小さな世界に没頭している。
それで構わない。むしろ好都合だ。
教室に着くと、クラスメイトたちはグループを作って談笑していた。
馬鹿げた冗談で笑い合い、お互いについて語り合っている。
そんな光景を見ながら、俺は静かに自分の席に着く。
教室の窓際の席。最後列で、窓の隣という絶好の位置だ。
授業中でも外を眺めることができるし、何より目立たない。
教師の視線も届きにくい。完璧な場所と言えた。
俺はそこで動画を見ながら、時間を効率的に捌いていった。
◇
ホームルームが始まると、担任の教師が入試案内の配布をはじめた。
高校一年生になったばかりだというのに、もう大学の話だ。
担任の口からは『将来のため』『人生の重要な選択』という言葉が飛び交う。
クラスメイトたちは真剣に聞いているフリをしている。
しかし、俺から見れば、それはあくまでフリをしているだけなことが、一目瞭然だった。
無駄だ。
今から3年後の大学受験のことを考えても、具体的な行動に結びつかなければ時間の無駄でしかない。
そしてこの話も3年後には何の意味も持たないだろう。
全てが無駄な時間だ。
入試案内をぼんやりと眺めながら、俺はスマホでこっそり動画を再生する。
机の下に隠すようにして、音は消して字幕だけを追う。
画面には海外の学生が、独自の勉強法を紹介している。効率的に知識を詰め込む方法だという。興味深い。
実際のところ、俺の成績は悪くない。
むしろ良い方だ。無駄な時間を使わないからこそ、効率的に勉強できる。
友人関係に時間を浪費せず、必要な情報だけを頭に入れる。それが俺のやり方だった。
◇
英語の授業。
先生が質問を投げかけるが、挙手する生徒はいない。
その結果、最終的に指名されたのは俺だった。
「綾小路くん、この文の訳を言ってみなさい。」
教師の声。
…嫌がらせか?
俺は本気でそう思った。
ただ、ここで反論したり、不満を述べるのは『効率的』ではない。
さすがにそれくらいのことを、俺は知っている。
教科書の該当部分に目を落とし、素早く訳す。
「『彼は人生の意味を探し続けたが、その答えは自分の中にあることに気づいていなかった』です。」
我ながら完璧な訳だ。
「正解です。次に…。」
先生の言葉は、すでに俺の関心の外だった。
やっぱり嫌がらせか?
俺は本気でそう思った。
…まあ、そもそも。
教室の中で、俺の存在に気づく人はほとんどいない。
ある意味で最も効率的な状態だともいえる。
誰かに話しかけられれば応対する必要があり、無駄な時間が生まれる。
だから、俺が目立たないように心掛けた結果ともいえる。
壁の一部のように、風景の一部のように、そこにいるだけの存在でいることが最も効率的なのだ。
俺の苗字である『綾小路』を読めない生徒もいる。
俺の顔と名前を一致させられない教師もいる。
それは、これまでの俺の生き方が結実した証だともいえた。
存在感を極限まで薄めることに成功している、ということだからだ。
時々、自分が本当に存在しているのかと疑問に思うことがあるほどだ。
この教室の中で、誰も俺のことを本当の意味で認識していない。
ただそこにいるというだけの存在。透明な存在。
それは心地いいような、どこか空虚で透明度の高いような、どこか不思議な感覚を抱いてしまう。
しかし、そんな半ば感傷のような時間は無駄だと感じた。
なによりも効率的ではない。
俺は、その勝手に湧き上がってきた思考の迷路を強制終了させた。
◇
午前中の授業がすべて終わり、昼食の時間となった。
ほとんどの生徒は仲間と集まって食べていた。
俺はひとり、静かに学食の隅で弁当を開けた。
周りの喧騒を遮断するため、イヤホンから音楽を流した。
母が作った弁当は質素ながらも栄養バランスを考えられている。
おにぎり、卵焼き、ブロッコリー、ミニトマト。シンプルだが十分だ。
効率的な栄養摂取ができる。
「あそこに座っている人って、いつも一人だよね。」
「友達いないんじゃない?」
「高校入って一ヶ月経つのに、可哀想…。」
聞こえてくる断片的な会話。
…ああ、そうかい。
俺は続けて思った。
『可哀想』、だと?
なんとも笑わせる言葉だった。
可哀そうなのは、言葉を発しているほうだろう、と。
そう、彼女らは人間関係で窮屈になり、そのような言葉が苦し紛れに出てきている。
俺からすれば、それは悲痛な叫びのようにも聞こえた。
対して、『可哀想』な俺は?
とっても、クリーンで効率的かつ安全だった。
何も悩むことはない。
何も苦しむこともない。
だから、俺は安全でクリーンで効率的に一人で過ごせていた。
三年後には誰も覚えていないような青春の一コマなど、価値がない。
そう自分に言い聞かせながら、弁当を食べ終えた。
◇
昼食を早々に切り上げ、俺は高等部棟の最上階へと足を向ける。
使われなくなった小さな資料室。
ここが俺の居場所だ。
高等部棟の最上階にある資料室。
授業で使われなくなった忘れられた場所。
埃を被った古い本棚と机が数脚あるだけの質素な空間。
窓に常時カーテンがされており、校庭から教室の中を見られる心配がない。
ここに来る生徒は誰もいない。
だからこそ、俺の『効率的』な時間を過ごすのに最適な場所なのだ。
誰も来ない。
そして、静かだ。
こんなところには不良生徒なんて来るのが、セオリーなのかもしれないけれど。
これまで、俺以外に誰も見ていない。
…もしかすると、俺が不良生徒なのか?
まあ、それはどっちでもいいや。
俺はくだらない思考を続けながら、資料室への道を進んだ。
階段を上りながら、自分の呼吸が少し荒くなっているのを感じる。
高等部棟は四階建てで、資料室は最上階にある。体力に自信があるわけではないので、少し息が切れる。
ああ、俺専用のエレベータが欲しい。
『周囲の生徒には見られないように移動せねばならない。』
その俺に課せられた特殊な任務との兼ね合いがあるため、専用エレベータは特に必須だ。
もちろん、そんな設備はこの学園にはない。
普通のエレベータすらない。
そんな下らないことを考えつつ、俺は苦労して最上階に到着した。
周囲を確認しながら、資料室の前に立つ。
周囲には誰もいない。
ドアには『第四資料室』と書かれた古びた札がかかっている。
他の三つの資料室は今も使われているが、ここだけは何らかの理由で放置されている。俺にとっては絶好の隠れ家だ。
資料室の扉を開け、いつものようにパイプ椅子に腰掛ける。
もし、日本にいてセーフティネットが不足している、と感じられる方にはぜひ来てもらいたい場所だった。
ここでは、誰も来ない静かな空間で、好きなだけ一人でスマホの動画に没頭できる。
ただ、ここは俺一人しか入ることが出来ないため、結局、来られても困るのだけれど。
…それにしても、資料室は最高だ。
窓から差し込む昼の光の中、スマホの画面に集中する。
指を上に滑らせ、次々と短い動画が切り替わっていく。これがこの世で最も効率的な娯楽だ。
短いコンテンツが絶え間なく流れ、常に新しい刺激を脳に与え続ける。
画面に映るのは、外国の猫がキーボードを踏んで歩き回る15秒の映像。
『職場で邪魔をする同僚あるある』というキャプションがついている。続いて表示されるのは、料理人が超高速で野菜を切り刻む様子。
そして次は、誰かの失敗を捉えた動画。スケートボードに乗った若者が手すりから派手に転落する瞬間。
思わず小さく笑ってしまう。これは間違いなく効率的だ。
最小限の時間で最大限の娯楽を得られる。長い映画を見たり、本を読んだりするより、はるかに効率的だ。
これこそが現代の最適解だ。
窓の外から差し込む光が、少しずつ資料室の床を這うように移動していく。
時間の経過を静かに示している。埃の舞う空気の中で、俺はスマホの画面だけを見つめ続ける。
現実世界から切り離された安息の場所。ここでは誰にも邪魔されない。
次の動画は、海外の高校生活を紹介するもの。
広々としたロッカールームでふざけ合う外国の高校生たち。
そこにはどこぞの漫画やアニメのごとくの世界があったが、俺には無縁だった。
彼らの笑顔を見ていると、どこか遠い世界の出来事のように感じる。
まるで別の星の生き物を観察しているかのように。
あんな風に他人と関わることが当たり前の世界があるのかと、そう他人事のように思った。
指で画面を上にスワイプ。次の動画へ。
そしてまた次へ。
時間が経つのを忘れるほど没頭する。
次々と切り替わる短い動画。数十秒で一つの世界が展開され、また別の世界へと移り変わる。
生身の人間と関わる必要がなく、自分のペースで楽しめる。
何より、飽きたらすぐに次に行ける。これほど完璧な娯楽はない。
心地よい麻痺感が全身を包む。
午前中の授業という無意味な時間で蓄積した疲労が、徐々に解消されていく。
これがこそが俺の趣味で日課だった。
最も効率的なストレス解消法。
動画の途中、ふと画面から目を離すと、窓の外に校庭で昼食を取る生徒たちの群れが見えた。
笑い合いながら弁当を食べる連中。校庭で部活の練習をする連中。
彼らはどうでもいいことをしている。
校庭の中央では、バスケットボール部らしき生徒たちが汗を流している。
その周りでは女子生徒たちが声援を送っている。応援されている男子は嬉しそうだ。
確かに女子生徒に囃し立てられて、気持ちいいのかもしれない。
でも、そんなことに何の意味がある?
彼らが今作っている思い出は、数年後には色褪せて、誰の記憶からも消えていくだろう。
それなのに、なぜそんなことに時間を費やすのか。
理解できない。
数年後には誰も覚えていないような無意味な時間を大切だと思い込んでいる。
そう、それはとっても虚無なように感じた。
無駄なことを大切にしまう。
それほど悲しいことはないだろう。
タイムカプセルを後から掘り起こしたとき。
中から思い出にないものが出てきたくらいに、悲しい出来事に違いない。
俺は、動画を再生した。
もう一度スマホの画面に目を落とす。海外の人気クリエイターがカメラに向かって自己啓発めいた言葉を語っていた。
『人生は短い。挑戦しなければ後悔する』
極論、そんな内容だった。
そうか。
どうせこいつも再生数稼ぎのために、適当なキャラ作りをしてるんだろう、と思った。
いや、本業に成功したから、次は名誉が欲しくなったのかもしれない。
しかし、俺の目には誤魔化しは効かない。
嘘、虚栄…。
承認欲求に塗れた現代人が話すことは話半分で聞くに限る。
そんな綺麗事より、無駄な挑戦を避け、効率的に生きる。
それが俺のポリシーだった。
次々と指で画面をスワイプし、新たな動画の波に身を任せた。
頭を空っぽにして、ただ映像に没頭する。
これこそが、今の俺にとっての安息だった。
予鈴のチャイムが鳴り、午後の授業の時間を告げる。
まだ動画を見ていたい気持ちを押し殺して立ち上がる。
誰もいない資料室で、俺は効率的に昼休みを過ごしていた。
資料室を出る前に、もう一度窓の外を見る。
校庭はすでに空いており、みんな教室に戻り始めたようだった。
やはり、あの賑やかな光景は一時的なものに過ぎなかった。
すべては過ぎ去り、忘れ去られる。
だからこそ、初めから関わらない方が賢明なのだ。
この学校の中で、俺は透明人間のような存在になっている。
それが最も『効率的』だということが最近、俺の中で証明されつつあった。
安全で効率的な日々。
そんな日常に守られながら、俺は教室へ向かって歩き出した。
五回目のスヌーズだ。
体が言うことを効かない。
いや、それ以上に…俺の精神が悲鳴を上げていた。
『なぜ俺は学校なんかに行かなければならないんだ!』
それは毎朝毎朝、同じ疑問だった。
しかし、その答えは決まっている。
中卒無職になるわけにはいかない、からだ。
だがしかし…。
この朝の瞬間だけは、いつもいつも絶対に学校に行きたくない精神との戦い。
もちろん俺は断じて不登校などではない。
それに社会契約や一度した約束は守る主義だ。
だからこそ、苦しむ。起きなければならぬ。
しかし、朝の俺はとにかく眠いのだ。
つまりは起きたくないんだけれど。
アラームが鳴り響いている。
これ以上は遅刻必至。
鳴り止まないアラームを消し、天井を見つめることにした。
俺はゆっくりと重力に逆らうかのように、ベッドから体を引きはがすように起き上がった。
自分の部屋の中では、俺の制服がハンガーにかけられているのが見えた。
ハンガーから視線を窓の外に移す。
そこに曇り空が見えた。
それはまるで俺の心境を表しているかのようだった。
いつもと同じような灰色の一日が始まろうとしていた。
◇
私立第三学園高等部に入学したのは今年だった。
つまり、俺は高校一年生。
思わず、ピカピカの一年生なんて言葉が思い浮かんだ。
まあ、ある意味でその通りかもしれない。
というのも、高校受験の段階で、俺は決めていた。
同じ中学の連中が行かないような学校を選ぶのだ、と。
その理由は単純だった。
新しい環境で、誰にも知られることなく、静かに高校生活を送るためだ。
そしてその願い通り、俺は中学時代の人間関係を断ち切り、『ピカピカの一年生』になった。
その代償がこれだ。
私立第三学園――その名前だけは進学校を掲げている割に、実際の大学合格実績は周辺の学校に比べて見劣りする。
近隣には本物の進学校や、スポーツで有名な私立があり、将来を真剣に考える連中や青春を謳歌したい連中は、誰もがそちらに流れていった。
かといって、偏差値が低いというわけもなく、成績が悪い連中は別の学校へと流れていく。
この中途半端な立ち位置の高校へ、俺の中学からここに流れてきたのは俺以外にいるのだろうか?
俺は寡聞にして知らないが、いないことを願っている。
まあ、それはいいのだ。
それよりも…。
ああ…。
もし、家から最短距離の学校にしていれば、と思う。
この第三学園は決して通えないほど遠くはないが、最寄りの高校よりは遠い。
そこにしていれば、より長い睡眠時間が確保できただろう。
しかし、背に腹は代えられない事情というものが、俺にはあったのだ。
◇
俺が起きて真っ先に洗面所での身支度をした。
必要最低限かつ効率的な作業。
顔を洗い、歯を磨き、制服に着替える。
髪は手櫛で整える。
俺にはおしゃれなんぞ関係ないし、無駄な時間は使わない主義だ。
鏡に映る自分の顔。
特徴のない、どこにでもいそうな高校生だ。
でもそれも気にならない。
だって、俺のことなんて誰も見ていないのだから。
「おはよう、お兄ちゃん。」
食卓に向かうと、妹のアカネが既に席についていた。
アカネは同じ学校の中等部三年生。
俺とは対照的に社交的で明るい性格をしている。
アカネはショートカットの髪に、きちんと手入れされた前髪。澄んだ瞳と整った顔立ち。
手首には編み込みのブレスレット。
細部まで気を配った身なりは、友人関係の豊かさを物語っていた。
「ああ。」
返事は最低限の言葉だけ。
余計な会話は効率が悪い。
「今日もそっけないね。クラスでは友達できた?」
アカネの問いかけは、毎朝のルーティンのようなものだった。
俺の答えが分かっていても、兄妹関係として最低限の会話として続けているのだろう。
「必要ない。無駄だ。」
「はいはい。」
そういって、アカネは呆れた表情を浮かべた。
きっと俺の苦労の末に生まれたこの崇高な理念を理解できないのだろう。
俺の『効率』という考え方を。
まあ、幸い俺は寛大だ。
アカネを無視して、朝食を開始した。
目の前の食卓には、母が出勤前に用意していったトーストと目玉焼き、少しの野菜サラダが並んでいる。
母は早朝から夕方まで働いているため、朝はすでに家を出ていることが多い。
朝食を用意するのが精一杯なのだ。
朝食も無言で済ませ、イヤホンを耳に差し込む。
動画配信サイトを開き、適当な動画を流しながら食べる。
指を上にスライドさせ、次から次へと短い動画が流れていく。
猫が飼い主の顔を踏みつける動画。
外国人がラーメンを食べて驚く動画。30秒で笑いを取る動画。
思わず小さく笑ってしまう。これは間違いなく効率的だ。
最小限の時間で最大限の娯楽を得られる。
長い映画を見たり、本を読んだりするより、はるかに効率的だ。
「お兄ちゃん、食事中にスマホ辞めなよ。」
アカネの声は、イヤホンごしに小さく聞こえた。
無視する。
目の前のトーストに口をつけながら、次の動画へとスクロールする。
人間の会話よりも、これらの方がよほど効率よく情報を得られる。
アカネは諦めたようで、自分のスマホを取り出して友達とメッセージをやりとりし始めた。
指先を器用に動かし、時折笑みを浮かべる。
おいおい、今さっき君は『俺にスマホを使うな』って言ったばかりじゃないか。
と、内心突っ込みを入れた。
しかし、俺は寛大な性格なので、それを口にはしなかった。
大方、友人とどうでもいい話をしているのだろう。
死ぬほど無駄な時間の使い方だと思った。
食事を終え、歯を磨き、カバンを持って玄関へ向かう。
アカネも後に続いてくる。兄妹で同じ学校だが、俺たちは一緒に登校することは絶対にない。
アカネには友達がいるし、俺は一人が効率的だからだ。
母が残した弁当箱をカバンに入れ、家を出た。
灰色の曇り空の下、俺は直射日光を避けることが出来ることに感謝しながら通学路を進んだ。
だがしかし、ここで一つはっきりさせることがある。
それは通学中、周囲の景色を眺めるのは時間の無駄ということだ。
その間にも情報を得ることができる。
現代文明の利器。スマホ。
俺は歩きながら、手にしたスマホの画面上に指を滑らせる。
すると、スマホ画面上で次々と短い動画が切り替わっていく。
これがこの世で最も効率的な情報収集だ。
画面には食レポをする外国人。日本のラーメンを評価している。
猫が鉄琴を弾く映像や、海外の有名俳優のインタビュー、何かの料理の作り方まで、十数本の動画を消費できる。
横断歩道で信号待ちをしている間も、通学路を歩いている間、俺はスマホから目を離すことはない。
周囲の人々の姿はただのぼんやりとした別のなにかの存在にすぎない。
彼らの存在は、スマホの小さな画面の向こう側の世界よりもずっと遠い。
画面には、世界中から集められた断片的な情報が次々と流れていく。
一本の動画を最後まで見ることなく、次々と新しい刺激を求めていく。
そうすることで、脳内の空虚さを埋めることができる。考える必要がなくなるのだ。
それこそがきっと効率的な生き方。
俺はそう信じて、歩き続けた。
◇
私立第三学園は、中等部と高等部が同じ敷地内にある一貫校だった。
ごく普通の鉄筋コンクリート造りの校舎が並び、中等部棟と高等部棟は別々の建物となっている。
その間には渡り廊下や体育館などが配置されている。
特別な特徴があるわけでもなく、どこにでもあるような学校だ。
生徒たちからは単に『第三』と呼ばれている。
俺にとっては、毎日時間を無駄に過ごすだけの場所以上の意味はなかったけれど。
校門をくぐると、学生たちが談笑しながら、靴箱のある玄関へと向かっているのが見えた。
ああ、面倒くさそう。
人生で最も面倒なのは、人間関係だ。
それを100%カットしている俺はかなり身軽で、効率的だった。
生徒たちの流れに紛れて、できるだけ存在感を消すように歩く。
彼らの会話は俺には届かない。
イヤホンから流れる動画の音声が、現実世界からの侵入を遮断してくれる。それが心地よかった。
高等部の靴箱に到着し、上履きに履き替える。廊下は生徒たちで溢れかえっている。
スマホゲームを一緒にやっている男子生徒たち、おしゃべりに花を咲かせる女子生徒たち。
彼らは俺の存在に気づくことなく、自分たちの小さな世界に没頭している。
それで構わない。むしろ好都合だ。
教室に着くと、クラスメイトたちはグループを作って談笑していた。
馬鹿げた冗談で笑い合い、お互いについて語り合っている。
そんな光景を見ながら、俺は静かに自分の席に着く。
教室の窓際の席。最後列で、窓の隣という絶好の位置だ。
授業中でも外を眺めることができるし、何より目立たない。
教師の視線も届きにくい。完璧な場所と言えた。
俺はそこで動画を見ながら、時間を効率的に捌いていった。
◇
ホームルームが始まると、担任の教師が入試案内の配布をはじめた。
高校一年生になったばかりだというのに、もう大学の話だ。
担任の口からは『将来のため』『人生の重要な選択』という言葉が飛び交う。
クラスメイトたちは真剣に聞いているフリをしている。
しかし、俺から見れば、それはあくまでフリをしているだけなことが、一目瞭然だった。
無駄だ。
今から3年後の大学受験のことを考えても、具体的な行動に結びつかなければ時間の無駄でしかない。
そしてこの話も3年後には何の意味も持たないだろう。
全てが無駄な時間だ。
入試案内をぼんやりと眺めながら、俺はスマホでこっそり動画を再生する。
机の下に隠すようにして、音は消して字幕だけを追う。
画面には海外の学生が、独自の勉強法を紹介している。効率的に知識を詰め込む方法だという。興味深い。
実際のところ、俺の成績は悪くない。
むしろ良い方だ。無駄な時間を使わないからこそ、効率的に勉強できる。
友人関係に時間を浪費せず、必要な情報だけを頭に入れる。それが俺のやり方だった。
◇
英語の授業。
先生が質問を投げかけるが、挙手する生徒はいない。
その結果、最終的に指名されたのは俺だった。
「綾小路くん、この文の訳を言ってみなさい。」
教師の声。
…嫌がらせか?
俺は本気でそう思った。
ただ、ここで反論したり、不満を述べるのは『効率的』ではない。
さすがにそれくらいのことを、俺は知っている。
教科書の該当部分に目を落とし、素早く訳す。
「『彼は人生の意味を探し続けたが、その答えは自分の中にあることに気づいていなかった』です。」
我ながら完璧な訳だ。
「正解です。次に…。」
先生の言葉は、すでに俺の関心の外だった。
やっぱり嫌がらせか?
俺は本気でそう思った。
…まあ、そもそも。
教室の中で、俺の存在に気づく人はほとんどいない。
ある意味で最も効率的な状態だともいえる。
誰かに話しかけられれば応対する必要があり、無駄な時間が生まれる。
だから、俺が目立たないように心掛けた結果ともいえる。
壁の一部のように、風景の一部のように、そこにいるだけの存在でいることが最も効率的なのだ。
俺の苗字である『綾小路』を読めない生徒もいる。
俺の顔と名前を一致させられない教師もいる。
それは、これまでの俺の生き方が結実した証だともいえた。
存在感を極限まで薄めることに成功している、ということだからだ。
時々、自分が本当に存在しているのかと疑問に思うことがあるほどだ。
この教室の中で、誰も俺のことを本当の意味で認識していない。
ただそこにいるというだけの存在。透明な存在。
それは心地いいような、どこか空虚で透明度の高いような、どこか不思議な感覚を抱いてしまう。
しかし、そんな半ば感傷のような時間は無駄だと感じた。
なによりも効率的ではない。
俺は、その勝手に湧き上がってきた思考の迷路を強制終了させた。
◇
午前中の授業がすべて終わり、昼食の時間となった。
ほとんどの生徒は仲間と集まって食べていた。
俺はひとり、静かに学食の隅で弁当を開けた。
周りの喧騒を遮断するため、イヤホンから音楽を流した。
母が作った弁当は質素ながらも栄養バランスを考えられている。
おにぎり、卵焼き、ブロッコリー、ミニトマト。シンプルだが十分だ。
効率的な栄養摂取ができる。
「あそこに座っている人って、いつも一人だよね。」
「友達いないんじゃない?」
「高校入って一ヶ月経つのに、可哀想…。」
聞こえてくる断片的な会話。
…ああ、そうかい。
俺は続けて思った。
『可哀想』、だと?
なんとも笑わせる言葉だった。
可哀そうなのは、言葉を発しているほうだろう、と。
そう、彼女らは人間関係で窮屈になり、そのような言葉が苦し紛れに出てきている。
俺からすれば、それは悲痛な叫びのようにも聞こえた。
対して、『可哀想』な俺は?
とっても、クリーンで効率的かつ安全だった。
何も悩むことはない。
何も苦しむこともない。
だから、俺は安全でクリーンで効率的に一人で過ごせていた。
三年後には誰も覚えていないような青春の一コマなど、価値がない。
そう自分に言い聞かせながら、弁当を食べ終えた。
◇
昼食を早々に切り上げ、俺は高等部棟の最上階へと足を向ける。
使われなくなった小さな資料室。
ここが俺の居場所だ。
高等部棟の最上階にある資料室。
授業で使われなくなった忘れられた場所。
埃を被った古い本棚と机が数脚あるだけの質素な空間。
窓に常時カーテンがされており、校庭から教室の中を見られる心配がない。
ここに来る生徒は誰もいない。
だからこそ、俺の『効率的』な時間を過ごすのに最適な場所なのだ。
誰も来ない。
そして、静かだ。
こんなところには不良生徒なんて来るのが、セオリーなのかもしれないけれど。
これまで、俺以外に誰も見ていない。
…もしかすると、俺が不良生徒なのか?
まあ、それはどっちでもいいや。
俺はくだらない思考を続けながら、資料室への道を進んだ。
階段を上りながら、自分の呼吸が少し荒くなっているのを感じる。
高等部棟は四階建てで、資料室は最上階にある。体力に自信があるわけではないので、少し息が切れる。
ああ、俺専用のエレベータが欲しい。
『周囲の生徒には見られないように移動せねばならない。』
その俺に課せられた特殊な任務との兼ね合いがあるため、専用エレベータは特に必須だ。
もちろん、そんな設備はこの学園にはない。
普通のエレベータすらない。
そんな下らないことを考えつつ、俺は苦労して最上階に到着した。
周囲を確認しながら、資料室の前に立つ。
周囲には誰もいない。
ドアには『第四資料室』と書かれた古びた札がかかっている。
他の三つの資料室は今も使われているが、ここだけは何らかの理由で放置されている。俺にとっては絶好の隠れ家だ。
資料室の扉を開け、いつものようにパイプ椅子に腰掛ける。
もし、日本にいてセーフティネットが不足している、と感じられる方にはぜひ来てもらいたい場所だった。
ここでは、誰も来ない静かな空間で、好きなだけ一人でスマホの動画に没頭できる。
ただ、ここは俺一人しか入ることが出来ないため、結局、来られても困るのだけれど。
…それにしても、資料室は最高だ。
窓から差し込む昼の光の中、スマホの画面に集中する。
指を上に滑らせ、次々と短い動画が切り替わっていく。これがこの世で最も効率的な娯楽だ。
短いコンテンツが絶え間なく流れ、常に新しい刺激を脳に与え続ける。
画面に映るのは、外国の猫がキーボードを踏んで歩き回る15秒の映像。
『職場で邪魔をする同僚あるある』というキャプションがついている。続いて表示されるのは、料理人が超高速で野菜を切り刻む様子。
そして次は、誰かの失敗を捉えた動画。スケートボードに乗った若者が手すりから派手に転落する瞬間。
思わず小さく笑ってしまう。これは間違いなく効率的だ。
最小限の時間で最大限の娯楽を得られる。長い映画を見たり、本を読んだりするより、はるかに効率的だ。
これこそが現代の最適解だ。
窓の外から差し込む光が、少しずつ資料室の床を這うように移動していく。
時間の経過を静かに示している。埃の舞う空気の中で、俺はスマホの画面だけを見つめ続ける。
現実世界から切り離された安息の場所。ここでは誰にも邪魔されない。
次の動画は、海外の高校生活を紹介するもの。
広々としたロッカールームでふざけ合う外国の高校生たち。
そこにはどこぞの漫画やアニメのごとくの世界があったが、俺には無縁だった。
彼らの笑顔を見ていると、どこか遠い世界の出来事のように感じる。
まるで別の星の生き物を観察しているかのように。
あんな風に他人と関わることが当たり前の世界があるのかと、そう他人事のように思った。
指で画面を上にスワイプ。次の動画へ。
そしてまた次へ。
時間が経つのを忘れるほど没頭する。
次々と切り替わる短い動画。数十秒で一つの世界が展開され、また別の世界へと移り変わる。
生身の人間と関わる必要がなく、自分のペースで楽しめる。
何より、飽きたらすぐに次に行ける。これほど完璧な娯楽はない。
心地よい麻痺感が全身を包む。
午前中の授業という無意味な時間で蓄積した疲労が、徐々に解消されていく。
これがこそが俺の趣味で日課だった。
最も効率的なストレス解消法。
動画の途中、ふと画面から目を離すと、窓の外に校庭で昼食を取る生徒たちの群れが見えた。
笑い合いながら弁当を食べる連中。校庭で部活の練習をする連中。
彼らはどうでもいいことをしている。
校庭の中央では、バスケットボール部らしき生徒たちが汗を流している。
その周りでは女子生徒たちが声援を送っている。応援されている男子は嬉しそうだ。
確かに女子生徒に囃し立てられて、気持ちいいのかもしれない。
でも、そんなことに何の意味がある?
彼らが今作っている思い出は、数年後には色褪せて、誰の記憶からも消えていくだろう。
それなのに、なぜそんなことに時間を費やすのか。
理解できない。
数年後には誰も覚えていないような無意味な時間を大切だと思い込んでいる。
そう、それはとっても虚無なように感じた。
無駄なことを大切にしまう。
それほど悲しいことはないだろう。
タイムカプセルを後から掘り起こしたとき。
中から思い出にないものが出てきたくらいに、悲しい出来事に違いない。
俺は、動画を再生した。
もう一度スマホの画面に目を落とす。海外の人気クリエイターがカメラに向かって自己啓発めいた言葉を語っていた。
『人生は短い。挑戦しなければ後悔する』
極論、そんな内容だった。
そうか。
どうせこいつも再生数稼ぎのために、適当なキャラ作りをしてるんだろう、と思った。
いや、本業に成功したから、次は名誉が欲しくなったのかもしれない。
しかし、俺の目には誤魔化しは効かない。
嘘、虚栄…。
承認欲求に塗れた現代人が話すことは話半分で聞くに限る。
そんな綺麗事より、無駄な挑戦を避け、効率的に生きる。
それが俺のポリシーだった。
次々と指で画面をスワイプし、新たな動画の波に身を任せた。
頭を空っぽにして、ただ映像に没頭する。
これこそが、今の俺にとっての安息だった。
予鈴のチャイムが鳴り、午後の授業の時間を告げる。
まだ動画を見ていたい気持ちを押し殺して立ち上がる。
誰もいない資料室で、俺は効率的に昼休みを過ごしていた。
資料室を出る前に、もう一度窓の外を見る。
校庭はすでに空いており、みんな教室に戻り始めたようだった。
やはり、あの賑やかな光景は一時的なものに過ぎなかった。
すべては過ぎ去り、忘れ去られる。
だからこそ、初めから関わらない方が賢明なのだ。
この学校の中で、俺は透明人間のような存在になっている。
それが最も『効率的』だということが最近、俺の中で証明されつつあった。
安全で効率的な日々。
そんな日常に守られながら、俺は教室へ向かって歩き出した。