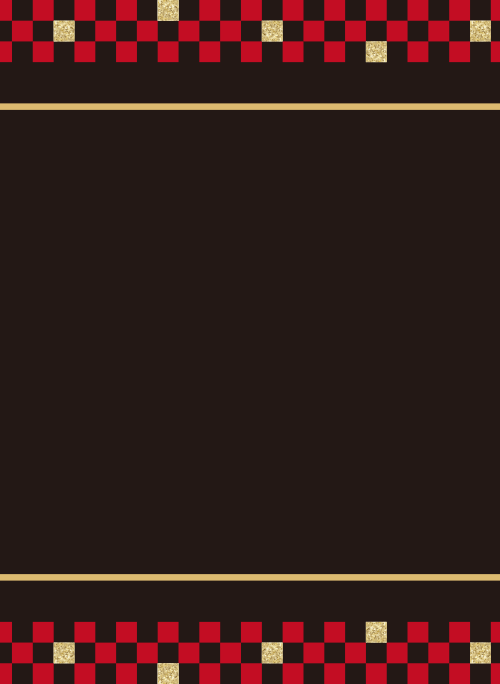「そんな中途半端な想いは彼女には迷惑だと思うぞ。だけどな、島村、俺は否定する気も、反対する気もない。人間なんて、いつ、どう変わるか分からない。今のお前と、大学生になったお前と、社会人になったお前と、同じなはずがない。恋愛だってそうだ。絶対変わらないなんて、言うほうがおかしい」
「…………」
「仮に今、その彼女への想いが本物としてだな、社会人になった時、変わっていても、誰もお前を咎めることはできない。破局しているかもしれないし、お前か、彼女のほうか、別の人を好きになっているかもしれない。そうだろ?」
「そんなこと、ないよ。つかさ、先生、暑苦しいよ。ちょっと言っただけじゃん。目標あったほうがいいだろ? だから」
止めようとする庸介に、柳沢は冷静な声で「島村」と名を呼んだ。
「お前が人の話に向き合うなんて珍しいからだ。いい機会だろ。今だけ俺の話を聞け。ちゃんと話そう」
「えーー」
ブーイングを向けながら、それでも庸介はそれ以上の文句を言わなかった。
「一般論だ。もし社会人になっても気持ちが変わっていなかったとする。好きだから、結婚しようと考える。今の世だから男が養うって感覚は薄いとしても、少なくても、お前は彼女を守っていかないといけない。お前、どうやって守っていく気だ?」
「守る? どうやって? どういう意味? 一緒にいたら、支え合ってやっていけるじゃん。それじゃダメなのかよ」
柳沢は、ダメだ、と言いきった。
「結婚したら子どももできる。お前は父親としても子どもを守らなくちゃいけない。気持ちはそれで支え合えても、食わせてやらないとどうやって生活するんだ。今のお前には大層に聞こえるだろうが、いずれわかる。教師としては、有利な将来の為に、なるべく良い大学に行けとしか言えない。だが、同じ男としてでは、どうすれば好きな女を守っていけるのか、それを考えろって言いたい。それは大学に入ってからでも遅くはない。いや、そもそも高校生の段階で将来を決めているヤツのほうが少ない。焦らず、ゆっくり考えればいい。だが、それはあくまで、自分の将来の為だ。中途半端な恋愛の為じゃない」
「……でも」
「でも?」
「彼女の方が年上で、夢に向かって驀進していて、俺なんかより、すごく先を進んでるんだ。中途半端になるよ」
「情けないこと言うなよ。好きだから傍にいたいなんて、ホントに子どもの言い訳じゃないか」
庸介は柳沢を上目遣いに見、それから顔を背けた。
「だったら、まだ適当などっかの推薦もらって、のんびりやるって言ってるほうがマシだ」
なおも不服そうな庸介に柳沢はため息をついた。
「もちろん、精神的な部分で支えることも大事だ。でも、そういうは、俺は抽象的で賛成できない。お前がどうしても、本気でその彼女の為に頑張るんだって言うなら、もっと実質的な面で支えてやるべきだと思う」
「実質的?」
「あぁ。カメラマンになりたいって言っているなら、将来、独立するかもしれない。なら、経営を学んで事務所をやりくりしてやる方法がある。税理士でもいいかもしれない。トラブルから守るなら弁護士って方法もある。売れっ子になるためのサポートなら、マーケティングを勉強する手もある。カメラマンを必要とするような会社に入って、仕事を回すのも手だ。マスコミ関係に進むとかな。営業能力があれば、彼女を売り込んでもやれるだろう。幾らでもやり方はある。今のお前で決めてしまう必要なんか全然ない。大学とはそもそもそういうところだと俺は思う。なにを目指し、どこに進むか。経済学部か、経営学部か、商学部か、法学部か、今決めなきゃいけないのは、この辺りだ。だが、絶対的に忘れてはいけないことがある。それは、どこの国でも、より高い大学を出ているほうが有利だってことだ。これは確率の問題だ」
「…………」
「島村、今のお前じゃ、彼女の気持ちを動かすことも、自分に向かせることもできないと思うぞ」
「でも」
庸介がそれでも言い返そうとした時、校庭から轟き渡るような悲鳴が上がった。
二人は驚き、立ち上がって窓を開けて外を見た。生徒たちが激しく騒いでいた。
「なんだ?」
庸介が呟いた時には、柳沢は身を翻して走り出していた。慌てて庸介もついて行く。
騒ぎの声を辿って進むと人だかりができていた。さらに救急車のサイレンも遠くに聞こえてくる。
人だかりを割って入って行く柳沢。対して庸介は近くの生徒になにがあったのかを聞いた。
返ってきたのは、男子生徒が飛び降りた、だった。だが、より庸介を驚愕させたのは、誰かが叫んだ名前だった。
(え?)
目を瞠り、人だかりを割って入る。そこで倒れている秀二を見つけた。
「秀二!」
血を流して倒れている秀二に庸介は震えた。
意識はないようだ。ヘタに動かしてはいけないと、先に駆けつけた教師たちが叫んでいる。さらに生徒たちに、下がるよう怒鳴っている。
間もなく救急車が到着した。
救急車のサイレンが止まり、救急隊員達が駆け寄ってくる。
そんな様子が、まるでスローモーションのように見えた。
(秀二、なんで)
呆然とする庸介は、自分が崩れ落ち、座り込んでいることすら気付いていなかった。
救急隊員が秀二を囲み、呼吸をみたり、脈を取ったりしつつ、ゆっくりとタンカに乗せる。
警察もやって来た。規制線を張って関係者以外を追い出した。
秀二は運ばれ、担任の柳沢が救急車に乗り込み、救急車が再びサイレンを鳴らせて走り去って行った。
庸介は呆然とそれを見送った。
「島村君」
誰かが呼んでいる。
「島村君、しっかりして。島村君!」
庸介は顔を上げた。二年の時の担任の顔があった。
「しっかりしなさい! 大里君は大丈夫だから」
「…………」
「生きているから、大丈夫だから!」
「で、も」
「息もしていたし、脈もあったわ。大丈夫よ、きっと助かるわ」
「でも! 先生、秀二が! 秀二が!」
庸介は教師に縋りつき、起こった現実に震えた。
血と共に倒れている幼なじみみの姿に、ただ恐怖するだけだった。
「…………」
「仮に今、その彼女への想いが本物としてだな、社会人になった時、変わっていても、誰もお前を咎めることはできない。破局しているかもしれないし、お前か、彼女のほうか、別の人を好きになっているかもしれない。そうだろ?」
「そんなこと、ないよ。つかさ、先生、暑苦しいよ。ちょっと言っただけじゃん。目標あったほうがいいだろ? だから」
止めようとする庸介に、柳沢は冷静な声で「島村」と名を呼んだ。
「お前が人の話に向き合うなんて珍しいからだ。いい機会だろ。今だけ俺の話を聞け。ちゃんと話そう」
「えーー」
ブーイングを向けながら、それでも庸介はそれ以上の文句を言わなかった。
「一般論だ。もし社会人になっても気持ちが変わっていなかったとする。好きだから、結婚しようと考える。今の世だから男が養うって感覚は薄いとしても、少なくても、お前は彼女を守っていかないといけない。お前、どうやって守っていく気だ?」
「守る? どうやって? どういう意味? 一緒にいたら、支え合ってやっていけるじゃん。それじゃダメなのかよ」
柳沢は、ダメだ、と言いきった。
「結婚したら子どももできる。お前は父親としても子どもを守らなくちゃいけない。気持ちはそれで支え合えても、食わせてやらないとどうやって生活するんだ。今のお前には大層に聞こえるだろうが、いずれわかる。教師としては、有利な将来の為に、なるべく良い大学に行けとしか言えない。だが、同じ男としてでは、どうすれば好きな女を守っていけるのか、それを考えろって言いたい。それは大学に入ってからでも遅くはない。いや、そもそも高校生の段階で将来を決めているヤツのほうが少ない。焦らず、ゆっくり考えればいい。だが、それはあくまで、自分の将来の為だ。中途半端な恋愛の為じゃない」
「……でも」
「でも?」
「彼女の方が年上で、夢に向かって驀進していて、俺なんかより、すごく先を進んでるんだ。中途半端になるよ」
「情けないこと言うなよ。好きだから傍にいたいなんて、ホントに子どもの言い訳じゃないか」
庸介は柳沢を上目遣いに見、それから顔を背けた。
「だったら、まだ適当などっかの推薦もらって、のんびりやるって言ってるほうがマシだ」
なおも不服そうな庸介に柳沢はため息をついた。
「もちろん、精神的な部分で支えることも大事だ。でも、そういうは、俺は抽象的で賛成できない。お前がどうしても、本気でその彼女の為に頑張るんだって言うなら、もっと実質的な面で支えてやるべきだと思う」
「実質的?」
「あぁ。カメラマンになりたいって言っているなら、将来、独立するかもしれない。なら、経営を学んで事務所をやりくりしてやる方法がある。税理士でもいいかもしれない。トラブルから守るなら弁護士って方法もある。売れっ子になるためのサポートなら、マーケティングを勉強する手もある。カメラマンを必要とするような会社に入って、仕事を回すのも手だ。マスコミ関係に進むとかな。営業能力があれば、彼女を売り込んでもやれるだろう。幾らでもやり方はある。今のお前で決めてしまう必要なんか全然ない。大学とはそもそもそういうところだと俺は思う。なにを目指し、どこに進むか。経済学部か、経営学部か、商学部か、法学部か、今決めなきゃいけないのは、この辺りだ。だが、絶対的に忘れてはいけないことがある。それは、どこの国でも、より高い大学を出ているほうが有利だってことだ。これは確率の問題だ」
「…………」
「島村、今のお前じゃ、彼女の気持ちを動かすことも、自分に向かせることもできないと思うぞ」
「でも」
庸介がそれでも言い返そうとした時、校庭から轟き渡るような悲鳴が上がった。
二人は驚き、立ち上がって窓を開けて外を見た。生徒たちが激しく騒いでいた。
「なんだ?」
庸介が呟いた時には、柳沢は身を翻して走り出していた。慌てて庸介もついて行く。
騒ぎの声を辿って進むと人だかりができていた。さらに救急車のサイレンも遠くに聞こえてくる。
人だかりを割って入って行く柳沢。対して庸介は近くの生徒になにがあったのかを聞いた。
返ってきたのは、男子生徒が飛び降りた、だった。だが、より庸介を驚愕させたのは、誰かが叫んだ名前だった。
(え?)
目を瞠り、人だかりを割って入る。そこで倒れている秀二を見つけた。
「秀二!」
血を流して倒れている秀二に庸介は震えた。
意識はないようだ。ヘタに動かしてはいけないと、先に駆けつけた教師たちが叫んでいる。さらに生徒たちに、下がるよう怒鳴っている。
間もなく救急車が到着した。
救急車のサイレンが止まり、救急隊員達が駆け寄ってくる。
そんな様子が、まるでスローモーションのように見えた。
(秀二、なんで)
呆然とする庸介は、自分が崩れ落ち、座り込んでいることすら気付いていなかった。
救急隊員が秀二を囲み、呼吸をみたり、脈を取ったりしつつ、ゆっくりとタンカに乗せる。
警察もやって来た。規制線を張って関係者以外を追い出した。
秀二は運ばれ、担任の柳沢が救急車に乗り込み、救急車が再びサイレンを鳴らせて走り去って行った。
庸介は呆然とそれを見送った。
「島村君」
誰かが呼んでいる。
「島村君、しっかりして。島村君!」
庸介は顔を上げた。二年の時の担任の顔があった。
「しっかりしなさい! 大里君は大丈夫だから」
「…………」
「生きているから、大丈夫だから!」
「で、も」
「息もしていたし、脈もあったわ。大丈夫よ、きっと助かるわ」
「でも! 先生、秀二が! 秀二が!」
庸介は教師に縋りつき、起こった現実に震えた。
血と共に倒れている幼なじみみの姿に、ただ恐怖するだけだった。