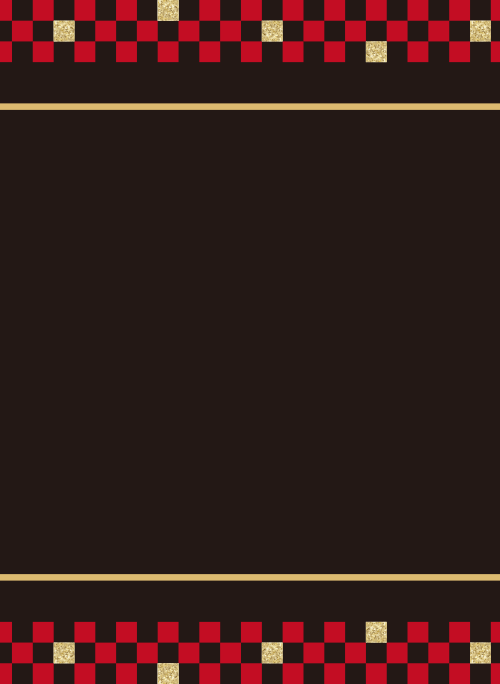翌日、自分の偏差値で理衣の学校に進めるかどうか聞こうと考えていた庸介だったが、午後から一回目の進路相談があることを、朝になって知った。
(俺、ほとほと、気にかけてなかったんだな。確かに、これじゃダメかも)
そんなことを考えながら自分の番を待つ。
クラスメートたちは机に向かって自習をしていた。終わった者から帰ってよかった。
「あ行」の秀二が教室から出て行く姿を眺めていたが、「か行」が少ないため、「さ行」の庸介もすぐに回ってくる。
間もなく自分が進路指導室に向かう順番が来た。
教室を出て、進路指導室の前に置かれている椅子に座る。五分程が経つと、クラスメートが出てきた。
「どうだった?」
「まぁまぁ。じゃ」
クラスメートが軽く手を挙げると、庸介もそれに合わせて手を挙げ、それから進路指導室の扉を開けた。
「失礼しま~す」
庸介は中に入った。
「次は島村か」
担任の柳沢の前に座り、身を乗り出す。
「先生、俺の話の前に、ちょい聞きたいことがあるんだけど」
「なんだ」
「秀二、大里秀二は希望のガッコに行けそう?」
「大里?」
「うん。あいつ、幼なじみみだからさ。ちょい気になって」
柳沢は資料をめくり、秀二の資料を見直した。
「そういうことは本人に聞け。で、お前の志望は?」
庸介は柳沢の返事に、秀二の志望が難しいことを感じた。
(そっか……秀二のヤツ、落ち込んでなきゃいいけど)
「島村?」
「あ、あぁ、えーっと、先生、日大って、俺の成績で入れる? あ、学部はどこでもいいかな」
柳沢は露骨に「え?」という顔をした。
「ンだよ。そんなに無理レベル?」
「あ、いや、もう少し上がれば推薦も可能だろう。もちろん学部によるが」
「そっか。へぇ」
「急にどうしたんだ。今までは推薦が貰える学校ならどこでもいいの一点張りだったのに。具体的に、日大なんて」
「別に」
柳沢は庸介の顔をジッと見つめた。柳沢は一年の時も担任だった。さらに二年の時の担任と仲が良い。だから庸介の考え方や、普段から口にしていることをよく知っていた。
「お前の姉も日大だよな? 確か、芸術学部。さすがにここは無理だぞ。成績だけの話じゃないからな」
「姉貴は関係ないよ。シスコンじゃあるまいし。そんな理由で志望するわけないよ」
「気に入った女が志望しているからとか、そんな理由じゃないだろうな?」
庸介の顔が強張った。
「ビンゴかぁ? ったく、お前、自分の人生だぞ」
「うっせぇなぁ。いいじゃん、どんな理由でも。真面目に受験勉強しようってんだから進歩じゃない?」
柳沢は呆れたように頭を掻いた。
「で、学部は?」
「だから、どこでもいいって」
「学部で偏差値が変わってくる。どこに進む気だ?」
「経済学部とか」
「彼女が経済学部なのか?」
庸介の顔がわずかに赤く染まった。さすがにそこまで言われたら恥ずかしくなったようだ。
「違うよ」
柳沢の視線に、ますますバツが悪そうに俯く。
「だって彼女、芸術学部でカメラマン目指しているから……」
「同じ学部ではないけれど、同じ学校には行きたい、か?」
「顔を合わせる機会もあるだろうし、連絡も取りやすそうだから。でもさ、将来の職業については、真面目に考えるつもりだよ」
「彼女の為にか?」
「そんな大層なことじゃないけど、まぁ、協力してやれる道を模索しようかなって。四年ありゃ、見つかるだろう?」
柳沢は持っていたボールペンを机に置いた。顔を上げ、真面目な顔を庸介に向けつつ、苛立ったように続けた。
「お前、根本的にわかってないな」
「なにが? どういう意味?」
「そんないい加減な気持ちで大事な進路を決めてどうする。もうちょっと真剣に考えろ。お前、言ってることと、やろうとしていることが全然違うじゃないか」
「え? どうして? 先生、大学に行ってから進路考えたって遅くないって言ってたじゃん。今までは推薦貰えるガッコって言ってたけど、これからは真面目に勉強して、この大学に受かろうと思うようになったから、進歩じゃない? これでも、真剣に考えたんだ」
しらっと言ってのける庸介に、柳沢はため息をついた。
「お前さ、その彼女になにを求めてるんだ?」
「え?」
「単なる大学時代を楽しく過ごすために、その彼女に近付こうっていうなら、絶対相手にされないぞ」
庸介は柳沢の顔を見た。担任の真剣な表情が、庸介からも軽薄な笑みを奪っていた。
「よく考えろ。その彼女はカメラマンになるために頑張ってるんだろ? 将来の構想もきちんと立てているってことだ。体育系にしろ、芸術系にしろ、こういう特殊な学部は潰しがきかない。だからみんな必死だ。そんなしっかりした女性が、単に今楽しく交際しようなんて口説きに応じるわけがないだろうが。お前とは次元が違う」
「そんなことはわかってるよ。だからさ、大学で真剣に進路を考えようと思っているんだ」
柳沢は首を左右に振った。
「違う。言ってる意味が違う。単につきあいたいだけなら、その彼女でなくてもいいことだ。いや、そのほうがいいだろう。こういう夢に向けて邁進している人間は、本当につらい時に支えてくれるヤツじゃなきゃ、心を動かさない。お前とは熱量が違うんだよ」
庸介はぐっと唇を噛みしめた。
(俺、ほとほと、気にかけてなかったんだな。確かに、これじゃダメかも)
そんなことを考えながら自分の番を待つ。
クラスメートたちは机に向かって自習をしていた。終わった者から帰ってよかった。
「あ行」の秀二が教室から出て行く姿を眺めていたが、「か行」が少ないため、「さ行」の庸介もすぐに回ってくる。
間もなく自分が進路指導室に向かう順番が来た。
教室を出て、進路指導室の前に置かれている椅子に座る。五分程が経つと、クラスメートが出てきた。
「どうだった?」
「まぁまぁ。じゃ」
クラスメートが軽く手を挙げると、庸介もそれに合わせて手を挙げ、それから進路指導室の扉を開けた。
「失礼しま~す」
庸介は中に入った。
「次は島村か」
担任の柳沢の前に座り、身を乗り出す。
「先生、俺の話の前に、ちょい聞きたいことがあるんだけど」
「なんだ」
「秀二、大里秀二は希望のガッコに行けそう?」
「大里?」
「うん。あいつ、幼なじみみだからさ。ちょい気になって」
柳沢は資料をめくり、秀二の資料を見直した。
「そういうことは本人に聞け。で、お前の志望は?」
庸介は柳沢の返事に、秀二の志望が難しいことを感じた。
(そっか……秀二のヤツ、落ち込んでなきゃいいけど)
「島村?」
「あ、あぁ、えーっと、先生、日大って、俺の成績で入れる? あ、学部はどこでもいいかな」
柳沢は露骨に「え?」という顔をした。
「ンだよ。そんなに無理レベル?」
「あ、いや、もう少し上がれば推薦も可能だろう。もちろん学部によるが」
「そっか。へぇ」
「急にどうしたんだ。今までは推薦が貰える学校ならどこでもいいの一点張りだったのに。具体的に、日大なんて」
「別に」
柳沢は庸介の顔をジッと見つめた。柳沢は一年の時も担任だった。さらに二年の時の担任と仲が良い。だから庸介の考え方や、普段から口にしていることをよく知っていた。
「お前の姉も日大だよな? 確か、芸術学部。さすがにここは無理だぞ。成績だけの話じゃないからな」
「姉貴は関係ないよ。シスコンじゃあるまいし。そんな理由で志望するわけないよ」
「気に入った女が志望しているからとか、そんな理由じゃないだろうな?」
庸介の顔が強張った。
「ビンゴかぁ? ったく、お前、自分の人生だぞ」
「うっせぇなぁ。いいじゃん、どんな理由でも。真面目に受験勉強しようってんだから進歩じゃない?」
柳沢は呆れたように頭を掻いた。
「で、学部は?」
「だから、どこでもいいって」
「学部で偏差値が変わってくる。どこに進む気だ?」
「経済学部とか」
「彼女が経済学部なのか?」
庸介の顔がわずかに赤く染まった。さすがにそこまで言われたら恥ずかしくなったようだ。
「違うよ」
柳沢の視線に、ますますバツが悪そうに俯く。
「だって彼女、芸術学部でカメラマン目指しているから……」
「同じ学部ではないけれど、同じ学校には行きたい、か?」
「顔を合わせる機会もあるだろうし、連絡も取りやすそうだから。でもさ、将来の職業については、真面目に考えるつもりだよ」
「彼女の為にか?」
「そんな大層なことじゃないけど、まぁ、協力してやれる道を模索しようかなって。四年ありゃ、見つかるだろう?」
柳沢は持っていたボールペンを机に置いた。顔を上げ、真面目な顔を庸介に向けつつ、苛立ったように続けた。
「お前、根本的にわかってないな」
「なにが? どういう意味?」
「そんないい加減な気持ちで大事な進路を決めてどうする。もうちょっと真剣に考えろ。お前、言ってることと、やろうとしていることが全然違うじゃないか」
「え? どうして? 先生、大学に行ってから進路考えたって遅くないって言ってたじゃん。今までは推薦貰えるガッコって言ってたけど、これからは真面目に勉強して、この大学に受かろうと思うようになったから、進歩じゃない? これでも、真剣に考えたんだ」
しらっと言ってのける庸介に、柳沢はため息をついた。
「お前さ、その彼女になにを求めてるんだ?」
「え?」
「単なる大学時代を楽しく過ごすために、その彼女に近付こうっていうなら、絶対相手にされないぞ」
庸介は柳沢の顔を見た。担任の真剣な表情が、庸介からも軽薄な笑みを奪っていた。
「よく考えろ。その彼女はカメラマンになるために頑張ってるんだろ? 将来の構想もきちんと立てているってことだ。体育系にしろ、芸術系にしろ、こういう特殊な学部は潰しがきかない。だからみんな必死だ。そんなしっかりした女性が、単に今楽しく交際しようなんて口説きに応じるわけがないだろうが。お前とは次元が違う」
「そんなことはわかってるよ。だからさ、大学で真剣に進路を考えようと思っているんだ」
柳沢は首を左右に振った。
「違う。言ってる意味が違う。単につきあいたいだけなら、その彼女でなくてもいいことだ。いや、そのほうがいいだろう。こういう夢に向けて邁進している人間は、本当につらい時に支えてくれるヤツじゃなきゃ、心を動かさない。お前とは熱量が違うんだよ」
庸介はぐっと唇を噛みしめた。