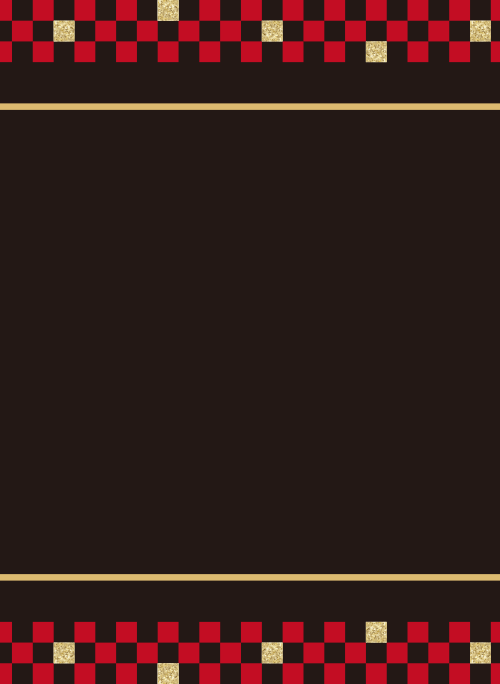何事もなく、一月が経った。
杏子と関係を持つことはなかった。というのも、彼女が男と歩いている姿を目撃し、すっかり気持ちが冷めたのだ。
誰でもいいなら自分でなくてもいいだろう、そう思った。面倒に巻き込まれるのも御免だ。何度かメッセージがきたが、時間がない、合わないと理由をつけ、会うのを断った。
ゴールデンウイーク、佐賀まで焼き物を見に行くと話していた綾は、理衣と話を詰め切れず、結局、間際になって動いたため、飛行機も新幹線も押さえられずに断念に至った。
なにやってんだか、と思う庸介だ。
五月晴れの続く清々しい中、庸介は一人、学校近くの公園にいた。
クラスメートはすでに受験に必死で、誰も相手にしてくれない。
秀二など、目の色が変わっている。受験生なのだから当然と思いつつ、庸介は芝生に寝転がって参考書を見ていた。
一応、する。それが庸介の信条だ。まったくしないのではない、相応にする、必死にならないだけ。
カシャリというシャッター音が耳に届いた。
何気なく見ると、理衣が鳥に向けてカメラのシャッターを切っている姿が目に入った。
(理衣さん)
プロが持っているような立派なカメラだ。いや、目指しているのだから当然かもしれない。
目が真剣だ。家で見せた優しそうな雰囲気はどこにもなく、張り詰めたものを感じる。
ワンショット、ワンショット、逃すことのできない真剣勝負であることが、ド素人の庸介にも伝わった。
この動画やAIが席巻する世の中で、カメラマンというのは食べて行けるのだろうか、と思う庸介だが、真剣にファインダーを覗く理衣の姿は美しい。
庸介は見入っていた。そして気づいた。綾が彫刻に取り組む目と同じだ。二人が目指すコースはそれぞれ違うのに、仲が良い理由がなんとなくわかった気がした。
「庸介君じゃない」
向こうから声をかけてきた。
「ここでなにしているの?」
「受験勉強」
「こんなところで?」
目を丸くする理衣は、それでも庸介の隣に腰を下ろした。
「集中できる?」
「まぁまぁ」
「……こんなところで参考書読んで頭に入るなら、きちんと取り組んだらかなり良い成績取れるんじゃないの?」
「いいんだよ、俺、推薦取れるトコなら、どこでも」
「そうなの?」
「うん。必死にするの、ヤだから。頑張って報われなかったら、頑張った分無駄になるだろ?」
「一生懸命取り組むことが無駄なの? 頑張らないと得られないモノだってあるのよ? 結果度外視で」
「いらない、そんなの」
理衣は驚いたように口を噤み、黙り込んだ。
「それよかさ、なんでそんなにカメラが好きなわけ? 画像加工ソフトとかでもいいんじゃね? むしろそういうアプリ使いこなせるほうが、これからの時代いいと思うけど。それに、カレシとか作って、楽しくやろうとか思わない?」
「思わない!」
怒ってプイと横を向く。今度は庸介が驚く番だった。
「なに、怒ってんの?」
「別に」
しばし横を向いたまま沈黙するが、やがて小さな声で話し出した。
「庸介君、恵まれすぎてるんだよ。だから一生懸命がイヤだなんて言うのよ」
「どういう意味?」
「わかんないなら仕方ないわね」
庸介はプッと笑った。
「なに?」
「なんかさ、理衣って面白いなって思って」
「はぁ? あのね、庸介君。年上に向かって、呼び捨てはナシでしょ! ちゃんと『さん』付けで呼びなさいよ」
「いいじゃん。理衣のほうが呼びやすい。ねぇ、やっぱさぁ、つきあわない?」
「つきあわない」
「どうしてさ? いいじゃん」
「受験生となんてつきあえません!」
もう一度プイッと顔を背けた。庸介はますます笑った。
「じゃあさ、受験を終えて、大学に入ったらつきあってくれる?」
「ムリ」
「どうしてさ。理衣と同じ大学行くよ」
「バーカ。そういう目的で受験なんてするもんじゃないでしょ? もうちょっとね、真面目にやんなさいよ!」
「俺の成績で理衣たちと同じ大学行けるかどうか、明日、先生に聞いてみるよ。もし今の成績じゃ無理って言われたら、一生懸命勉強する」
「余裕って言われたら?」
「受験勉強する必要ないじゃん。今からでもつきあえる。ね?」
理衣はすっくと立ち上がった。
「理衣?」
「そういう不純なことを言う人とはつきあわない。いくら綾の弟でも。余裕なら、もっと上を目指すべきよ。私はね、真面目で一生懸命が好きなの。だから気が合わない。お断り」
歩き出す理衣を追いかけ、後ろから抱きしめた。
「庸介君!」
「だって、なんかすごく気に入ったんだもん」
「だからそういう問題じゃ――」
理衣の言葉が、ふと途切れた。不思議に思って視線を追うと、そこに杏子が立っていた。
「知ってる子?」
「え、ま、まぁ」
杏子がスタスタとこっちに歩み寄って来る。理衣の顔をチラリと見ると、庸介に向けて笑いかけた。
「私以外の暑苦しくない女ね?」
「…………」
「年上? だったら物分かりが良くて、軽いつきあいには丁度良いじゃん」
理衣に顔を向けて嫌味っぽく笑う。対して理衣の顔が見る見る険しくなっていった。
「ねぇ、お姉さん。ヨースケ、次貸してよ」
挑発的な口調に理衣は心底ムカついたようだった。抱きしめる庸介の腕を振りほどき、顔を向けた。
「次、貸してほしいんだって。よかったじゃない、ボク。ちゃんと次があって。じゃあね」
「ちょっと待てよ。違うって」
「綾に、あんたの弟はモテるって言っておくわ」
「理衣! 違うってば!」
理衣は庸介を無視して駆け出した。それを追いかけようとする庸介の腕をすかさず杏子が取る。
「待ってよ、せっかく会えたのに! 今度はヤる約束でしょ?」
「そういうのが暑苦しいんだよ。くだらねぇコト言うなよ」
「だって!」
「他にストックいっぱいあンだろ?」
「ストック?」
「男と歩いてるの見たよ」
「…………」
「とにかく、もう連絡してくるなよ」
そこまで言って、慌てて理衣を追いかける。しかしながら、わずかな差で人ごみに紛れてしまった理衣を見つけることができなかった。
(ったく、杏子のヤツ。オトコがいるんだから、俺なんてどうでもいいだろうが。邪魔しやがって)
自分のことを棚に上げ、杏子に八つ当たりをした。
杏子と関係を持つことはなかった。というのも、彼女が男と歩いている姿を目撃し、すっかり気持ちが冷めたのだ。
誰でもいいなら自分でなくてもいいだろう、そう思った。面倒に巻き込まれるのも御免だ。何度かメッセージがきたが、時間がない、合わないと理由をつけ、会うのを断った。
ゴールデンウイーク、佐賀まで焼き物を見に行くと話していた綾は、理衣と話を詰め切れず、結局、間際になって動いたため、飛行機も新幹線も押さえられずに断念に至った。
なにやってんだか、と思う庸介だ。
五月晴れの続く清々しい中、庸介は一人、学校近くの公園にいた。
クラスメートはすでに受験に必死で、誰も相手にしてくれない。
秀二など、目の色が変わっている。受験生なのだから当然と思いつつ、庸介は芝生に寝転がって参考書を見ていた。
一応、する。それが庸介の信条だ。まったくしないのではない、相応にする、必死にならないだけ。
カシャリというシャッター音が耳に届いた。
何気なく見ると、理衣が鳥に向けてカメラのシャッターを切っている姿が目に入った。
(理衣さん)
プロが持っているような立派なカメラだ。いや、目指しているのだから当然かもしれない。
目が真剣だ。家で見せた優しそうな雰囲気はどこにもなく、張り詰めたものを感じる。
ワンショット、ワンショット、逃すことのできない真剣勝負であることが、ド素人の庸介にも伝わった。
この動画やAIが席巻する世の中で、カメラマンというのは食べて行けるのだろうか、と思う庸介だが、真剣にファインダーを覗く理衣の姿は美しい。
庸介は見入っていた。そして気づいた。綾が彫刻に取り組む目と同じだ。二人が目指すコースはそれぞれ違うのに、仲が良い理由がなんとなくわかった気がした。
「庸介君じゃない」
向こうから声をかけてきた。
「ここでなにしているの?」
「受験勉強」
「こんなところで?」
目を丸くする理衣は、それでも庸介の隣に腰を下ろした。
「集中できる?」
「まぁまぁ」
「……こんなところで参考書読んで頭に入るなら、きちんと取り組んだらかなり良い成績取れるんじゃないの?」
「いいんだよ、俺、推薦取れるトコなら、どこでも」
「そうなの?」
「うん。必死にするの、ヤだから。頑張って報われなかったら、頑張った分無駄になるだろ?」
「一生懸命取り組むことが無駄なの? 頑張らないと得られないモノだってあるのよ? 結果度外視で」
「いらない、そんなの」
理衣は驚いたように口を噤み、黙り込んだ。
「それよかさ、なんでそんなにカメラが好きなわけ? 画像加工ソフトとかでもいいんじゃね? むしろそういうアプリ使いこなせるほうが、これからの時代いいと思うけど。それに、カレシとか作って、楽しくやろうとか思わない?」
「思わない!」
怒ってプイと横を向く。今度は庸介が驚く番だった。
「なに、怒ってんの?」
「別に」
しばし横を向いたまま沈黙するが、やがて小さな声で話し出した。
「庸介君、恵まれすぎてるんだよ。だから一生懸命がイヤだなんて言うのよ」
「どういう意味?」
「わかんないなら仕方ないわね」
庸介はプッと笑った。
「なに?」
「なんかさ、理衣って面白いなって思って」
「はぁ? あのね、庸介君。年上に向かって、呼び捨てはナシでしょ! ちゃんと『さん』付けで呼びなさいよ」
「いいじゃん。理衣のほうが呼びやすい。ねぇ、やっぱさぁ、つきあわない?」
「つきあわない」
「どうしてさ? いいじゃん」
「受験生となんてつきあえません!」
もう一度プイッと顔を背けた。庸介はますます笑った。
「じゃあさ、受験を終えて、大学に入ったらつきあってくれる?」
「ムリ」
「どうしてさ。理衣と同じ大学行くよ」
「バーカ。そういう目的で受験なんてするもんじゃないでしょ? もうちょっとね、真面目にやんなさいよ!」
「俺の成績で理衣たちと同じ大学行けるかどうか、明日、先生に聞いてみるよ。もし今の成績じゃ無理って言われたら、一生懸命勉強する」
「余裕って言われたら?」
「受験勉強する必要ないじゃん。今からでもつきあえる。ね?」
理衣はすっくと立ち上がった。
「理衣?」
「そういう不純なことを言う人とはつきあわない。いくら綾の弟でも。余裕なら、もっと上を目指すべきよ。私はね、真面目で一生懸命が好きなの。だから気が合わない。お断り」
歩き出す理衣を追いかけ、後ろから抱きしめた。
「庸介君!」
「だって、なんかすごく気に入ったんだもん」
「だからそういう問題じゃ――」
理衣の言葉が、ふと途切れた。不思議に思って視線を追うと、そこに杏子が立っていた。
「知ってる子?」
「え、ま、まぁ」
杏子がスタスタとこっちに歩み寄って来る。理衣の顔をチラリと見ると、庸介に向けて笑いかけた。
「私以外の暑苦しくない女ね?」
「…………」
「年上? だったら物分かりが良くて、軽いつきあいには丁度良いじゃん」
理衣に顔を向けて嫌味っぽく笑う。対して理衣の顔が見る見る険しくなっていった。
「ねぇ、お姉さん。ヨースケ、次貸してよ」
挑発的な口調に理衣は心底ムカついたようだった。抱きしめる庸介の腕を振りほどき、顔を向けた。
「次、貸してほしいんだって。よかったじゃない、ボク。ちゃんと次があって。じゃあね」
「ちょっと待てよ。違うって」
「綾に、あんたの弟はモテるって言っておくわ」
「理衣! 違うってば!」
理衣は庸介を無視して駆け出した。それを追いかけようとする庸介の腕をすかさず杏子が取る。
「待ってよ、せっかく会えたのに! 今度はヤる約束でしょ?」
「そういうのが暑苦しいんだよ。くだらねぇコト言うなよ」
「だって!」
「他にストックいっぱいあンだろ?」
「ストック?」
「男と歩いてるの見たよ」
「…………」
「とにかく、もう連絡してくるなよ」
そこまで言って、慌てて理衣を追いかける。しかしながら、わずかな差で人ごみに紛れてしまった理衣を見つけることができなかった。
(ったく、杏子のヤツ。オトコがいるんだから、俺なんてどうでもいいだろうが。邪魔しやがって)
自分のことを棚に上げ、杏子に八つ当たりをした。